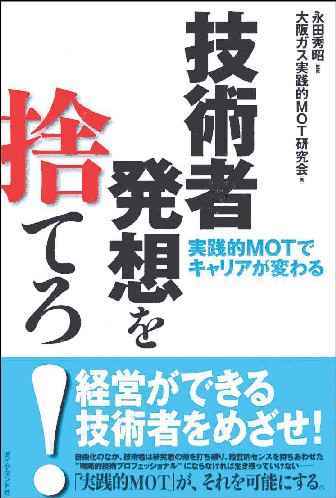「技術者発想を捨てろ!」
実践的MOTでキャリアが変わる
永田 秀昭 監修 大阪ガス(株) 常務取締役
大阪ガス実践的MOT研究会 著
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478890161/qid%3D1115268451/249-0721754-6461157#product-details
電気新聞の紹介で目に留まり読んでみることにしてみたが、
いやー、非常に満足、満足。
自分の思う課題に対してビシ、バシと明快に回答をもらえた。
大阪ガスについては、4年前の水素関係セミナーで技術者から話を聞いたことがあるが、
(3.家庭用固体高分子型燃料電池コージェネレーションシステムの開発について
大阪ガス株式会社 家庭用コージェネレーションプロジェクト部長 本田 國昭 氏)
そのとき、「なかなかやるな」と感じていたが、
この本を読んで、なるほどなあと思った。
電力会社に比べて、ガス会社の方が非常に必死になっている。
電力会社は甘いと反省させられる次第であった。
今、大学ではやりのMOT講座であるが、
ビシネスで技術を生かしきらなければ意味はない。
そういう意味で、大阪ガスの実践的MOT研究会の取り組みは素晴らしいと思う。
ビジネスで儲けにならない技術は意味がないとまで言い切る。
顧客重視の姿勢が非常に出ている。
大学ではなく、企業である。
人の役にたつ技術を開発して、商売する。それが基本だ。
学問的な研究埋没スタイルではダメ。
その技術に対するロマンをビジネスのロマンと重ね合わせることができたとき
成功は半分以上見えてくるのである。
そこで編み出された6つの法則。含蓄がある。
1 技術者は、人に誇れるコア技術を持て
2 「技術のロマン」に「ビシネスのロマン」を重ね合わせろ
「ロマンの説明は、瞬時に心に響いてこなければならない。
これが基本である。理性よりも感性を優先させることである。(ウンウン)
人は感動で大きな力を発揮する。
この力こそが、ビジネスのロマンには必要なのだ。(ソウダ、そうだ!!)
若いときに是非成功体験を経験させ、感動する実感を持たせるようにしろと説いている。(納得)
3 技術の工程表を疑え
4 ドリームパワリングを発揮しろ
5 技術者は奥の院から外に出よ
6 戦うためのツール「プリゼンテーション力」を磨け
特に前々から思っていた、やらされ仕事ではなく「夢」を持った仕事ができないか?ということ。
に対して、2番、4番が光を与えてくれた。
私が夢と言っている言葉が、ここでは「ロマン」となっているが同義である。
永田氏の思いは全く同じ。彼はそれを現場で実践に移せた。
まねでもいいから見習いたいものだ。
最終章に営業部門でMOT経営に成功した永田氏が、
製造部門の事業部長に転勤し組織風土改革を行った事例が非常に参考になる。
ガスを作る工場、すなわち「製造所」に戻ってきたのである。(16年ぶりの製造部門)
16年前に技術者たちが燃えていた極低温の技術も、すでに確立され、
今は維持・保守が中心になっていた。
数千人いた製造所の人員も、スリム化、少数精鋭化して300人規模になっていた。
(発電所運営も同様な時代である。いまや原子力発電も運転・保守の時代だ)
優秀な技術者である彼らは、漠然とした将来への不安をいくばくか抱えながらも、
では不安を解消するために、いま何に燃えていけばいいのか、はっきりわからない状態にある
ことは容易に想像できた。
…設備が高経年化するなかでは、コストを減らしながらも、リスク軽減のためのメンテナンス投資を
より一層手厚く行う「選択と集中」を図らねばならない。
この新たな難関を前にして、舵取りしていこうという時、その中心となるべき製造所にいる技術者たちに
覇気が感じられない。
こうした重要な仕事を任されている人たちが、不安の中で仕事をしていることは決していいことではない。
→ 法則2 「技術のロマン」に「ビシネスのロマン」を重ね合わせろ から始めた。
「事故ゼロの製造所」から「強い製造所」と目標が変化
(事故ゼロやヒューマンエラーゼロという目標は大嫌いである。そう常々思っていたらちゃんと
書いてくれてます)
事故ゼロはプレッシャーであり、やらなければならないことである。
それでは厳しさしか伝わらない。
「強い」となるとあいまいになるものの、誰でもが感情的、感覚的に描ける。
さらに「強い製造所ってどんなもんだろう」と疑問も出てくる。
そこが重要なところである。
つまり言葉ひとつでイメージが広がり、飛躍してゆく。
そこにアイディアが生まれ、これまでにないやり方と結びつくのである。
☆スーパーシックスシグマOG(大阪ガス)ウェイ
永田氏が製造所改革で取り組んだユニークな手法。
自分で本を読んで構想をまとめ、自らがコンサルタント的に動いて取り組んだ。
素晴らしい。
独自のやり方なので、特に外部の指導者は招聘しなかった。私自信がコンサルタントであればいい。
(自信過剰ではない、共感を覚える)
これまでは上からの改革であった。
「これまでとは違う、何かこう永遠に続く仕組みを持ちながら、そして上から言われるのではなく、
メンバー自らが手を挙げ、嬉々として取り組んでいける方法はないものだろうか。
自分たちの相談に乗ってくれる上司がいて、成果をあげればルールに従って金額で評価する。
そんな取り組みができないだろうか」
(全くの同感である。品質管理は末端の個々人の当事者意識にかかっている。
いかに個人が自分の仕事に誇りと責任感をもって取り組むことができるか?
これがテーマである。 と思っている)
そこで取り入れて絶大なる効果を発揮したのが
「技術者をプラス評価する仕組み」である。
これが目からうろこである。
さわりの全文を引用してみよう。
エネルギーの効率的活用とか、紙の使用量の削減、人員の効率化など、
どの企業でも必ずといっていいほど、熱心に取り組んでいるものだ。
目に見えて削減すればコストも削減される。
顕在コストの削減は取り組みやすい。
削減の成果を金額として計算しやすいので、評価もしやすい。
ところが、水面下にある大きな「潜在リスクに基づく潜在コスト」は
「絶対に起こしてはダメ」、「会社が大変になるぞ」と上司からきつく言われるものである。
評価の面でもうまくいってゼロ評価である。
起きなくて当たり前のこととされ、トラブルを起こしたときにはじめて莫大な「マイナス評価」
を浴びせられる。
もちろん、これは当然必要なことである。トラブルについてのマイナス評価はなくてはならないものだ。
しかし、それだけでは足りないのである。
プラス評価のない、マイナス評価だけの世界では苦しいのである。
すべてがうまくいっても「ゼロ評価」だから、こうした製造業に携わる技術者たちは氷の上の
「プラス評価」以上に、氷の下の「マイナス評価」におびえる日々を送っている、と言っても過言ではない。
すなわち「トラブル完璧ゼロ」という呪縛に日々、脅えているのである。
この状況を変えるには、どうすればいいのだろうか?
氷の上の利益が増えていくのと同じように、下の氷が溶けていく、つまりリスクが減っていくことも
プラスの金額で具体的に評価できる仕組みがあればいい。
→ ということで具体的な評価基準は書かれていないが、リスク低減策を実施すれば
部下が上司に申告し、それをオープンな基準に基づいて金額で評価することにより
一人一人の貢献度が定量的に示される。
どんなささいなことでも、それが評価され金額であらわされるのでやる気が出る。
ウェブで公開しているので人真似でもよい。
目標は1人年間3000万円としたが半年で8割達成したという。
やったら、当たり前ではなく、やっただけのことが正当に評価される。
この仕組みの導入により、みんなの目の色が変わった。
すごい!
でも、この手法は真似ようと思えばできるのである。
なんとか、こういう仕組みを我々も取り入れたいと思う。
あとはアイディアをいかに大事にするかという方法論が随所に散りばめられていて参考になった。
◎ 月曜日の朝は「メール」をやめて、「アイディアの応酬」をせよ
さて、週末などに至福の時を過ごしたり、リラックスした時間を設けることで、
たくさんのアイディアを抱えた技術者たちが、月曜日の朝、再び会社に集まってくる。
ところが、会社に来ると、いいと思ったアイディアも徐々に縮こまり、だんだんと勢いが
失われていくことがある。これほどの損失はない。
土日に何も考えていなかった人ほど、月曜の朝に「メールでも見よう」となるのである。
(耳が痛い)
すぐ取り掛かれるのがメールだけ、というのはいかにも寂しいではないか。
月曜の朝、まずアイディアを出し合って、みんなで評価しながら、
いいものをどんどん具体化するための行動を起こすことである。
そこに戦略性が加わり、戦略的技術プロフェッショナルへと進化する。
すなわち、「土日で考え、月火水で動き回り、木金でなんらかの成果を出し、
また、土日で戦略を練る」というサイクルを作ろう。
1週間がこのように動きだせば、技術者の工程表は見違えるようによくなる。
月単位の工程ではなく、毎日がリアルタイムで動き出す。
土日の「至福の時」に出てきたアイディアをすぐ活かさないで、月曜日の朝いちばんにメールを
している技術者は、まだまだ「技術者の工程表」に生きているのである。
月曜に限らず、毎日の朝が活発な議論で始まれば、なおいい。
大阪ガスのHPより
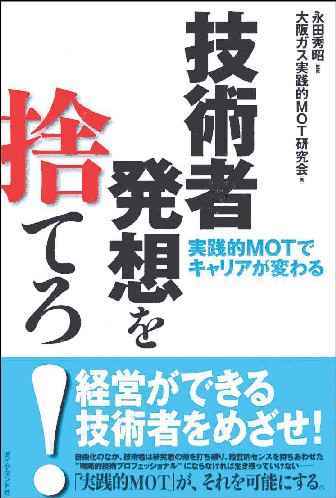 |
「技術者発想を捨てろ!」ー実践的MOTでキャリアが変わるー が、今月初め、ダイヤモンド社より刊行されました。
(定価:税込み 1680円)
永田常務(
ガス製造・発電事業部長
)監修、大阪ガス実践的MOT研究会(代表:永田常務、アドバイザー:松村副社長、中谷副社長)著である本書は、大企業病にかかった技術者たちに処方箋つまり実践的MOTを与え、「経営ができる技術者」というキャリアパスを示すものです。
大阪ガスの技術者たちが現場で体験してきた実例、いろいろな会社との実際の取引のなかでの経験をもとに、どうすれば技術者の発想を変えられるか、つまり「経営ができる技術者」であり「強い
“戦略的技術プロフェショナル”
」となれるのかを、本書の中で「6つの法則」としてまとめています。
大阪ガスの優れた技術力の例、またそれらをベースに新市場を切拓いていった事例が豊富に収録された本書は、販売開始以降、紀伊国屋書店や旭屋書店で週間ベストセラー第2位にランクされるなど早くも大きな反響を呼んでいます。
(参考)
【大阪ガス実践的MOT研究会】
大阪ガスの役職員十数名で構成された私的研究会。天然ガス拡販などを通じて蓄積された「技術をビジネスに活かす手法」つまり「実践的MOT」を調査・研究・保存し、さらに次代へ役立てることを目的として活動している。その活動の最初の成果が本書である。 |