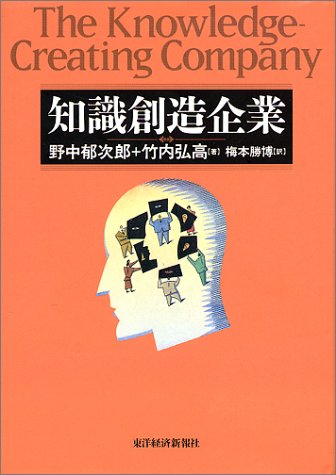「知識創造企業」
野中 郁次郎 +竹内 弘高 (著) 梅本 勝博 (訳)
東洋経済新報社
野中郁次郎先生はあまりにナレッジマネジメントで有名であったが、
この本は読んだことがなかった。
非常に優れた書き物だと思った。
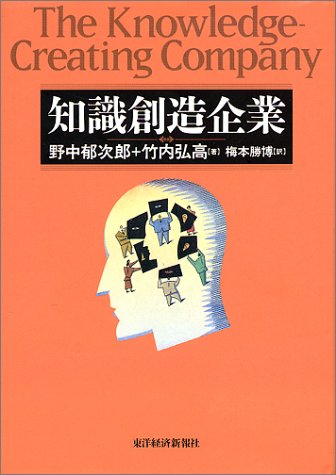
ただ読むのは疲れた。
海外で出版されたものを日本で出すために本人ではなく別の人が翻訳しているというヘンな感じ。
であるからして、横文字がやたら出てきて読みにくいこと。
西洋と東洋の哲学的考え方の根源を有名な哲学者の考え方を整理しているのが
第2章である。
「知識と経営」
これは非常に難解であるが、作者の若い時の勉強の報告のような感じだったなあ。
しかし、ここは先輩学者の研究成果を時代を追って解説しており大変勉強になる。
よく読めました。マル。
そして、この書のなかで新鮮だったのは、
「ミドルアップダウン」といく言葉であった。
トップダウンでもなく、ボトムアップでもない、
その中間に位置するもので
まさにミドルマネージャーが「組織的知識創造」には重要な役目を果たすのである。
ちょうど同じ時期にシックスシグマを読んだのだが、ここでもミドルマネージャが
ブラックベルトとして活躍するのである。
シックスシグマは一応トップダウンとされている手法であるが
これもまさに「ミドルアップダウン」という気がした。
効率一辺倒の組織では決して成しうることのできない
冗長性のある組織が知識創造を起こして会社を発展させる。
そういう願い、思いがこの書になって現れたのだと感じた。
「冗長性」の重要性をつくづく感じた。
ミドルマネージャーが会社の源泉。
トップでもなくダウンでもない。
同感である。
二律背反(二項対立)を可能とする東洋的(陰陽)の考え方が野中さんにはある。
これは「ビジョナリーカンパニー」でも、「木をみる西洋人、森をみる東洋人」でも主張されていたことである。
さて、野中先生の組織的知識創造の理論は4つの変換モードで説明される。
1 共同化 暗黙知 → 暗黙知 (言葉を使わずに体で覚える、体得する)
松下自動パン焼き器 田中郁子が弟子入りして「ひねり」を発見
2 表出化 暗黙知 → 形式知 文書化
暗黙知がメタファー、アナロジー、コンセプト、仮説、モデルなどの形を取りながら
しだいに形式知として明示的になっていく。
演繹的、帰納的の組み合わせ。
リーダーの豊かな比喩的言語や想像力が、メンバーの暗黙知を引き出すための重要な要素
「メタファー」という言葉を使っている。
メタファーとは【隠喩】 (いんゆ)
言葉の上では、たとえの形式をとらない比喩。
「…の如し」「…のようだ」などの語を用いていない比喩。
「雪の肌」「ばらの微笑」の類。メタファー。暗喩。
「大辞林」より
3 連結化 形式知 → 形式知
異なった形式知を組み合わせて新たな形式知を作り出す
製品コンセプトのような中範囲のコンセプトが企業ビジョンのような壮大なコンセプトと結びついて
新しい意味を作り出す。
アサヒビール 「Live Asahi for Live
People」
このコンセプトに沿って「コクとキレ」のスーパードライが誕生
4 内面化 形式知 → 暗黙知
行動による学習
形式知を体化するプロセス
実際に他の人の経験を追体験しなくても起こりうる。
ある、サクセス・ストーリーが組織のメンバーにその話の本質と臨場感を感じることができれば、
過去の経験が暗黙的なメンタル・モデルになることもありうる。
⇒ このことは最近目にしたJALの新社長の取り組みがコレだ。
新町敏行新社長は御巣鷹山事故に原点回帰を求めて行動を開始している。
現場を回り、20年前のフィルムを社員に見せ、意見交換行っている。
衝撃的な映像を見せられて関係者は新たな思いを抱いている。
5 スパイラル化
暗黙知と形式知が相互作用するときにイノベーションが起こる。
このためには「場」の提供が大事
組織的知識創造は個人レベルから始まり、メンバー間の相互作用が、課、部、事業部門、そして組織という
共同体の枠を超えて上昇・拡大してゆくスパイラルプロセスなのである。
促進する5つの条件として
「意図」
目標への強い思い、コミットメント
「自立性」
自由な行動を認める。チームはクロスファンクショナルな構成
「ゆらぎと創造的なカオス」
快適な習慣的状態が中断されるブレイクダウンが重要
・社員に危機感と高遠な理想を与えるのがトップマネジメントの役割
あいまいなビジョンは(戦略的多義性)組織にゆらぎを発生させる
環境にいいところではひらめきは鈍る。
⇒これは同感。人間追い詰められればひらめく。
「冗長性」
ゆるやかな結びつきがよい結果を生む。
「最小有効多様性」
組織構造を頻繁に変える。
人事異動も頻繁(松下)
組織的知識創造のフェーズ
暗黙知の共有 → コンセプト創造 → コンセプトの正当化 → 原型の構築 → 知識の転移
以上の実際の例を具体的に挙げて説明している
松下電器 ホームベーカリー
GE ジャックウェルチによるトップダウンの例
3M ボトムアップの例
キャノン ミドルアップダウンの例 使い捨てカートリッジというブレイクスルーコンセプト
マツダ RX−7の成功
第6章
新しい組織構造として「ハイパーテキスト型」を提案
ビュロクラシー(官僚組織)とタスクフォースを組み合わせたもの
平時には官僚的であるが、戦時にはきわめてタスクフォース志向のアメリカ軍
日本軍の官僚機構での失敗は「失敗の本質」で読んだ。
このときの経験が、この提案につながっている。
官僚機構への批判
官僚機構は、個々の職能をコントロールし結果が予測できることを重視するから、状況が安定しているときにうまく機能する。
それは、きわめて形式的、専門化、中央集権化されており、
業務プロセスを組織的に調整するための標準化に大きく依存しながら定型業務を効率よく大規模に行うのに適している。
したがって、それは、非常に合理化された反復的業務を特徴とする安定した成熟産業でよく見られるのである。
しかし、官僚的なコントロールは、個人の自発性を殺ぎ、不確実で急激に変化する時代には逆機能になるコストを伴う。
そのほかにも、ビュロクラシーの逆機能として、
組織内部の抵抗、繁文縟礼(はんぶんじょくれい)、緊張、責任回避、手段の目的化、セクショナリズムなどを挙げることができる。
ビュロクラシーは組織要員のモチベーションを阻害することもある。
多くの心理学者たちは、ビュロクラシーより成員参加型で有機的な組織構造のほうが、やる気を促す点ではより効果的と
主張してきた。
--------------------------------------------------------------------------------------------------
繁文縟礼
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
繁文縟礼(はんぶんじょくれい)とは,規則が細かすぎ,煩雑な手続きが多く,非常に非能率的な状況を指す。
膨大な公文書を束ねて保存するために使われる赤い紐が転じて,レッドテープ(Red Tape)ともいう。
アメリカの社会学者ロバート・キング・マートンが,官僚制の逆機能の一つとして指摘したものである。
本来は,明確な規則と公正な手続きによって事務を処理する合理的なシステムであったものが,その形式的・技術的な
側面に縛られることによって,非合理的な傾向を示すようになるというもの。
特に代表的な事例を挙げると,マックス・ヴェーバーが指摘した合理的管理様式である文書主義の逆機能である。
会議の議事録,業務上の各種書類,指示・命令を伝達するための命令書など,もともとは業務内容等を文書によって明示し,
記録・保管することによって,業務の客観性・正確性を確保するための合理的な手続きである。
これらはメインの業務を円滑に進めていくサブ業務だが,それがメイン業務として大きな負担となり,
膨大な量の文書を作成し,保管することが目的と化してしまう。
さらにそれが進むと,些細なことにも書類の発行を要求されるようになり,業務の遂行の障害となっていくというような
状況である。
------------------------------------------------------------------------------------------------------
タスクフォースはビュロクラシーの弱点に対処する組織構造。
しかし、その時限性から、タスクフォースチームで作られた新たな知識は、プロジェクト完了後ばらばらになり、
他の組織成員へは容易に伝わらない。
したがって、知識を組織全体へ幅広く伝えながら連続的に利用するのに不向きである。
ということでこれらのういいところを統合する組織としてハイパーテキスト型組織が提案されている。
具体的企業例として
花王とシャープが挙げられている。
花王では「大部屋制度」のもとで、それぞれひとつの大きなオープンスペースに配置されている。
役員室のフロアーの半分は、「意思決定ルーム」と呼ばれるスペース。
役員たちが自分の部屋にいることは少ない。
研究所でも、研究員は自分の机を持たず、大きなテーブルを共同で使う。
(まさに私が理想としている姿である。いつかきっとこういう職場にしたいと思っている)
常盤社長(当時)の説明
研究開発という仕事は、放っておくとどうしても独立してグループを作りがちであり、孤立する性質があります。
そういうことが起こらないように、いくら心構えや精神を説いてみても部屋が小さく分かれていたり、
組織が細かく分かれていたのでは、無駄になってしまいます。
そこで実際の壁を取り払って、同時に精神的な壁も取り払おうとしたのです。
1991.5.21インタビュー
花王のシステムは、大きな円盤に小さな取っ手のついた日本式文鎮にたとえられることがある。
→ これに対して後藤社長は以下の掲載をしている。マイHPから引用する。
2004年11月3日掲載
「ピラミッド」は「文鎮」に勝る
日経ビジネス 10月18日号 経営者の眼 後藤 卓也 花王会長
…
文鎮型では人材が育たないと考えるからだ。
そもそも人材が育つには、判断をする場が必要だ。
(中略)
入社3年目と10年目、20年目の社員が同じ判断しかできないのはおかしいし、それでは困る。
大事なことは、情報を持っていることよりも、何を感じてどう行動するこのかだと私は思う。
(中略)
私が人材育成にこだわるのは、フラット化であれ何であれ、あらゆる問題を解決できる「理想の組織」は
ありえないと考えているためだ。組織を決定ずけるのは所属する構成員のパーソナリティとコミュニケーションに尽きる。
(中略)組織を作って人を配しても会社は機能しない。
実際にやらなければならないのは、組織の重要な構成員を育てることだ。
そして彼らが立場立場で判断のできる人材となれば、ピラミッド型は早くて強い組織にもなる。
---------------------------------------------------------------
全くの同感である。
ヒエラルキー組織は組織員が官僚的にならない限り非常に合理的な組織なのである。
人材を育てるのに適している。
シャープは完璧なハイパーテキスト型組織
R&Dは完全な独立した緊急プロジェクトを結成
「金バッジ」を付与し役員と同じくらいの権限を与える。(ただし期限付き)
このSE(スーパーエクセレント)商品に認定されるための条件は厳しい
・まったく新しい流れを市場に作る
・まったく新しい技術を使う
・まったく新しい材料を使う
・まったく新しい製法を使う
これをすべてに満たさなければならない。
辻社長の言葉
「まねをするな」
トンボにならなければいかん、と言ったんです。
トンボの目は複眼だ、しかも羽がある。
情報を複眼的に吸収して、実験する。
逆に目だけ大きくて上ばかり見ているヒラメになるな、と言ったんです。
これからの仕事は険しいだろうと思いますが、やはり創造的な社員をどれだけ創り出せるかということが重要で
またそれにはそういう仕事環境が必要です。
第7章
グローバルな組織的知識創造
東洋は文脈、暗黙知重視
西洋は単語、形式知重視
このような文化の違いを乗り越えて知識創造を達成した例として
日産のプリメーラ・プロジェクトが示されている
プリメーラとはスペイン語で1番
(1) 日本と英国で生産
(2) 部品の80%をヨーロッパで調達
(3) ヨーロッパが主要市場だが日米でも売る
実際にアウトバーンに社員1500人を送り体験させ暗黙知を形成
選抜したエンジニアを1年間海外駐在 現地のライフスタイルや価値観を身につけさせた
矢崎軍団 試乗パイロットの妥協なき意見 暗黙知を言葉に表出化するのがうまかった
英国日産は300人の中堅エンジニアを日本に派遣し暗黙知獲得の共同化プロセス、OJT体験(日本の生産ノウハウの体得)
この共同化が極めて重要 「異文化間共同化」の好例
海外の人間の学習を助けるために日産が作ったマニュアルは、日本の工場で長い間に内面化された暗黙知を表出化することに貢献
もうひとつの例として「新キャタピラー三菱のREGAプロジェクト」
2つの会社がジョイントベンチャーを組み開発して成功したもの
相互理解を妨げている原因は、言葉の壁ではなく、
価値観やさまざまな問題へのアプローチの仕方にあることに気づく。
2人の本部長(日本人、米国人)の共同化の努力 仕事だけでなくプライベートな生活でもなるべく多くの時間を一緒に過ごした。
論理プロセスの苦手な日本人エンジニア なぜ?に答えられない
自分の経験を明確な言葉にすることが上手な日本人エンジニアは少ない。
設計センターの日本人エンジニアたちは、暗黙知に基づくコミュニケーションが外国人には通用しないことを
思い知らされた。
こうして、表出化の達成が、REGAプロジェクトにとって重要な課題になったのである。
日本人エンジニアは、自分で好きなように設計していた。
課長が「こう決めた」と言えば、なぜかと質問するものはいなかった。
それが、外国人にはっきりあいまいなところがないように説明しなくてはならなくなった。
摩擦もあったけれども、彼らと一緒に働くようになって、われわれは技術、経験、ノウハウを手に入れた。
それは貴重な財産になった。
第八章
実践的提言と理論的発見
○ 知識ビジョンを創れ
トップは知識ビジョンを創り、それを組織全体に伝えなければならない。
知識ビジョンは、社員に自分たちが住む世界の心象地図を提示し、
どのような知識を追求し創造すべきか、そのおおよその方向を示す「分野」や「領域」を画定する。
それは組織の意図でもあり、その土台の上に企業戦略が策定されなければならない。
トップマネージャは、自分の志の高さと組織の意図が企業の創る知識の質を決定することを知っていなければならない。
○ ナレッジクルーを編成せよ
プロジェクトリーダーのための昇進プログラムも作るべきである。
(シックスシグマも同じだ)
従来の「減点」評価は、新しいものを創りだすナレッジ・エンジニアには適していない。
評価基準を加点法に変更することは、知識創造企業にとっての義務。
○ 企業最前線に濃密な相互作用の場を作れ。
大きなオープンスペース、外部世界との相互作用の場を提供する
製品開発は反復的でダイナミックかつ連続的な試行錯誤のプロセス
企業は進んでチームに自立性を与えると同時に、ゆらぎと創造的カオスを許容しなければならない
非専門家の参加も奨励
○ ミドル・アップダウン・マネジメントを採用せよ
社内の縦と横の情報の流れの交差するところに位置し、夢と現実のギャップを埋める
「結び目」、「架け橋」、「ナレッジ・エンジニア」として位置づけられる
(欧米では、彼らは癌あるいは滅亡しつつある種族と呼ばれている。)
○ ハイパーテキスト型組織に転換せよ
ヒエラルキーレイヤー
タスクフォースレイヤー
知識ベースレイヤー
この3つのレイヤーをクルー・メンバーは自由に動き回れることができるが、
1つの時点では、1つのレイヤーにしかとどまれない。
1つのレイヤーから別のレイヤーに移る能力こそ、ハイパーテキスト型組織を伝統的な組織構造と区別する重要な特徴のひとつ。
マトリックス組織のように2つの職務をこなさなくてよいから、ひとつの時点でひとつのレイヤーでいることはクルーの持久力を高めるだろう。
○ 外部世界との知識ネットワークを構築せよ
◎ 理論上の含意
最も重要なことは、知識変換 暗黙知⇔形式知
ここで、変換を実行するための出発点は二項対立を超越しなければならない、という認識である。
西洋には二項対立で世界を見ようとする強い思考癖がある。
しかし、これは対立するものではなく相互に補完しあってある総合(シンセンス)を創るのである。
AとBを同時に見て、最良の部分を統合して、Cをつくり出す。
CはAといBの両方jから独立したものである、「あいだ」あるいは「中間」にあるのではない。
日本でのほうが容易。
武士道教育 哲学よりも「行動」
禅仏教 「心身一如」
心身と精神(AとB)から総合(C)を創ることは西洋より日本のほうが容易。
いやー、たいへん読み応えがあり疲れたが、勉強になった。