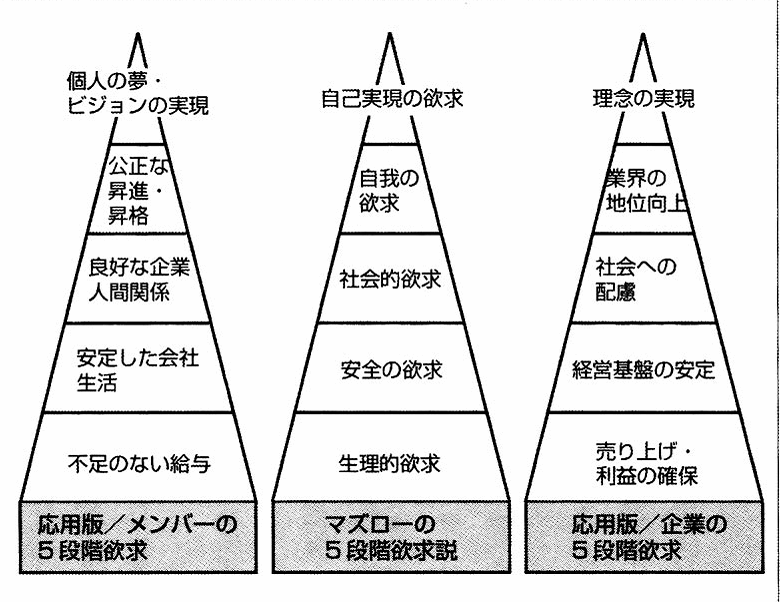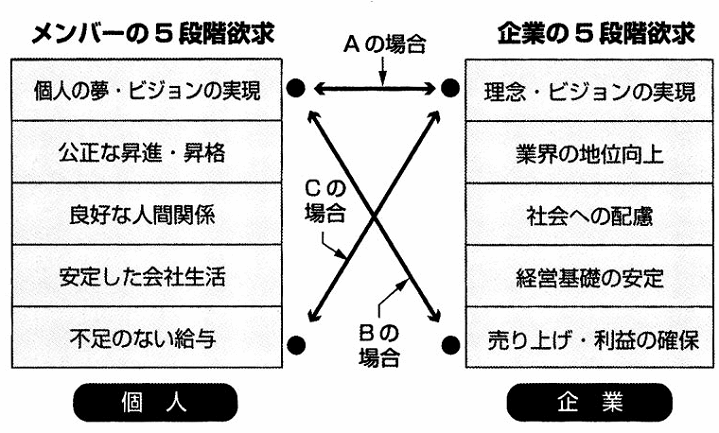A:◎ 個人と企業の欲求が高くて同一 最も望ましい状態
B:× 個人が企業内での自己実現を求めても、企業が望むのは
業績のみ 一体感は生まれにくい
C:△ 企業の理念は高いが、個人が望むのは高給のみ
会社からの動機付けや教育で変えることは可能
F.R.カッペル 「企業成長の哲学」 ダイヤモンド社 (45年以上前の本) を引用しながら以下の主張
非常に納得できる。
成長力たる企業たらしめるものは何かと言えば、それは活力にあふれた人材のほかならない。
「活力」という言葉自体が、人間本来の属性であることを示している。
では、そうした活力を引き出すものは何かと言えば、それは人をワクワク・ドキドキさせるような、
難しいけれどもなんとか挑戦し、しかも実現できる夢、その鮮明な将来映像なのです。
したがって、そのような鮮明な将来映像をもったビジョンが求められてきます。
企業の阻害要因 影響の大きい順
1 社内のつぶし屋 ⇒ システム依存症の既得利権者
2 戦略的事業剪定力の不足 ⇒ 理念実践力と戦略指導力を欠いたリーダー
3 過去からのしきたりに固執 ⇒ 責任のない世界をつくる「アイヒマン型人間」
4 外部環境変化の把握不足 ⇒ システム依存症の、慣れると考えなくなる人
5 革新的ビションの構築力不足 ⇒ 理念実践力と戦略指導力を欠いたリーダー
6 決断力の不足 ⇒ 人間的力・活力を信じないリーダー
7 資源配分における全社的統制上の問題 ⇒ 選択と集中に徹しないリーダー
○ 細分化された仕事がつくる責任の無い世界 − アイヒマン型人間の弊害
→ (私は官僚主義の問題としてとらえている、このアイヒマンという言葉が強く残り、この部分はどうしても書き残さなければならないと思っていました)
第二次世界大戦下、ユダヤ人の強制収用所移送を担当したナチス親衛隊の一人の大佐がいました。
彼の名はカール・アドルフ・アイヒマン。大戦終了後、彼は多くのユダヤ人の殺戮に大きくかかわった罪で裁判にかけられることになりました。
当時のイスラエルの首相ベン・グリオ氏は、アイヒマンについてこう述べています。
「殺人鬼であると同時に忠実な官僚であった」と。
フランスのドキュメント映画、エイアル・シヴァンについて、
「彼は実に良きマネージャーであり、また平凡でもある。ただし自分の使命は理解しても、その目的を考えようとしない。
目的を考えずに手段を考える。」と評しました。つまりアイヒマンは著者流に解釈するならば、経営の効率化や安定化に熱心な
マネージャであっても、理念に立ち返って、なすべき変革の方向性を探るリーダーではなかったということです。
アドアスミスが広めた分業化が生産性向上に寄与したが、その繁栄と富の引き換えに、我々は仕事の目的、
もっと正確に言えば、目的の意味を問わなくなってしまった。(←要約文)
仕事が細分化され、おのおのの担当者は自分に分担された細切れの仕事の効率化にのみ熱心となり、それ以外のことはあまり考えようと
しなくなってしまったのです。たとえ狭い職場であっても、分業化が徹底された職場においては、「隣は何する人ぞ」とばかりに、
まわり及びその仕事の目的や意味についてはまったくといっていいほど無関心となってしまいました。
…
我々の中にアイヒマン以上のアイヒマン型思考の人間が、もはや日本社会の隅々までわたって増殖を繰り返しているという今の現状を
しっかりと踏まえなければなりません。
…
戦略はあくまで究極の企業目的である理念を踏まえ、理念を一歩現実に近づけたビジョンを実現する手段・道具にしかすぎません。
その道具を使いこなす人間としては、道具を使う目的の意味をしっかり理解し判断しなければ、人間自らが道具に同化してしまうという、
いわばアイヒマン現象の罠に陥ってしまいます。
そうならないためにも、戦略という道具を使う究極の意味を常に問い直す責任を我々は持っています。
今、この責任に基づくリーダーシップを切に求められています。
それは細分化された仕事が生み出す責任のない世界、この弊害を除去する風土を醸成するものだと言えるでしょう。
このパワーの源は責任です。ただし責任という言葉を語る場合、そこに個々のメンバーの生き方やこだわりや理想があってこそ
仏に魂が入れられます。理想へのこだわり、理念の温故知新から人間的パワー、活力を育み、自発的な責任を生み出さなければなりません。
それはなぜかといえば、責任の自覚だけでは人は疲れてしまうからです。
やはり個々のメンバーの生き方へのこだわり、感情の伴った知恵という観点から、自覚する責任を自発的な責任に転換することが肝要です。
この原動力は、希望をあきらめない信念と、深い人間理解の信念です。
→ 非常にいい言葉である。自分の人生哲学というものをしっか持つことが大事だと心から思う。