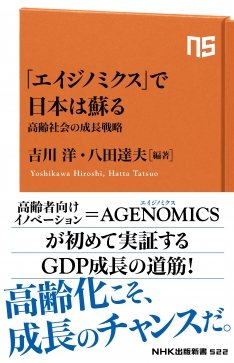
内容紹介
「エイジノミクス」で日本は蘇る − 高齢社会の成長戦略
吉川 洋/八田 達夫 NHK出版新書
高齢化こそ、成長のチャンス!
「高齢者向けイノベーションの経済学=エイジノミクス」を提唱し、創薬、ロボティクスから自動運転、混合介護、雇用改革まで、
最先端の実例を豊富に収集・分析して、日本経済成長の途を説く。
高齢の著者が書いた本なので、イノベーション的な発想はなくイマイチ感が残った。
地方のこともあまり知らないようで、都会中心で考えているところも不満が残った。
しかし、実践編になると非常に興味深い内容があり勉強になり楽しめた。
〇 新しい老化モデル
終末期まで健康で過ごす人が多いことである。
70歳までに介護が必要となる人は男性で19%、女性で12.1%に過ぎない。
男性の10.9%は要介護期間なしに終末を迎えられる「恵まれた」パターンを示す。
(女性は70台以降は恵まれたパターンは男性の数字より低い)
そして大部分の人(男性の7割、女性の9割近く)は80台になっても多少の助けがあれば
日常の生活を続けることができる。
→心強いデータである。
○ 介護予防の成功例
高知市 「いきいき百歳体操」
→ これは知らなかった
そもそも体操を開発したのは介護予防が目的であり、筋力アップ、体幹強化、嚥下力アップなど身体機能を
維持・強化することにあった。
(高知県の一人当たりの医療費は全国最高であった)
しかし、体操の普及をきっかけにう、顔見知りの住民が声をかけることで、閉じこもりがちな病弱な人を
誘い出すことに成功したり、近所同士の交流が活発になったりした。
また、体操やその会議が、地域住民の憩いの場、交流の場へ発展するという結果になった。
○ 介護度を下げた和光市
2014年の日本の高齢者人口3300万人のうち18.4%が要介護認定率の全国平均。
(「介護保険事業報告」厚労省)
認定率で言えば、高知市よりも有名なのが和光市であり、「和光モデル」という言葉すら生まれている。
要介護にならない、要介護度を改善させる、またそうした方向へインセンティブを与えることに成功し、
効果を上げている、。
和光市の要介護認定率は、2914年で9.4%と全国平均の半分程度なのである。
・まちかど健康広場
日常的に歩いていける生活圏内に小規模な施設を作った
・喫茶サロン
中学校の学区の準じた校区にひとつの割合で提供
また学校の空き教室も利用しながら、外出先の機能・魅力の向上を図った
これが、トレーニング体操、地元の野菜を使った料理教室などに発展
◎ どうすれば人は外出するのか
・「用事」「行先」を作り出す
定年退職後、楽しい生活を送るには「キョウヨウ」と「キョウイク」が必要だ。
今日、用がある。
今日、行くところがある。
→ポケモンGoは見事にこの課題を解決した
・東京都「シルバーパス」
目的は高齢者に外出を促すこと。
パス発行費用を負担したほうが高齢者を要介護に陥らせるよりも安くつくと見ている。
→高松市のゴールドイルカも同じだろう。
香川県で言えば、糖尿病の透析のため年間500万円一人にかかる
手軽に外出できるツールと行先をつくれば、劇的に改善されるハズである。
☆化粧をすれば出かける気になる
資生堂「化粧療法」
高齢者のQOL(生活の質)には、外出や人との交流など、社会とのつながりが極めて重要であること、
そして、身だしなみや化粧を意識することが、
「前向きな気持ち」や「出かけたくなる気持ち」になり、社会とのつながりを維持する役割を持つことを解説する。
2011年、化粧療法を導入した施設スタッフが「参加者のよだれが止まった」と報告してから、
化粧と嚥下の関係、口腔衛生への影響を研究することとなった。
参加者の唾液成分の分析で、唾液中の嚥下に関わる物質の濃度が変化していることがわかった。
・ポールウォーキング
加齢などで脚が弱って歩きにくくなった人が、2本のポールを持つとバランスよく歩けるようになるのである。
○ 北九州市 介護ロボット特区に認定 2015年12月
特区を利用して「シニアハローワーク」も設置
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290019-n1.html
● なぜ定年退職者は再就労できないのか
シルバー人材センターでは就労時間を週20時間までに制限していることがネック
◎ マエカワはなぜ跳ぶのか
「日本発信の世界的モデルになる可能性を秘めている」と野中郁次郎が言うほどに前川製作所を
発展させてきたのは、現同社顧問の前川正雄だ。
前川は、東京・深川の町工場だった前川製作所を親から引き継いで1971年に社長になった。
同社は製氷・冷蔵事業を手がけた町工場から、産業用冷却装置メーカーとして抜群の競争力をもつ
多国籍企業に成長した。
…
前川は社長就任後まもなく、会社の定年制をなくしている。
以来40年、前川製作所は定年のない会社としてやってきた。
定年のない会社と言っても、いちおう、40年前の制度として、60歳定年後の再雇用ということに
なっている。
いまでは国内に3100人、海外に1500人という規模の大企業になっているが、60歳になった
社員のほとんどがそれ以後も働き続ける。
同社に長期間勤める社員は、工場で製造する機械についての知識はもちろん、エンジニアリングやサービスまでを
知り尽くした熟練エンジニアだ。
240人が65歳以上で、80歳を超える社員も働いている。
高齢社員は11%に及ぶ。
「働き意欲があって、その能力があるなら、高齢であることを理由に一律退職させてしまったら、
会社にとっても、本人にとっても損失になる」と前川は説く。
そして自著では「定年のない会社がイノベーションを遂げる」と明言している。
なぜ前川は「飛躍」できたのか。
食品エンジニアリングへの業容拡大に際して、鶏肉加工ロボットが開発されたからだ。
その開発は、同社の老・壮・青の共同作業によるイノベーションであったという。
野中はこの点をもって、まさに高齢社会のイノベーションのモデルになり得ると述べたのである。
以上