P.F. ドラッカー (著), Peter F. Drucker (原著), 上田 惇生 (翻訳)
ダイヤモンド社
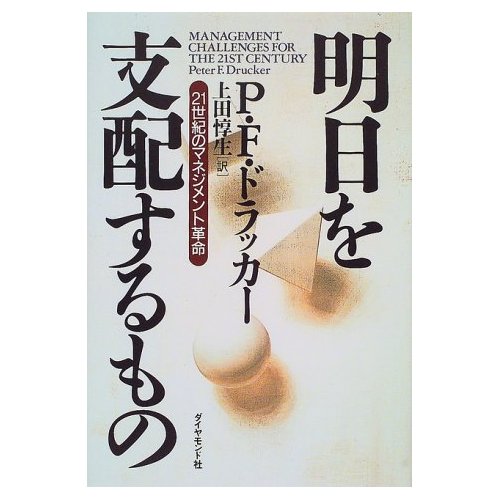
「明日を支配するもの―21世紀のマネジメント革命」
P.F. ドラッカー (著), Peter F. Drucker (原著), 上田 惇生 (翻訳)
ダイヤモンド社
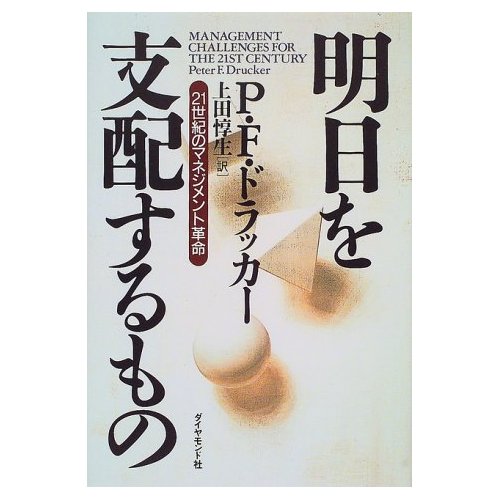
ドラッカーのを通勤途上で読んでいます。
ドラッガーは組織論で有名でありこれまで手にしたことがなかったのが自分でも意外である。
日経新聞の私の履歴書は興味深く読んでいたが、これくらいである。
ということで、せっかくなので最新の著作(1999年)を読んでみることとした。
日本のことをよく知っており、応援してくれていると強く感じた。
非常に示唆に富んだ内容であったが、同時期に読んだトム・ピーターズの主張とも
似通った点も多々あった。
第1章 マネジメントの常識が変わる
○ 仕事マーケティング
○ 非顧客(ノンカスタマー)が顧客以上に重要
最大のシェアを誇るものにとってさえ、非顧客のほうが顧客よりも多い。
ところが非顧客についての情報を持つものは稀である。
変化はつねに非顧客の世界で始まる。
○ マネジメントの役割
マネジメントとは、組織に成果を上げさせるためのものであり、
まず初めにそれらの成果を明らかにし、
次にそれを実現するために、手にする資源を組織化しなければならない。
マネジメントとは、自らの外部において成果を上げるための機関である。
☆マネジメントの世界は組織の内部にあるという前提は今日ではまったく意味をなさない。
第2章 経営戦略の前提が変わる
これからの時代において確実なもの5つ
(1) 先進国における少子化
(2) 支出配分の変化
(3) コーポレート・ガバナンスの変容
(4) グローバル競争の激化
(5) 政治の論理との乖離
(1) 先進国における少子化
ベビーブームによる団塊の世代(その過半数が肉体労働者になあrず、その多くが知識労働者となった世代)
が高年者となる2010年以降退職の意味が変わる。
3,40年に及ぶフルタイムの労働の後であっても、肉体労働による心身の疲労が蓄積されていないために、
その圧倒的に多くが、身体的にも精神的にも働き続けることを望む。
日本が真っ先にこのパラダイムシフトを受けるのである。
これからの経営戦略は、仕事のますます多くの部分、しかも重要な部分が、今日の定年を過ぎた人たち、
幹部でもなければ肩書きもない人たち、従業員でもない人たち、少なくとも毎日出勤してくるフルタイムの
従業員ではない人たちによって行われるようになることを、当然の前提としなければならない。
(2) 支出配分の変化
顧客の全支出のうち、自社が提供するカテゴリーの製品やサービスに使ってもらう割合についての数字である。
この数字の増減を追っている企業は、事実上皆無といってよい。
支出配分の変化こそ、あらゆる情報の基本である。
また同一カテゴリー内での変化も重要。
20世紀の成長分野は、①政府、②医療 ③教育 ④余暇
生産性や産出能力の伸びでは、④の余暇の取り分が他の3つの分野を合わせたものに相当していた
現在の成長産業
20世紀後半30年の成長産業は金融サービス業だった
先進国の中年以降の豊かな人たちの退職準備のための金融サービス
もし長生きしたら退職金では足りない⇒30年後の財政基盤のための投資
(3) コーポレート・ガバナンスの変容
企業は誰のためにあるか。
これからは、ますます多くの人たち、特に高年まで生きることが確実と思われる人たちにとって、
老後の保障は、自らの投資に対する見返り、すなわち企業の所有者としての所得に依存することになる。
したがって、株主にとっての利益につながるかたちでの業績の重要性が減ずることはない。
しかし彼らは、配当にせよ株価にせよ、短期的な利得は必要としない。
問題は20年後、30年後の利得である。
⇒ ザ・ゴールでもこの点は強く感じた
これに加え、あらゆる組織にとって、知識労働者としての従業員のニーズを満足させることが必要となる。
少なくとも彼らを惹きつけ、とどめ、生産的な存在とするために、彼らのニーズを重視することが
不可欠となる。
知識労働者にとって意味があり、彼らのやる気を引き出すような、金銭とはかかわりのない成果についても
明らかにしなければならない。非金銭的な見返りが必要とされている。
今やあらゆる組織が、自らにとっての成果の意味を徹底して検討する必要がある。
成果とは、これまでは当然かつわかりやすいものだった。だが、もはやそうではない。
組織としての経営戦略を、その成果について新しい定義を前提として組み立て直さなければならなくなっている。
⇒ まったくの同感である。これは自分で気がついていることと同じでわが意を得たりで痛快であった。
(4) グローバル競争の激化
リーダー企業が基準を決める
(5) 政治の論理との乖離
3つの世界が重なりあっている。
金と情報にかかわる真にグローバルな経済の世界
物の移動が自由であって、サービスと人の移動の障害が大幅に除去された地域共同体の世界
国とそれぞれの地方からなる経済的というよりも優れて政治的な世界
企業はこの3つの世界を同時に生きなければならない。
第3章 明日を変えるのは誰か ◎チェンジ・リーダー
● チェンジ・リーダーにとっての3つのタブー
① 現時と平仄(ひょうそく)が合わないイノベーションを手がけること
少子化、支出配分の変化、コーポレート・ガバナンスの変容、経済のグローバル競争の激化、政治の論理との乖離など
新しい現実と平仄が一致するイノベーションが成功する
② 真のイノベーションと単なる新奇さを混同すること
③ 行動と動作を混同すること
組織改革は動作に過ぎない。それは、何をいかに行うかという問題に取り組んだ後に行うことである。
これら3つのタブーはあまりに魅力的である。
この罠から逃れる方法は唯一つ、変化の初期段階を組織化すること、すなわちパイロットである。
○ パイロットの効果
蒸気機関はワットが発明し、産業革命をもたらしたとされている。
しかし、ワットが考えた使途はひとつ、「炭鉱の排水」だった。
売り込み先も炭鉱会社だけだった。
産業革命の父の名に本当に値したのは、彼のパートナー、「マシュー・ボールトン」だ。
彼は、当時イングランドの最大の産業だった繊維産業、特に綿の紡績に蒸気機関が利用できるはずと考えた。
事実、彼が初めて紡績会社に蒸気機関を納入した15年後には、綿糸の価格が7割下がった。
その結果、史上初めて大衆市場が生まれ、今日の意味での工場が生まれた。
近代資本主義が生まれ、近代経済が生まれた。
第4章 情報が仕事を変える ◎新情報革命
○ 技術(T)から情報(I)へ
第5章 知識労働の生産性が社会を変える ◎先進国の条件
○ テイラー(1856~1915)の偉業
自ら肉体労働と肉体労働者を経験し、新しい技術や道具ではなく、労働の側、すなわち働く者の生産性を向上させた。
テイラーの手法は簡単。
まず、初めに、仕事を個々の動作に分解する。
次いでそれらの動作に要する時間を記録する。
次にムダな動作を探す。
実際に肉体労働の仕事を分解してみると、伝統的に絶対とされてきた動作のきわめて多くがムダで役にたたないことが明らかとなる。
次にこうして不可欠なものとして残った動作を短い時間で簡単に行えるようにする。
そして、それらの一新された動作を組み立て直す。
テイラーは仕事に知識を適用した最初の人であった。
TQCもテイラーの手法である。
米軍はテイラーの科学的管理法を軍事に利用して成果を上げた。
日本も戦後、この手法によった。
○ 先進国の運命を決める知識労働の生産性
テイラーの手法は「肉体労働者」のものであり、知識労働には適用できない。
先進国における中心的な課題は、知識労働の生産性の向上である。
生産性向上の条件
(1) 仕事の目的を考える
(2) 働く者自身が生産性向上の責任を負う。自らをマネジメントする。自律性を持つ。
(3) 継続してイノベーションを行う
(4) 自ら継続して学び、人に教える。
(5) 知識労働の生産性は、量よりも質の問題であることを理解する。
(6) 知識労働者は、組織にとってのコストではなく、資本財であることを理解する。
知識労働者自身が組織のために働くことを欲する。
6番目の条件以外は、肉体的労働者の生産性向上のための条件とは、ちょうど逆である。
肉体労働においても仕事の質は重要であるが、制約にすぎない。
最低の条件があるだけである。TQCの偉業はこの基準を下回る製品をゼロ近くまで減らしたこと。
これに対し、知識労働では、仕事の質は制約どころではない。仕事の本質である。
(1) 仕事の目的を考える
知識労働の生産性の向上のために最初に行うことは、行うべき仕事の内容を明らかにし、その仕事に集中し、その他のことはすべて、
あるいは少なくとも可能な限りなくしてしまうことである。
だが、そのためには知識労働者自身が、仕事が何であり、何でなければならないかを明らかにしなければならない。
これらの問いかけを行い、答えにしたがって行動するならば、知識労働の生産性は2倍、3倍に急増する。
病院での例 ⇒ これは驚いた。
看護婦の答えは2つに分かれた 患者の看護と医師の補助
しかし生産性を邪魔していることは一致
それは書類書き、花生け、電話の応対という雑用だった
これをアウトソースしたことにより看護婦の生産性は上がり、患者の満足度も倍以上になった。
そして中途退職が激減した。
これらのことが4ヶ月間で起こった。
○ テクノロジスト(高度技能者)が鍵
AT&Tの例
電話工の仕事の質を定義し直した。
電話工は一人で働いており監督するわけにいかなkった。
そこで彼ら自身に定義させた。
20件か30件に1件の割合で監督がチェックに出かけることにしたが、客に面倒がられ、電話工を不愉快にさせるだけだった。
そこで、仕事の質を苦情件数で判断することにした。
これは電話工自身に仕事の質を管理させるということだった。
知識労働者であるとともに肉体労働者である人たちの生産性向上の条件は以下の3つ。
・仕事は何かという問いかけを行う
・彼らテクノロジストの仕事の質を担保する
AT&Tの例では電話工自身が顧客満足をもたらす責任を負った
この認識があって、はじめて手にすべき体系的知識が明らかとなる
・テクノロジストは知識労働者であることを認識すること
○ 仕事マーケティング
知識労働が主体となってきた現在はマネジメントは命令と服従の関係ではない。
上司と専門家の関係は、オーケストラの指揮者と演奏者の関係に似ている。
従業員は仕事のパートナーとしてマネジメントしなければならない。
パートナーシップの本質は対等性にある。
パートナーに対しては理解を求めなければならない。
知識労働者の動機付けは、ボランティアの動機付けと同じ。
ボランティアは、まさに報酬を手にしないがゆえに、仕事そのものから満足を得なければならない。
組織の使命を知り、それを最高のものと信じられなければならない。
とくにこれからは、人をマネジメントすることは、仕事をマーケティングすることを意味する。
マーケティングの出発点は、組織が何を望むかではない。
相手が何を望むか、相手にとっての価値は何か、目的は何か、成果は何かである。
つまり、適用すべきはX理論でもY理論でもなく、いかなる管理論でもない。
そもそも問題を定義しなおさなければならない。問題は人の働きか方についてのマネジメントの
仕方ではない。理論においても実務においても、問題は成果についてのマネジメントの仕方である。
ちょうどオーケストラやフットボールの中心が音楽や得点であるように、人のマネジメントの中心になるべきものは成果である。
100年前に肉体労働の生産性が中心的な問題であったように、知識労働の生産性が中心的な問題となる。
これは人と仕事についての前提を大幅に変えなければならないことを意味する。
すなわち、行うべきは、人をマネジメントするのではなく、リードすることである。
その目的は、一人ひとりの人間の強みと知識を生産たらしめることである。
☆ 資本財としての知識労働者
⇒ 「資本としての人」という言葉に初めて接して新鮮な思いをしました。
○ 資本財としての知識労働者
肉体労働者と知識労働者の違いは、彼らをめぐる経済的な原理において最も大き
い。
経済学も、現実の経営者も、肉体労働者をコストとして扱う。
しかるに、知識労働者を生産的な存在とするためには、資本財として扱わねばなら
ない。
コストは管理し、減らさねばならないが、資本財は増やさなければならない。
… …(例示がいくつか)
肉体労働を行うものは、生産手段を所有しない。
経験は豊富かも知れないが、その経験も、ほとんどの場合、彼らが働いている場所
においてでしか価値がない。
持ち運びできるものではない。
ところが、知識労働者は生産手段を所有する。
頭の中にしまわれた知識は持ち運びができ、大きな価値を持つ。
まさに生産手段を所有するからこそ、彼らの流動性は高い。
もちろん彼らが特定の組織を必要としないわけではない。
彼らのほとんどは、組織と共生関係にある。
彼らと組織はお互いを必要とする。
だが彼らは、近代工業における肉体労働者のように、
仕事が彼らを必要とする以上に、彼らが仕事を必要とすると片づけることのできな
い存在である。
経営陣の職責のひとつに、資本財の保全がある。
このことは、知識労働者のもつ知識が資本財となり、しかもそれがますます重要に
なりつつある今日、何を意味するか。
労務管理上いかなる意味を持つことになるか。
最高の労働者を惹きつけ、とどまらせるためには何が必要か。
彼らの生産性を向上させ、組織の業績に結びつけるためには何が必要か。
(このテーマはまさに我々のテーマですよね)
…… 大幅に飛ばして
やがてまもなく、コーポレート・ガバナンスについては、もう一つ大きな波がやっ
てくる。
すなわち、法的な所有者の利益とともに、知識労働者、すなわち組織に富の創出能
力を与える存在としての人的資源の利益の観点から、
雇用主としての組織とその経営を見直さなければならなくなる。
なぜならば、企業、さらにはあらゆる種類の組織にとって、自らの生存は、知識労
働者の生産性によって左右されるようになるからである。
まさに、最高の知識労働者を惹きつけ、とどめる能力こそ最も基礎的な生存の条件
となる。
しかし、果たしてこの能力は、定量的に評価できるであろうか。
それとも把握不可能だろうか。
これからはこの問題が、経営陣、投資家、資本市場にとって最大の関心事となる。
さらには、資本ではなく知識労働者が統治の主体となったとき、資本主義は何をと
は何を意味することになるか。
知識労働者が、知識を所有するがゆえに、唯一とも言うべき真の資本財となったと
き、自由市場とは何を意味することになるのか。
知識労働者は、いかなるものであれ、売買の対象とはならない。
企業買収や企業合併によって自動的に手に入れることはできない。
価値ある存在でありながら、彼らにはいわゆる市場価値なるものはない。
伝統的な意味における資産ではないということである。
これらの問題は、私の能力を越えることはもちろん、本書の領域をも越える。
しかし、知識労働者の興隆と、知識労働の生産性の重要度の増大が最大の問題と
なったということは、
今後数十年のうちに、まさに経済体制そのものの構造と本質に、基本的な変化が生
じざるを得なくなったことを意味する。
☆ これまでの100年間は、肉体労働の生産性向上に成功した国や産業が世界経済のリーダー役となった。
初めにアメリカ、次いで日本とドイツが続いた。これに対し、これからの50年間は、世界経済のリーダー役
となるのは、知識労働の生産性向上に成功した国や産業である。
第6章 自らをマネジメントする ◎明日の生き方
これから、組織に働く人たち、特に知識労働者たるもいのは、自らの組織より長生きする。
労働時間は50年に及ぶ。
仕事を変えることができなければならなくなる。キャリアを変えなくてはならなくなる。
知識労働者のほとんどが、自らをマネジメントしなければならなくなる。
自らを最も貢献できるところへ位置づけ、つねに成長していかねばならない。
マネジメントの問題
(1) 自分は何か、強みは何か
(2) 自分はところを得ているか
(3) 果すべき貢献とは何か
(4) 他との関係において責任は何か
(5) 第二の人生は何か
○ 書面か口頭か
仕事の仕方で知っておくべきことが、自分は読む人間か、聞く人間かである。
世に中に読み手と書き手がいるということ、しかも両方できる人はほとんどいないということを知らない人が多い。
自分がそのいずれかであるかを認識している人はさらに少ない。
これを知らないことがいかに大きな害を及ぼすかとの実例。
・アイゼンハワー大統領
ヨーロッパ最高司令官時代は記者会見の花形 あらゆる質問に答えられた
大統領になった途端に同じ記者たちにバカにされることとなった
???
アイゼンハワーは、自らが読んで理解する読み手であった
最高司令官時代は30分前に広報担当者が記者の質問を書いて渡していた
大統領は前任のルーズヴェルトとトルーマンはどちらも聞き手だった。
二人はそのことを知っており「自由質問」による会見を楽しんでいた
ルーズヴェルトにいたっては二人の閣僚による小1時間の解説を頼み、彼らへの質問も口頭だった。
アイゼンハワーは同じようにしないといけないと思い込んでいた。
耳では記者たちの質問を理解できなかったのである。
その数年後はジョンソン大統領が自分は聞き手であることを知らないために評判を落とす。
ケネディは自分が読み手であることを知っていた。最高の書き手を集め、問題の検討に必ず書いたものを要求した。
ジョンソンはそれを引き継いだために失敗した。
書いたものを理解できなかった。議員はだいたいが聞き手なのである。
これは右ききか左ききかといったようなもの。
左ききは10人に一人くらい。
聞き手が読み手になるのは、またその逆も難しい。
⇒ これがショックだった。
そして自分は果してどちらなのだろうか?と分からなくなった。
おそらくは「読み手」人間のタイプだと思うが自信はない
・学び方
世界一流の著述家の多くは学校の成績が悪い。
原因は、彼らが、聞くことや読むことによっては学べなかったことにあった。
彼らは、自らが書くことによって学ぶという種類の人たちであった。
そのような学び方を許している学校はなかった。
学び方は人によって違う。
GMのスローン
彼が必要としていたのは話しを聞いてくれる者だった。
必ず答えを出させた。 イエス、ノー、条件付きイエスの3つ
CEOとして極端であるが成功している医師や弁護士に多い
ベートーヴェン 膨大なメモ
優れた学術書を書いた大学教授
教えているのは自分が話しをするのを聞きたいからだ。そうすることによって初めて書けるようになる
⇒ 知ってわかったことを私は第三者にすぐに話すことにしている
これは自分が話すのを聞いて勉強しているのかも知れない。
今後も続けていこう
・価値あること
組織には価値観がある。そこに働く者にも価値観がある。
組織において成果を上げるためには、働く者の価値観が組織の価値観になじむものでなければならない。
同じである必要はない。だが共存しなければならない。
さもなければ、心楽しまず、成果も上がらない。
ドラッガー自身1930年代半ば、ロンドンの投資銀行で働き、順風満帆だった。
強みを存分に発揮していた。しかし、資産管理では世の中に貢献しているという実感がなかった。
彼にとって価値あるものは、金ではなく人だった。
金持ちになることに価値を見出せなかった。
大恐慌のさなかにあって金も見通しもなかったが辞めた。正しい行動だった。
優先すべきは価値観の方である。
○ 果すべき貢献
自分の果すべき貢献を考えることは、知識の段階から行動の段階への起点となる。
貢献したいと思うかでない。
何に貢献せよと言われたかでもない。
何に貢献すべきかである。 ⇒ ガーン!
このような問題が成立すること自体、人類にとっては初めてである。
誰にとっても貢献すべきことはきまっていた。
農民や職人のように、仕事できまっていた。
今日、知識労働者の興隆が状況の変化をもたらしつつある。
すでに日本以外の先進国では、組織人間なるものや人事部主導の人材開発などは、遠い昔のことである。
そもそもキャリアは、本人以外の者が計画できるものではなく、すべきものではないとされている。
自らの貢献は何かという問いに答えを出すための要素
・状況が求めるもの
・自分の強み、仕事の仕方、価値観
・成果の意義
単に好きなことをするというだけでは、自由はもたらされない。きままに過ぎない。
それではいかなる成果も上げられない。いかなる貢献も行えない。
自分の果すべき役割は何かという問いからスタートするとき、人は自由となる。
責任を持つがゆえに、自由となる。
○ 関係にかかわる責任
読み手が書き手に変わることは稀である。逆も稀である。
しかし報告するほうとしては、報告書を書いたり、あるいは口頭で説明する能力を一応の水準までもっていくことはできるはずである。
上司に仕事をしやすくさせることは、部下のつとめである。
そのためには、上司を観察し、彼らの強み、仕事の仕方、価値観を知るだけでよい。
これこそまさに、上司をマネジメントするうえでの秘訣である。
これとまさに同じことを、共に働く人全員について行わなければならない。
人によって彼らの強み、仕事の仕方、価値観が違うのが当たり前である。
成果を挙げる秘訣の第一は、共に働く人たち、自らの仕事に不可欠な人たちを理解し、
その強み、仕事の仕方、価値観を活用することである。
仕事とは、仕事の論理だけでなく、共に働く人たちの仕事ぶりに依存するからである。
組織は、もはや権力によっては成立しない。
信頼によって成立する。信頼とは好き嫌いではない。信じ合うことである。
そのためには、互いが理解していなければならない。
互いの関係について互いに責任を持たなければならない。それは義務である。
組織の一員であろうと、組織のコンサルタントであろうと、取引先であろうと、流通業者であろうと、
共に働く者は、互いの関係についての責任がある。
付録 日本の官僚制を理解する
日本の官僚がいかに考え、いかに働き、いかに行動するかを理解するうえで必要なことは、日本にとっての優先順位を知ることである。
アメリカは安全保障に次いで経済
日本は最も重要なのは「社会」である。
日本が一般的でアメリカが例外。
政治にとって、経済は唯一の関心事ではないことはもちろん、最大の関心事でもない。
制約条件に過ぎない。
理念と社会こそ、最も重要である。
⇒ 納得である。