真山仁 著 東洋経済印刷
http://www.toyokeizai.co.jp/pub/recommend/06147-06148/index.html
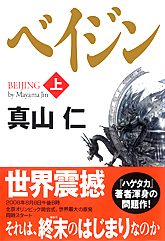
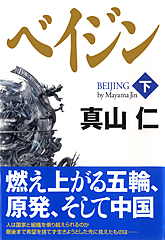
舞台は2008年8月8日の北京。そう、北京オリンピックの開催日にいったい何が…
世界最大の原発“紅陽核電”運転開始と北京五輪開幕の同時スタート。その時、希望と絶望が訪れる
同期入社のMさんから薦められて読んだ
筆者は、若いけれども古きよき日本の価値観を持つ人だと思う。
だから、すんなりと読める。
我々世代に受ける理由だろう。
これが真山さんの真心から出た訴えであり、そこを狙って書いたたものでないこと
を祈りたい。
若干そんな懸念も受けてしまうので。
ホリエモン騒ぎのときに「ハゲタカ」が出たタイミングといい、
北京オリンピックにあわせての出版というのも、何か我々世代がマーケティングさ
れたのでは
ないのだろうかという疑義が湧いてしまうのである。
いろいろなものを問題提起し、(今回は中国という国の価値観、生き様)、
古き良き時代の日本の持つよい価値観を維持すべきというのが筆者の意図のように
感じる。
ちょっと軽い感じだが、響いてくるものはある。
(東洋経済印刷のHPより)
「偉くなれ。偉くなって、この理不尽な国から絶望や嘆きを消して、希望の国にしてくれ」
北京(ベイジン)五輪、原発、そして中国をテーマに絶望と諦観を、希望に変える闘いが始まる。
2008年8月8日、五輪開幕に沸く中国・北京。
メインスタジアムでは、世界最大規模の原子力発電所「紅陽核電」から、運転開始を伝える光が届いた。
だが、それ は、世界中の人々の命をおびやかす、絶望的なクライシスの始まりだった……。
時は遡り、2005年。大亜重工業の田嶋伸悟は、大連郊外に建設する「紅陽核電」の技術 顧問として参画するため、中国に到着。
同じ頃、中国共産党中央紀律委員会のドン学耕(ドン・シュエグン)は、中国側の責任者として同地に赴く。
ドンには、大連市での党要人の汚職摘発という〈密命〉も課されていた。
二人は、さまざまな困難に遭遇しながらも、核電完成のために悪戦苦闘を続ける。
そして迎えた五輪開会式当日、田嶋は本格送電の直前に事故の予兆を感じ、
<上巻>
序章 開幕一時間前
第1章 ミッション
第2章 郷に入っては
第3章 嵐の中で
第4章 柳絮(りゅうじょ)は風に
<下巻>
第4章 柳絮は風に(承前)
第5章 鉄飯椀(ティエ ファン ワン)
第6章 カウントダウン
第7章 ブラックアウト
■著者紹介
------------------------------------------------------------------
作者は真山仁さん。
http://www.mayamajin.jp/index.html
代表作は「ハゲタカ」
これはNHKで土曜日のドラマとして放映されたのを見ていたので知っていた。
http://www.nhk.or.jp/hagetaka/
ハゲタカでは従業員による会社買収:EMOということばに感激した。
Management Buy Out :MBOは知っていたが、
まさか従業員が会社を買うことがあるのかという驚きであった。
Employee Buy Out エンプロイー・バイアウト、EBO
(注) 上記NHKのHPより
経営陣が中心となって自分達の会社や事業部門を株主から買い取り独立する行為を
マネジメント・バイアウト(Management Buy-Out、MBO)というが、経営陣ではなく
従業員が中心となって行う場合はエンプロイー・バイアウト、EBOと呼ばれる。(因
みに経営陣と従業員が一緒に行う場合はMEBO)
さて本書のテーマは、中国で、世界最大原発を北京オリンピック開幕日(2008.8.8)にあわせて運開させるという
国家プロジェクト。
伊方発電所と同じPWRであり、三菱重工や日本原子力発電などと重なる
しかし四国電力の名前がなかったのが寂しいなあ
---------------------------------------------
上巻33ページ
…。
もうひとつが、嶺南3号機(敦賀3号機)のようなPWRだ。
…。
関西電力や北海道電力、九州電力などが、このタイプを採っている。
--------------------------------------------------
ハゲタカでも感じた作者のテーマだが、台風で被災した作業員の慰霊祭をやろうとする田嶋の言葉に出ている
「何が足りないか。その答えが掴めた気がする」
「何です?」
「一体感だよ。確かにおまえさんが言うとおり、技術顧問は皇帝のようにどっしり
と構えているべきかも知れない。
だが、俺は民の中にいたい。舐められかも知れないが、それ以上に一体感を大切に
したいんだ」
「しかし、慰霊祭は民工自身が望んでいません」
なおも引き下がらない大町に、田嶋は柔らかな笑みで答えた。
「そんなことはない。昨夜夜、文監督と飲んだんだ」
文監督とは、嵐の夜に田嶋に掴みかかった現場監督だった。
「彼に、俺の想いを伝えた。そしたら、奴は俺に抱きついて泣いてくれたよ。日本
人は好きじゃないが、
おまえは親友だと」
「そんなことまで……」
…
「慰霊祭は、鎮魂のためだけにやるんじゃないよ。生き残った人たちにも必要なんだ。」
「それはこの国の習慣にないことです。」
「ならば、ここだけのやり方を作ればいい。見ろ、絶対に根付かないと言っていた挨拶だって、連中は
口にするようになったじゃないか」
日本の原子力発電所では定番の「ご安全に」とう挨拶も定着している風景が出てきた。
「一体感」 組織としての一体感、これはまさに私自身のテーマでもある。
ハゲタカで「EBO」に感激したのもそういうことだ。
毎夜それは生まれ、毎夜それは消えるもの それは希望
希望という言葉もキーワードとなっている。
トゥーランドット姫 3つの難問 オペラ
http://ww3.enjoy.ne.jp/~oyf/turandoto.htm
http://www.tvq.co.jp/ana/kaji/2006/12/post_184.html
これが出てくるのはIAEA本部のあるウィーンでのこと。
ネットで調べるまで、トゥーランドット姫が中国北京の王女とは知らなかった…。
あらすじはこちらでわかった。
http://homepage3.nifty.com/akoda/kansho/opera/opera40.html
【下巻】
戦艦大和の西島大佐のことを父が語って、田嶋の人生の目標となった。
大佐のすごさは、決して言い訳をしない男気じゃ、部下の責任をすべて被った。
まさに、人の上に立つ人物の鑑だ
⇒ 西島大佐の本を読んでみようと思う。
その田嶋の言葉
「諦めからは何も生まれない。希望とは、自分たちが努力し、奪い取るものだ」
「やればできるんだ」ではなく、「やらなければできないんだ」という西島技術大佐の言葉
「原発は、我々に素晴らしい恩恵を与えてくれる。だが、人間の心に隙が生まれた瞬間、神の火は、悪魔の劫火に変わる」
ただ、ブラックアウトになるが、その設定には大いに疑義がある。
● 建設中は、余所から送電してもらわなければならず、工事用送電線を使った送電を、地元電力会社に依頼していた。
そして「2日前まで核電につながっていた工事用の送電線が、根こそぎ盗まれています」
運開前のことである。
☆外部電源がつながれていない状態では運転できない。
ディーゼル発電機の信頼性以上の話しである。
ここがよくわかっていないのだろう。ちょっとひどいと思った。
そのほか、ありえないような話しがボコボコ出てくる。
蒸気発生器の伝熱管の材質が違う ⇒ 誰が検査しているのだ。 ありえない。
耐震設計の問題 ⇒ 手抜き工事
ラジオの管理区域内持込 田嶋は最後は黙認したが、このラジオが格納容器内で発火して火災になってしまう。 そんなのアリか。
シビアアクシデント対策については、断片的に書かれているが、ちょっと無理筋が目立つ。