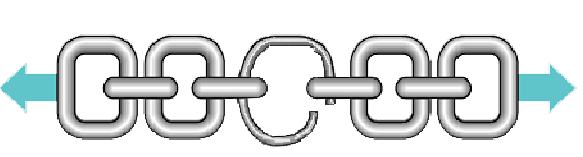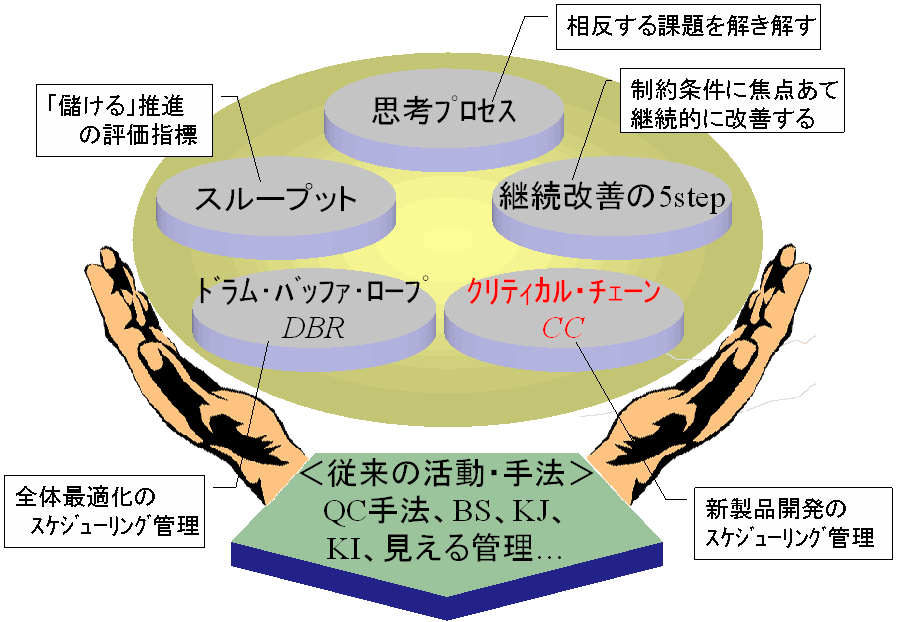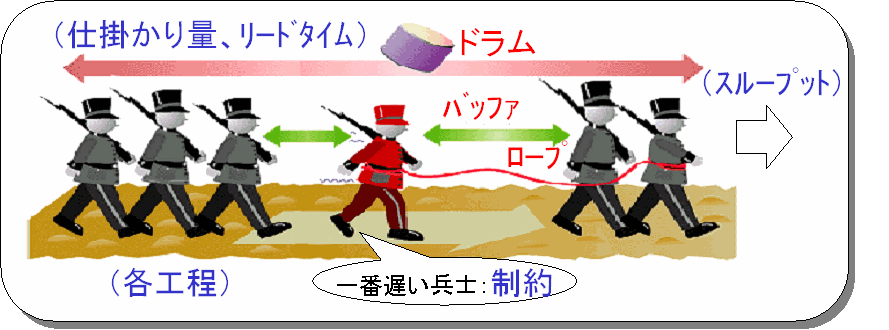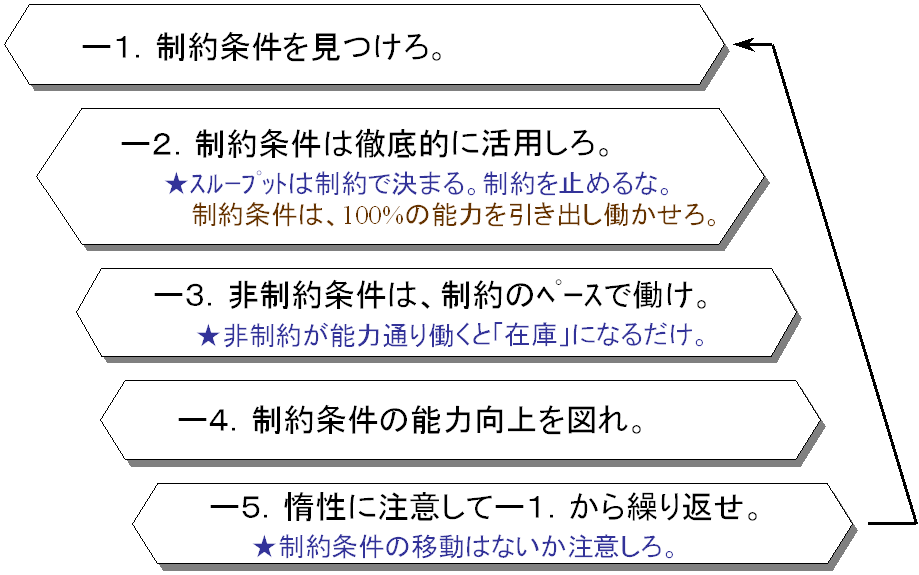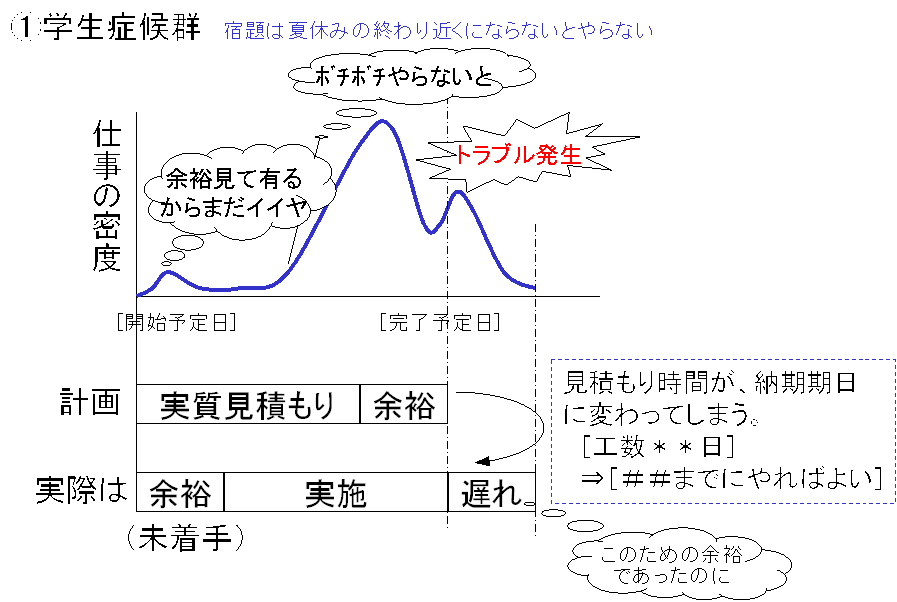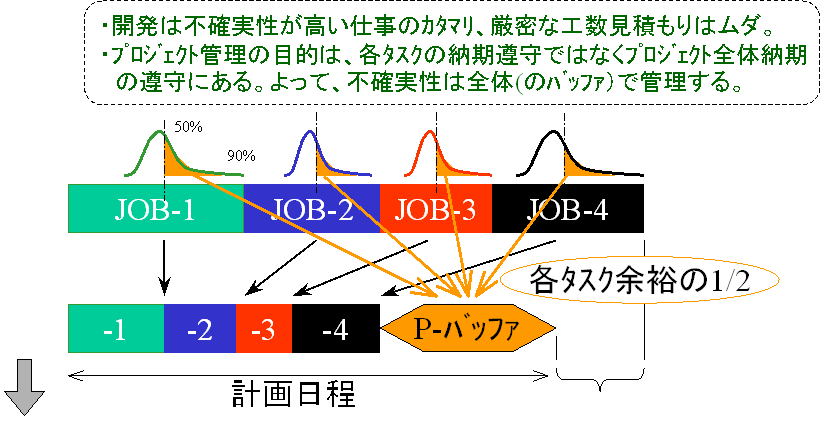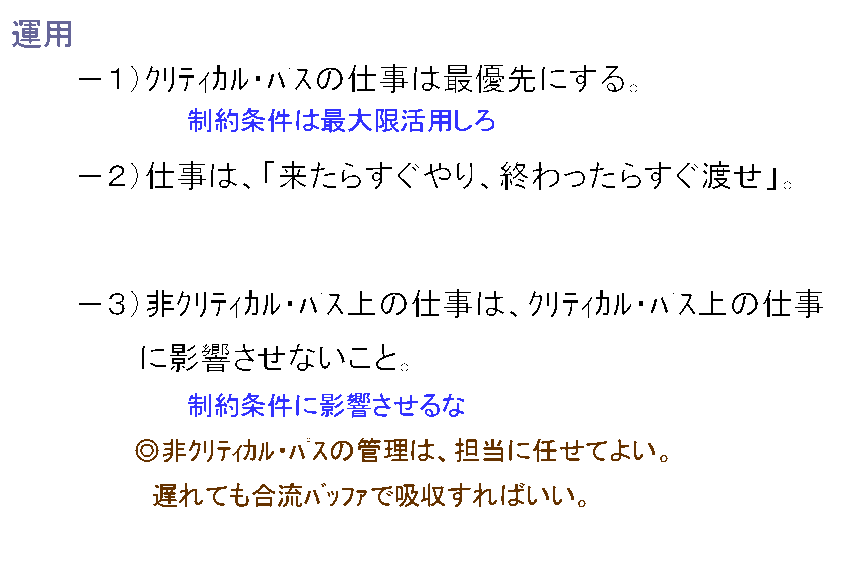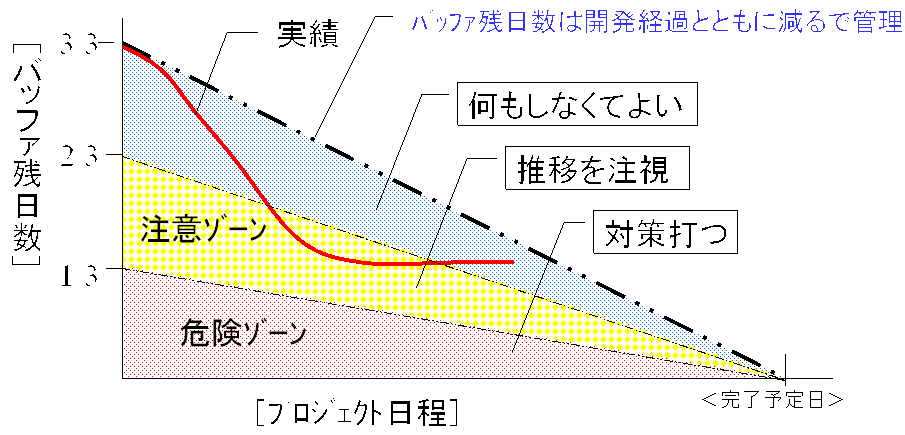クリティカル・チェーン
TOC(制約条件の理論:Theory of Constrains)のプロジェクトマネジメントへの適応編。
ビジネススクールでの学生達との議論で中身がよくわかるようになっている。
学生達は座学ではなく、実際の自分たちのプロジェクトでの問題解決を図っていくのである。
どんなものでのWin−Winの解決があるはずだ。それがTOCの精神。
それがどこまでも貫かれる。
リック先生が主人公。一人称で多く登場するがその他のメンバーもみんな主役だ。
いろいろな業界の問題解決を生徒とともに考えて実現してゆく。
その痛快さが小説として読みやすくしている。
リック自身が、将来の見通しを得られないことや、
浪費癖のある妻ジューディースとの夫婦関係で悩ましこと
代理出産を決意することは、これまでのゴール1,2での
良妻との関係とは違う設定でとまどった感があった。
ここまで追い込むこともないのではないかと思ったが、はらはらさせられる面ではあった。
代理出産費用が融資との関係で気づきになっているところはうなったが、
ちょっと設定としては気に入らないものであった。
ポイントは制約条件を見つけて、そこをベースにペースを合わせ、制約条件の能力向上を図るということを
繰り返すことによって飛躍的に改善されるということ。
これを製造でなくマネジメントにも展開したのである。
個別のセーフティをはがして、目標達成の前にバッファーとしておくことで納期は半分にできてしまうので
ある。個別見積もりでは50%でなく80,90%カバーするセーフティを入れてしまうからである。
全体最適、スループット管理である。
なお、リソースの競合がある場合にクリティカル・チェーンという言葉が生まれたのであった。
このあたりを非常にうまくまとめている資料を自己実現道場でいただいた。
肝の部分だけ拝借させていただく。
-------------------------------------------------------------------------
優先順位に関する理論:重要なことを大事にし、重要なところへ集中
鎖の強度は、一番弱いところで決まる。
弱いところ以外を補強しても、強度アップにならない。
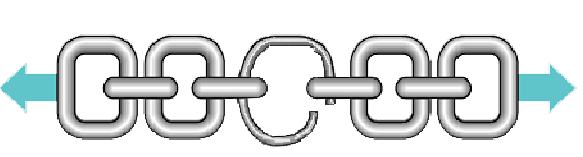 TOCの手法
TOCの手法
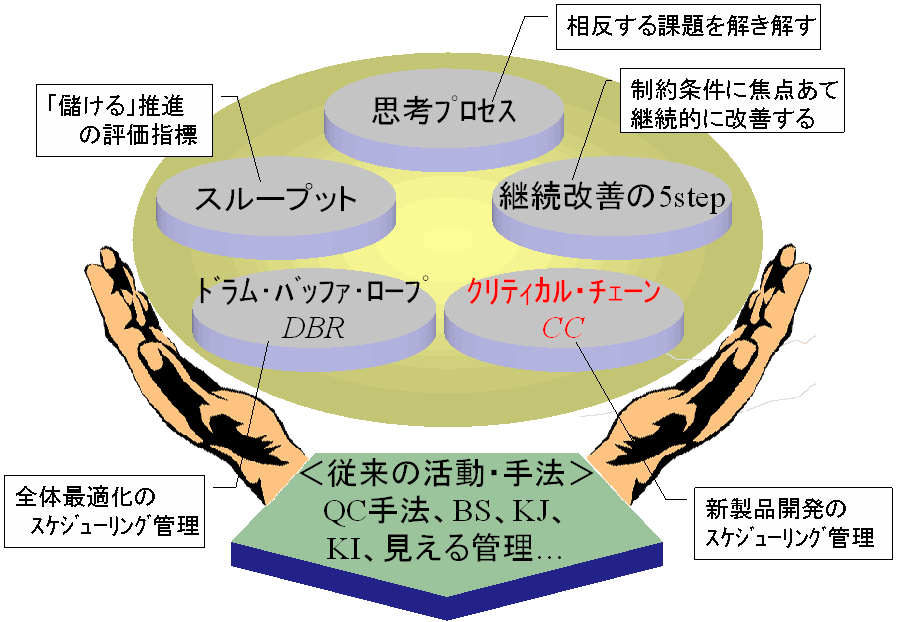
・隊列の乱れは必ず起きる。
・隊列は,一番遅い兵士より速く進められない。制約条件
・隊列全体の最大速度のためには、一番遅い兵士を立ち止まらせるな。
・他の兵士は、一番遅い兵士の歩調に合わせろ。ドラム
・一番遅い兵士が転んでも、全体に影響でないように前後に間隔を作っ ておけ。バッファ
・先頭の兵士は、一番遅い兵士に合わせて歩け。ロープ
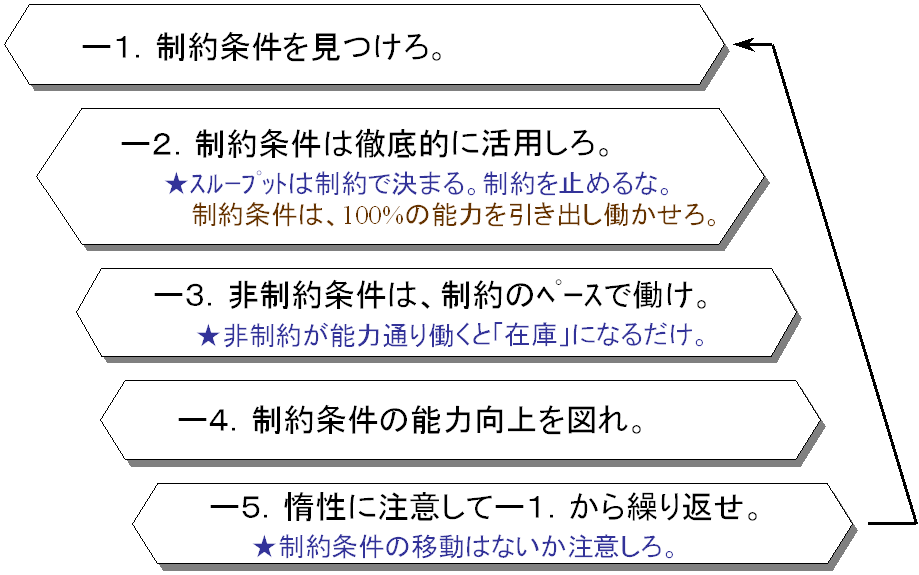
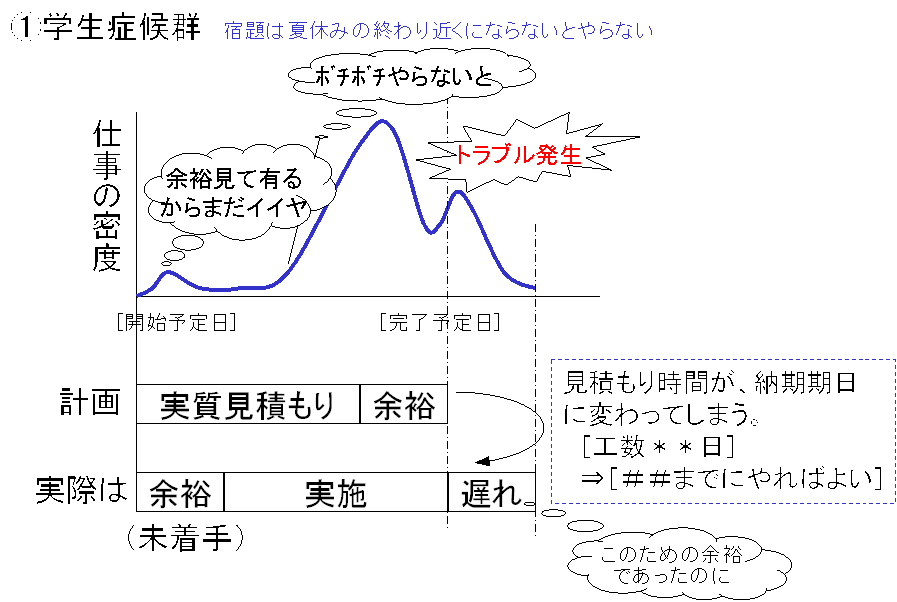
プロジェクト・バッファの設置
:クリティカル・パス上の最終タスクの後にバッファ(余裕日程)設置
・各タスクの見積もり工数は完了確率50%の工数使用。
・バッファを一カ所に集める。:プロジェクト・バッファ
・バッファサイズは、全安全余裕の1/2:全タスクが遅れる確率は低い
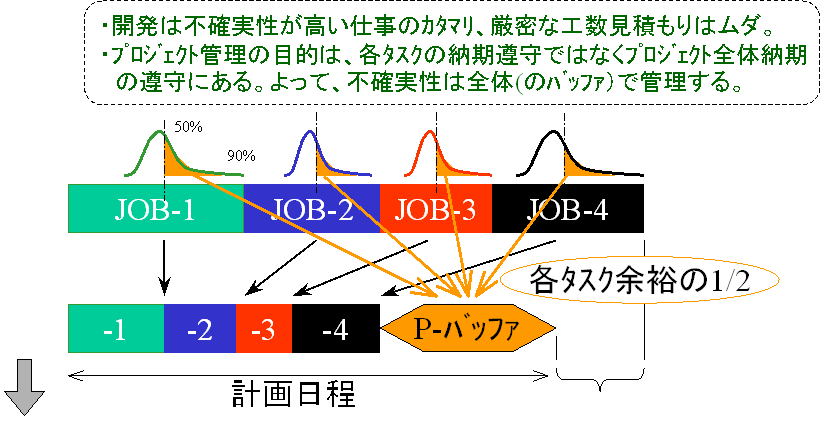
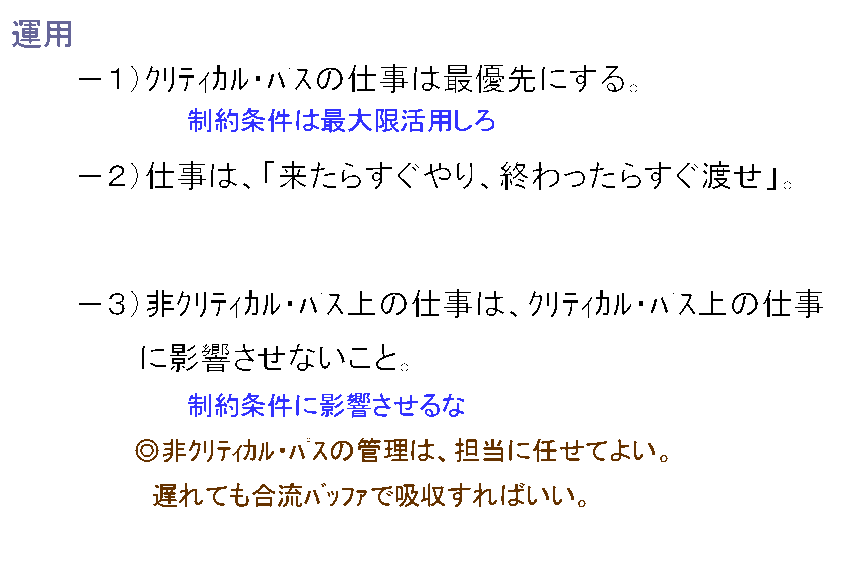
◆スケジュール管理方法
スケジュールの管理はプロジェクト・バッファの残日数で管理する。
☆クリティカル・チェーンは、「遅れを前提とした計画」である
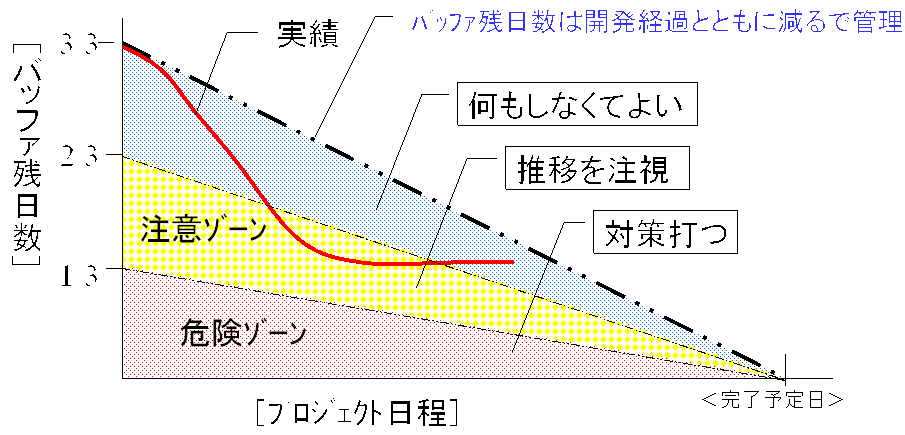
後は本のなかでの記載で付箋をつけたところ抜き出しておこう。
○ 甘いのでは?
人を増やしてプロジェクトの管理・監督を強化すれば?
人が増えるということは、作業調整のための時間と労力も増えるということ。
人が倍になれば、調整努力は4倍必要になる。
今でも作業調整のために無駄な会議が多すぎるとクレームが出ている。
⇒ ここは正確でないのではないかという疑問。
筆者は数学者なのにちょっと甘いのでは?
2人なら関係は1本
4人なら関係は 4×3÷2=6本で 6倍だ
20人なら 20×19÷2=190
○ 確率分布
行動と結果には不確実性がある。確率分布の表を書いて、どこにその作業の見積もり時間を設定するか?という
場面。これは非常によくわかった。
人間はどうしても余裕をたくさん見てしまうというのがよくわかった。
○ 安い業者を選んでどれだけ節約できたか
信頼できる業者よりもコストの低い業者を選んでいることに関して (よくあること)
どれだけのコストが節約されたか?
せいぜい5%程度
プロジェクトが遅れた理由は、実はコストの低い業者から機械の納入が遅れたのが一番大きな原因だった
機械のコストは5%節約できただろう。投資全体からするとたぶん3%程度。この節約のせいで、3年で
ペイバックできるプロジェクトが台無しに。
後半ではこの問題に対して以下の解決を図っている。
納期を早くすると高い金額を支払うという条件で業者と折り合いをつけ、
不確実性を減らす(発注の10日前に予告)ことに成功している。
○ 適切なコントロール・メカニズム
プロジェクトをマネジメントする何かいい方法はないか?
注意が散漫にならないようにする。
この答えは上記でまとめていることである。
○ 個別最適は誤り
優れたコスト・パフォーマンスを実現するには、優れたローカル・パフォーマンスを図るしかない。
企業やマネージャの多くは、この仮定が正しいと考え、これにしたがって行動している。
TOCでは、これが今日企業が抱える一番の根本的問題。
あるものは在庫の山ができ、あるものは在庫切れがあり全体としてスループットが増えない事態。
○ 前工程が早く終わっても
もともと予定していたタイミングでスタートします。
予定より早く作業を終わらせても、最初のステップはそれを報告しないから。
作業を早く終わらせてもご褒美はない。
いやそれどころか、もし早く終えたら、次からは早くしろとプレッシャーをかけられる。
だから適当に時間をつぶす。
○ セーフティがムダにされる3つの理由
学生症候群 ギリギリまで作業に取り掛からない
作業の掛け持ち
ステップ間の従属関係
○ 納得させる時代
どんな時でも周りの協力は必要。
ちゃんと説明して納得させたうえで、協力してもらわないといけない。
ただ人に命じて仕事をさせる時代は終わったのだ。
みんなに自分で考え、自らイニシアティブをとってもらうには、
ただ人に命じるだけではダメ。
○ Win−Loseは×
リードタイムはお金を出して買わねばならない。
建築業者は、決して自分たちからリードタイムを短くしようとはしない。
それは自分たちの利益に反するから。
すなわち下請け業者のプラスは、デベロッパーにとってはマイナス。
制約条件の理論では、そんなことはあり得ない。
Win−Lose(片方が得をして、もう一方が損をする)のシチュエーションなど
存在しないんだよ。
⇒ 力強い!! 非常に感銘をうけたところだった。
Win−Win達成のためにはコンフリクトを見つけ、制約条件を見つけろと説く
この場合の解決策はちょっと難しかったが、以下のものとなった
デベロッパーが入札を受け付ける際に、リードタイムを短くすることと、もしそれを果たせない場合は
大きなペナルティを課すことを条件として明記すれば、他の業者は怖がって誰も入札しない。
デベロッパーの投資利益率はずっと高くなるし、リスクも軽減できる。
一方、仕事が取れた下請けは大きな利益が得られる。
⇒ 短くする場合のボーナスではなくダメな場合のペナルティを課すことで不確実性をなくして
発注者としての利益を上げる。なるほど。
WIN−WINを目指せ!
TOC万歳。