「黙ってられるか」
川淵 三郎/著 新潮社
【内容紹介】
「Jリーグ」を誕生させ、日本をサッカーW杯常連国にまで押し上げ、改革を推し進めてきた川淵三郎が、
指導者論、メディア論、そして日本サッカーへの本音を隠すことなく語り尽くす。渡邉恒雄との特別対談も収録。
【著者紹介】 1936年大阪府生まれ。早稲田大学在学時にサッカー日本代表に選出。
Jリーグ初代チェアマン。日本サッカー協会相談役、日本トップリーグ連携機構会長。
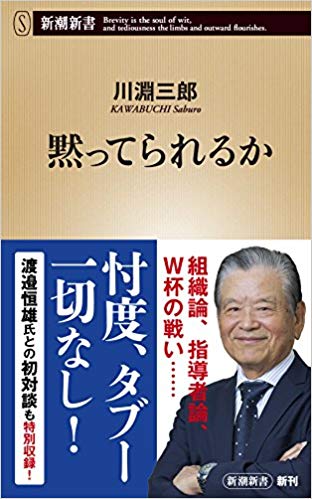
なかなか面白い本だった。
まあ、自信家の川渕さんならではの書きっぷり。
古河電工時代のわんぱく仕事ぶりや、退社してJリーグの発足発展に理念を見出したことなどの
ことは知らなかったので理解が進んだ。
山中さんの「ヴィジョン&ワークハード」が出て来たときには嬉しかった。
ヴィジョンは私は「天命を知る」ということばが浮かんだ。
私はその思いを感じた瞬間があったからである。
Jリーグ参加条件は興業として成り立たせるために必須で、
団体の法人化(企業スポーツではない)
年代別のユースチームを持つこと
一定のプロ選手の確保とライセンスを持った指導者の確保のほか
地域住民・自治体・企業の三位一体の支援体制を構築すること
そしてナイター設備を備えた15000人以上収容できるスタジアムの確保
といった厳しい条件だった。
1980年代後半から1990年代初頭はバブル経済の真っただ中で、自治体にも企業にも体力があった。
自治体は、芝生のピッチやナイター設備、観客席の増設など改修に着手した。
クラブの運営費については、入場料収入などを含めて3~5億円くらいあれば、プロとしての活動ができると
見込んでいた。
ところが、自動車メーカーが集まる会合で三菱自動車の社長が、
「クラブへの投資に10億円用意している」と言ったことから、
僕はクラブの親会社に対して「10年間で10億円の投資をしてくれれば、
10年後以降は入場料収入やマーチャンダイジングなどで自主運営でき、
会社は恩返しをできるようになると思う。それまでなんとかお願いしたい」というように
なっていた。
バブル期の頂点だったという時代背景にも助けられたが、こうしたことがうまくいったおかげで、
Jリーグは順調にスタートを切ることができた。
娘さんから教わったという健康法、つま先を床につけかかとをあげておろすのを1日30回というのは私も始めることとした。
「足は第2の心臓。人間は足から死ぬから、つま先立ちの運動をしてみたら?」
指導者の使命は、スポーツマンシップというものを理解し、それをもって選手を教育し、指導することに尽きる。
言うまでもないが、スポーツマンシップとは
①ルールを守る
②審判員の判定に従う
③対戦相手に敬意を払う
つまり、関わるすべてのものをリスペクトした上で、全力で戦うこと。
それを理解していれば、自然とフェアプレーは身につくものなのだ。
日大アメフト部の監督の件に触れているが、
今年のワールドカップのポーランド戦のボール回しの作戦は果たしてフェアプレーだったのだろうか。
川渕さんに聞いてみたい。
クラマー監督を川渕さんは尊敬している。
またそれだけの人だったようである。
本当の友達とは誰かということを実践で教えてくれている。
川渕さんが誹謗中傷に苦しめられていたとき、ふらっと協会に立ち寄ってくれて、
「川渕さん、今日はカレーでも食べない?」と、声をかけてくれた人がいた。
こういう時の友人こそ、本当の友人なんだなと思ったものだ。
そして、クラマーさんが話してくれていたのはこういうことかと、しみじみと思った。
1964年東京オリンピックで日本代表がアルゼンチンに勝ってベスト8に残った試合後
関係者でごった返したときに、部外者を外に出して選手だけへ話した言葉
「ジェントルマン、今日はよくやった。
どれだけ頑張ったかということは自分たちが一番よくわかっているはすだ。
そして君たちは、今日は新しい友達がいっぱいできるだろう。
その新しい友達と喜びを分かち合いたまえ。
いま一番友達が欲しいのはアルゼンチンの選手だ。
僕はこれからアルゼンチンの選手たちのところへ行く」
そして次の準々決勝。
日本がチェコに完敗すると、ロッカールームは閑散としていた。
その日もクラマーさんは、
「ジェントルマン」と同じように呼びかけ、そして僕ら選手にこういった。
「君たちはよく頑張った。とりあえず今日はサッカーのことはすべて忘れよう。
数は少ないが、今日来る友達こそ君たちの本当の友達だ」
この言葉はとても印象的だった。
まさに人生そのものを指導してくれていたのだ。
Jリーグの使命
Jリーグは今年、開幕してから25年という節目を迎えた。
10クラブでスタートしたJリーグはこの四半世紀で54クラブへと拡大した。
しかし、この十数年、ヨーロッパのプロリーグなどと比べて放映権料などが低かったこともあり
各クラブも選手の強化や外国人選手の招へいにかけられる金額が限られていた。
それが2016年にDAZNと2017年から10年間の放映権料契約を結び、
J1,J2,J3のリーグ戦全試合がDAZNで生中継されることが決まった。
放映権料として10年間で2100億円という巨大な金額がJリーグに入ってくることになった。
言わずもがなだが、この使い方が今後の日本サッカーを決める。
ここ数年一番問題になっているのが観客数が頭打ちになっていること。
ドイツの平均42000人に対し、日本は19000人
これを30000人にする努力が必要となる。
イニエスタの神戸入りはすばらしいと三木谷会長を絶賛している。
J1クラブ全体の観客動員数、入場料やマーチャンダイジングの拡大に貢献してくれるはず。
そしてイニエスタは、ユース時代に育成で育ててくれたコーチら数人も一緒に連れてきた。
イニエスタの加入は、間違いなくJリーグの次の50年の発展にむけて大きなターニングポイントとなる。
日本サッカー協会
「JFAこころのプロジェクト」の紹介
アスリートが「夢先生」として小中学校の教壇に立ち、自分の経験を語る。
サッカーくじ導入の話
自民党のスポーツ議員として森さん、麻生さんの名前が挙がっていた。
くじの導入で、ベストメンバー規定をいれて八百長防止
「直前5試合に先発出場した選手が5人以上いること」の補足基準を作った。
罰則は、罰金2000万円以下、勝ち点はく奪など
アリーナ文化を日本にも
スポーツ観戦と音楽ライブそして飲食を一緒に楽しめるアリーナこそが
今後の発展に重要だと説いていた。
小池知事はそこをまったくわかっていないとこき下ろし。
そのほか、サッカー以外のスポーツ団体の改革に現在奔走していることを
書いておられ、
◎何よりも大切なデータ
データの大切さを理解できるようになったのは、会社勤めをしていたことが大きい。
サラリーマン時代に物事の定量的な把握の仕方を徹底的に勉強させられた。
それがその後とても役にたった。
会社勤めの経験の有無と数学的センスは大きく関係している。
ハッキリ言って、多くの競技団体にこういう経験をした人材が不足している。
あこがれはアメリカのアメフトのNFL
レギュラーシーズンのホームゲームはたったの8試合しかない。
1試合平均7万人入ったとしても56万人。
しかしそれで経営が成り立っている。
もちろんテレビの放映権料は莫大だが、1試合1試合の希少価値をつくり出していることも
見逃せない。高額なシーズンチケットが何年間待っても買えないような状態なのだ。
最後は読売新聞のドン渡邊恒雄氏との対談という構成であった。