天才物理学者の見たこと、考えたこと、話したこと
新堂 進/著 サイエンス・アイ新書
【内容紹介】
相対性理論を提唱した天才科学者・アインシュタイン。
彼は当時、何を見、どう考えて相対性理論に辿り着き、そして周りの人々にどのように関わって生きたのか。
アインシュタインの人生と理論を、名言や図版を交えて読み解く。
【著者紹介】
1971年長野県生まれ。専門はプログラマ。
そのかたわら物理学にも興味を持ち、数々の書籍を読み漁る。
筋金入りのアインシュタイン・ファン。著書に「マンガでわかる相対性理論」など。
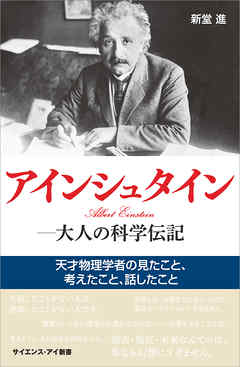
新書で見つけて予約したが、なかなか楽しく読めた。
お父さんが電力を経営していたこと、E=MC2 で原子力発電の父 であることから
非常に原子力専攻で電力会社OBの私とは関係性が深い科学者だ。
それでも、この本を読むまで知らないことが多かったと気づかされた。
特に女性の話はまったく知らず、結構苦労しているアインシュタインさんに親しみを覚えた。
イスラエルを建国した父ということも知らなかった。
大人の科学伝記という言葉はなかなかいいと思った。
別の科学者の分もあるのなら読んでみたいものだ。
ただ相対性理論のところは難しかった。
非常にわかりやすく書いてくれてはいるのだが…。
☆ 特許庁での有意義な仕事
もし光速度不変の法則が正しいとしたら、どんなことが起こるだろう。
思考の翼を思いっきり羽ばたたせることができた。
なにしろ時間ならたっぷりある。
「特許局での仕事中」という時間が。
もし大学教授の助手になっていたら、日々の仕事に追われ、そうはいかなかったろう。
結果的には幸運だった。
→なにが幸いするかわからいことだ。
○ 絶対時間と固有時間
絶対時間;「時間の流れ」はただひとつであり、誰もが同じ「今」を生きていると思われているが、
固有時間;実際には「時間の流れ」が無数にあり、スピードが違えば時間も違うのである。
名言集21
成功をAとすると、A=X+Y+Zという式が成り立つ。
Aは仕事、Bは遊び。そしてZは…。
Zが何かは明らかにされていない(沈黙という説もあるが)。
明らかにされていないところに、真実がある。
○アインシュタインの教授デビュー
アインシュタインの名が科学者の間に広まってくると、大学も彼を放っておくわけにはいかなくなった。
「これほどの立派な論文の作者がいつまでも特許庁の役人でいるのはおかしい。
彼の才能を埋もれさせるつもりか?」
1909年、30歳でチューリッヒ大学の助教授になれたのである。
アインシュタインは給料には欲がなかった。
ある程度の生活ができれば、それ以上は望まなかったのだ。
彼が望んでいたもの、それは、自分の研究に専念できる時間。
そして安らぎであった。
○アインシュタインと音楽
アインシュタインにとって、音楽は生涯の友であった。
幼いころはバイオリンを嫌々習わされていたが、13歳のときに突然、モーツアルトの美しさに目覚めた。
以来、すっかり大好きになり、自らバイオリンの練習をするようになる。
アマチュアにしては上手なほうだったらしい。
●病床のアインシュタイン
胃の痛みに苦しめられるのを、エルザが献身的に看病。
そこでついにミレーバとの離婚を決意する。
戦争、ミレーバとの離婚問題、そして闘病生活。
アインシュタインは、心身ともに疲れ切っていた。
名言集37
戦争と、僕たちの離婚問題と、どちらが先に片付くだろう?
結果的には戦争が先に片付いた。それほどミレーバとの離婚問題は長引いたのだった。
○アインシュタイン来日
有名になったアインシュタインは、世界中の国々から歓迎を受けた。
アメリカ、イギリス、フランス、ベルギー、パレスチナ、そして1922年(大正11年)には日本にも訪れている。
日本の「改造社」というマスコミ会社が、「世界の有名人を日本に招こう」という企画をしており、
その一環として招待されたのだ。
滞在は1か月以上に及び、東京、名古屋、大阪、福岡などの各地で講演を行い、奈良、京都など各地を巡った。
奈良公園では鹿せんべいを求めておじぎをする鹿におじぎを返し、京都の料亭では舞子による芸を楽しんだ。
アインシュタインはすっかり日本が気に入った。
もともと、小泉八雲の本で日本に憧れを持っていたが、想像以上だったのだ。
日本人の奥ゆかしさ、風習、文化、それらに「美」を感じたアインシュタインは
以来、すっかり日本びいきになったのである。
○ノーベル賞
アインシュタインは、ノーベル賞の賞金として18万スイスフラン(現在の価値でいうと約3200万円)を受け取った。
しかし彼はその賞金を目にすることなく、すべてミレーバへ贈った。
離婚問題でもめているときの約束を果たしたのであった。
○ルーズベルトへの手紙
アインシュタインのかつての助手だった、レオ・シラードという科学者(アメリカに亡命)が
アインシュタインの名声を利用して手紙を送った。
「ドイツに対抗するためにアメリカも原爆を作るべきだ」
アインシュタインは、ハーンの実験の重要性をすぐに悟った。
質量からエネルギーを取り出せることを予言したものの、遠い先のことだと考えていた。
それがまさかこんなに早く実現しるとは思ってもみなかったのである。
アメリカが原爆開発に乗り出したのはその2年後の1941年。
結果、どうなったか?
ドイツは原爆開発に成功せず、アメリカは成功した。
しかしそれを使うまでもなくドイツは降伏。
残るは日本だけである。
アインシュタインとシラードは、今度は「原爆を使わないでくれ」と訴えたが、またもや無視された。
秘書のデュカスから広島原爆投下のニュースを聞いたアインシュタインは言葉を失った。
そして激しい自責の念にかられたのである。
以来、ますます熱心な平和主義者となるのだった。
○2%の人々
アインシュタインはあちこちで平和を訴える演説もしていた。
中でも有名なのは1930年にニューヨークで行われた「2%演説」。
国民の2%が戦争に反対すれば、その国は戦争を起こせない。
なぜなら2%を超えると刑務所がパンクするからだ。
○アインシュタインとシオニズム
アメリカへ亡命したアインシュタインは、同じ境遇のユダヤ人に救いの手を差し伸べることを惜しまなかった。
アインシュタインはユダヤ人のヒーローだった。
ユダヤ人は「国を持たない民族」である。
彼らの祖先は昔、侵略にあい滅ぼされ、以来、世界中に散ったのだ。
国を持たないことで差別も受けた。
下賤な職業とされた金貸しの仕事にしか就けず、しかし皮肉なことにそのおかげで金持ちのユダヤ人が増え、
ヒトラーに妬まれたのではあるが。
「ユダヤ人の国を造ろう。そうすれば差別されずに済む」
こうした考えをシオニズムという。
ナチス・ドイツの迫害以降、この考えはますます高まっていった。
アインシュタインは、シオニズムの指導者、ハイム・ワイズマンとともに
母国設立の資金を集めた。
この活動は実を結び、1948年、中東のイスラエルにユダヤ人の母国ができた。
その後、ワイズマンはイスラエルの初代大統領になった。
ワイズマン崩御後は、アインシュタインに次期大統領の白羽の矢が立ったが、
彼はその申し出を丁重に断った。
当時73歳。一国の大統領になるには高齢すぎたのだった。
●量子論
アインシュタインは、量子論の研究が進めば進むほど、それに反感を覚えるようになった。
中でもアインシュタインが嫌ったのは、「ミクロの世界は確率的にしか決まらない」という点だ。
「どこに何があるか?」は、確率的にしか決まらないのだ。
「不確かでわからない」のではなく、
「原理的にわからない」のだ。
なぜだか不明だが、とにかく量子論ではそうなるのだ。
これを「不確定性原理」という。
アインシュタインは、この「不確かさ」が気に入らなかった。
もしも神が自然法則をそのように創ったとしたら、
「あまりも不完全」であり、「あまりにも美しくない」のだ。
「神がサイコロを振るはずがない」
それがアインシュタインの考えだった。
ボーアとアインシュタイン
アインシュタインの量子論への批判はボーアを悩ませたが、最終的にはいつもボーアが勝利した。
○アインシュタインの脳
→これには驚いた
アインシュタインは、派手なことを好まず、墓石も望まず、あるまま自然に帰ることを望んだ。
その意志に従い、葬儀は身内だけで行い、遺体はなくなったその日に火葬にされ、遺灰は近くのデラウェア川に流された。
しかし一つだけ彼の意志に沿わないことが行われた。
脳の摘出である。
それはアインシュタインの解剖を担当したトーマス・ハーベイ医師によって、本人にも遺族にも無断で行われた。
アインシュタインの脳となれば研究的価値が高い。
彼はそれを手中にしたかったのだ。
脳はホルマリン漬けにされ、知人の研究者らにはスライス片が送られた。
その事実が判明したのは、彼の息子が学校で放った一言だった。
「僕んち、アインシュタインの脳があるんだ!」
このニュースはマスコミで報じられ、息子ハンスの知るところとなった。
ハンスは「金儲けに使わない」「研究を行いその成果を発表する」の二つを条件に、脳の所有を認めた。
しかし目立った成果を挙げられなかったハーベイ医師は、大学病院を解雇されてしまう。
脳は現在、プリンストン大学などに保管されている。
さてその結果わかったことと言えば、
「認知症の症状がないこと」
「数学をつかさどる部分が発達していること」
「言語をつかさどる部分に軽い障害があること(だからこそ、それを補うためにほかの部分が発達したのかも知れない)」
くらいだった。
以上