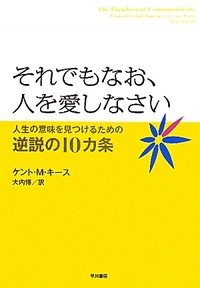「それでもなお、人を愛しなさい」
人生の意味を見つけるための逆説の10カ条
ケント・M・キース 大内博/訳 早川書房
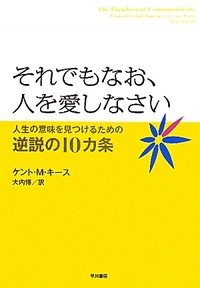
これも佐々木さんの本を読んで読もうと思った書である。
「逆説の」の和訳がどうもしっくりこない。
逆説でもなんでもなく、ふつうの倫理的道徳的生き方で、昔の日本人なら当然といったものである。
ただ、それができている人が何人いるのかというのは別だが。
非常に日本的、東洋的な考え方のようにも感じた。キリストの教えともいえるが。
それは人類普遍の真理なのかもしれない。
素晴らしいことはそれを実践できていること。
またそれを悟ったのが10代ということは非常に驚かされる。
この教えはお父さんから受け継がれていることをこの本を読んで知ったのであった。
|
投稿者:四国の井崎 投稿日:2012年 8月 8日(水)05時44分9秒 |
|
| |
男子サッカーは残念でした。
佐々木常夫さんの本を読んでいたら、この10か条の紹介があったので引用してみます。
http://blogs.yahoo.co.jp/chanchan_yanagi/23391626.html
『それでもなお、人を愛しなさい』 ケント・M・キース 早川書房
1 人は不合理で、わからず屋で、わがままな存在だ。
それでもなお、人を愛しなさい。
2 何か良いことをすれば
隠された利己的な動機があるはずだと人に責められるだろう。
それでもなお、良いことをしなさい。
3 成功すれば、うその友だちと本物の敵を得ることになる。
それでもなお、成功しなさい。
4 今日の善行は明日になれば忘れられてしまうだろう。
それでもなお、良いことをしなさい。
5 正直で素直なあり方はあなたを無防備にするだろう。
それでもなお、正直で素直なあなたでいなさい。
6 最大の考えをもった最も大きな男女は、
最小の心をもった最も小さな男女によって撃ち落とされるかもしれない。
それでもなお、大きな考えをもちなさい。
7 人は弱者をひいきにはするが、勝者の後にしかついてゆかない。
それでもなお、弱者のために戦いなさい。
8 何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。
それでもなお、築きあげなさい。
9 人が本当に助けを必要としていても、
実際に助けの手を差し伸べると攻撃されるかもしれない。
それでもなお、人を助けなさい。
10 世界のために最善を尽くしても、
その見返りにひどい仕打ちを受けるかもしれない。
それでもなお、世界のために最善を尽くしなさい。
|
本を読んで付箋をつけたところを以下に引用する。
P11 はじめに
高校3年生の終わりに行われた生徒の表彰式に出席するために体育館に足を踏み入れた瞬間にひらめいた洞察があります。
その瞬間、3年生として達成したことや学んださまざまな事柄、そして、私が力を貸すことができた人たちのことを思って非常な
満足感を覚え、表彰してもらう必要などないと感じたのです。
私はすでに報われていました。立派に仕事をやってのけたことから生まれる充実感と満足感をすでに体験していたのです。
表彰されようとされまいと、充足感と満足感がありました。
P54 「リボ・アロハ」という人に優しい地域社会をつくろうとするプロジェクト (第4条)
そのためには日常生活の中で礼儀正しさや思いやりを示すことを提案
そのリスト
・お年寄りや子供を尊敬する
・どんな場所でもそこを離れるときは、前よりもきれいにして立ち去る
(日本のサッカーの応援はこれができていて賞賛されていましたね)
・他人のためにドアを開けてあげる
・他人のためにエレベータのドアを押えてあげる
・何か植物を植える
(3.11復興に植物がいかに心を癒してくれたかということをNHKで先日放送していました)
・運転マナーを守る。他の車を優先させる
・異なる文化のイベントに参加する
・ショピング・カートを所定の位置に戻す
・外気に触れ自然を楽しむ
・ゴミに気が付いたら拾う
・お隣さんと分かち合う
・微笑を浮かべる
P71 第6条関係
ここで大きなビジョンを持って生きた人として、日本人として唯一 渋沢栄一が紹介されています。
P81 第7条関係
お父さんの勇気ある行動を紹介しています。
部下の軍法会議で正しい審理が行われるように証人依頼を敢然と行い、どれほど圧力がかかろうと
貫きとおした。
無くなっていたベストが見つかり裁判にならずに済んでハッピーエンドとなったが、お父さんは真を貫ききった。
P104 ケント氏の解説
評価の問題はたしかに大きな問題です。多くの人は自分がやっていることに対して充分な評価を受けていないと感じています。
上司は自分を評価してくれない、だから彼らのために最善を尽くす必要などないと感じています。
この問題に対する答えはこうです。
私たちはみな自分自身の誠実さと基準を持っていて、それに基づいて立派な仕事をすることにより意味や満足感を得るということです。
私たちがやることを誰もしらなくても、誰も評価してくれなくても、それは問題ではありません。
そんなことは無関係に、私たちは正しいことをしなければなりません。
これは自分の問題であって、他人の問題ではないのです。
これは私たち自身がどれだけ気にするかという問題であって、他の人がどれだけ気にするかという問題ではありません。
(ある女性が「一隅を照らす」を信条にしていると聞いて、その言葉どおりの姿勢を感じていたので心を打たれたことがあります。
それをここを読んでいて思い出しました)
P113
「生きることの意味」に心の焦点を合わせるようになれば、世の中は変わり始めるでしょう。
見返りを期待することなく、ごく自然に人助けをするようになるでしょう。
会社の組織の中で誰が出世するかなどということは気にしないで、
お互いに助け合うようになるでしょう。
自分が大切だと思うことのために人生を生き、心の命じるところにしたがって、
自分の人生の使命を果たすようになるでしょう。
それが権力や富や名声に結びつかなかったとしても。
あらゆる決定は、対抗意識に基づいてだはなく、一人ひとりにとっての最善、会社にとっての最善、社会にとっての最善という観点からなされるでしょう。
自分自身の権力を強くするために問題をつくりだしたりせずに、自分にとっての意味を高めるために問題を解決するようになるでしょう。
意味志向の人たちが社会の先頭に立って、評価されるとか拍手喝采を浴びることなど意に介さずに、本当に必要な問題に取り組み、
本当の問題を解決していけば、世の中はずっとましな場所になるでしょう。
⇒最後の言葉は今の日本人全員が心に刻むべき言葉だと思いました。