岩波 明/著 文春新書
(内容紹介)
空気が読めない、同じ失敗を繰り返す、極端なこだわり…。成人期の発達障害の代表的な疾患、アスペルガー症候群などの自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如多動性障害(ADHD)を中心に疾患の種類、治療事例を解説。
(著者紹介)
1959年神奈川県生まれ。東京大学医学部卒業。昭和大学医学部精神医学講座主任教授(医学博士)。同大学附属烏山病院長を兼任、ADHD専門外来を担当。著書に「狂気という隣人」など。
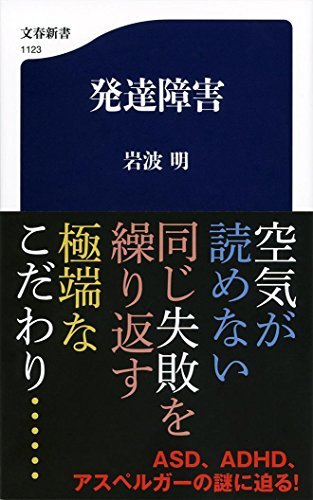
今年、損保系某高松支店長から採用面接では「アスペに気をつける」という言葉を聞いて
アスペルガー症候群もポピュラーになったんだなあとつくづくと感じた。
確かに法律もできているくらいだから当然だろう。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hattatsu/
そんなときにこの新刊のタイトルを目にして読んでみることに。
最近ではアスペルガーとは言わないことを知った。
かつてはアスペルガー症候群は独立したカテゴリーだったが、
DSM−5ではASDの中に含まれている。
DSMとはアメリカ精神医学会による精神疾患の診断・統計マニュアルであり、現在は2013年に発表された
第5版が刊行されている。DSM−5においては、アスペルガー症候群という用語は使用されなくなり、
「ADSの一部」と変更された点に注意する必要がある。
一般に「発達障害」とは、アスペルガー症候群を中心とする自閉症スペクトラム障害(Autism Spectrum Disorder),
注意欠如多動性障害(ADHD)などを漠然と示していることが多い。
注意すべきは、「発達障害」という病名は総称であり、個別の疾患ではない点である。
東野圭吾の「危険なビーナス」で初めて知ったサヴァン症候群が発達障害に関連しているとはビックリだった。
ダウンの名付けたイディオ・サヴァンは、フランス語の白痴(idiot)と賢者(savant)を合わせた造語である。
その後、白痴という用語は差別的であるという理由から用いられなくなった(現在の診断基準においては「白痴」は
「最重度精神遅滞」に相当している)。
このためその後の時代では、「サヴァン状態」(savant condsition)「サヴァンのある人(people with savant)」等の
様々な用語が生まれたが、現在では、この疾患の研究者であるドナルド・トレッファートが提唱した「サヴァン症候群」が
一般的に使用されている。
その定義として、レオン・ミラーは
・ある領域で一般的な基準(障害のない人たちの基準)と比べて優れている
・その領域におけるその人の能力は、その人の全般的な能力と比べて乖離している
という2点を挙げている。
○ シネステシア(共感覚)
この言葉も初めてしった。これも発達障害との関連が認められている。
シネステシア(synesthesia)は医学用語、心理学用語としてはあまりなじみのないうものかもしれないが、
この現象は「外部からの刺激に対して通常の感覚だけでなく、異なる種類の感覚も同時に生じる現象」
として定義されている。
これまでにシネステシアに関しては、さまざまな感覚の組み合わせが報告されている。
例を挙げると、「文字に色を感じる」「音に色を感じる」「形に味を感じる」などの減少が知られている。
⇒初めて聞いた。これから体験の有無を聞いてみたいと思う。私自身には全く経験がないことであるが
結構の頻度があるらしい。あまり人に言わなくなるのでわからないそうだ。
● フラシュバック
ASDなどの発達障害においては、過去の体験、特に嫌な辛い体験のイメージをまざまざと思いだす体験
(フラッシュバック)を繰り返すことが見られる。
特に子供時代のいじめの体験を何度も思い受かべることが多い。
このようなフラッシュバック体験も、記憶機能の亢進(こうしん;高ぶること)と関連していると考えられるが、
本人にとってはかなりの苦痛である。
◎ オキトシン
最近になり、ASDの関連で、オキシトシンという脳のホルモンが注目されている。
通常オキシトシンは出産や授乳に関連し、子宮平滑筋の収縮、乳汁分泌の促進作用を持つホルモンとして
知られているが、これ以外にも、社会生活においてヒトの「他人への信頼、愛着」が増加する作用があることが
明らかになった。
このオキシトシンを治療薬として用いて、ASDの社会性、対人関係の障害を治療する試みが開始されている。
ASDに対するオキシトシンの連続投与により、社会性の障害の改善がみられるとする報告がこれまでいくつかあり、
今後の研究が期待されている。
◎ 「Kaien」
多くの就労移行支援事業では、身体障害、発達障害を含む精神障害のすべてを受け入れている。
発達障害に特化した事業所は少ないが、「Kaien」がその代表的なものである。
利用料については多くが無料で利用可能であるが、一部は前年度の所得によって自己負担が発生する場合もある。
「Kaien」は株式会社であり、代表の鈴木慶太氏が2009年に設立した企業である。
鈴木氏は元NHKのアナウンサーという異色の経歴の持ち主だが、3歳の息子が自閉症に罹患していることが
判明したのをきっかけとして、発達障害の就労支援を推進しようと考えるようになったと述べている。