江藤 淳・松浦玲 講談社学術文庫
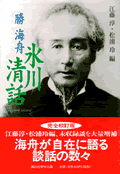
NHKの大河ドラマ「篤姫」にすっかりはまってしまった。
http://www9.nhk.or.jp/taiga/atsuhime/
最初はガキが出てきて「なんじゃいこれは」と思って大して興味もなかったが、
他にいいTV番組もないのでたまに見ていたら、俄然面白くなってきて、2月以降は欠かさず見た。
総集編も全部である。
この中で篤姫は別格として、カッコ良かったのが島津斉彬と勝海舟である。
そして、何かの本で勝海舟の明治時代以降の放言録があるというのを知って、楽天ブックスで取り寄せて読んだのであった。
文庫本なのに1000円もして驚いたが、なかなか面白いものであった。
編者の江藤氏は昔の「氷川清話」の間違いや筆者(吉本襄)の改ざんをこっぴどくこき下ろしていたが、
それを読んでいない者にとってはどうでもよいこと。
このこだわりがちょっと鼻についたが、それもまあ仕方のないことだろう。
「学術文庫」と銘打っていることだし。
初めて読んだ氷川清話が正しいものであったというのは幸運であった。
流れに特に違和感はなかった。
勝が明治維新後30年後まで長生きしたということは初めて知った。
そして、果たして明治政府のやり方はいいのか?
徳川の時代の殿様の方が現場をもっと大事にしていた。
明治政府が何か間違っていると嘆いている姿は可哀想でもあった。
富国強兵、殖産興業、そして結果的に軍国主義へと突き進んでしまったのは
明治維新後の新政府のやり方が本当に正しかったのか?との疑問も湧く。
勝が最も人物を認めていたのは西郷南州であった。
何度も出てくる。
それも江戸城の無血開城を果たした二人ならでは当然でもある。
小松帯刀との出会いが篤姫ではあったのだが、名前が一度も出てこないことを見ると
原作者の創作であったようでガックリした。
天璋院の話は一度だけ出ているが、ほとんど眼中にはなかったと言ってよい。
篤姫では、小松帯刀、勝海舟、西郷、坂本竜馬あたりがとても好ましく描かれています。
私は氷川清話で勝の独談を読んで、篤姫の比重はずいぶん低いことがわかりました。
西郷が非常に高く評価されておりましたが、残念ながら小松帯刀の名前は出てきませんでした。
勝と小松の接点は篤姫ではありましたが、ほとんどなかったのでしょう。
勝が大政奉還の頃、突如として出てくる理由がわかりました。
氷川の自宅に2年間幽閉されていたんですね。
年齢を調べてみた。
小松帯刀は、やはり天璋院とは同い年であり、西郷や大久保よりも年下であった。
勝海舟 1823 〜 1899
天璋院 1835 〜 1883
西郷隆盛 1828 〜 1877
大久保利通 1830 〜 1878
小松帯刀 1835 〜 1870
坂本竜馬 1836 〜 1867
勝は、若い時代は剣士の修行をしっかりやり、そして支援してくれるスポンサーも2人ほどいたりして学んでおり、
基礎はしっかりしており、人徳もあったものと思います。
戦略家であるが政治家ではない。
しかし庶民の酸いも甘いも知っている。今で言えば暴力団や姉御たちにも信頼されている。
竜馬が逆に説得されたのもわかるような気がします。私は悪い印象を持っておりません。
徳川が静岡でなんとかやっていけたのも勝がいたからこそでしょう。
確かに自己顕示欲は確かに強いと思いますが、明治政府に対して厳しい言葉を吐き続けていたようです。
現場主義が明治政府の政治家にはないといい続けています。
ということで、以下の抜書きは本の順番とはゼンゼン合っておりません。
ポイントとして挙げた、
後援者
修行
徳川の政治
を書いた後、人物評や時事言などとします。
◎ 後援者(スポンサー)が2人
・「渋田利右衛門」
貧乏で本を買う金もなく本屋で立ち読みさせてもらっていたときに知り合った北海道箱館の商人で、
わざわざ貧乏屋敷まで来てくれて、本を買うお金として200両を渡し、面白い蘭書があったら翻訳して送ってくれと依頼。
その後もずっと通信していたが、長崎に居る間に残念ながら亡くなってしまった。
信じられない話であるが、こんなことがあるというのは、勝が何かひきつけるものを持っていたのだろう。
・「都甲(つこう)斧太郎」
原子力安全委員長の「とごう」先生と同じかと思っていたら「つこう」と読むのでエッツ?と思った。
26歳のときにこの先生にお世話になった。他の誰とも交わらなかったのであるが、勝だけは可愛がってくれ、
西洋の学術を教えてくれた。40歳ほど上の歳であり、孫のように可愛がってくれたとのこと。
やはり長崎留学中に亡くなられたとのこと。
この後援者2人によって、西洋の学術をしっかり勉強したことが勝の広い見識になっているのではと思う。
それにしても、後援者をひきつける光るものを持っていたのだろう。
これはホラには思えなかった。
先生が常に言って平生嘆息しておられた言葉
「今日のごとき制度にては所詮この国を維持することはあたわずして、遂には外国に降伏せざるべからざるのの
悲境に陥るであろう。しかるにもし強いて今日の制度を維持せんとするときは早晩内乱を醸して、一時は惨憺
たる有様になるに違いない、ゆえに今日に当たり誠心誠意に西洋の事情を研究するは最も必要のことであるが、
うらむらくはこれを研究する人に乏しい。」
そして始終教訓された言葉
「そうして自分は66歳にもなり、もはや前途の望みも絶えたけれど、お前は未だ壮年にもあり、将来種々の艱難(かんなん)に
遭遇であろうけれども、十分堪忍して幕府に知られざるようにして蘭学を研究して、十分斯国のために尽くさなければならぬ」
◎ 剣士の修行
剣術の家筋であり、島田虎之助に学ぶ。島田塾に寄宿
指南の言葉
「今時みんながやり居る剣術は、かたばかりだ。
せっかくの事に、足下(あなた)は真正(ほんとう)の剣術をやりなさい」
自分で薪水の労を取って修行。
寒中になると、島田の指示に従うて、毎日稽古がすむと、夕方から稽古衣1枚で、王子権現に行って夜稽古をした。
いつもまず拝殿の礎石に腰をかけて、瞑目沈思、心胆を練磨し、しかる後、起って木剣を振り回し、更にまた元の
礎石に腰をかけて心胆を練磨し、また起って木剣を振り回し、かくいう風に夜明けまで5,6回もやって、それから
帰ってすぐに朝稽古をやり、夕方になると、また王子権現に出かけて、1日も怠らなかった。
時々同門生が2,3人来ることもあったが、寒さと眠さとに壁壁して、いつも半途から、近傍の民家の百姓家を叩き
起こして、寝るのが常だった。しかしおれは、馬鹿正直にもそんな事は一度もしなかったヨ。修行の効は瓦解の前後に
顕れて、あんな艱難辛苦に堪え得て、少しもひるまなかった。
ほんにこの自分には、寒中足袋もはかず、袷(あわせ)1枚で平気だったヨ。
暑さ寒さなどということは、どんな事やらほとんど知らなかった。
ほんに身体は、鉄同様だった。
今にこの歳になって、身体も達者で、足下も確かに、根気も丈夫なのは、全くこのときの修行の余慶だヨ。
◎ 禅の修業も2年
19,20のときの2年間、禅もやっている。
はじめはひっくり返る連中であったが、段々修行が積むと、少しも驚かなくなって、例のごとく肩を叩かれても、
ただ僅かに目を開いて視るくらいのところに達した。
座禅と剣術。この2つが土台となって、瓦解の時分、万死の境を出入りして、ついに一生を全うできた。
勇気と胆力とは、畢竟この2つに養われたのだ。
危機に際会して逃げられぬ場合と見たら、まず身命を捨ててかかった。
しかして不思議にも一度も死ななかった。
ここに精神上の一大作用が存在するのだ。
→ ものすごい修行を4年間やったそうである。一体いつ眠っていたのかと思うが、すごいと思う。
その修行のおかげで、命を落とすことなく天命をまっとうしたのではないかと感心している。
ほら吹きとの揶揄もあるようだが、そんなことはないと思う。
こんな背景があったとは知らなかったが、納得である。
真似しようと思ってもとても出来ないが…。
○ 民情に通じた徳川の政治
・人心を慰安する余韻
世の政治は、何事でも杓子定規の法律万能主義でやろうとする。
それは理屈はなかなかつんでも居ようが、どうも法律以外、理屈以上に、言うに言われぬ一種の呼吸があって、
知らず識らず民心を纏めるという風な妙味がない。
人心を慰安するところの余韻がない。
徳川氏などは、深くこの辺に意を用いたものだ。
たとえば、久能山だとか、日光だというものを、世の中の人は、ただ単に徳川氏の祖廟(そびょう)とばかり
思っているだろうが、あれは決してそうではない。
あそこには、ちゃんと信長、秀吉、家康、3人の霊を合祀してあるのだ。
一方では天下に厳命を下して、豊国の廟を毀(こぼ)たしめるかと思えば、他の一方には、
まだこんなに深く意を用いたところがある。これで織田豊臣の遺臣なども、自然に心を徳川に寄せてきたものだ。
この辺の深味は、とても当世の政治家には分からない。
→ へー。そんなことをやっていたとは知らなかった。深いなあと感心。
・ 民情に通じた徳川の政治
徳川氏の政治の極意は、よく民に親しみ、その実情に適応する政治を布くに在ったのだ。
その重んずるところは、その人にあるので、法律規則などには、あまり重きを置かなかった。
八代将軍に至りて、初めて諸法度の類も出来上がったくらいだが、これとてもすべて北条時代の式目が土台と
なって居る。それは彼の貞永式目というものは、深く人心に染み込んで、久しく世に行われて来たものだから、
新たに土台から作りかえるよりは、この旧慣による方が、かえって人心を治め易いという深い慮からでたのだ。
なかなか注意したものではないか。
それで、この民を親しむについて、民間の実情を探るためには、よほど骨を折ったものだ。東照宮(家康)の
ごときも、駿府に隠居された後は、ただただじっと城中に引き籠って居られたかと思うと、どうしてどうして
なかなかそうではない。常に駿府近傍の庄屋とか、故老とかいう人々を集めて、囲碁会というものを催し、
輪番にその人々の家へ碁を打ちに行かれたそうだ。
今に静岡近辺の旧家には東照宮が来て碁を打たれた、という座布団がだんだん存して居る。
なに、ほんとに道楽で碁を打たれるものか。ただただかかる席上の事とて、互いに無遠慮になり、
出放題の世間話なども出て、果ては賓主相忘れるというような佳境に入ることが、とりも直さず、
東照宮に深慮の存するところである。
人物評論など
・こぶんのない方が善い
何でも人間はこぶん(乾児)のない方が善いのだ。
みなさい。西郷も乾児のために骨を秋風に曝したではないか。
おれの目でみると、大隈も板垣も始終自分の定見をやり通すことが出来ないで、乾児に担ぎ上げられて、
ほとんど身動きも出来ないではないか。
およそ天下に乾児のないものは、恐らく勝安芳一人だろうよ。
それだから、おれは、起きようが寝ようが、喋ろうが、黙ろうが、自由自在気随気儘だよ。
…
西郷も、もしあの弟子がなかったら、あんなことはあるまいに、おれなどは弟子がないから、この通り今まで
生き延びて華族様になって居るのだが、もしこれでも、西郷のように弟子が大勢あったら、独りでよい顔も
して居られないから、何とかしてやったであろう。しかし、おれは西郷のように、これと情死するだけの親切は
ないから、何とか別の手段を取るヨ。とにかく西郷の人物を知るには、西郷くらいな人物でなければいけない。
俗物には到底分からない。あれは政治家やお役人ではなくて、一個の高士だものを。
・西郷の力と大久保の功
この東京が何事もなく、百万の市民が殺されずに済んだのは実に西郷の力で、その後を引き受けて、この通り
繁昌する基を開いたのは、実に大久保の功だ。それゆえにこの二人のことをわれわれは決して忘れてはならない。
西郷と別れて江戸城に無事帰りついての実感。
西郷の働きが行き渡って居るのに実際感服した。
談判が済んでから、たとえ歩いてとはいうものの城まで帰るに時間はいくらもかからないが、
その短い間に号令がちゃんと諸方へ行き渡って、一度繰り込んだ兵隊をまた後へ引き戻すという動きを見ては、
西郷はなかなか凡の男でない、といよいよ感心した。
畢竟、江戸百万の人民が助かり、家も焼かれないで、今日のように繁昌しておるのは、
みんな西郷が諾と言ってくれたおかげだ。
おれは始終このことを思っているから、世間が奠都(てんと)際などと騒ぎ出さないうちに、
ちゃんと心ばかりのことはしておいた。
・市井の人物
近所の料亭「青柳」でのやりとり。
繁昌しているように声をかけたところ、こんな話を女将から受けた。(傑物であった)
「殿様、只今娘に宅の様子を御話しがあったそうですが、殿様には、私どもの暮らし向きは、とても
お解りになりますまい。殿様には、ちょっと景気がよいように見えましょうが、実のところを申せば、
只今金といって一文もありません。それがため亭主は、せっかく才覚に出かけているのでございます。
けれども大晦日のことですから、どこへ行っても、到底間に合う気遣いはありますまいと存じます。
お見かけのところは、ほんの世間に対する体裁を繕う義理ばかりで、よし金がなくて苦しくても、するだけの
ことは、致しておかないと、自然と人気が落ちて参りまして、終にはお客さんが、ここのものは肴までが
腐っておると思し召すようになってしまいます。
全体、人気の呼吸と申しますものは、なかなかむつかいしいもので、いかほどの心の中では苦しくても、
お客様方には勿論、家の内の雇人へでもその奥底を見せるといけなくなります。この苦痛を顔色に出さず、
じっと我慢しておりますと、世の中は不思議なもので、いつか景気を回復するものでございます」
その胸にある苦痛を少しも顔色に形(あら)わさず、いかにも平気らしい様子を見て、おれもその時は、
ひどく感心した。全体、外交のかけひきといえば、なかなかむつかしくて、とても尋常の人では出来ない
ように思っている人もあるが、つまりこのお神さんの呼吸のほかに、何にもあるものではない。
ただ外交ばかりでなく、およそ人間窮達の消息も、つまりこの呼吸の中に存すると思うよ。
勝は感心してポンと30両の金を貸してあげたそうだ。
返しに来た女将に、金は突き返して
「この金をお前にあげる。実は、この間のお前の話で、おれも大変よい学問をした。
お前はなかなか関心な奴だ。ちゃんと胸の中に孫呉の奥義を諳(そら)んじ、人間窮達の大哲理を
了解しておるのだ。この金は、かような結構な学問をしたその月謝と思うて進上するから、取っておけ」
と言ったそうな。
最後の嬉しげなことを言うから、勝さんもあんまり好かれないのでしょうね。
女将が言ったのならいいが、自分で言ってしまってはぶち壊しである。
・塚本 定次 (松尾芭蕉)
おれのために、芭蕉翁についてよい解釈を与えてくれたのもこの男だ。
全体おれは平生から芭蕉という人はどうしても尋常のものでない、その余徳が深く人間(じんかん)に入って居る
ことは、ただ発句の巧妙なるゆえのみではあるまい、きっとほかに何かそのわけがあるだろうと思って居たところが、
この塚本という男の言うには、いわゆる近江商人なるものは、実にその芭蕉の教導訓示によりてできたものだそうだ。
このことを聞いて、おれは積年の疑団がここに初めて氷解し、大いに釈然とした。
関連URL 二代目塚本定右衛門(定次)の家訓
http://www.a-koubou.jp/article/13306922.html
近江商人と商いの信用
http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/article.php?storyid=505802034
松尾芭蕉(ウィキペィア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B0%BE%E8%8A%AD%E8%95%89
でも近江商人との接点はよくわからなかった。
時事数十言
○ 日清戦争と中国感
おれは大反対だったよ。
日清戦争はおれは大反対だったよ。
なぜかって、兄弟喧嘩だもの犬も食わないじゃないか。
たとえ日本が勝ってもどうなる。支那の国はやはりスフィンクスとして外国の奴が分からぬに限る。
支那の実力がわかった最後、欧米からドシドシ押し寄せてくる。
つまり欧米人が分からないうちに、日本は支那と組んで商業なり工業なり鉄道なりやるに限るよ。
一体支那5億の民衆は日本にとって最大の顧客さ。
また支那は昔時から日本の師ではないか。
それで東洋のことは東洋だけでやるに限るよ。
おれなどは維新前から日清韓3国合縦の策を主唱して、支那朝鮮の海軍は日本で引き受けくることを
計画したものさ。今日になって兄弟喧嘩をして、支那の内輪をサラケ出して、欧米の乗ずるところと
なるくらいのものさ。
→この見識、構想は正解だと思う。
・江戸の衰退を防ぐ
世間では不景気だなどと嘆じて居るが、これは上に立つ人の心がけ一つでずいぶん救済の方法もあるものだ。
おれが江戸城引渡し後の始末を付けたときは、なかなか今日くらいのことではなかった。
江戸は大阪などとは違って、その繁昌は何も商業が盛んだとか、物産が豊かだとかいうのではなくて、
ただ諸大名や旗本が大勢住んで居たからだ。
それゆえ幕府が一朝瓦解すれば江戸は忽ち衰微して、百万の人民は明日から喰うものがない騒ぎだ。
しかし幸いに遷都の議も行われて、土地もあまり衰微せず、横浜も開港場になったから、そこへ移って
商売を始めるものも出来、どうかこうか餓死は免れたが、しかしその当時おれもずいぶん困ったよ。
その中でも殊更困ったのは、いわゆるならずものの連中で、彼らは窮すればどんなことでもやりかねない
ものだから早くなんとかしなくてはいけない。そこでおれはかねてこの社会の親分を調べ上げておいたから、
自分でそれを尋ねて行って、子分を動かないように頼み込んだ。然諾を重んずる点においては、流石に
あの社会はえらいもので、宜しい受合いましたといったら、それはもはや大丈夫のものだ。
しかし幾らならずものだといっても食はないでは居られぬから、それぞれ手当ての金は上からくれてやったのだ。
それから待合とか、料理屋とか、踊りの師匠とか、三味線の教師とか、一番世間の景気に関係するところへは、
またそれぞれ金をくれて、今日に困るということのないようにしてやった。
こういう風にして、とにかく世間を不景気に陥らせないように防いで、さて一方では銘々相当な職業に
ありつかせるように奔走してやったから、江戸も衰えるどころではない、段々に繁昌してきたのだ。
その骨折というものは、とても一通りの事ではなかった。
たとえば貧乏人に金をくれてやるのでも、下手をするとかえって弊害を増すばかりだから、ちょっと人の
気がつかないような風にうまくくれてやるのだ。その呼吸はなかなか難しいが、まあ旗本のお歴々が零落して
古道具屋をでも始めていると、夜分など知らないふりでそれを冷やかしに行って、1品か2品か言い値で
高く買ってやるとかいう工夫だ。そうすると、この人も自然商売に面白みが出来ていつとなく立派な商人に
なるのだ。金もこういう風にうまく使えばよい。
→ 今の麻生内閣の迷走中の一律給付金とは、配慮の仕方がゼンゼン違う
・きせん院の戒め
勝は、近所に住んでいた、昔は評判だった祈祷師であったきせん院が今は落ちぶれていたが、
よく見舞いに行っていた。
ある日の言葉
貴下はまだ若いが、なかなか根気が強くって末頼もしい方だによって、私が一言お話をしておきますから、
是非覚えていてください。必ず思い当たることがあります。一体、私の祈祷が当たらなくなったに就いては、
2つの理由があります。
一つの理由は、或る日一人の夫人が、富の祈祷を頼みにやってきました。ところがそれが素敵な美人であったから、
必ず煩悩に駆られて、それを口説き落とし、それから祈祷をしてやりました。ところが4,5日すると、
その祈祷に効験があって、当選をしたといって礼にきましたから、また口説きかけると、かの美人は恐ろしい
眼で睨み付け、「亭主のある身で不義な事をしたのも、亭主に富籤を取らせたい切な心があったばかりだ。
それに又候不義を仕掛けるなどとは、不届千万な坊主めが」と叱った。その眼玉と叱声がしみじみ身にこたえた。
それから今ひとつは、難行苦行をする身であるから、常に何か生分のある物を喰って、滋養を取っていましたが、
或る日の事、両国で大きなすっぽんを買ってきた。ところが誰も怖がって料理をするものがいないから、私が
自分で料理をしようとすると、彼のすっぽんめが首を持ち上げて、大きな眼玉をして私を睨んだ。
私はなーにと言いつつ、首を打ち落として料理して喰ってみたが、しかし何となく気にかかった。
この2つのことが、始終私の気にかかって居て、祈祷もいつとなく次第に当たらなくなったのです。
それといって、何もこの二つがたたるというわけでもあるまいが、つまり自分の心に咎めるところがあれば、
いつとなく気が飢えて来る。
すると鬼神と共に動くところの至誠が乏しくなってくるのです。 そこで、人間は平生踏むところの筋道が大切ですよ」
この話を聞いて、おれも豁然(かつぜん)として悟るところがあり、爾来今日に至るまで、常にこの心得を
失わなかった。全体おれはこの歳をして居りながら、心身共にまだ壮健であるというのも、畢竟自分の経験に
顧みて、いささかたりとも人間の道筋を踏み違えた覚えがなく、胸中に始終この強味があるからだ。
この一個の行者こそ、おれが一生の御師匠様だ。
・咸臨丸での番外エピソード
このときの米人の歓迎はたいしたものだった。
すると2,3日して突然裁判所から咸臨丸艦長勝麟太郎として明何日其方へ相尋ねたき義あり出頭すべしという
手紙がきた。行ってみると塑(でく)のごとく裁判官が上座に居って、其方が艦長か。
実は其方の水兵のものが米国の2貴婦人に向かってコンナ品を与えて侮辱をした。
ソレでその貴婦人たちは怒って訴えて来た。その証拠品はコレである。
早速其方は水兵共を処罰すべしとのことであった。
ソレで俺はびっくりして、一体我が水兵は何をしたのかと怪しみながらその証拠品というヤツを一見に及ぶと、
驚くなかれ、二冊の春画サ。ソコでその証拠品を受け取り帰ろうとすると、その裁判長め、法服を代へ、
今度は打って変わった態度でさて言うには、唯今は公法の手前甚だ失礼した。
今度は個人としての話だが、この春画は実に珍しいもので、侮辱された2婦人は勿論自分なども大層欲しいと
思って居る。ソコで物は相談だが、侮辱した水兵には金を出すからこの品は譲ってくれまいか、との事である。
このメリケンの官憲め、そのくらいの事なら何も大形におれを召喚なそするまでもないものだと内心甚だ不平で
あったが、また一面から見れば公私の区別截然としていることに感心した。
ソレから艦に戻って水兵を調べ上げ、謹慎を命じた上、今度は艦長の名義でもって前の裁判官に向け、
其方共の願い出の趣聞き届け候何日何時日本軍艦に出頭すべしと手紙をやったが、その夜裁判官の2人が
コッソリでかけて来て、今日の手紙はあまりヒドイ、どうか内分にして渡して欲しいと泣きを入れたから、
そのままくれてやったよ。
馬鹿馬鹿しい話だが、外国の奴らは公私の区別をキチンとするのは感心だよ。
以 上