出口 治明 幻冬舎新書
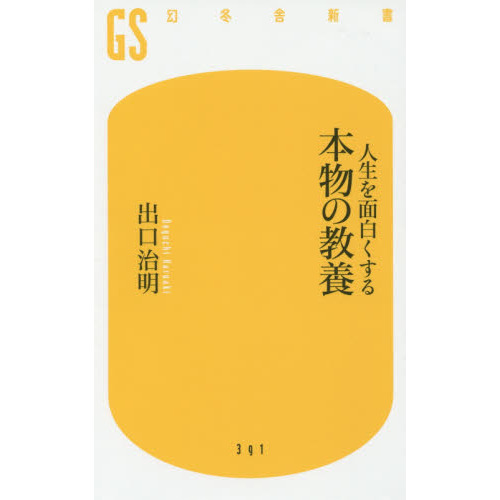
同期入社のW氏からゼヒ読むようにと薦められた本。
私としてはインパクトはロボットの石黒先生の本の方だったなあ。
(こちらはまだ読後記を書いていない)
出口の主張はそれなりにわかるし重視しておられることも理解できるが
あまり琴線に響かなかった。
人種がちょっと違うかなといった感じ。
それは平田オリザ氏の著書でもそう感じた。
一番思いにピッタリきたのが石黒先生だった。
理科系と文化系の違いなのだろうか…。
平田オリザさんは出口さんのこの本でも登場している。
P118
書店は楽しい、図書館も活用
最近はごく一般の図書館でもかなりの冊数が揃っていますし、相互連携で
近隣自治体の図書館からも取り寄せてくれるシステムも整備されています。
劇作家の平田オリザ氏は、図書館こそ21世紀に施設だと語っています。
文化の公共性を担い、地域コミュニティの鍵となるポテンシャルを秘めていると
図書館の今日的重要性を指摘されています。
→ 私は家内が図書館勤務を何年もやってきたのでこのシステムはよく知っている。
会社もやめたのでこれからは図書館をよく利用していこうと思っている。
あと、カルビーの松本CEOの講演で聞いた言葉が、この出口さんの著書でも
出てきた。
どちらの言葉なのか。
人から知ってこれは素晴らしいと思って使うのはいいが、自分の言葉でない場合は
誰から聞いたかを紹介すべきだと思った。
2人とも自分の言葉ではないのかも知れないが…。
自分もこの言葉はその通りだと思う。
P247 人間の脳力はみんな「チョボチョボ」
ライフネット生命は少数精鋭主義です。
と言っても、「精鋭を少数集める」のではありません。
「少数だから精鋭になる」と考えています。
◎少数精鋭ではない! 少数だから精鋭になる!!
この言葉を監査役全国会議2016春で特別講演で松本CEOからお聞きして
非常にインパクトを受けました。
私は少数だから精鋭にしなくてはならない課長の役をやらされたことがあるので
非常によくわかります。
そしてミーティングは最大6名までかと思っています。
少数だから精鋭になる!という言葉はいただきだなと思った次第。
しかしちゃんと誰から聞いたということはこのように伝えるわけです。
出口さんか松本さんのどちらか、あるいは二人ともそういうことを
なされていない。
ネットで調べてみたが、いろんな人が言っているようだ。
一体どなたが元祖なのだろうか?
『少数だからこそ精鋭になる』〜ヤマトホールディングス瀬戸会長の言葉 2012年12月
http://keieikikaku-shitsu.com/report_marketing/sales_strategy/457.html
よく言うのが少数精鋭ではなく、少数だから精鋭なのだ、と。
それが当社の競争力の源泉であり、少数であるために、得意分野に経営資源を集中する。 【西本利一/東京製鉄社長】
http://www.gdl-j.co.jp/archives/001511.html
優秀な人間が数名集まることを「少数精鋭」と言いますが、私は、【少数】だから【精鋭】になると捉えています。
例えば、私がベンチャー企業にいた時、創業当初の社員が少ない時には、全員が、100%以上の力を発揮しました。
元電通マン【藤沢涼】の挑戦 2015年2月
----------------------------
印象に残ったのが文脈とはあまり関係のない上記2か所。
他のところは、自称教養人である出口さんの自慢話の域を出ない感がしてあまりいい感じはしなかった。
ちょっと何か違うんだよなー。
こんなこと言っていると家内から相当辛辣な言葉を浴びそうなことがたくさんあるなーと感じた。
まあ、個人の価値観の問題なので前半部分はそこにお付き合いさせられるので少々苦痛であった。
第1章 教養とは何か
第2章 日本のリーダー層は勉強が足りない
第3章 出口流・知的生産の方法
第4章 本を読む
第5章 人に会う
第6章 旅に出る
やっぱ自慢話だよなー。
とにかく「面白いこと」が価値観
本をたくさん読んでいるのはスゴイと思う。
そして丁寧に読むということはわかるが、書評も現職になるまで書いたことがなかったことが意外。
私はこうやって書評、感想文を書かないと読んだことにはしていない。
そのところのこだわりが出口さんとは違うと思った。
人それぞれの読み方があるということであろう。
後半の、「教養としての時事問題」についてはその通りと、こちらは非常に読みやすかった。
お急ぎの方はここだけ読めばいいかと。
第7章 教養としての時事問題(国内編)
第8章 教養としての時事問題(世界の中の日本編)
全体的な書評はWEB記載を引用しておく。
http://blogos.com/article/142716/