−学ばない子どもたち 働かない若者たち
内田 樹 講談社
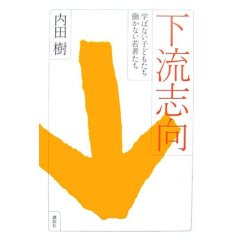
○ 労働主体から消費主体へ
学校が「近代」を教えようとして、「生活主体」や「労働主体」としての自立の意
味を説く前に、すでに子供たちは立派な「消費主体」としての自己を確立している。
すでに経済的主体であるのに、学校へ入って教育の「客体」にされることは、
子供達にまったく不本意なことであろう。 (「オレ様化する子どもたち」)
今の子どもたちと、今から30年前の子ども達の間の一番大きな違いは何かというと、
それは社会関係に入っていくときに、労働から入ったか、消費から入ったかの違いだと思います。
僕達が子どもの頃、子どもの社会的活動への参加は、まず労働主体としての自分を立ち上げると
いう形で進められたと思います。
…
子どもが家族という最小の社会関係の中で、最初に有用なメンバーとして認められるのは、
家事労働を担うことによってだった。家族に対して、わずかなりとも労働力を提供し、
それを通じて、感謝と認知をその代償に獲得し、幼い自我のアイデンティティを基礎づけていく。
そういうところから子どもの社会化プロセスが始まった。
やがて、家庭内労働にとどまらず、外の社会的活動にも子どもはかかわってゆくけれど、
労働を行い、他人に何か贈り物をして、それに対する感謝と社会的承認という対価を受け取る
という交換を自我のアイデンティティを基礎づけにするという点では変わらない。
…
今の子どもにはそういう機会がない。
逆に消費活動への参加はあまりにも早い時期から促されている。
→ ということで、学校の授業を消費主体で臨むことになる。
したがって「その勉強して何の役にたつのか?」という「教育内容を買う」という発想での問いが出てくる。
…
社会的能力がほとんどゼロである子供が、潤沢なおこづかいを手にして消費主体として市場に登場したとき、
彼らが最初に感じるのは法外な全能感だったはずです。
子供でも、お金さえあれば大人と同じサービスが受けることができる。
このような全能感は僕たちの子供がおそらくまったく経験したことがなかった質のものだと思います。
消費することから社会活動をスタートさせた子供はその人生のごく初期に「金の全能性」の経験を持ってしまう。
そのスタートラインにおける刷り込みの重みは創造される以上に大きいと僕は思います。
それは単なる拝金主義的傾向が刻印されてしまうということとは違います。
そいうではなくて、消費主体として立ち現れる限り、買う主体の属人的性質については誰からも問われないということです。
⇒ ここはうなった。なるほどである。
○ 三方一両損という調停術
⇒ こういうリスクヘッジ方法があるのだということを教えるべきと説く
左官屋が三両入った財布を拾います。財布に入っていた印形から落とし主がわかったので、持ち主の大工のところへ
届けに行きました。ところが大工は落とした金はもう自分のものでないから持って帰れと受け取らない。
言われた左官屋も「金が欲しくて届けたわけじゃない」と意地をはって、金の受け取りを拒否します。
この裁きをつけるために大岡越前が二人を呼び出します。
お白州にかしこまった二人に、奉行は自分の懐から一両出して、二両づつを与えます。
二人とも三両入るところが二両となったのだから一両の損。仲裁に入った奉行も一両出したので一両の損。
「これで三方一両損」で無事に仲裁が成り立ちます。
⇒ この話は初めて知った
…
この紛争解決法は争いを「丸く納める」ことを目的としている。
すなわち、調停的仲裁は、紛争当事者のどちらかが「正しい」かを明らかにすること
− 現代の法による「裁判」はこれを目的とするのであるが −
を目的とするのでなく、「丸く納める」こと
− 紛争当事者のあいだに「仲のよい関係」(紛争という「角」がなくなった関係)をつくること−
を目的としている。
(川島武宣 「日本人の法意識」 岩波新書)
⇒ なるほどねえ。日本人ならではの解決法。いい文化だと思う。
最近の何でも「訴えてやる!」という傾向にはうんざりしているので、こういう調停法をいろいろ
教えてくれれば、世の中ずいぶんよくなるんじゃないかと思う。
心がけたいポイントである。
なかなか実践できないが。調停者自身も損をかぶって納めるというなんぞはできないことだ。
○ リスクヘッジの基本
「間違っても大丈夫」だと思っている人間だけが「絶対に正しくなければダメだ」というようなことを口走るのです。
「間違ったら死ぬ」という条件が与えられたときには、人間は「正解を当てるためにはどうするか」ではなく、
「間違わないためにはどうするか」ということを優先的に考えるのです。
…
日本人が無防備なのは
それは戦後60年間戦争をしたことがなかったからです
… (外交、政策などの記述)
不思議だとは思われませんか?
リスク社会が到来したぞと警笛を乱打しながら、誰も「リスクをヘッジする仕方」を国民的にアナウンスしないというのは?
○ 自己決定・自己責任
リスク社会を生き延びることができるのは「生き残ることを集団的目標に掲げる、相互扶助的な集団に属する人々」だけです。
ですから、「リスク社会を生きる」というのは、巷間言われているように、
「自己決定し、その結果については一人で責任を取る」ということを原理として生きることではまったくないのです。
「自己決定し、その結果については一人で責任を取る」というのはリスク社会が弱者に強要する生き方(というよりは死に方)なのです。
○ 相互扶助
相互扶助・相互支援というのは、平たく言えば「迷惑をかけ、かけられる」ということなのだから、
「迷惑をかけられる」ような他者との関係を原理的に排除すべきではないだろうということです。
○ 自信
「自分についていい感じを持つ(feeling good about onself)」ことはアメリカではひさしく称揚されてきた教育理念。
子供が「セルフ・セスティームを高めること」は教育上よいことであると考えられてきました。
けれども、忘れてならないのは、自信を持つのは彼が属する社会集団にうおいて支配的な価値観に合致する場合だけである。
(美術や音楽に優れていても、運動能力やビジネスセンスに高い評価を与える社会集団ではあまり自信を持てない)
…
階層が閉鎖的になると、子供は階層内部的な評価を通じてしか「自信」を高める道がないので、子供は所属階層のイデオロギー性を
いっそう「濃縮」した仕方で体現するようになる。
そのようにして、わずかな世代交代の間に、階層は急速に閉鎖的になる。
⇒ 内容は非常に怖いが説得を受けてしまう論理である。
○ 教育の権利を義務と感じるわけ
教育の「権利」を「義務」と読み違える倒錯が起きた理由は、経済合理性の原則が社会のすみずみに入り込んだせいである。
子供たちが成熟の最初の段階で、おあずおのれを「消費主体」として立ち上げるようなことは歴史上初めてのことである。
それは単に生活が豊かになったとか、物質的欲望が亢進したということではなく、
そのさらに以前の問題として、子供たちが「時間」と「変化」について自らを閉ざすように、
幼くして自己形成を完了させてしまったということです。
○ 働くとは
(この問いについては私のコミュニケーションの大きなテーマになっているが、内田さんが働くことの義務感ということで
書いてくれている。)
サラリーマンの労働も、もしそれを人間的活動たらしめたいと思ったら、交換の基本ルールに従わねばなbらない。
「働く義務がある」ということをあらゆる人間社会がその基本的な倫理としてきたのは、
「働くことで、すでに受け取ったものを返さなければならない」という反対の給付の義務感が僕たちの社会生活の
すべての始点にあるからです。
この義務感・負債感を抜きにして労働のモチベーションを基礎づけることはできない。
「働かなくてはならない」というのは、労働について装飾的に追加されたイデオロギーではなくて、労働の本質なのです。
○ ニートの理由
彼らは労働することそのものに不合理さを感じているからこそ、労働から逃避しているので、
どうして労働することを不合理と感じるかという、根本の問題を見過ごしている限り、
どのような施策も問題を悪化させることにしかならないだろうと僕は思っています。
労働から逃走する若者たちの基本にあるのは消費主体としてのアイデンティティの揺るぎなさです。
彼らは消費行動の原理を労働に当てはめて、自分の労働に対して、賃金が少ない、十分な社会的威信が得られないことに
「これはおかしいだろう」と言っているのです。
そして等価交換を原則とした場合、彼らの言っていることはまったく正しいのです。
…
彼らは自らを等価でない交換には決して応じない「クレバーな消費主体」として自己規定し、
そのことからわずかなりとはいえ満足感と達成感を得ています。そうである以上、「学び」や「労働」のような、
本来等価交換ではないダイナミックなプロセスに身を投じるという決断が、彼らの側から自主的に出てくることはありません。
○ 単位
⇒ これは知らなかった。
一単位というのはみなさんご存知ないと思うんですけど、45時間の「ワーク」のことです。
45時間というのは通常の労働者の1週間の労働時間、月、火、水、木、金が8時間で40時間、プラス土曜日5時間働いて
45時間。45時間の労働をもって1単位とすると。
これを学生に当てはめる場合は、15時間勉強すると1単位です。
どうして学生の場合は15時間の「ワーク」で1単位認定するかというと、学生というのは予習復習に学校外で15時間づつ、
計30時間「ワーク」するものだと定義されているからです。
まるで実情とは違うのですが、とにかく15+30で45.これで1単位。
124単位で卒業するということは、単純計算すれば5580時間の「ワーク」をした者には学士号を与えるという発想なのです。
○ 人材
僕は(作者は僕を多用し、ですます調で書いてあるがあまりいい気がしない)、「人材」という言い方をしないようにしているんですけれど、
それは「人間は製品ではない」という基本的なことについて、その言葉が誤解をもたらしかねないからです。
だって、「自己組織化する製品」なんてこの世に存在するわけないから。
そこらへんに置いておくだけで自動的に機能が高度化する電化製品とか、戸棚に入れている間にどんどん風味がよくなる缶詰とか、
ありえないでしょう。
でも人間が教育を通じて身に着ける最良の資質というのはそういう力なんです。
時間が経過するにつれて、さまざまな経験を取り込んで、自分自身の質を向上させてゆく能力、教育の目標はそれを習得させることに
尽きると僕は思っています。
しかし、教育の「入り口」でも「出口」でも、市場原理が深々と入り込んできている。
そのせいで、子供たちもあるいは卒業生を迎える社会も、学ぶことの意味を見失ってしまっている。
○ 音楽も学び
孔子は「君子の六芸」として、礼、楽、射、御、書、数を挙げている。
○ 師匠
師匠を持たないものは敗れる。
師弟関係で重要なのは、どれほどの技量があるとか、何を知っているとかいう数量的な問題ではない。
師から伝統を継承し、自分の弟子にそれを伝授する。師の仕事というのは極論すると、それだけである。
「先人から受け取って、後代に手渡す」だけで、誰でも師として機能しうる。
○ 宗教的な人間
日本人はゆっくりと宗教的な成熟に向かってゆくだろうと予測している。
これはやはり時間の感覚のことですが、宇宙には起源があり、終末がある。
時の始まりがあり、終わりがある。
その悠久な流れの中のこの一瞬、という時間の捉え方ができる人間のことを「宗教的な人間」あるいは「霊的な人間」と
読んでよい。自分がこの広大な宇宙の、他ならぬこの場所に、他ならぬこの瞬間に、他ならぬこの人と一緒にいるという事実に、
人知を超えた「何かおおいなるもの」の意思を感知できると、人間はとても豊かな気持ちになれる。
⇒ 納得である。
内田さんの主張は気づき、納得を促してくれた。今後も注目していきたい。