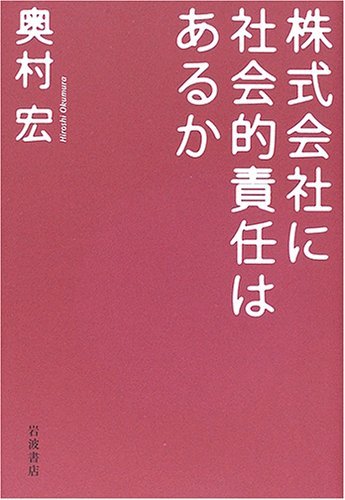「株式会社に社会的責任はあるか」
奥村宏 岩波書店
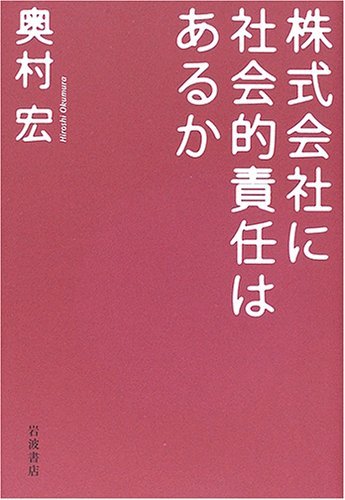
この本もE先輩から貸していただいた本だったが、これまでが80〜100点とすると
30点くらいの評価という感じで、残念ながら最低ランクだった。
オッ!と思ったのは株主の有限責任論。
株主は企業が潰れると、投資資本が紙くずになるだけで、企業の罪についての責任を問われないこと。
無責任な感じをうけるが、これが株式会社の株主なのである。
法人が株主になると、そして持ち合いになるとますます無責任となる。
そういわれればそうです。
企業は巨大化する方向に動いていますが、改めて怖さを感じました。
以下章毎にポイントと思ったところを抜書きしました。
第1章 流行する「企業の社会的責任」論
企業本来の機関としてのあり方、つまり利己的で人に道徳的懸念を失わせる文化、
エンロンは、そうした特長を極限まで−実際、わが身を滅ぼすまで−
引き伸ばした点では独特だった。しかし、取り立てて変わっているわけではない。
エンロン崩壊は、企業の機関としての性格的欠陥の現れなのである。
そこで改めて「企業の社会的責任」ということが問題になったのである。
第2章 株式会社の責任
L.E.ミッチェル
有限責任は、企業の非社会的進化の一因である。企業は、自らの収益性の最大化
という目的によって、道徳性をひどく損なわれた存在なのである
有限責任の下では、自分以外の株主が誰であるかを気にする必要がない。
こうして、有限責任が無責任を生み出している。と指摘。
アダムスミスが「国富論」で株主は配当のことしか考えないと言って株式会社を批
判したが、
この株主の受動性と無責任性は株式会社制度が発展し、巨大株式会社になって人間
を支配するようになった段階で、
今改めて問題になっているのだ。
第3章 無責任会社
日本の株式会社の多くは近代株式会社制度が前提となっている
(1)資本充実
(2)ディスクロージャー
の原則から外れており、それは株式会社とはいえない存在になっている。
さらに近代株式会社制度では株主総会が最高機関になっており、株主主権の原則に
立っているとされているが、
日本の会社の株主総会は全く形骸化しており、株主総会の名に値しないものになっ
ている。
このような日本の株式会社の現実から、われわれは果たしてそれが株式会社といえ
るのか、
そしてそれが社会的責任の主体になりうるのか、ということを考えていく必要があ
る。
日本の株式会社の実態をふまえないまま、抽象的、一般的に「企業の社会的責
任」を論じるのは
空疎な議論であるばかりでなく、現実の矛盾を隠蔽し、問題をはぐらかすものだと
いわねばならない。
● 誰も責任を取らない株式会社
第4章 法人とは何か
・法人擬制説
・法人否認説
・法人実在説
われわれも株式会社を見る場合、あたかもそれが実体であるかのように考える。
その典型が法人実在説であり、「会社それ自体論」であるといえる。しかし、株式
会社は分解できない
究極の単位ではない。それを較正しているのは株主、経営者、従業員などであ
り、株主にも法人株主、
機関投資家、個人などいろいろある。それを分析することこそが現代の株式会社論
の課題である。
人間は実体だが、株式会社はそうではない。それはあくまでも機能のために作られ
たものである。
それをあたかも実体であるかのように多くの人がとらえていること、そのことこそ
が問題なのである。
もっとも、現実に存在する株式会社を株主のものだとして、株主に分解してしまっ
たのでは会社の実態
はわからない。そこから「会社それ自体論」も生まれてくる。しかし、会社は本
来、実体としてとらえられる
べきものではなく、機能としてとらえられるべきものである。ある機能のために
人々が作ったのが会社である。
それがあたかも実体であるかのような存在になり、それが人々の生活を支配するよ
うになっている。
⇒ 機能と言われると抵抗あるなあ 会社の理念は機能とは違うと感じるのだが…
機能を理念として読み替えるかなあ
このような会社を変えようとするならば、何よりもこれを機能としてとらえること
が必要である。
本来人々が目的とした機能を会社が果たしているのかどうか。本来の機能とは離れ
て人間生活を支配し、
脅かしているのではないか。そうであるなら本来の機能に合わせて会社を変え、そ
れに見合った新しい企業を
作っていくことが必要である。
法人論争や「企業それ自体論」を現代的視点から取り上げる場合、以上のような実
体から機能への転換が
必要なのである。そうしなければ、現在の株式会社の矛盾を解明することができな
いし、企業改革にもつながらない。
これに対し、法人実在説や「会社それ自体」論者はマンモス化した会社をそのまま
是認するか、
あるいはそれを共産主義への過渡期とみるという、奇妙な議論になってしまう。そ
れは株式会社を賛美するか、
あるいは是認するもので、企業改革の発想はそこからは出てこない。
もちろん法人擬制説や法人否認説のように株式会社をすべて株主のものとして還元
したのでは、株式会社の実態は
つかめないし、現代の株式会社の矛盾を明らかにすることもできない。
◎ 以上、法人とは何かということを論じてきたのは、法人としての株式会社が社会
的責任の主体になりうるのか、
ということを議論するためである。
第5章 責任とは何か
最後のまとめの文章
現代の株式会社は19世紀や20世紀前半には考えられなかったほど巨大な力を
持って人間を支配している。
それはもはや株式会社がスタートした段階では考えられなかったような存在になっ
ている。
株式会社の原理が現実には合わなくなっているのである。
本来は社会的責任の主体にはなりえないはずの会社が、にもかかわらず社会的責任
があるといわざるをえなくなっているのだ。
これは責任倫理の問題である以上に、株式会社の問題である。
そこでは会社の責任を追及しようとしても責任の主体が明確でない。
株主資本主義のいうように会社の主体が株主だとするなら、株主の責任を追及しな
ければならないが、株主有限責任で
それができない。
第6章 企業犯罪の責任
ここはタイトルだけ書いておこう
チッソ水俣病の責任
ミドリ十字の責任
三菱自動車の欠陥車事件
「法人には犯罪能力がない」− 日本の刑法
法人処罰
法人の民事責任 (クボタの例)
代表者の責任
最後だけ記述しておく
芝原氏「経済刑法」で以下のように指摘
会社の社長(法人の代表者)などの企業のトップは、自分自身がその犯罪行為を現
実に行った場合と、
部下の犯罪行為について、共謀共同正犯、教唆犯、幇助犯が成立する場合以外
は、原則としてその刑事責任は
問われません。両罰規定の適用がある犯罪についても、株式会社など事業主が法人
である場合は、この規定
によって処罰されるのは法人であって、法人の代表者である個人(自然人)が処罰
されるわけではありません。
そこで、従業者の違法行為に基づいて法人を処罰するだけでなく、これに加えてそ
の法人の代表者を処罰すべきだ
という考えも主張されています
⇒ これほど厳密法で処罰せずとも、社会的に制裁を受け、代表者は自ら責任を取
ることでいいのではないでしょうか?
第7章 経営者の責任
責任を取らない経営者
経営者の社会的責任
なぜ責任を取らないのか
それは経営者の責任を追及する者がいないからである。 (と書いてます。)
株主総会の形骸化
機関投資家の圧力
コーポレート・ガバナンス
株主代表訴訟の限界
最後の部分のみ記載
会社のために良かれと思ってしたことであるというので免罪される(株主代表訴訟
の判例)ということになれば、
公害でも薬害でも、その他ほとんどの企業不祥事は会社のためにやったことなの
で、結果として会社に損害を
与えたとしても、取締役の責任を問われないことになる。株主代表訴訟の限界がこ
こにある。
会社のために行われた犯罪ことが問われなければならないのである。
現在の株式会社制度を前提として改革するとすると、会社が犯した悪事の責任は法
人としての会社を代表している
経営者が負うようにすべきである。そして、「企業の社会的責任」は「経営者の社
会的責任」としなければならない。
⇒ 違和感あり。実態的に現在はそういうふうになっているのではないか。
筆者の言う「社会的責任」が刑法、民法と犯罪に関するものに限定しているよ
うに感じてならない。
企業の社会的責任とは、倫理はもちろんだが、もっと高い志によるものではな
いか。
最近読んだ、松下幸之助さんのこの言葉がずっといい。
会社は「公事」と言い切っておられます。
公事という言葉には当然社会的責任が強く意識されます。
それは会社としても同じことなのです。社会から適正な利益を頂戴することは
お願いするが、その利益は無意味に
使うわけではありません。その半分以上は税金、配当などの形で社会に還元し
ています。
そして残りは、よりよき再生産のための資金として使っていくのです。
その一部は従業員の生活の向上へ回す、一部は整備へも回す、というわけで
す。
そうして、そのように利益が生かされていくところから、お互いの社会生活は
全体として、国民全体、社会全体と
して向上していく。こういうことのために、会社は大きな役割を持ってい
る、と解釈できるわけです。
だから会社の経営は単なる私事ではなく、公事なのです。
そういう考えからみると、その会社の社会に対する貢献が多ければ多いほ
ど、それは報酬として、利益として
返ってきます。しかし、いくら儲けたいと思っても、その利益に相当しないよ
うな仕事をしていたならば、
しだいにそれは社会から削られていくことになるわけです。
だからお互いの実力というか、お互いの働きが社会から喜ばれないような状態
であれば、社会からの感謝の報酬も
もらえない、ということになります。これはもう極めて簡単なことだと思うの
です。
http://homepage2.nifty.com/shigamatsu/Book/MichihaMugen.html
第8章 企業の社会貢献
・法人に博愛心があるか
企業批判に対抗して企業の社会貢献活動が行われていることがはっきりしてる。
そして景気が悪化したり、企業批判が下火になると、社会貢献活動も下火になる
ということを繰り返している。
⇒社会貢献活動の最たるものは法人税の納付と雇用維持である
筆者のいう社会貢献活動はフィランソロフィーやメセナなどの寄付活動 と
いうとらえ方なのでこんな
暴言になっている。
・三井報恩会、三菱財団、トヨタ財団
企業批判に対しては社会事業への寄付によって対抗するというやり方は戦前から
今日まで一貫している。
ただ名前が寄付から社会貢献活動、あるいはフィランソロフィーやメセナと変
わっているだけである。
・アメリカの財団
アメリカの財団は企業の創始者あるいはその一族が、その所有株式を財団の基金
として拠出し、
これによって相続税を免れること、そして財団の理事をその一族が指名すること
で財団を通して
一族が会社を支配するということを目的としている。後者は事実上の持株会社機
能を果たすものである。
ロックフェラー財団にせよ、フォード財団にせよ、社会事業や学術研究に寄付
し、それによって企業の
宣伝になっている。もちろん、ロックフェラーやフォードなどが個人として博愛
心をもってこのような
財団活動をしていることは考えられるが、その面だけをとらえてこれを慈善活動
だと単純に考えることは
できない。
・寄付と政治献金
ロックフェラー財団やフォード財団が学者に寄付する場合、大金持ちの資本家が
学問研究に介入していると
批判されたが、それでもそのカネは「自分のカネ」である。やり方が良いか悪い
かは別として、自分で稼いだ
カネを使って学問研究に影響を与えている。これに対して日本の経営者は「他人
のカネ」で自分の利益あるいは
思想を守ろうとしている。企業財団ではもちろん理事会で寄付の内容を決める
が、その理事を決めているのは
企業の経営者だからである。
法人=企業を個人と同じような実体と考えるところに大きな問題はあるが、その
法人=会社のカネを政治家に
献金するのは経営者である。その経営者が「他人のカネ」を使って、みずからの
政治的意思を献金という形で
表している。このことをどう考えるか。
⇒実態はちょっと逆ではないのか?個人のカネを会社の意思にしたがって献金し
ていることも筆者は知って
いるのか?
寄付と政治献金はともに経営者が会社のカネ、すなわち「他人のカネ」を使っ
て、自分の好みに合った人に
カネを供与するという点で共通している。
・社会貢献する側の責任
夏目漱石の学習院大学の講演(1914年)のことば
いやしくも論理的に、ある程度の修養を積んだ人でなければ、個性を発揮する価
値もなし、権力を使う価値もなし、
また金力を使う価値もないということになるのです。それをもういっぺん言い換
えると、この3者を自由に
享(う)け楽しむためには、その三つのものの背後にあるべき人格の支配を受け
る必要が起こってくるのです。
もし人格のないものがむやみに個性を発揮しようとすると、他(ひと)を妨害す
る、権力を用いようとすると
濫用に流れる、金力を使おうとすれば、社会の腐敗をもたらす。ずいぶん危険な
現象を呈するにいたるのです。
・社会的責任投資(SRI)
SRIの基準から投資不適格とされた会社がSRIファンドを売り出すという奇妙
なことが起こっている。
(野村證券:女性差別で投資不適格 2003年)
これに対して森岡孝二氏は「野村自身が「社会的責任に関する基準に合致する世界
の企業」として評価されることが
先決であろう」というが、投資信託を販売して儲けるためには何でもやるという投
資信託会社、そしてそれを販売する
証券会社の態度がここによく現れている。社会的責任も要は儲けるためであるとい
うことで、それは倫理や道徳を
売り物にするのと同じではないか。
第9章 株式会社の危機と社会的責任
・株式会社の歴史
・株式会社の危機
・株式会社の矛盾−日本
・株式相互持合いの矛盾
・「持ち合い崩れ」のあとに来るもの
・社会的責任をいわざるをえない矛盾
最後の文章
会社本位法人資本主義の原理になっていたのだが、それによって日本の会社は成長
し、そして日本経済も高度成長を
とげた。この法人資本主義が行き着いたところが80年代のバブル経済であった
が、やがてバブルが崩壊するとともに
法人資本主義の構造が崩れはじめた。株式の「持ち合い崩れ」が起こり、銀行に対
する公的資金の投入が行われる。
一方、企業不祥事が多発し、企業批判が激しくなる。
そして企業内部から従業員による内部告発が起こり、「会社人間よ、さらば」とい
われるようになる。
こうして会社本位主義が崩れるとともに若者の意識も変わる。
これまでの「就社」から「就職」へと学生の意識が変わり、どんな会社で働くかと
いうことより、
「どんな仕事をするのか」ということを考えるようになる。
そして「就社」しないフリーターが増えているが、これは会社がもはや若者にとっ
てかつてのような魅力のある存在で
なくなっていることを表しているといえる。
このような「脱会社人間」という社会のムードに対して、会社はそれに対抗するた
めにも社会的責任ということを
強調せざるをえない。そうしなければ、社会は会社の存在を許さないし、そして若
者は会社にやってこないからである。
⇒ なんか無理筋ロジックのような気がする。
本来の会社とは?という原点に立ち返ろうとしているだけではないのかという
思いがする。
第10章 責任ある企業にするために
・株式会社批判
・株式会社への逆戻り
・企業改革を阻止するCSR
CSRはお得です という言葉の引用 (情けない、トホホである)
次の展開にもいい気はしない
筆者はCSRのことはあまり勉強していないと思われる。
「会社は誰のものか」という問いに対して「会社は社会のものなのです」という
法人は社会にとって価値を持つから社会によってヒトとして認められているの
だ、
したがって法人は社会に役にたつことをしなければならない
−これは至極当然のことのように聞こえる。しかしそれは
「人間は社会に価値を持つから社会に認められているのだ。したがって人間は社
会にとって役にたつことをしなけれな
なたない」といったらどうか。
⇒ ちょっとこれまた無理筋の展開
会社は社会に認められるものでなければ存続することが出来ないことを忘
れているのでは?。
それは終身教科書の説教であっても、それによって人間が実際どういうことを
しているかということの説明には
ならない。それは「良いことをし、悪いことをしないようにしましょう」とい
うのと同じで、道徳的説教であっても、
人間を解明したものではないし、いわんや社会科学ではない。
⇒ この簡単なことを人々に納得させて実行させることが大事である。
解明する必要などどこにあるのか?
また解明などできるとは思わない。
道徳的説教こそが大事だと、私は思うが。
その道を悟ることができることが。
筆者は1930年生まれで高齢なのにおそらく悟られているはずと思うの
だがちょっと違和感大である。
・忘れられている株式会社の研究
・労働組合の社会的責任
・従業員の社会的責任
・企業改革の方向
誰かが青写真を描いて、みんながそれに従うというのでは悲惨な結末になる。もと
もと、株式会社にしても誰かが
青写真を描いて、それに従って作ったものではない。それはイタリアやドイツ、あ
るいはオランダ、イギリスなどで
人々がさまざまな工夫をして作り、失敗を重ねながらできたものである。株式会社
だけでなはない。合名会社にしても
合資会社にしてもそうだし、その他の非営利企業もそうである。
おそらく21世紀中に生まれるであろう新しい企業は、人々のさまざまな実験の中
から生まれてくるだろう。
それは誰かが頭の中で考えて作りだしていくものではなく、企業の現場で働く人た
ちによって作られていくもので
あろう。
ただ、われわれはなぜ株式会社が危機に陥ったのかということを解明し、そこから
企業改革の方向を示すことはできる。
株式会社が危機に陥った原因のひとつは、その規模が大きくなりすぎたことにあ
る。その点では国有企業も同じであるが、
規模が大きくなりすぎ、組織が肥大化したためにそれは非効率になり、官僚主義が
はびこって、管理不能になった。
これまで何回も、株式会社が大きくなりすぎたために、無責任になっているのだと
いうことを指摘してきた。
そこで経営者あるいは代表者が責任を持てるようにするためには、大企業を解体し
てできるだけ小さくすることが
必要であるという結論に達する
(この後、これまでの規模の拡大路線には株式会社が有利であった。
重化学工業時代はそれでよかった。しかし時代は変わったのであると解説)
・株式会社に変わるもの
・求められる思想の転換
ハンナ・アレントは「人間の条件」の中で労働(レイバー)と仕事(ワーク)を区
別して考えるべきだと言ったが、
人間はこれまで企業を労働の場として考えてきた。
⇒ エッツ?まさか。そんなの古いでっせ。
これに対して人間が仕事をする場として企業を考えるべきではないか。
企業に雇われ、企業のために労働するのではなく、人間が主体となって仕事をする
場として企業を考えることが
必要である。
⇒ これはもう私の会社論そのものである。
ドラッガーも言ってますよね。
そこには企業を実体としてとらえるのではなく、機能としてとらえることが必要で
ある。
⇒ 筆者の使う「機能」という言葉は好きではない。
企業を実体としてとらえるところから「会社人間」が生まれ、会社が主人公になっ
て人間を支配するようになる。
⇒ こんなイメージは持っていないがなあ。
人間が仕事をする場として企業を作っていく。
このように企業に対する考え方、思想を根本的に変えていく必要がある。
⇒ うーん。すでにこういうことになっているという理解なのであるが。
最後の最後
「法人である株式会社の責任は、まず何よりもその代表者である経営者がとらねば
ならない」
これが本書での私の主張であるが、そのためには株式会社という企業のありかたを
変えていかねばならない。
そのような企業改革の思想が、いま求められているのである。
以上