角居 勝彦 小学館新書
【内容紹介】
競馬ファンが最も注目する実力派調教師が語り尽くす、競馬の真髄。
レースそれぞれが持つ意味や戦い方から、愛馬の秘話、調教の工夫、
競馬場でのパドックや返し馬の見方まで、目から鱗が落ちる理論とエピソードが満載。
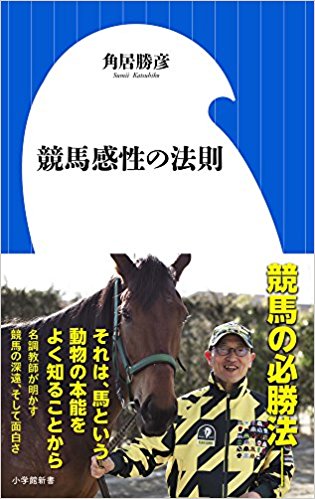
角居調教師は新進気鋭の調教師として注目しており、PO馬指名では
私に初めてG1のタイトルを取らせてくれたトールポピーがいる。
騎手でなく調教助手から調教師となったので、下積み経験があり、自分が調教師になったらこうしようという
ビジョンをお持ちであった。
角居チームとして仕事に当たる。
短距離路線は捨て、マイル以上を主戦とする。
といったところか。
最初はクラシックレース、グレードレースについて語り、その後個別テーマについて解説するという
スタイルで、入りやすく読みやすい。
また2017年の発行なので最新でありタイムリーであった。
よく図書館が買ってくれたものだ。
競馬もしっかりスポーツ文化として認知されたようで嬉しい。
● シーザリオ
(オークス馬シーザリオは虚弱体質だったことを知りました。)
デビューが遅れたのも体質が弱かったからです。
前足の種子骨(つなぎの上の球節の骨)に隙間が多く、密度が高まらないまま馬体が成長してしまう。
待っていても骨が強く固まらないので、ゲート試験を経てとにかく競馬をしてしまおうと判断しました。
脚元に不安はあったものの、人間の指示をよく聞き、調教もしやすかった。
…
アメリカンオークスでも見事に期待に応えての凱旋帰国。
ひと夏ゆっくり休ませましたが、ここでウィークポイントが悲鳴を上げます。
種子骨靭帯炎、おそらくアメリカでも気になっていたはずですが、メンタルの強さで我慢していたんですね。
緊張が解けた途端に痛み出すことはよくあります。
走ると痛がるので、放牧後の調教も進みません。
→引退 期待どおりエピファネイヤ、リオンディーズと2頭のG1馬を送りだした。
◎安田記念は多彩、大阪杯G1はGood
大阪杯がG1になったことで、大阪杯、安田記念、宝塚記念が「春の古馬3冠」と言われるようになるかも知れません。
(秋の天皇賞(東京)との対比で説いている。)
東京の1600mは広くて直線が長く、道中できちんとタメを作ることができれば、最後は鋭く切れる。
馬と騎手にとっては仕掛けどころが2000m、2400mとそれほど変わらない。
東京ならではの特徴で、中距離馬でもここでスピードを試したくなります。
力比べがしやすいので、多彩な資質を持ったメンバーが集まるし、牡馬の場合、ここで結果を出せば
種牡馬としての価値がぐんとアップします。
…ダイワメジャー、アグネスデシタル、ジャスタウェイ
またスプリンターでもチャレンジしてみたいレースです。
速い流れのなかでも4コーナーを回るまで我慢できれば、最後の直線でもう一度やれる面がある。
香港スプリント連覇など1200mで無敵を誇ったロードカナロアは13年にここを勝ち、
種牡馬としての可能性がさらに広がりました。
15年に勝ったモーリスは、その後秋のマイルCS、香港マイル、チャンピオンズマイル(香港)と連勝街道を走りました。
16年の安田記念こそロゴタイプの逃げに屈して2着でしたが、2000mに距離を伸ばした天皇賞秋に圧勝、さらに
同じ2000mの香港カップも制して種牡馬入りしました。
●角居厩舎は短距離嫌い?
角居厩舎は開業以来、スプリンターズSのみならず高松宮記念にも1頭も管理馬を出していません。
角居厩舎では血統的に中距離の馬を多く預からせていただいています。
その関係で、従業員教育など調教システムが短距離馬育成に向いていないのです。
それともうひとつ、調教師の姿勢の問題もあります。
たとえば、1600mでは引っかかってしまったから距離を短くするという考え方がある。
たしかに有効な方法のひとつです。
しかしそれは、こちらの調教技術が後退しているようで抵抗があります。
馬の能力をしっかり引き出すという意味ではやや安易な姿勢ではないかという気がするのです。
◎天皇賞秋とウォッカ
気を使ったのは同世代のダイワスカーレットにどのタイミングでぶつけるか。
競走馬は、短期間に同じ相手に3回競り負けるとダメ。
強い3歳馬なら同じレースに出ることも多く、気の弱い馬だと戦意喪失なんてことになりません。
2008年 ダイワスカーレットとの差はわずか2cm
◎マイルCS
マイルは馬の距離適性を見る分水嶺です。
マイル以下(1200m、1400m)のレースでは、スピードだけの一本調子の競馬でも勝てる、
しかしマイルはスピードも必要ですが、どこかでタメを作らなければいけない。
ジョッキーの指示をきちんと聞けるかどうか、ここに適性が顕れる。
ヨーロッパではマイル以下の距離の競馬は重要視されません。
角居厩舎ではスピード豊かな新馬でも、まずはマイルを走らせます。
少なくともマイルをきちんと走れる馬に育てたい。
JRAの平地G1のおよそ三分の一はマイル戦です。
どのコースも、ゴール前の直線が見ものです。
どこでタメを作っているのか。
馬がジョッキーの指示にきちんと反応しているのか。
そんな視点で競馬を見るのも面白いのではないでしょうか。
◎外国人騎手
エピファネイアくらいのパワーとスピードのある馬が、引っかからずに走るには騎手にもパワーが要ります。
大きい馬体で上下動が大きく、日本人騎手細い体と腕力では制御が難しいこともある。
それで仕方なく馬群の一番後ろにつけざるを得ない。
→へー、そうなんだ。ひっかかるのが怖いので最後方しかないということなのか。初めて知った。
しかし、外国人騎手は引っ掛かっても「押して」中団くらいで我慢できる。
スミヨンは身長があり(173cm)、体重も普段は54kgくらい。
足が長くて下半身に力があります、
馬の上下動の振幅を、足と下半身の力でうまく吸収できる。馬に不自由な思いをさせず、
膝の動きでスピードをコントロールするのです。
(ジャパンカップのエピファネイア)
「いつもなら行きたくて仕方がないのに、今日は4コーナーまで自然と抑えられちゃった。
直線、力を出し切るぞ。オッ、ちょうどゴーサインが出た」
→武豊も身長があるので同じような感じかな
ルメール、デムーロとの比較
ルメール 163cm
Mデムーロ 158cm
Cデムーロ 163cm
武豊 170cm
ムーア 167cm
◎阪神JF
ひと昔前、2歳馬の初期調教は翌年のクラシックに照準を合わせていたのですが、
セレクトセールの活況など情況のスピード化もあって、2〜3か月ほど前倒しになった。
本来、牝馬の資質を見定めるレースは桜花賞でした。
それが今では阪神JFになっています。
◎朝日杯の阪神開催は正解
中山1600mはコース形態が曲者です。
枠の有利不利がはっきりしている。
スタートして最初のコーナーを回ると、すぐに小さくカーブを曲がって3コーナーへ、
外枠は絶対的不利、内枠の先行馬は圧倒的有利。
しかも直線が310mと短く、力を出し切れないこともしばしばです。
高低差も大きく、馬にとってはタフなコースです。
ファンからすればコース的妙味があり、枠順の有利もオッズに反映されるのでいいかも知れません。
しかし陣営は違う。
王者を決めるコースとしてはどうなのか。
輸送負担もある関西の有力馬が参戦に二の足を踏む傾向がありました。
(朝日杯を阪神へ、中山では2000mG1を開催となって)
中山で行われるマイルG1はなくなりました。
師走のこの時期、有力2歳馬にとって大事なのは来春への「ものさし」を見つけること。
中山の朝日杯ではそれが適いにくかった。
14年からは直線が長い阪神の外回り1600mに変更になりましたが、やはりマイルを走ることで、
クラシックに向けた調教が難しくなる可能性が高くなります。
15年にはリオンディーズがデビュー2戦目でこのレースを制して一躍クラシック候補と言われました。
3歳春は弥生賞から皐月賞、ダービーと使いましたが、微妙に掛かりグセが顔を出し、結果を出すことができませんでした。
相手関係もあり、すべての原因が「このレースを使ったこと」とは言えませんが、
できるなら将来マイラーとして大成しそうな馬こそ、ここを使うようにしたいものです。
●ホープフルS ぴんとこない
中山に移ってからまだ3年ですが、どうしてもオープン特別という印象が拭えません。
この時期、関西馬が中山に遠制する意義を考えてしまいます。
関西の陣営からすれば、中山の馬場が悪くなっていく時期に出かけたくはない。
以上がG1レース このあとは重賞レース編となっている。
○冬のダート戦の効用
芝のレースが減る冬の競馬は工夫が必要で、冬の硬い芝を走らせるよりもダートを使ったほうがいい場合もある。
未勝利戦などは5着に入らないと次のレースの優先出走権が得られません。
いつまでも使えないよりはダートで掲示板に載れば、次は狙ったレースを使える……という考え方もあります。
ダートと比べて芝は軽いので、変速ギアの多い馬が有利です。
レース後のジョッキーのコメントに、「ギアが一段上がった」というのがありますね。
ギアが入る瞬間、馬体は微妙に沈み込む。
その時、路盤が柔らかいと加速がつきません。
硬い路盤が変則ギアを活かすのです。
だから芝向きの馬を砂で走らせる妙味があります。
ただし冬限定。ずっとダートを走っていると、どうしても本来のスピードが落ちていくんですね。
→ふーん。そんなことがあるのかと勉強になりました。
●金鯱賞の度重なる開催時期変更に苦言
G2レースの施行時期がしょっちゅう変わるというのはどうでしょうか。
古くからの競馬ファンというのは、重賞レースと季節感を結び付けてとらえます。
かえってレースの注目度を削ぐことにはならないでしょうか?
→そうだ、そうだ、その通り!!
◎ポップロックの好走とペリエ騎手
私はヨーロッパの騎手の手綱さばきに改めて着目するようになった。
彼らは一様に脚が長く、下半身に力がある。」
その特徴をフルに使って馬の上下動の振幅を制御する。
馬に不自由な思いをさせず、膝の動きでスピードをコントロールできる。
強い筋力を前提にした巧な騎乗でこそ、強い馬は動かせる。
そう確信できた意味でも、ターニングポイントになった馬です。
9歳まで日本で走った後はアイルランドで現役を続け、引退後はチェコで種牡馬になったと聞いています。
私の仕事は、預かった馬を種牡馬として返すこと。
それが叶った馬でもあります。
第3章は競走馬の四季。生まれてから競争馬になるまでの推移を解説してくれています。
◎脚の振り方
(牧場での騎乗運動で)この時期、私が注目するのが脚の振り方です。
内側から外に振りだすタイプと、外から内へ脚を巻いてくるタイプがいる。
馬体の中心上に脚を持っていくとスピードが出るので、脚はどうしても内向します。
脚が内向きのタイプだとさらに内側に蹄を回すため、故障につながりやすい。
内から外へ脚を振りだす馬の方が安全です。
◎新馬戦のジョッキーは大切
鞍上の指示に従わせ、馬に余計なストレスを「残さず、きちんと競馬を教えてくれるジョッキーがいい。
斤量は軽いほうがいいに決まっていますが、技量のほうがはるかに大事です。
◎新馬の距離
かつて早い時期の新馬戦といえば1200mなど短い距離ばかりでした。
ところが短い距離だと必ずスタートから押されるので、タメる競馬ができずにゴール板を駆け抜けることになる。
我慢が利かなくなる危険性があるわけです。
角居厩舎では基本的に逃げ馬を作らない。
2歳のうちに、きちんとタメることを覚えさせます。
なのでクラシックを狙う馬は秋の東京あたりをデビュー戦に選んでいます。
最近では夏場に1800mの新馬戦があるので、クラシックを狙う馬でもデビューが早くなり、選択肢が広がりました。
スタートで押されても、タメを作る場面があるので競馬に幅が生まれます。
次走がぐっと楽になるんですね、。
ただし角居厩舎のスタートは比較的ゆっくりです。
ウチの厩舎のように、芝の中距離以上のレースに使っていきたい場合は、新馬戦や未勝利戦に勝ってしまうと
次に使うレースがあまり多くない。
だから夏場に入厩してもゲート試験だけ受かって、牧場や外厩に戻しておくことも多いのです。
○冬場のスタッフ
馬に跨る人間も元気でなければいけません。
人馬の齟齬を防ぐため、ウチでは調教前にスタッフの身体をしっかりほぐしておきます。
馬以上に動いてもらわなきゃ困る。
冬は鞍上の動き、配慮がカギを握るんですね。
○なぜひとつも勝てないのか
大敗の理由はわかりやすい。
しかし2着や3着が数回続くような場合、惜しい競馬だったというより、その方が居心地がいいと思っている可能性があります。
3頭併せの馬なりの調教を繰り返していると、抜きんでるよりも並んでゴールすればいいと勘違いすることも。
そのあたりを疑えば、坂路でしっかり差をつけて交わす調教に切り替えます。
不調の核を見極める感性が必要です。
○地方競馬での再生
とにかく一度勝てば、多くのことが好転すると期待したい。
そういう馬には「出戻り」が大きな選択肢となります。
ダートで走れて先行力があり、小回りが得意なタイプならば、地方に出す決断をします。
◎サンクスホースプロジェクトhttp://www.thankshorseproject.com/
→こんな試みをしているとは知らなかった。いいことだと思う(2016年3月発足)
ホースセラピー業界や養老活動団体との連携も図ります。
障害を持っている人や高齢者が馬と接することで元気になって下さる。
馬は人間の気持ちの変化がわかるので、人が喜べば馬も幸せになります。
こころが通いあうんですね。
引退後の競争馬の生きる道を作ったこのプロジェクトは
生産界へ戻せない馬でもなんとかしてあげたいという
同師の思いからできたプロジェクトでいいなととてもいいなと思った。
○夏の水
馬は人間を含めた動物の中で最も大量に汗をかき、大量に水を飲みます。
1日に30リットル以上!
それだけ水分循環に優れている。
栗東の水は美味しいと言われていますが、ウチでは専用の機械を通して水素水を飲ませています。
いい水を飲んでいるわけです。
ゴクゴクと水を飲んで上手に汗をかける馬は熟睡できて、夏バテしません。
●降級馬でも
一度崩れてしまった馬は、いくら降級して相手の力関係が下がるからといっても、すんなりと勝てるとは限りません。
レースで悪い負け方をした場合、調教も崩れていることが多い。
馬券検討のひとつとして、降級馬が、それまでのレースで崩れていないかどうかを見極めることが大事です。
◎日本の競馬を変えたセレクトセール
この時期にセレクトセールが行われるおかげで種付けが早くなった。
当歳馬は大きく成長しているほうが高く売れるので、通常は3〜4月に出産するところを、1〜2月に早めるようになった。
そして7月の晴れ舞台で輝く馬体を披露するために、栄養管理や昼夜放牧のシステムが発達しました。
…
ダービーの翌週から新馬戦が行われるようになったのも、無関係ではない。
競馬界はセレクトセールを起点にして動いているといってもいいかも知れません。
◎放牧明け
大事なのは休み明けの所作、休み前に頑張れば頑張ったほど、休み明けがキーポイントになります。
調教で絞り上げて競馬で強く走ることを「丸めて弾ける」と表現します。
→初めて聞いたわ
強い馬ほどそれを繰り返す。筋肉の収縮度合いが強まり、大きく跳べるようになる。
しかし長期休養に入れると筋肉が緩んでしまい、休み明けに「丸められる」ことに大きなストレスを感じやすい。
伸びた筋肉が丸まることを拒否する。調教が難しくなるんですね。
もちろん放牧は馬体を休ませるためにあり、メンタル面でのリフレッシュ効果も無視できない。
強い馬ほどその兼ね合いが難しい。
放牧は諸刃の剣です。
◎騎手のタイプ「柔らかい」か「強い」か
能力があって引っ掛かり気味の馬には、柔らかい手綱がいい。
馬が力を出したがって行きたがるのだから、強く制することができる「強い」騎手のほうがいいのでは、
と思われるかも知れませんが実際は逆です。
スタート後、馬が行きたがったっり、前の馬との距離が詰まっていたりすると、騎手はスピードを抑えたくなるのですが、
そこで強く手綱を引くと馬は余計にひっかかってしまう。
行きたがっている馬の気持ちを酌み、手だけでなく膝や腰を巧く使って馬のエネルギーを抜いてやる。
それが「拳が柔らかい」ということ。
代表格は武豊騎手、福永祐一騎手、浜中騎手、四位騎手などです。
逆に、エンジンのかかりにくい「ズブい」馬には、強く追える騎手がいい。
こちらの代表格は岩田騎手、内田騎手、川田騎手です。
開業当初、デルタブルースの鞍上をまだ地方騎手だった岩田騎手に依頼したのもそのためでした。
◎ジョッキーは馬に嫌われる?
馬にとって競馬場はストレスを感じる場所、そこに登場するカラフルないでたちの人がレースで激しく追ってムチを振るう、
馬にとって怖い存在です。
ジョッキーは馬に嫌われてこそ。
精一杯追って、馬の能力を最大限に引き出してもらわなくてはいけません。
いきおい、リーディング上位のジョッキーに依頼することが多くなります。
だから角居厩舎では、若いジョッキーを育てる意識はやや希薄です。
「馬に嫌われる」までになるには最低3年。
素質馬を多く預からせていただいているので、新馬戦からきっちり馬に競馬を教えてくれるジョッキーに手綱を託すことになります。
腕を信じているから、あまりジョッキーへの指示はしません。
★一人の腕利きより5人の平均的厩務員
腕利き厩務員が厩舎を牛耳ってきた時代、思うように仕事が進められないもどかしさを持っていた若手厩務員や調教助手たちは、
ずっと「このままでいいのか」という思いを溜め込んでいました。
私もその一人で、自分の思うようにさせてくれないイライラが募っていました。
私が調教助手として師事した松田国英先生も、ある時期いた厩舎では腕利きの調教助手がいて、
あまり乗せてもらえなかったそうです。
調教師試験に合格してからは、1年間森秀行厩舎で勉強し、開業後はチームとしての厩舎運営を始めました。
私も3年間、松田先生のチームの一員としてみっちり鍛えられました。
一人の腕利きよりも、5人の平均的な厩務員。調教師が思い切ったリーダーシップを発揮し、
誰がどの馬を担当しても勝利に持ち込めるように仕上げる。
これが厩舎のチーム力です。
★進上金プール制
角居厩舎では担当の総取りではなく3:2に分け、2%を厩舎にプールしておく。
厩務員の頭数で割って配分します。
すると「勝った馬はオレがつくった」という傲岸な意識は薄まり、厩舎全体で勝ち鞍を稼ぐチーム気質が
生まれてきます。
進上金の5%を全部プールする厩舎もあるようです。
進上金のプールは、腕利き厩務員が若手を育てる動機づけになる。
若手の育てた馬が勝てば、自分の懐も潤うわけです。
お金のことではあるものの、そうやってチーム力が向上していきます。
◎「引っ掛かる」人のほうが成功する
調教師は馬をつくることと同時に人をつくります。
人を育てて、厩舎力を高めます。
チームで馬をつくっていけば、皆が厩舎のやり方を理解して実践してくれるので、
成績がガクンと落ちることはないと思います。
…
チームとは不思議なもので、メンバーはリーダーに従順であればいいとは限りません。
厩務員、調教助手は前進気性があったほうがいい。
意見を言い過ぎる、やりすぎるくらいのほうが能力がわかるんですね。
馬と一緒で、おとなしいよりも気性が強くて、引っ掛かるほうが勝つ。
強い気性をリーダーがどうやってコントロールするかだけの問題です。
私も調教助手時代はそいういうタイプでしたし(笑)。
●マンネリ心配?
現在角居厩舎には馬に乗れる調教厩務員が15人、攻め馬専門の調教助手が3人います。
ありがたいことに角居厩舎を気に入ってくれているのか、顔ぶれはあまり変わらない。
そうするとどうしても新鮮さが失われてきます。
2016年、「勝利数は増えたけれど重賞が1つしか取れなかった」というのは、
もしかしたらその弊害かも知れない。
→重賞1つとは信じられない低さである。
あれだけの素質馬を預かっていてこれでは多分馬主から相当文句を言われていることだろう。
成功体験に固執せず、守りに入らずチャレンジしていく、リーダーにはその気概が絶対に必要です。
→これは決意表明とみたい。
そういえば最近角居厩舎の馬はじれったい成績である。
調べてみたら、2017年11月現在 G1 1勝、G2 2勝、G3 1勝とまずまずでしたわ。
○調教の変化
追い切りの方法も以前と今では違います。
たとえば併せ馬。以前は、先行馬の外側から能力の高い馬が追い抜くパターンでした。
しかし藤沢和雄先生が固定観念を覆してから調教理論がより進化して、
先行するのが強い馬になった。
能力の高い馬を、若駒や課題のある馬が追いかける。
追う馬は初期の調教が多く、強い馬を目標にさせるわけです。
走りかたからスピードまで、模倣させる意味もあります。
馬は先行馬に追いついて抜きたいから、単走よりも強い調教になる。
その本能を刺激します。
しかし、力のある馬はなかなか抜けるものではない。
「かなわないな」と諦めさせてもいけません。
そこで工夫がいります、
3頭併せのとき、先行した強い馬を大外に走らせ、おいかける2頭を内側に入れる。
巧くコーナーを立ち回らせれば抜けるはずです。
強い馬の立場になれば、後進には負けられない。
コースハンデがあっても抜かれないように頑張る。
そういうことを教えるのです。
→なるほどねー。
たしかに藤沢厩舎の追い切りは多彩であるが、こういう意味があったとは知らなかった。
これからグリーンチャンネルの調教ビデオもしっかり見てみよう。
●調教師はホンネは言わない?
2頭併せで、先行させた馬を抜かせるように目論んだのに抜けなかったとします。
そういう調教の意図は、こちらからは言わないものです。
記者に聞かれたとしても、「先行馬はオープン馬だし、抜かせるような調教じゃなかった」
なんてケムにまくかもしれません。
何も私の性格が悪いというわけではなく、調教師とはそういうものなんです。
たとえ信頼できる記者に対してでも、
「そう簡単に分かられてたまるか」という思い(自負)が調教師にはあるように思います。
→コメント頼みではなく、しっかりみて判断して下さいということか。
◎勝てない馬はパドックでわかる
落ち着いて周回できない馬。これは見ていても分かります。
騎手の指示にきちんと従わなくては競馬には勝てません。
パドックで馬に指示を出すのは引いている人間(主に厩務員)。
その者の言うことに耳をかさず興奮している馬は期待できません。
同様に、鳴いたり色気を出したりする馬も集中力を欠いている。
馬っ気を出す「私は一番強い!」という主張は幼さの裏返しで、じっと我慢できない証拠です。
やはり我慢できる馬が強い。
ガキ大将か優等生かというなら優等生タイプです。
ガキ大将のほうが大きな可能性を感じさせるような気もしますが、
きちんと調教を経ているわけですから、暴れるよりも我慢するほうが高レベルです。
クラスが上がれば上がるほど我慢の度合いが重要になります。
→ パドック派の私としては納得の説明である。
◎角居調教師の理念
開業から16年。勝ち鞍も増え、調教師としての技術も進化してきてはいますが、理念は同じです。
☆ 実績を重ね、馬を生産界へ戻してやること
☆ 世界に通用する馬をつくること
年ごとの具体的目標は400走以上で60勝、これも変わっていません。
→ 今後とも注目厩舎、調教師である。