TBSブリタニカ 仁平和夫
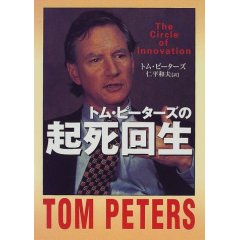
Sさんに教えてもらったトム・ピーターズ。
読んでみたがとても面白い。
この本はイラスト、写真がふんだんに入っていて読みやすい。
小笹さんの本を読んだときにイラストの効果を痛感したが、
その本家はトムではなかったかという気がする。
ハッパをかけられる。トム・ピーターズが言う「ワーオ!」を求めよである。
この後、ドラッガーを読んだが言っていることは通じるものがあると感じた。
プロローグ
☆ トム・ピーターズは「知」よりも「心」の人間である。
ディーン・レバロン 第一線の証券研究者にして常軌を逸した機関投資家(ハーバードビジネススクール刊行の「輝かしき同窓生」での紹介)
によるトム・ピーターズの紹介
同じことを冒頭でトムが信条として語っています (10個挙げてますが最初の2個だけ記します)
1 私はビジネスが好きである
2 私はビジネスは心だと思っている。それだけだ
すごい製品。感動するサービス。細かい気配りを忘れない人たち。
顧客や製品に情熱を燃やすリーダー。
百花繚乱。百家争鳴。
その集合体がビジネスだと思っている。
(すなわち、ロバート・マクナラの対極に位置するのが、トム・ピーターズなのだ。)
第1章 距離は死んだ
第2章 やるんだったら破壊
☆ 改善だけでは越えられない溝がある。
漸進主義はイノベーションの最大の敵。
進化はどうでもいい。革命を考えろ。
組織は、変えるより壊すほうが簡単だ。
そのために変人、奇人を集める。
壊すことを真剣に考える。(ドラッガーも同じことを言っている)
第3章 忘れなければ生きていけない
☆ 細かいことは忘れろ
イノベーションを目指すなら、すばやく試作品を作れ
遊び心を大切に、新しい発想にいつも心を開くこと
☆ 失敗を忘れろ
第4章 誰だってミケランジェロになれる
「人々が(教会)礼拝にお供物を持ってくるのは、毎日の仕事とは違う、何か大切なことをやりたいと思うからだ」
と述べていることにブー!!
毎日の仕事を大切なものにすべきではないのか!!
トムの言うとおりだ!
フットボールのコーチは現役のクォーターバックほどボールをうまく投げられない。
オーケストラの指揮者は第一バイオリンの奏者ほどバイオリンをうまく弾けない。
コーチング、指揮、演出とは、要するに、イノベーションの追及、オリジナリティの追及、新しいものの追及である。
あるいは、緩めたり、締めたりすることと言ってもいい。
それこそがエクセレントの極みである。
清掃のミケランジェロが会社にいるか?
⇒ この言葉には打たれた。
第5章 ホワイトカラー革命
☆ 新しいプロフェッショナルの条件
1 (ひときわ)ぬきんでた能力
⇒ トムは「タレント」と称している
2 プロジェクトこそすべて
3 顧客サービスに熱中(目に見える結果を出す)
4 ネットワークづくりの名人
5 自立心旺盛。みずから、わが巌にならん。大樹の陰に寄らず。
⇒ 私は4,5は合格だと思うが…
第6章 すべての価値はプロのサービスから
購買でも、ワーオ!は起こる
情報システムでも、ワーオ!は起こる
ロジスティックスでも、ワーオ!は起こる
その他どんな分野でも、ワーオ!は起こる
そう考えないのであれば、(悪いけど)あなたには問題がある。
5つのP プロジェクト、プロ化、挑発(Provocation)、パートナーシップ、パフォーマンス
あらゆる仕事をプロジェクトに変えよ!
第7章 中間管理職は絶滅の危機
☆ 中間削除、ガラス張り、顧客のエンパワーメント
第8章 システムこそ命
システムは「美」にあり :美しく、優雅で、明確で、簡潔であるべき
システムエンジニアリングは美術部に名称変更すべき
⇒ この言葉にはハッとした。
今日から始めよう。
たとえば次のような伝票・書類を机に並べ
航空貨物運送状、返品処理規定、請求書、病欠規定
並べたら、次の項目に基づいて10点満点で採点してみよう。
官僚色皆無が10点、官僚プンプンが1点、4,5人の同僚と相談しながら採点するのがベスト
美しさ
無駄のなさ
優雅さ
焦点
1回だけで終わらさず、これを毎週繰り返す。
IRL(知識調査研究所、カリフォルニア州)によれば、
組織が正式の会議やコンピュータから学ぶことはほとんどなく、非公式の「言葉のやりとり」から
学ぶことが多い。IRLは、これを「実習コミュニティ」と呼んでいる。
IRLの研究によれば、たとえば、効率性だけを追求する「心なき」リエンジニアリングは
− もし、共同学習んお基盤になる「実習コミュニティー」をうかつにも壊してしまうようなことがあれば −
取り返しのつかない打撃を組織に与えかねない。
こいつは結構難しい。たとえば、航空管制センターの効率を上げようとして、騒音を遮断するヘッドホンを管制官に
つけさせたらどうなるか。
生産性はむちろ落ちる。なぜ?管制官は、まわりの同僚のおしゃべりを聞くともなしに聞きながら、多くのことを
学んでいるからだ。その騒音をカットしてしまえば、効率は悪くなる。IRLの調査結果ではそうなっている。
⇒ 直感的に私はこのことを理解している。
だからがんばるタイムなどとフロアーを1時間も無言にしてしまう愚挙をやっているのを見ると腹がたってしまう。
☆ システムの社交面
ハイテク企業のCEOハティム・チャフジは自他ともに認める技術屋だが成功のカギは
「5%がテクノロジーで、95%が心と姿勢だ」と断言する
共有。自然に出来上がっていく組織。それがキーワードだ。
そしてそれはそう簡単に手に入るものではない。
チャフジは共有の広がりが大切だと力説する。
CEOでありながら、ほとんど本社にいない。
すぐに走り出す文化。
すべてを共有する文化という福音伝道のために、いつもあちこちを飛び回っている。
第9章 欲しくて悶える
「問題は何もない。ただ無難だけが取り柄かも」
これを聞いた社長は「無難だけが取り柄一掃キャンペーン」に乗り出した。
バーガー・キング社の反撃が始まった
ありふれ化の波が品質改善運動を呑み込む。
ありふれ化は必然にあらず。規格どおりの品質ほど、質は悪い!
ありふれ化にノーと言え。
ワーオ!にイエスと言え
ドメインが目指すワーオ!
ドメインでは、家具を売りません。夢を売るのです。
第10章 ブランドや、ああブランドや、ブランドや
・エナジーワンは 断然、目だっている
電力業界 あまり名の知られていないユティリティコープ(カンザスシティー)のトップは
供給する電力をブランドにするという使命感に燃えている。
・ サザン電力 ビル・ダールバークCEO
「人は、電力会社のことを考えるとき、誰の顔を思い浮かべるか?
誰の顔も思い浮かばない」
☆ どうすれば 断然、目立てるか
寝ても覚めてもブランド、ブランドと唱えよ
第11章 タレント鑑定家になろう
☆ マーシー・カーシー(カーシー・ワーナーの創立者)
私は会社を経営するのが大好きだ。
みんなが一緒になって、いい仕事をするのが大好きだから。
…いろいろな人たちが集まり、力を合わせて働くことが好き。
無から何かを生み出し、誰もが充実感をおぼえるようにしたい。
それは簡単なことではないし、挫けそうになることもあるけれど、
つねに目標を見失ってはいけない。いったい何をしたいのか?
何をするにせよ、結局のところ、美しき生きることが目標なのだ。
☆ 態度を見て雇え、技能は後から鍛えればいい
1 知識は変わる。資質は変わらない。
2 探していない人を見つけることはできない
3 人を評価する最善の方法は、仕事ぶりを観察すること
4 応募してこない人を雇うことはできない
(ピーター・カーボネラ)
☆ 「他人の才能を心から喜ぶ」
これこそまさに、名コーチになる条件だ。
☆ 採用の基準は何より多様性
他のことはあとでどうにでもなる
多様性を雇い、多様性を育む
☆ 人の価値も減損する
第12章 ウーマンパワーが世界を動かす
女性の力を活かし、女性の市場に目をむけている会社は(呆れるほど)少ない。
なんて、もったいない!
自動車購入の決定の65%は、女性が下す。
なのに、自動車の女性セールスマンは7%しかいない。
女性が決定権を持っている比率(オーストラリアでの調査)
家具購入 94%
休日の過ごし方 92%
住宅購入 91%
銀行口座の開設 89%
医療保険の加入 88%
☆ 男と女では、買い物する理由が違う
男はただ取引したいと思い、女は関係をつくりあげることに関心がある
オリンピックの競技で、男性は、勝者と敗者を見届けるまでテレビの前を離れようとはしない
女性は選手がどういう人か、どうやってオリンピックに出場できたか、
そのためにどんな犠牲を払ったかを知りたがる。
女性は一体感を求めており、その渇望は女性の心に深く根をおろしている
男は「切り離す」ことに熱中する 権威でも家族でも
何でも自分ひとりのものにしようとする。
女たちは「つながり」を大切にする
男は権利を心配し(他人の権利を尊重し)、女性は権利よりも責任を心配する。
男は序列がはっきりしたヒエラルキーを好み、
女は、みんなが仲間になることを目的とするネットワーク型の組織を好む
そして、もうひとつ大きな違いがある。
問題を解決するためには、男はどんな争いも辞さないが、女は愛情と保護を重視する
第13章 大きな差がつくのは、いつも小さなこと
デザインの重要性を訴えている
☆「正気か!」と言われたことは、やったほうがいい。
「それはいい」と言われたら、それはすでに誰かがやっている。
御手洗 富士夫(キャノン社長)
☆ 燃え上がるには熱狂が必要!
偉大な交響曲を作り上げるのは、想像を絶する高みにのぼりつめようとする演奏者一人ひとりの力である。
楽譜をなぞるだけでは、偉大な交響曲はできない。
演奏者一人ひとりが音に魂をこめないかぎり、聴くものの胸を打つことはない。
これを会社に当てはめると、どうすればいいだろう。
「熱狂ばらまき主任」というポストをつくったらどうか。
☆ 燃え上がるには病的執着が必要! そして仲間が必要!
以 上