「国家の品格」
新潮社
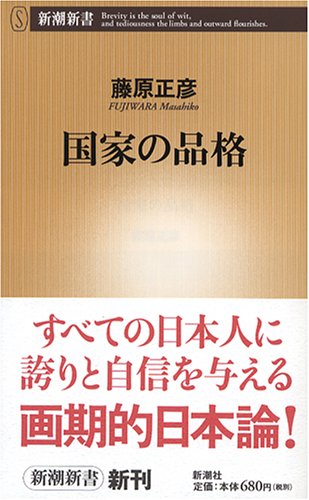
この国のけじめとダブル部分はカット
Sさん
思っていたとおりの答えでした。
お気に召さないだろうなというのは直感的に感じていましたので。
その理由をはっきり聞くことができました。
>「この国のけじめ」は全くピンときません。
>マックナーニ氏の主張は同じ山に登っているという”共感”と、
>現代の組織が抱える問題をWin-winで解決する本質的なアプローチだという”確信”があります。
>しかし藤原氏の主張は価値観としてはあっても良いと思いますが、登っている山は違うと感じますし、
>武士道精神(伝統的日本的価値観)が現代の問題のソリューションになるとは思えません。
ただ私はマックナーニ氏の
「家庭と会社の価値観は同じ」
という言葉に反応しました。
その意味から、社会全体の価値観が望ましいものにならない限り
幸せなゴールはないのではないかと思った次第です。
昨日自宅に帰ると家内が「国家の品格」を借りてきてくれていました。
文庫本ですぐ読めそうです。
それを60ページほど朝読みましたが、そこでもいいことが書いてありました。
藤原さんは最初からこの考えではなかった。
自分で変わったのでした。これを知ったのがよかった。
藤原さんはアメリカで3年。
論理の世界になじんで日本へ帰って「論理、合理性」一本で勝負した。
しかし日本では浮いた。
そしてイギリスへ1年。
そこで伝統を重んじる文化、価値観に接し、論理だけではダメ。
むしろ情緒が大事と悟る。
なんと、まさにエプソン花岡社長の説かれる「情と理」でした。
論理もその「出発点」が間違っていると、後の論理が正しければ誤りとなる必然。
(頭の悪い人間の方が途中で論理的に間違えて正解になることはある)
○論理には出発点が必要
出発点Aを考えてみると、AからBに向かって論理という矢印が出ていますが、Aに向かってくる矢印はひとつもありません。
出発点だから当たり前です。
すなわち、このAは、論理的帰結ではなく常に仮説なのです。
そして、この仮説を選ぶのは論理ではなく、主にそれを選ぶ人の情緒なのです。
宗教的情緒も含めた広い意味の情緒なのです。
情緒とは、論理以前のその人の総合力といえます。
→ 我々の言う「人間力」も同義ではないでしょうか?
その人がどういう親に育てられたか、どのような先生や友達に出会ってきたか、
どのような小説や詩歌を読んで涙を流したか、
どのような小説や詩歌を読んで涙を流したか、
どのような恋愛、失恋、片思いを経験してきたか。
どのような悲しい別れに出会ってきたか。
こういう諸々のことがすべてあわさって、その人の情緒力を形成し、
論理の出発点Aを選ばせているわけです。
出発点の例として、1週間何も食べていない人間のパン泥棒
・日本は法治国家である。 窃盗罪だ。法律で処罰すべき → 捕まえる
・可哀想。人間の命は一片の法律よりも重い → 見逃す
論理はいずれも正しい。
花岡さんの言われる「情と理」
感覚的にはしっかり受け止めていましたが、こういう説明をきくと、
その順序も内容もわかったようになります。
返信1
--------------------------------------------------------------------------------------
>藤原さんはアメリカで3年。
>論理の世界になじんで日本へ帰って「論理、合理性」一本で勝負した。
>しかし日本では浮いた。
>そしてイギリスへ1年。
>そこで伝統を重んじる文化、価値観に接し、論理だけではダメ。
>むしろ情緒が大事と悟る。
プロジェクタを担当したほとんどの期間の大ボスI事業部長(PJ-X時の事業部長の後任)を思い出しました。
北米とシンガポール合わせて10年近い海外経験のある方でしたが、私は当初、
自分の考えをハッキリ出さず皆の意見を言わせてから決定するマネジメント手法にもどかしさを感じていました。
決断が遅れる、または軸が定まらないと感じたからです。
たしか2002年の秋、直属の上司部下の関係で親しく口が聞ける関係になっていたある飲み会の席上で疑問をぶつけました。
「私は短気で本当はアメリカ式にトップダウンでことを進めたい、でもその手法は日本では通用しないと考えこうしている」という返事でした。
それ以上の説明はありませんでしたが、「合資形成の文化」と共に「部下に考えさせ力を引き出す(=成長)」があると理解しました。
Iさんは専務まで昇任され3年前退職され、年に5−6回ゴルフでご一緒しています。
>なんと、まさにエプソン花岡社長の説かれる「情と理」でした。
「国家の品格」を読んでいないので何とも言えませんが、ニュアンスが少し違うかもしれません。
花岡社長のこの言葉は、企業風土改革の方針として”行動の軸=実現力””マネジメントの軸=人間力”と位置づけられ、
人間力とは”情と理”であると説明されています。
実感としてはまず”理”、シナリオがあり、社員全員の力がなくては実現できない、だからマネジメントには”情”が重要という印象です。
私個人とは”情”への比重のかけ方が若干違いますが、100%支持しています。
>すなわち、このAは、論理的帰結ではなく常に仮説なのです。
>そして、この仮説を選ぶのは論理ではなく、主にそれを選ぶ人の情緒なのです。
>宗教的情緒も含めた広い意味の情緒なのです。
>情緒とは、論理以前のその人の総合力といえます。
仮説立案も総合力も論理+情緒だと私は思います。
-------------------------------------------------------------------------------------返信2
ついに道場にも出ましたね、「国家の品格」。
発行部数は、すでに200万部を超えているそうで、これは、あの「バカの壁」よりはやいスピードでの200万部突破だそうです。
天邪鬼なところのある私としては、正直
流行本を読むことにちょっと抵抗もあったのですが(笑)、
この本は、読んでみて「わが意を得たり!」との思いを感じたました。
S>「この国のけじめ」は全くピンときません。
S>藤原氏の主張は価値観としてはあっても良いと思いますが、登っている山は違うと感じますし、
S>武士道精神(伝統的日本的価値観)が現代の問題のソリューションになるとは思えません。
志>思っていたとおりのSさんの答えでした。
志>お気に召さないだろうなというのは直感的に感じていましたので。
私も、志賀松さんと同じです。
おそらく鈴木さんは、藤原氏の主張になにか違和感を訴えられるのではないか、私もなんとなくそんな気がしていました。
確かに、暴論や押し付けがましさを感じる部分もありますので・・・
ただ、私には、心に響くものがありました。
国際社会の中での日本を強く意識し、日本人の個性や有り様について、非常にわかりやすく平易に、しかも力強く書いてある本で、
多少大げさにいえば、数年前、映画「ラストサムライ」を見て、日本人である「自分」のアイデンティティを深く認識し、号泣したときに通じる感覚がありました。
(さすがに、この本を読んで泣くことはなかったですが・・・〔笑〕)
いまの日本、日本人は自分自身を見失っているのではないか、
それは、アングロサクソンの優れている部分と日本人の得意でない部分を比べているせいではないか、
自分たちが飛躍する、さらに成長するためには、日本と欧米を、どっちが優れているか、といった対立軸、単純な優劣比較と捉えるのではなく、
アングロサクソンの優れているところを認めるのと同じように、日本の伝統的な価値観や自分たちの優れているところを再認識するところからスタートする
必要があるのではないか、と思います。
自己革新のためには、“自己否定”も必要だけど、そのベースにはまず“自己肯定”がなければいけないのではないか、
欧米人のいいところを真似るために、自分たちのいいところまで捨てる必要はない、
世界に唯一無二の、日本人という自分たちの個性に誇りをもつべき、誇りを大切にすべき、
と思います。
私は、この本を、単に日本礼賛、伝統懐古を謳った本というのではなく、
歴史に根ざした自分たちの、かけがえのない文化、伝統的価値観を大事にしながら、そのうえで欧米人の優れた部分を取り入れることをすすめた本と、
理解しています。