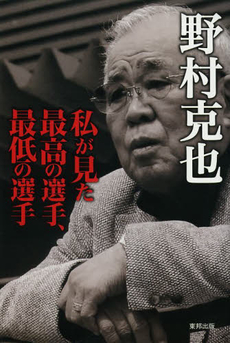
پuژ„‚ھŒ©‚½چإچ‚‚ج‘IژèپAچإ’ل‚ج‘Iژèپv
پ@–ى‘؛پ@چژ–çپ@پ@“Œ–Mڈo”إ
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@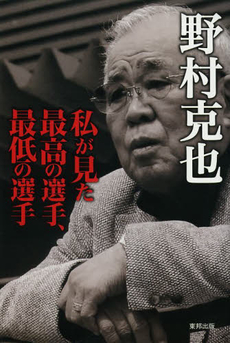
گVٹ§‚إ‚ ‚éپB
‰ئ“à‚ھگ}ڈ‘ٹظ‚©‚çژط‚è‚ؤ‚«‚½پB
–ى‘؛‚³‚ٌ‚ھƒvƒچ–ى‹…‚ة“ü‚ء‚½‚ج‚ھ‚P‚X‚T‚S”NپB
ژ„‚ھگ¶‚ـ‚ꂽ—‚”N‚ج‚±‚ئ‚ب‚ج‚©پB
ٹھ––‚ة‚»‚ج‚P‚X‚T‚S”N‚©‚ç‚جƒmƒ€‚³‚ٌ‚جƒ{ƒ„ƒL•t‚«—ً‘مƒxƒXƒgƒiƒCƒ“
‚ج•tک^‚ھ‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ھپAگج‚ح‚و‚ƒvƒچ–ى‹…‚ًŒ©‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ب‚آ‚©‚µ‚¢پB
–{•¶‚ج•û‚إ‚حپAچإچ‚‚ج‘Iژè‚ح‚¢‚¢‚ھپAچإ’ل‚ج‘Iژè‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح
‚»‚ٌ‚بˆ«•¶‚إ‚ح‚ب‚پA‚»‚ٌ‚ب‚ة–â‘è‚ح‚ب‚¢‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚½پB
‰؟’lٹدپAگlگ¶ٹد‚جˆل‚¢‚à‚ ‚é‚ج‚إپA•]‰؟‚ھ’ل‚¢‘Iژè‚àƒvƒ‰ƒCƒh‚ح
ڈ‚آ‚¢‚ؤ‚ح‚¢‚ب‚¢‚¾‚낤‚ئˆہگS‚µ‚½پB
‚¢‚‚آ‚©‹L‰¯‚ةژc‚ء‚½ƒtƒŒپ[ƒY‚ھ‚ ‚é‚ج‚إڈ‘‚«—¯‚ك‚ؤ‚¨‚±‚¤پB
گ´Œ´‘Iژè
ƒzپ[ƒ€ƒ‰ƒ“ƒoƒbƒ^پ[‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‘fژ؟‚حژ„‚≤‚ً‚ح‚é‚©‚ة—½‚¢‚إ‚¢‚½‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚à
‰كŒ¾‚إ‚ح‚ب‚¢گ´Œ´‚ھپAŒ‡“_‚ًچژ•‚إ‚«‚¸پi“àٹp‚ھ‘إ‚ؤ‚ب‚¢پjپA‰¤‚ح‚¨‚ë‚©ژ„‚ج
–{—غ‘إگ”‚à’´‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½پB
‚±‚ج‚±‚ئ‚ًژv‚¤‚ئپuŒ‡“_‚ھ’·ڈٹ‚ًڈء‚·پv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚»‚ج’ت‚肾‚ئژv‚¤پB
پu’·ڈٹ‚ًگL‚خ‚·‚ة‚حپA’Zڈٹ‚ً’b‚¦‚ëپv‚إ‚ ‚éپB
‚â‚ح‚肱‚ê‚ھگ³‚µ‚¢پB
‹{–{‘Iژè
‹{–{‚ة‚ئ‚ء‚ؤپAƒSƒچ‚ً“]‚ھ‚·پA‰E•ûŒü‚ض‘إ‚؟•ش‚·‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئژ©•ھ‚ھƒ`پ[ƒ€‚ة‹پ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚¾‚ء‚½پB
‚·‚ب‚ي‚؟پuڈo—غ—¦‚ًچ‚‚كپAگi—غ‘إ‚ًگS‚ھ‚¯‚éپv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚¾پB
‚»‚µ‚ؤژç”ُ‚ً–پ‚‚±‚ئپB
”½•œ—ûڈK‚ھŒب‚ً–پ‚¢‚ؤ‚¢‚پB
پu•½–}‚ج”ٌ–}پv‚ئ‚¢‚¤Œ¾—t‚ھ‚ ‚éپB
•½–}‚ب—ûڈK‚ة‚àˆس–،‚ھ‚ ‚èپA‚»‚جˆس–،‚ً—‰ً‚µ‚ؤ“w—ح‚ًڈd‚ث‘±‚¯‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚حپA
’N‚ة‚إ‚à‚إ‚«‚邱‚ئ‚إ‚ح‚ب‚¢پB
‚»‚ê‚ح‚à‚ح‚âپu”ٌ–}پv‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB
‹{–{‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚جپu•½–}‚ج”ٌ–}پv‚حپAپuƒSƒچ‚ً‘إ‚½‚ب‚«‚لپA‰E‚ض‘إ‚½‚ب‚«‚لپv‚ئ‚¢‚¤
ƒoƒbƒeƒBƒ“ƒO—ûڈK‚¾‚ء‚½پBژ„‚جژwژ¦‚ًگM‚¶پAپuٹؤ“آ‚³‚ٌ‚ج–]‚ق‚و‚¤‚ب‘Iژè‚ة‚ب‚ç‚ب‚«‚لپA
ژg‚ء‚ؤ‚à‚炦‚ب‚¢پv‚ئژ©ٹo‚µ‚ؤپAƒSƒچ‚ً‘إ‚آ—ûڈK‚ً“O’ꂵ‚½‚ج‚¾‚낤پB
‚»‚جŒ‹‰ت‚ھ‚Q‚O‚O‚Oˆہ‘إ‚إ‚ ‚éپB
پuƒvƒچ‚ئ‚ح“O’ê‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًپAژ„‚ح‹{–{‚©‚çٹw‚ٌ‚¾پB
چ‚ˆن‘Iژèپiچم‹}‚ج‘م‘إ‚جگط‚èژDپA‘م‘إƒzپ[ƒ€ƒ‰ƒ“‚Q‚V–{‚ح“ْ–{‹Lک^پj
چم‹}‚حڈم“c—کژ،ٹؤ“آ‚ة‘م‚ي‚èپA‚P‚X‚V‚UپA‚P‚X‚V‚V”N‚ة‚حگ¼–{ٹؤ“آ‚ھ‚ب‚µ“¾‚ب‚©‚ء‚½
‘إ“|‹گگl‚ً‚Q”NکA‘±‚إگ¬‚µگ‹‚°‚½پBچ‚ˆنƒپƒ‚‚ة‚ح“ٹژè‚جƒNƒZ‚¾‚¯‚إ‚ب‚پA“ٌ—غژè‚جƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“پA—VŒ‚ژè‚ج‰ح”Wکaگ³‚ç‚جژç”ُ‚إ‚جƒNƒZ‚âپA’·“ˆٹؤ“آ‚ھƒxƒ“ƒ`‚إڈo‚·ƒTƒCƒ“‚جƒNƒZ‚ـ‚إ
‰ً“ا‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB‚¢‚آ‚جٹش‚ة‚©چ‚ˆن‚حپuژ©•ھ‚ھگ¶‚«‚ؤ‚¢‚‚½‚كپv‚¾‚¯‚إ‚ب‚پAپuƒ`پ[ƒ€‚ھ
ڈں‚آ‚½‚كپv‚ةƒپƒ‚‚ًژc‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
چم‹}‚ح’·‚¢ٹش‚aƒNƒ‰ƒX‚ةٹأ‚ٌ‚¶‚ؤ‚¢‚½‚ھپAƒXƒyƒ“ƒTپ[‚ج‰ء“ü‚إƒ`پ[ƒ€‚حٹشˆل‚¢‚ب‚•د–e‚µ‚½پBƒXƒyƒ“ƒTپ[ƒپƒ‚‚ھچ‚ˆنƒپƒ‚‚ة‚ب‚èپA‰©‹àژ‘م‚جچم‹}‚جƒoƒCƒuƒ‹‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ء‚½‚ج‚¾پB
گىڈمٹؤ“آ
گىڈم‚جƒ~پ[ƒeƒBƒ“ƒO‚حپAپuگlٹش‚ئ‚حپv‚ئ‚¢‚¤گlٹiŒ`گ¬‚ةٹض‚ي‚邱‚ئ‚ھ‘½‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤پB
‚±‚ê‚àژ„‚جچl‚¦•û‚ئˆê’v‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
ژdژ–‚ًچs‚¤‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚حپAپu‚ب‚؛‚»‚جژdژ–‚ً‚·‚é‚ج‚©پv‚ًچl‚¦‚邱‚ئ‚©‚çژn‚ك‚ب‚¯‚ê‚خ
ˆس–،‚ھ‚ب‚¢پB‚ب‚؛ژdژ–‚ً‚·‚é‚ج‚©‚ئ‚¢‚¤–â‚¢‚ة“ڑ‚¦‚é‚ة‚حپu‚ب‚؛گl‚حگ¶‚«‚é‚ج‚©پAگ¶‚ـ‚ê‚ؤ‚«‚½‚ج‚©پv‚ً‚©‚ٌ‚ھ‚¦‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB
‚»‚ê‚ًچl‚¦‚ؤڈ‰‚ك‚ؤƒ`پ[ƒ€‚ة‚ا‚¤‚â‚ء‚ؤچvŒ£‚·‚é‚ج‚©پA‚ا‚ٌ‚بژdژ–‚ً‚·‚ê‚خ‹‹—؟‚ھ‘‚¦‚é‚ج‚©‚ئ‚¢‚¤‹ï‘ج“I–ع•W‚ةچs‚«’…‚پBژ‚؟ڈê‚ة“O‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپB
پ@پ¨‚ـ‚ء‚½‚‹¤ٹ´‚·‚éپBƒEƒ“¤ƒEƒ“پB
Œ»چف‚جٹؤ“آ‘œ
Œ»چف‚ج–ى‹…‚حپA‘Oڈq‚µ‚½‚و‚¤‚ةژ—‚½‚و‚¤‚بگيڈp‚ً‚ئ‚ء‚½‚¤‚¦‚إ‚جپu•—پv—ٹ‚ف‚ج‘¤–ت‚ھ‹‚¢پB
‚P‚Q‹…’c‚ھپAŒآگ«‚ھژ¸‚ي‚ꂽ‹à‘¾کYˆ¹‚ج‚و‚¤‚ب–ى‹…‚©‚ç’E‹p‚·‚é‚ة‚حپAژ©‚çپu–ى‹…‚ئ‚حپv
‚ًٹm—§‚µ‚½ٹؤ“آ‚ج‘¶چف‚ھ•s‰آŒ‡‚ة‚ب‚邾‚낤پB
–ى‹…ٹد‚ھٹm—§‚µ‚ؤ‚¢‚ê‚خپAگي—ھپAگيڈp‚ج‘I‘ً‚جچھ‹’‚à‹¹‚ً’£‚ء‚ؤگà–¾‚إ‚«‚éپB
ٹؤ“آ‚جگس”Cٹ´‚حپAٹm‚½‚é–ى‹…ٹد‚ب‚µ‚ةگ¶‚ـ‚ê‚ب‚¢پB
‚»‚ê‚ح–ى‹…‚ةŒہ‚炸پAˆê”تٹé‹ئ‚إ‚àˆêچ‘‚جگژ،‚إ‚à“¯‚¶‚±‚ئ‚¾پB
Œ¾چs•sˆê’v‚â’©—ç•é‰ü‚ح‹–‚³‚ê‚ب‚¢‚ھپA‚»‚ꂼ‚ê‚ج‰؟’lٹد‚ھ‚ش‚آ‚©‚èچ‡‚¤‚±‚ئ‚إپA‘gگD‚ھ‚و‚è‚و‚پA‚و‚è‹‚‚ب‚邱‚ئ‚à‚ـ‚½پAژ–ژہ‚إ‚ ‚éپB
پ@پ¨گ[‚”[“¾پB
‚»‚µ‚ؤƒmƒ€‚³‚ٌ‚ح’يژq‚جپA‹{–{‚ئˆî—t‚ھٹؤ“آ‚إ‘خŒˆ‚·‚é‚ج‚ًŒ©‚½‚¢‚ئڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éپB
‚±‚ج‚Qگl‚حٹؤ“آ‚جڈًŒڈ‚ً”ُ‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ئپB
ٹؤ“آ‚ئ‚µ‚ؤŒ ˆذ‚ً•غ‚آ‚½‚ك‚جڈًŒڈ‚ًˆب‰؛‚ج‚S‚آ‚¾‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚éپB
‡@
”\—حپپ”»’f—حپA‘gگD—حپAژw“±—ح‚ب‚ا
‡A
گM—ٹپپگ³’¼پAگ½ژہپAŒھ‹•‚ب‚ا‚جگl•؟‚ة‚و‚ء‚ؤŒ`‚أ‚‚ç‚ê‚é
‡B
’mŒbپپŒoŒ±‚â’mژ¯‚©‚ç—N‚«ڈo‚é’mŒb‚ً‚à‚ء‚ؤڈ•Œ¾‚·‚邱‚ئ
‡C
ˆ¤پپژq‚ًˆ¤‚·‚éگe‚ج‚و‚¤‚ةپAŒµ‚µ‚³‚àچ‚ك‚ؤ‘Iژè‚ةگع‚·‚é
‚»‚µ‚ؤپAچإŒم‚جŒ‹‚ر‚ج•¶‚à‚و‚©‚ء‚½پB
‚Q‚O‚P‚S”N‚ةƒvƒچ–ى‹…‚ح‚W‚O”N‚ًŒ}‚¦‚éپB
‘ٍ‘؛‰hژ،‚ھگأ‰ھ‘گ“م‹…ڈê‚إƒxپ[ƒuƒ‹پ[ƒX‚⃋پ[ƒQپ[ƒٹƒbƒN‚ç‚ئŒفٹp‚ة‚ي‚½‚è‚ ‚ء‚½‚ج‚ح
‚P‚X‚R‚S”N‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB‚P‚Wژژچ‡‚ًگي‚ء‚ؤ‘S”s‚µ‚½‚ب‚©‚إپA“¶ٹç‚جڈ”N“ٹژè‚ھŒ©‚¹‚½
‰ُ“ٹ‚ةپA“–ژ‚جƒtƒ@ƒ“‚ح–¢—ˆ‚ً–²‚ف‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
گl‚حگ¯‚ةŒü‚©‚ء‚ؤژè‚ًگL‚خ‚·‚ئ‚¢‚¤پB‚¾‚ھپAژè‚ًگL‚خ‚µ‚½گو‚ة‚ ‚éگ¯‚حپAچإڈ‰‚©‚ç‚»‚±‚ة‚ ‚ء‚½‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢پAگl’m‚ꂸ“w—ح‚ً‚µپA’Zڈٹ‚ًچژ•‚µپA’·ڈٹ‚ًگL‚خ‚µپAƒ‰ƒCƒoƒ‹‚ئ‚ج‹£‘ˆ‚ة‘إ‚؟ڈں‚ء‚ؤڈ‰‚ك‚ؤپA’N‚ج–ع‚ة‚à‹P‚¢‚ؤŒ©‚¦‚éگ¯‚ئ‚µ‚ؤپA‚¢‚ـ‚و‚¤‚â‚‹َ‚ة‚ـ‚½‚½‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾پB‚»‚ٌ‚ب–¢—ˆ‚جگ¯‚ة‚ب‚é‘Iژ肽‚؟‚àپA‚¢‚ـ“D‚ة‚ـ‚ف‚ê‚ؤˆêگS•s—گ‚ة—ûڈK‚µ‚ؤ‚¢‚éپAŒoŒ±‚ًگد‚ٌ‚إ‚¢‚éپB
–{ڈ‘‚ھپAƒvƒچ–ى‹…‚ج—ًژj‚ًگU‚è•ش‚é‚«‚ء‚©‚¯‚ئ‚ب‚é‚ئ“¯ژ‚ةپAگ¯‚ً–عژw‚·ژلژز‚½‚؟‚جژwگj‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚‚ê‚ê‚خپAچK‚¢‚إ‚ ‚éپB