NHK「東海村臨界事故」取材班 (編集) 新潮文庫
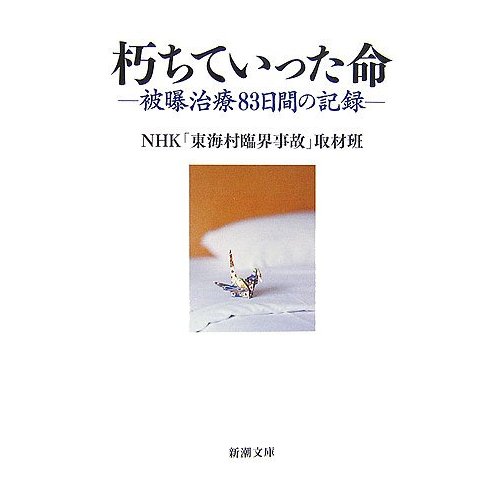
JCOの臨界事故で致死量の放射線被曝をした大内さんの壮絶な生への戦いであった。
原子力工学科だったので、マウスで被爆実験・解剖をしたことがあるので放射線の影響は知っていたつもりであったが、あまりにすさまじい。
マウスは線源がガンマ線(コバルト60)であったが、大内さんは中性子線である。
これは非常に厳しいと言わざると得ない。
染色体が全部壊れ、再生機能が失われてしまっている。
そんな大内さんを東大の前川チームが支える。
ハンパではない治療。海図のない航海。
これだけ被爆して約3ヶ月も生存したことは奇跡であろう。
しかも一度心臓停止したのを心臓マッサージで蘇生させている(59日目 心停止49分)。
こんな中家族は夫・父が直ることを信じて励ましあう。
とてもすばらしい家族愛が貫かれていた。
私自身、緊急被爆医療の組織立ち上げに関与したことがあり前川先生も知っていた。
えらそうなワンマンなおっさんやなあと思っていたが、この闘病の指揮官としては本当に全力を尽くしたと思う。
延命治療への疑問を各自が投げかけている。
これは医者にとって大きなテーマであろう。
新米医師の山口さんの感想 (50日目頃) (全文引用)P125〜P126
山口は、自分のやっていることが実際にだれの幸せや喜びにつながっているのかが、わからなくなっていた。
客観的に見ると生き長らえる見込みが非常に低い患者であることは、だれの目にも明らかだった。
助かる見込みが非常に低いという状況の中で、日に日に患者の姿が見るも無残な姿になっていく。
その患者の治療に膨大な医薬品や血液などの医療資源が使われていく。
しかし、そうしておこなった処置は患者に苦痛を与えているのだ。
医療者はこの状況に、この治療に、どこまで関わっていくことが許されるのか、山口はつねに考えていた。
同時に、医療チームの多くのスタッフが同じようなことを思いながら、それを誰にも口に出せないということも感じていた。
ーーーーーーーーーーーーー
看護婦も大内さんに直らないのに続けることは大内さんに苦痛だろうと思っていた。
前川先生に一人の看護婦が「いつまで、こういう治療を続けるのですか?」
と聞くと、前川はあいまいに微笑を返し、答えなかった。
先生も迷っているんだと感じた。
この看護婦はこの経験で大きく成長する。
自分が変わったと思った。いつも患者の側にいようと強く思うようになった。
「先生の指示でこういうときはこうしなさいと言われても、患者さんがいやがっていたり、
言葉で言えなくても苦しがっているようだったら、苦しくないように治療してほしいと、きちんと言いたいと思うようになりました。
いつも患者さんの側についていたいと、前よりも、もっと思うようになったんです」
そして自らの生き方について考えた。
「自分にとって大切な人とはいっぱい話しをして、その人がもし口をきけなくなって治療するしかないという選択を迫られたときに、
この人はこういう人だったからこの治療は続けてくださいとか、この治療はやめてくださいとか、そういうことが言えるくらい、
たくさんたくさん話しをしたいと思うようになりました。
もう一人の看護婦も気づいた
助かる見込みのない患者さんにとっての「生」を考えるようになりました
この人にとっては治療をしても苦痛だけしか感じていないんだろうなという患者さんを見ていると、いままでは、
そんなことをしても患者さんの苦痛な時間を長くしているだけだ、
早く楽になりたいと思っているんじゃないかとどこかで思っていました。
でも、大内さんと出会って、その考えは変わりました。
どんな状況でも患者さんは、決して早く楽になって死にたいなんて思っていない。
前向きに、「よくなりたい、がんばりたい」と思っている。
そういう意思を持って病気と闘っている人もいるんだということを、
大内さんのケアをしていて強く感じました。
最後の解剖で、心臓だけが放射線にやられずしっかりとした筋肉を保ちつづけたことが異様であった。
大内さんの生への自己主張だと筆者は語る。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
このすさまじい被爆医療の経験の後、前川先生は全国での緊急被爆医療の構築に奮闘されたのである。
当時の安全委員会の青木先生、そしてこの本にも出てくる三菱重工の衣笠先生らと
愛媛県でのネットワーク構築に関していろいろ対応したことが思い出される。
幸い県立中央病院、そして地元の八幡浜病院が協力してくれて体制ができたのである。