マンガでよくわかる
行動科学を使ってできる人が育つ!
石田 淳/著 temoko/作画 かんき出版
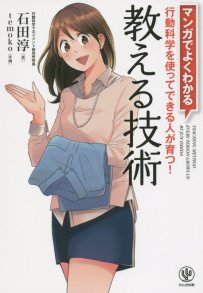
これもマンガ本。
図書館のマンガの一般書で興味あるものは片っ端から読んでみようかと。
これは「行動科学」という新しい分野の解説なので興味を持った。
マンガオンリーとは言い難く、文章の説明がかなり多かった。
やっぱり文章は完結に1枚程度でまとめて欲しい。
確かに章の最終ページには1枚もので掲載はあったが
それ自体はイマイチ感が残った。
行動科学というが、ハウツーの一種としては使えるが
根本、肝のところはやっぱりコミィニケーションであった。
そのエッセンスは同じである。
知らないことやオモシロイと思ったところを書き残しておこう。
第1章 教えるとはどういうことか?
◎ 部下の「根性」や「やる気」を正すのが上司の仕事ではない。
部下の「望ましい行動」を引き出すことである。
☆ プライベートの話で信頼関係の土台づくり
まずはあなたから、仕事以外の話を
⇒ 私が重視している価値観に触れあうこと
そのきっかけとなるのがこれまでの経験の話なのだ。
部下に失敗談を話そう
⇒ これも私のモットーだ。
成功話をしても自慢話にしかならない。
それよりも失敗談を語ることが人をひきつけリラックスさせる。
何より自分をよく知ってもらえるのだ。
第2章 どう伝えればいいのか?
☆ 具体的な行動で表現する 「MORSの法則」 ⇒これは知らなかった
Measured 計測できる;数値化できる
Observable 観察できる;誰が見ても、どんな行動をしているかがわかる
Reiiable 信頼えきる;どんな人が見ても、それが同じ行動だと認識できる
Specific 明確化されている;何をどうするかが明確になっている
あいまいな指示もこのように具体化する
売上を伸ばす ; 1日10人のお客様におすすめ商品を案内する
商品知識を増やす ; 毎日3商品分の社内資料を読み込む
チーム力を上げる ; 一緒にシフトに入る全スタッフの業務前に声をかける
☆参考ツール 「視覚支援プログラム」
1960年代にアメリカのノースカロライナ州立大学を中心に体系化された
「TEACCH(自閉症及び関連するコミュニケーション障害のある子どもたちのための治療と教育)」
などで活用されている学習法。
このような子供たちは、視覚による学習能力が優れているため、
ビジュアルを用いて示してあげると、スムーズに理解し、実践できるのである。
● やらないことリストを作る
部下に物事を伝えるとき、多くの人はまず優先順位を決めますが、
「劣後順位」を決めることこそが重要。
⇒ ふーん、そうかな。なかなか気が付かないな。
例)
・あなたに達成して欲しい目標はAです。
そのためにはコレとコレをやってください。
一方、コレとコレは目標達成とは無関係なので、やる必要はありません。
第3章 ほめることが人を成長させる
☆ 人間の行動原理に基づく「ABCモデル」
A Antecedent 先行条件;行動の直前の環境
B Behavoir 行動 ;行動・発言・ふるまい
C Consequence 結果 ;行動した直後に起きた環境の変化
ABCには明確な因果関係があります。
先行条件(A)によって行動(B)が引き起こされたとき、
得られた結果(C)が望ましいものであれば、
それが(A)に影響を与えるので、再び行動(B)が引き起こされます。
つまり、行動によってよい結果が得られれば、その行動は繰り返され、
一方、結果が望ましいものでなければ、人はその行動をしなくなります。
第4章 継続するために
● モチベーションは「やる気」ではなく、本来は「動機・動機づけ・自発性」という意味
「モチベーション」という言葉。
ビジネスやスポーツの世界はもちろんのこと、
今や子供たちまでもが当たり前のように口にしていますが、
「動機・動機づけ・自発性」といった本来の意味ではなく、
もっぱら「やる気」の同義語として使われているようです。
⇒ うーん、自分自身もそのようなふうに使っているような気がする。
ただ本質的なところは外してはいないという思いもある。
本来の意味での「モチベーション」=動機づけや自発性 を上げる方法としては
・部下に向かって
「その仕事の意義を語る」
「その業務を成功させたら、どんなに素晴らしいことが待っているか、鮮明にイメージさせる」
などがあります。
⇒ 私がよく使う話が「大聖堂の石切職人」です。
◎ 補助輪を外してあげる
「プロンプト」 正しい行動が起きるように補助してあげること
「フェイディング」 最終的にプロンプトなしで正しく行動できるよう、徐々にプロンプトを外していくこと
この言葉は知らなかった。 自転車の補助輪を例にあげて説明がありわかりやすかった。
なるほどねと納得。
以上、心理学の言葉や概念をいくつか学んだが、すでに既知の内容であった。
整理がついてよかった。