ポール・クルーグマン 日本経済新聞社
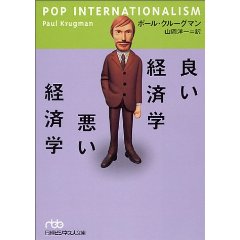
これまたE先輩から渡された本である。文庫本なので読みやすかった。
この本を貸していただいた後でポール・クルーグマン氏はノーベル経済学賞を受賞している。(2008年)
普通に考えていることが経済学的にはゼンゼンダメであるということを、痛烈に教えていただいた気がする。
そもそも貿易とは両国がwin-winなものであるということ
保護主義的な考えはガーンと殴られた感じである。
ある特定の業者は不利を受けるかも知れないが、国民的に言えば輸入は総合的には国家にとって「利益がある」から行われるのである。
言われてみればその通りだな。
簡単な式
貯蓄 − 投資 = 輸出 − 輸入
わかりにくかったので一橋大学経済学部卒の企画部のグループリーダーに教えてもらった。
以下の解説
GDE(総支出) = C(消費) + I(投資) + EX(輸出)−IM(輸入)
GDE=GDP(総生産) … Y(所得)
よって、 Y=C+I+EX−IM
Y−C−I=EX−IM
Y−C=所得−消費 =貯蓄(S)
S−I = EX − IM
これで証明されたのであった。
以下印象に残ったところを書き残しておこう。
第3章 貿易、雇用、賃金
アメリカの労働者の平均賃金は第二次大戦の終了から1973年までの間に実質ベースで2倍以上になった。
しかし、それ以降、実質賃金は6%しか上昇していない。
さらに賃金が上昇したのは高学歴の労働者だけであった。
ブルーカラーの実質賃金は73年以降ほとんどの年に下がっている。
……
アメリカ経済がぶつかっている問題は大部分が国内要因によるものであり、グローバル市場が現在のように統合されていなかったとしても、
アメリカ経済の苦境にはほとんど変わりがなかっただろう。GDPに占める製造業の比率が低下しているのは、工業製品に対する支出が
相対的に減少してきたからである。雇用に占める製造業の比率が低下しているのは、企業が労働者に代えて機械を導入しており、
残った労働者を以前より効率的に使っているからである。賃金が停滞しているのは、経済全体の生産性の伸び率が低下してきたからである。
そして非熟練労働者がとくに打撃を受けているのは、ハイテク経済では非熟練労働者に対する需要が減っているからである。
いずれの場合にも、貿易は小さな要因でしかない。
⇒ この説明に納得である。
第4章 第三世界の成長は第一世界の繁栄を脅かすか
第三世界との貿易が増えたとき、第一世界の全体的な賃金水準はほとんど影響を受けないとしても、理論的には、
熟練に対する賃金のプレミアムが上昇し、賃金の不平等が広がることになる。
また、「要素価格均等化」によって、北の低熟練労働者の賃金は南に向かって低下するなずである。
⇒ そういうことで、先進国における労働者の格差が広がることになるのか。
★ この章の最後の主張
ここで取り上げているのは、狭い範囲の経済問題ではない。
欧米が自分たちの生活水準を守るといった間違った考え方にしたがって輸入障壁を築き上げれば、世界経済の現状で最も明るい面を
破壊することになりかねない。広範囲な経済開発がようやく始まり、数億、数十億の人たちが生活水準の向上を期待できるようになったのだ。
第三世界の経済発展は脅威ではなく、機会である。世界経済にとって本当の脅威になっているのは、第三世界の成功に対する第一世界の恐れなのだ。
第5章 貿易をめぐる衝突の幻想
ここで冒頭の基本式が出てくる。
そして、この文章となる、
経済理論には、きわめて単純で、議論の余地がないが、経済学に詳しくない人にとっては落とし穴になる点がある。
前述の会計恒等式がそうだし、賃金がその国の平均生産性によって決まり、個々の工場の生産性で決まるわけではないこともそうだ
(もっとも、整合性がとれている理論よりも、混乱した理論の方がはるかに説得力があり、数値や数式で混乱ぶりを指摘しても、誤った見方に
しがみつこうとする人が多く、なかには怒り出す人もいる)。つまり、経済学者はそれなりに価値のある知識を持っている。
第6章 アメリカの競争力の神話と現実
競争力を懸念する声が一般的になっているが、「競争力」という言葉が何を意味するのかについては、まともな議論がほとんどなされていない。
おそらく、「競争力」という用語を使うとき、ほとんどの人が国を企業に似たものと考え、貿易とは企業間の競争を大規模にしたものと考えていると
いえるだろう。
(⇒ ドキッツ! 私もそう思っていました)
いうまでもなく、企業経営の世界では、競争力という言葉ははっきりとした意味を持っている。
競争力を持たない企業とは、競争相手よりも製品が劣っているか、コストが高い企業であり、市場シェアを失って、いずれ存続できなくなる。
しかし、国は企業とは性格が違う。国の間の貿易は、企業間の競争とは大きな違いがあるため、国について「競争力」という言葉を使うのは
誤解を招きかねず、意味がないと見ている経済学者が多いほどである。
この後、国際競争の論点整理に続く
貿易相手国と比べて、すべての産業で生産性が劣っている国は、生産性の高さではなく、賃金の低さで競争しなければならない。
しかし、それで悲惨な状況に陥るわけではない。それどころか、通常、貿易によって利益を得られる。
決定的な点は、限られた市場をめぐる企業間の競争とは違って、貿易がゼロ・サム・ゲームではなく、ひとつの国の利益が他の国の
損失になるわけではないことだ。貿易はプラス・サム・ゲームであり、したがって、貿易に関して「競争」と言う言葉を使うのは、誤解を
招きかねない危険なことなのである。
第7章 経済学の往復外交
アメリカとメキシコの二国の貿易で考えてみている。
二国の賃金の比率によって結果が変わってくる。
メキシコの賃金が高すぎれば、生産性が高いアメリカの労働者の方が、ほぼすべての製品を低コストで生産できることになる。
逆に、メキシコの賃金が極めて低ければ、ほとんどの製品は、メキシコで生産するほうが低コストになる。
しかし、両国の賃金の比率は理由なく決まるわけではなく、市場の力によって決まってくる。
したがって、極端に高くも極端に低くもならないものとなり、どちらの国も、かなりの製品を相手国により低コストで生産できる水準に
なるのが通常である。国際経済学の有益な用語を使うなら、アメリカはすべての生産で絶対優位にあるが、どちらの国も、かなりの製品で
比較優位を確保できる。
貿易のパターンに関しては不満があるかも知れない。
しかし、この例では、両国とも貿易によって実質所得が向上する。
どちらの国も、賃金の比率よりも生産性の比率の高い製品だけを輸出するので、輸入側では、自国の労働者は生産した場合よりも
輸入した方が労働を節約できる。
貿易から切り離されている場合より、限られた製品の生産に特化し、残りを輸入する方が有利になる。
両国の賃金の比率がどうであろうと、そうなる。
→ 経済学的にはそうであろうが、技術力の維持の観点からは経済的だからと言って外に出すと空洞化してしまう恐れがある。
この点についての考察は残念ながらない。技術屋でなければわからない点だ。見落としだと思う。
☆全員は利益を得られない
各国内部の所得分配に大きな影響が及ぶ。
熟練労働者と非熟練労働者があり、アメリカの方が熟練労働者の比率が高い場合、貿易によって、アメリカ全体で見れば実質所得が
上昇するが、非熟練労働者が打撃を受けることになる。
しかし、国内所得分配に関する懸念は、通常、国の競争力の問題とされているものとは大きく違っている。
そして経済学者は、以前から、自由貿易が国益を損ねるとする議論を怪しげなものと考えてきた。
利益集団による身勝手な主張にもっともらしい理由をつけただけだと、冷ややかに見ているのである。
→ この主張には納得である。日本も所得再配分について早く政策を打たねばならない時期と言える。
第8章 大学生が貿易について学ばなければならない常識
・アメリカ経済が世界経済の一部になったといっても、実際にはその比率は極めて限られている。
実際には、輸出、輸入ともアメリカの国民総生産の8分の1ほどにすぎず、アメリカが生産する付加価値のうち少なくとも3分の2は、
貿易の対象にならない「財とサービス」である。
・大学の講義では初歩の初歩をできるかぎり鮮明に理解させるべきである。
さまざまな曲線やリプチンスキー効果を教えるべきだ。
しかし、ほとんどの学生にとって準備が必要なのは、テレビに出演する「専門家」、ベストセラーの著者、1日3万ドルを稼ぐコンサルタントが、
予算制約式を理解しておらず、ましては比較優位を理解していない世界なのである。
第9章 常識への挑戦
・常識はいつの時代も、現実の証拠よりはるかに強い。わずか2年前は、国際経済問題に関係する要人の多くは、
自由市場 + 通貨価格の維持 = 繁栄
という等式を疑いませんでした。残念ながら、世の中はそれほど単純でありません。この2年間に起きていることを見れば、それがよくわかります。
第10章 NAFTAの実体
NAFTAとは北米自由貿易協定
第11章 アジアの奇跡という幻想
・ソ連の経済成長を研究する経済学者の多くは、やがて、まったく違う結論に行き着いた。ソ連経済が実際に急成長をとげていることについては、
異論はなかったが、成長の性格について新しい解釈を示し、ソ連の成長見通しを見直す必要があると主張した。
こうした新解釈を理解するには、少し回り道をして、成長会計に関する理論を見てみる必要がある。
成長会計というと、一見、難解そうだが、実はごく常識的なことである。
・シンガポールの経済成長は、測定できる投入の増加によってすべて説明できる。効率性が向上していることを示すものは何もない。
この点で、リー・クアンユー時代のシンガポール経済とスターリン時代のソ連経済とは、双子のようによく似ている。
どちらも、資源の動員のみによって経済成長を達成しているのだ。いうまでもなく、現在のシンガポールはソ連のどの時代よりも
(最盛期のブレジネフ時代よりも)、はるかに豊かである。これはシンガポールの効率性がいまだに先進国を下回っているものの、
かつてのソ連と比べれば、先進国に近いからである。むしろ重要なのは、シンガポール経済がつねに、比較的効率性が高かったことだ。
シンガポールではつねに資本や、教育を受けた労働者が不足していた。
第12章 技術の復讐
・1979年に職務経験5年の大卒労働者と、経験年数が同じの高卒労働者との賃金格差は30%であったが、89年には、74%に広がっている。
技術変化が起きていなかったとしたら、非熟練労働者と比べて熟練労働者の雇用コストが大幅に上昇しているので、企業は熟練労働者を削減し、
できるだけ非熟練労働者で間に合わせようとするはずだ。しかし、実際にはそれと反対のことが起きている。全般に、企業は従業員の平均技能水準を
引き上げている。
したがって、技術変化にともなう労働需要の変化こそ、アメリカで賃金格差が拡大している最大の原因であり、ヨーロッパで失業率が上昇している最大の
原因であるといえよう。しかし、別の解釈もできる。熟練労働者の需要の増加は、各産業のなかで技術の需要が拡大したことにより、産業構造が変化し、
熟練労働者の比率の高いセクターの比重が大きくなったことの結果だとも考えられる。
たとえば、労働力の豊富な途上国との貿易が増えたことで、産業構造が変化したとも考えられる。
しかし、事実を見るかぎり、非熟練労働者の需要が減少したのは、生産するモノが変ったからではなく、生産する方法が変ったからである。
・産業技術は当初、労働力を大幅に節約できるとともに、巨額の資本を必要とした。つまり、技術の進歩によって、企業家は一定の生産量をあげるために、
人手を減らして投資を増やすようになった。その結果、労働需要が減少し、およそ50年にわたって実質賃金が停滞した。この間、イギリスの資産階級の
所得は急増している。
現在の先進国でも同じことがおきているというのが、経済学者のほぼ一致した見方である。
産業革命期との違いは、技術進歩の利益にあずかっている人が、資本家ではなく高度な技術を持つ労働者である点だけだ。
産業革命が、労働を節約し資本を必要とする性格の技術変化であったことは容易に理解できる。
…
それでは、最近の技術変化についてはどうだろう。つまり、財やサービスを生産する方法のどこが変ったために、非熟練労働者の価値が下がった
のだろう。
はっきり言ってしまえば、それはわからない。
・ 将来、税理関係の弁護士の多くがエキスパート・システム・ソフトに取ってかわられることはあるかも知れない。
それでも、人間でなくてはできない仕事、しかも賃金の高い仕事はまだ残っている。
庭の手入れ、家の掃除など、ほんとうに難しい仕事はたくさん残っているはずだ。
消費財価格が着実に低下し、こうしたサービスが家計支出に占める割合はますます大きくなっていく。
ここ20年間、優遇されてきた高度な専門能力を有する職業が、19世紀はじめの機織りと同じ道をたどることになるかも
知れない。機織りも、糸紡ぎの機械化にともなって所得が急増したが、やがて、産業革命の波が自分たちの職種に及んで没落した。
したがって、現在のように所得格差が拡大し、ふつうの仕事の価値が下がる現象は、一時的なものに終わると私は考えている。
むしろ、長い目で見れば、形勢が逆転することになるだろう。
不自然だからこそ希少価値のあった特殊な仕事は、ほとんどコンピュータによって取って代わられるか、簡単になる。
しかしだれでもできる仕事はまだ、機械が代わりをすることはできないだろう。
つまり、今の不平等な時代が過ぎ去り、輝かしい平等の時代が訪れることになるだろう。
もちろん、さらに長い目で見れば、人間のすることを機械がすべてこなせるようになる。
しかし、そのころには、この問題を考えるのも機械の仕事になっている。
第13章 世界経済のローカル化
・コンピューターやロボットに人間の代わりをさせることができない仕事、人間の感性を必要とする仕事は、直接に人と接するタイプの仕事でもある。
農業、製造業、対人サービス以外のサービス業の生産性がきわめて高くなったため、アメリカ経済は他の分野、つまり貿易財以外のモノとサービスを
生産ことに力を入れるようになっている。ロサンゼルス住民の多くが地元で消費されるサービスを生産しているのは、このためだ。
ニューヨーク、ロンドン、パリ、それに現在のシカゴでも事情は同じである。
…
ロサンゼルスは典型的な工業都市ではないが、アメリカのほかの大都市とくらべれば、製造業の比率が高いことはたしかだ。
統計があれば、ロサンゼルスの工業製品輸出が輸入を上回っていることがおそらくわかるだろう。
ロサンゼルス住民の多くが、目に見えるものを生産しているわけではないが、そrふぇは、目に見えるものを生産するのが得意なために、
目に見えないものの生産にエネルギーを傾けているからである。100年前のシカゴと違うからといって、いまのロサンゼルスに問題が
あると考えるべきではない。
以 上