西田 宗千佳 朝日新書
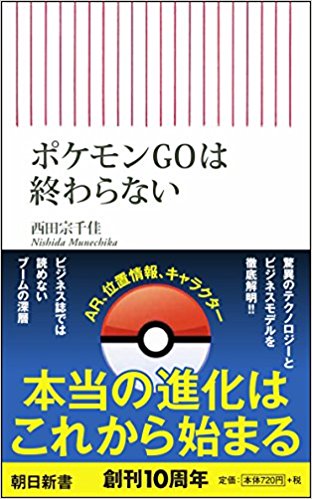
昨年の7月22日にダウンロードして毎日休みなくゲームして
現在レベル38 我ながらよくやるわーと思うが、
なにせ体重が5kg減に成功。
ポケモンGoさまさまである。
新刊からこのタイトルをみつけてさっそく予約。
誰も予約は入っていなかったのが不思議。
この本を読んでただちに実行に移したのが幸せタマゴの使用をやめること。
● ポケモンGoは「時短」にお金を使わせる
ポケモンGoでの課金アイテムの扱いは、
「なくてのゲームは進むが、あるとより便利になる」というもの。
別の言い方をすれば「時間短縮」である。
…
ゲーム内通貨を支払ってゲームを有利に進める、という構造(「ペイトゥウイン」)
はポケモンGoにもある。
ただし、ポケモンGoの場合には、キャンディ・クラッシュのように「プレイし続けること」に
お金を使う必要はないう。また、実質的な対戦要素であるジム戦で重要なのは
「どれだけ強いポケモンを持っているか」であるが、
ポケモンの強さは、主に集めたポケモンの量に比例する。
すなわち「どれだけポケモンが多い場所を歩いたか」で決まる。
時間を短縮する要素はあるが、そこまで有利になるわけではない。
ポケモンGoは、メジャーなスマートフォン向けゲームの中では、かなり課金の必要性が「薄い」
ゲームであるといっていい。
ポケモンGoが課金の必要性が薄いゲームになった背景には、ナイアンティックの思想がありそうだ。
イングレスもプレイヤーへの課金要素は薄く、ほとんどのプレイヤーが無課金で遊んでいる。
薄く課金する、というモデルは珍しいものではなく、近年は増える傾向にある。
短期的な利益には結びつかないが、手軽でユーザーが逃げにくいからだ。
→ポケモンGoは圧倒的ユーザー数で大きな売上を上げている
⇒幸せタマゴは得点を2倍にするだけでトレーナーレベルアップの速さには貢献するが
強いポケモンをゲットすることには寄与しない。
強いポケモンは孵化装置から孵ったポケモンが非常に多いため、孵化装置は購入する必要がある。
この孵化装置を購入し続けているが、幸せタマゴの購入はレベル38に到達し、
ポケモン進化も終了してしまったポケモンが増えたこともあり、
レベル40が最後でもあるし、あまり早くレベルアップするインセンティブが薄れたため
購入を止めることにした。
● ポケモンGoは他のゲームに影響しない
ポケモンGoほどのヒットになれば、他のスマートフォン向けゲームに大きな影響が出ているのでは…?
と思う人が多いはずだ。
だが、意外なことに、滝澤氏は「調べてみたが、他のゲームアプリの売上にはほとんど影響していなかった。
ゲームのプレイ時間も短くなっていない。
背景にあるのは、圧倒的なプレイヤー数の多さだ。
ポケモンGoは、これまでスマートフォンでゲームをしなかったような人々をひきつけることに成功したため、
比較できないということである。
一方、他のアプリはどうか?
「若干日本国内で、暇つぶし系のアプリに影響が出たようだが、それもすぐに持ち直した。
ポケモンGoが他のゲームから奪ったというより、新たな「スマホアプリを使う時間を作った」というほうが正しい。
⇒ 私も該当者であるのでよくわかる。
ジジババユーザーは皆新しいユーザーだろう。
● ポケモンGoで本当に笑うのは「スマホ関連企業」
任天堂や株式会社ポケモン以上に笑いが止まらない企業がある。
それがアップルとグーグルだ。
スマートフォンで使われるアプリの決済には、OSを作っているメーカが運営するアプリストアを利用する必要がある。
このアプリで決済された取引は、一般的にその3割が「ストアの利用料・手数料」として運営先に支払われる。
⇒ 3割とは法外である。
高々1割で5%くらいが妥当なところだと思うが3割とは驚いた。
これはアップルもグーグルも笑いが止まらないことだろう。
◎ 意外性にあふれた「ポケストップ巡り」
「トマソン的」なものは、一般的なガイドブックに載ることは少ない。
だが、ポケストップとしては掲載されている。
毎日のように歩いている街でも、ポケモンGoをひとつのきっかけとして別の道を歩くようになったり、
知らない街を歩くのがより楽しく感じたりするようになる。
これは、地図の上に「情報を加えていく」エンターテイメントである。
位置情報ゲームの醍醐味である。
⇒ ポケストップで初めて知った場所というのが数えきれない。
こんなに毎日通っていたのに知らなかったことに愕然とさせられるが
そういう新発見の喜びというのがこのポケストップにはある。
ポケストップの多くは神社仏閣や歴史的構造物、銅像などだ。その地域で有名なものが選ばれているようだ。
特筆すべきは、王道と言える建造物・銅像などのほかに、街角にあるちょっとしたものも多く登録されている。
◎ ポケモンGoのデータはどうやって生まれたか
ポケモンGoで使うポケストップやジムのデータは、元々イングレスのために作られたデータである。
ポケストップにはその土地の「見るべき場所」が詰まっている。
その土地に住んでいるのに「こんな場所があったのか」と驚くことも珍しくない。
そうした情報はイングレスのプレイヤーたちが集めたものだ。
街中をプレイヤーが歩き、発見したものが、イングレスの中で「ポータル」としてまとめられていった。
ポータルの総数は定かではないが、2015年の段階で500万を超えていた。
全世界でこれだけの「見るべき場所」の情報を集め、整備するのにどれだけのコストがかかるだろうか?
ポケモンGoは数週間のタイムラグはあったものの、アメリカ・ヨーロッパ・日本・オーストラリアといった
主要地域で一気に立ちあがった。
それができたのも、ポケストップの元となる情報がポータルという形ですでに存在していたからである。
ナイアンティックは公式に、「イングレスのポータル情報をポケストップとジムに流用している」ことを
明けしている。
ただしすべての情報を流用したわけではないようで、一部を選択して使っているようだ。
…
ナイアンティックがこれだけたくさんの情報を集められたのは、イングレスが成功したからに他ならない。
イングレスはダウンロード数こそ1400万件程度でポケモンGoに比べ少ない。
…
イングレスは稀有な位置情報ゲームであり、ポケモンGoとは違うゲーム性を有しており、
今も強いブランド力を持っている。
…
ポータルの基準となるのは「文化的・芸術的・宗教的に重要な場所」とされた。
ポータルの名前や追記されているコメントも、基本的には、ポータルを登録した人々の手に
よるものである。
旅行中にポケモンGoをするのが楽しいのは、ポケストップ=ポータルの情報が、
通り一編の観光ガイドとは異なる面白さを持っているからだが、そこには、いんぐれす・プレイヤーの
センスが大きく影響していたのである。
● 続発しるトラブルの原因はどこに
ネットワークの世界には「メカトーフの法則」と呼ばれるものがある。
「ネットワーク通信の価値は、接続されているシステムのユーザー数の二乗に比例する」
と定義されるのだが、要は「利用者の数は社会にべき乗的な影響を与える」ということであり、
ある一定の数を超えるとインパクトが急速に高まる。
⇒この言葉は知らなかった。納得できる
要は…で言い換えているが言い換えの方が難しい言葉のような気がする(苦笑)
参加者の数が仮に10倍の差であったとしても、
そこで社会に与える影響の大きさは100倍以上になる。
ポケストップの問題
● グーグル的解決法の功罪
ナイアンティックは、ポケストップやポータルの位置、ポケモンの発生場所などについて、
クレームを受け付ける窓口も設けている。
その情報を元に、事後的に対処していく……というのが現状である。
これはいかにもアメリカ的というか、「グーグル的」なやりかたと言える。
検索情報やプライバシー保護、著作権保護についても、現在のインターネットでは、
こうした「問題が起きてからそこだけすばやく対処してゆく」方法が採られている。
そうすることで一部での摩擦は避けえないものの、より広く、より多くの情報を扱うことができる。
摩擦が起きるとそれを問題視し、
「あってはならない」と日本人は考えがちだが、完璧に問題が起きない状況があり得ないことを考えると
「グーグル的」解決法が現実解であり、論理的なやりかたと言える。
⇒なるほどねー、ある程度納得ではあるが、システムトラブルもやたら多いのが現実である。
◎ 地域パートナーとなる条件とは何か
彼らが組むことで「地域に貢献できる」ことが最大の選択理由なのだ。
パートナーシップによる自治体や自社への利益そのものが目的でなく、
「ゲームを楽しむ人々へのホスピタリティ」が重用である、という姿勢が見える。
◎ コンテンツ・ツーリズムの成功の鍵とは
リピータを呼ぶ観光とは何か?
観光業界で俗に「滞留型観光」と呼ばれるものがそれだ。
従来は、目的地がいくつか存在し、そこを巡ることが「観光」だった。
いわば「目的型観光」だ。
だが、滞留型観光では、目的地に留まり、その地域に長くいることで体験できることから
楽しみを見つけていく。
…
その土地でいかに良い体験ができたかが重要だから、見ただけでは終わらない体験がなければいけない。
ポケモンGoのような位置情報ゲームを使い、観光地を回ることは、滞留型観光と非常に相性が良い。
…
何度も指摘しているように、ポケモンGoで起きているトラブルは、
ポケモンGoをプレイする人々と、そうでない人々の間で価値観がすれ違っているから起きている。
そこでは、ポケモンGoが潤滑油ではなく逆に摩擦を深めるものになってしまった。
ここまで存在が広まれば、「位置情報ゲーム」の意味を周知し、地域観光に活かしていくことも
不可能ではないはずだ。
○ そこにないものが見える「記憶のポケストップ」
記憶のポータル
震災が示した「過去の情報」の価値
現在、「未来へのキオク」には、2011年3月の震災前のもの、2011年7月の被災直後のもの、
そして2013年以降に撮影されたものと、複数の時代の風景が、ストリートビューを介して
みられるようになっている。
位置情報で拡張される現実
デシタルの地図は「多層」な存在
我々は常に「位置」を補足されつつ生きている
「ジオフェンス」という概念
位置で情報が串刺しされた世界へ
スマートフォンが生み出した変化とは、
単にどこでも情報が引き出せる、ということではない。
スマートフォンを持つことで我々は、自らが意識する・しないにかかわらず、
さまざまな情報を発信している。
その価値がネットワークに蓄積されることで、情報の価値がさらに高まっていく、
というのがスマートフォンの本質なのだ。
以上なかなか興味深い内容であった。