柴田 昌治 日本経済新聞社
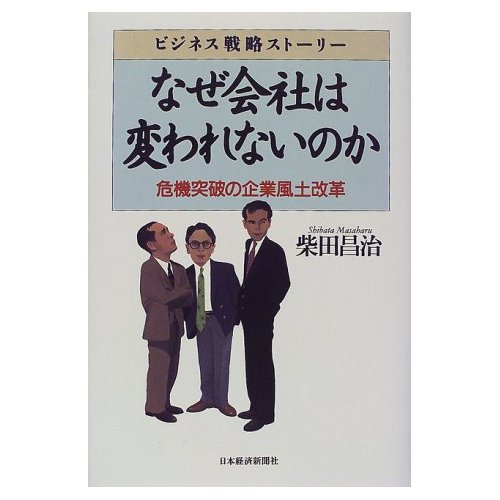
会社の若手のSさんから薦められて読み始めた。
彼が今の自分を若い改革人「瀬川」君に重ねているのかも知れないなと思いながら読んだ。
交流を深めている長野のYさんの使っているキーワードがいくつか出てきましたので「オオッ!、コレだな」と感じた。
基本的に柴田さんの主張である「場」をつくって、社員自身がみずから動く会社風土にしよう
というのは、私もまったく同じです。
Yさんの返事
私が、最初に「柴田昌治さん」の本と出会ったのは、もう10年以上前だと記憶しています。
「何が日産自動車を変えたのか」でした。
その後、シリーズで出される「組織風土改革関連」の著作に、心を打たれました。
リクルート時代の私の優秀な部下が、リクルートを退職し、柴田さんの会社に転職したことも、私にとっての関心を高めました。
多くの著作を読み、明快な主張を知り、その部下が、「リクルート」や「私」よりも「柴田昌治」の方が「自分の全身全霊を投入できる」と判断したことにも納得しました。
偉そうなコメントを、お詫びしますが、私は、柴田さんの主張を「覚えた」「学んだ」と言うことではなく、
「私自身の生き方、大切にする価値観」を、見事にわかりやすく表現してくれた人(著作)と出会ったと感じました。
私のスタイルが、柴田さんの主張を読んで、さらに、エネルギーを貰った気がします。
☆ 「私自身の生き方、大切にする価値観」を、見事にわかりやすく表現してくれた人(著作)と出会った感じました。
これは、まったくの同感です。
コンサルタントの長野さんの言葉(P93)
「ああいう場をきちっとつくっていくことが意外と大事なんですね。
たとえば、相談しあえて問題意識を共有できる仲間がいれば、一緒になって会社を
よくしようとする動きが生まれる。
互いに学びあいながら自分を変えていく、そういうエネルギーのある人たちが集まる場が
増えていけば、企業の体質も耕されていきます。それがわれわれの言うところの場づくりなんですね」
○ 気楽にまじめな話しができる場
KTCはリーダーを交えての「青臭い議論の場」を提言していました。
Y>「想定聴衆」が共有化され、日頃の問題意識・感受性をベースに、フリーに感じたままを論じ合うことで、
Y>「試作品がブラッシュアップ」されることは、私が好きな「真面目な話を気楽にする」ことであり、楽しみです。
Y>それぞれの方の「強く反応する部分」や「捉え方」「視点」は異なると思いますが、
Y>そのことが、相互の新鮮な気付きになりますね。
○ プロセスデザイン
出てきました。Yさんの非常に大事にしている言葉が。
その内容がこの本を読んでよくわかりました。
私も大事にしているポイントです。
何人たりとも、現状とのたゆまない対話によってしか現状をより正確に把握することなどできない。
その意味では、単なるヒアリングという意味ではなく、企業の現状をその現場にいてよく知っているクライアント企業の人々との情報の交流、
担当者とのやりとりを通じてこそ新しい知恵も生み出され、コンサルタントとしての役割も果たし得ると言えるのだ。
私たちはこのようなコンサルテーションを、旧来のそれと区別して、「プロセスデザイン」と呼んでいる。
したがって、プロセスデザイナーは先生と呼ばれたり、またそのように扱われるのをよしとしない。
「さん付け」もごく当たり前と考えているし、「クライアント企業の中に信頼関係に基づく仲間を作っていくこと」と
「仕事が成功すること」がほぼ同義であることを知っている。
○ コーディネーター
いわゆる司会のうまい人(仕切るのがうまい人)がコーディネーターに向いているわけでは必ずしもない。
むしろ、仕切るタイプより「人の話しをうまく引き出す能力を持っている人」のほうが向いていると思うこともしばしばある。
漫才のボケとツッコミで言えば、ボケタイプの方が適している。
少しボケながら人の話しをどんどん引き出して、要所では流れをうまくリードできる、そういうタイプが一番合っている。
プロセスデザインナーという仕事は簡単そうで難しい
(長野談)
自然にね、相手の気持ちになって自然に考えて、不自然なことをやらないというのかな。
目線が高いところにあると、どうしても相手を変えようとしてしまいますからね。
そういうスタンスだと、おそらく場を共有できないで壊してしまうことになるでしょうね。
風土改革ノート2
(物語の途中で解説記事が入っている。)
気楽にまじめな話ができる関係
お互いに信頼し合う関係、相談しあえる関係を組織の中に築いていくことこそが、
「言ってもムダ」とお互いがけん制しあう安定状態を崩していく上でのキーワードなのである。
ということは、つまり、風土・体質の改善というのは、
「けん制しあう人間関係」を「信頼し合い、相談しあえる人間関係」に変えていくことなのだ。
言い換えれば、互いに目線を合わせて相手を人間として尊重しながら、お互い学びあうことこそ
風土・体質改革の出発点なのだ。
…
お互いがけん制しあっている状態では「気楽にまじめな話をする」機械がほとんどなくなって
きてしまうということになる。組織がまだ新しかったり小さかったりすると、
比較的「言ってもムダ」というようなお互いのけん制的な機能は働きにくい。
若い組織では、時と必要に応じて、ちょっとまじめに雑談をしたりすることはあるものだ。
つまり「青臭い議論」をするようなことがよくある。
しかし、組織が老化してくると、素朴な疑問や改善意欲も薄らいでしだいにそれが少なくなる。
アフターファイブで同僚と飲みに行っても、せいぜい上司の悪口を言うくらいで終わってしまったり
する。
「気楽でまじめな話」の効果
・ふだん聞かれないはなしがバラバラと出てきやすい
もしかしたら重要ではないかなと思う程度の断片的な情報を気楽に口にしやすい。
ざっくばらんな雰囲気で出てくる生の情報、育ってきた情報というのは意外に戦力になるものである。
第3章 改革はなぜ失敗するのか
・瀬川がインフォーマルな2泊3日のオフサイトミーティングをやりたいと申し出たときの
紺野部長の答えは「既存の体系的なプログラムの中でやるべき」との堅いものだった。
人事部とTQM推進室が主管となってやってきた小集団活動は、社長交代を機に「コスト・
技術・情報感度の進化」をテーマに活動。課長以上はマネジメントの改革を、以下の層は
チーム活動での業務改革を目的に、各部門の課題にそってテーマを申告させ、その進捗を
事務局が管理していた。活動は半年毎に実績をまとめて報告会を行い、優秀な職場は
表彰をうける。ただし、業務として位置付けられたこの活動は、あくまでTQC推進室の
ペースで運営、管理されているため、テーマ申告から自己評価、実績報告に至るまでの
書類作成も含めて、やらされる側の負担になっていた。
⇒ 伊方発電所のTPM活動もまったく同じ印象である。
常に疑問を感じていた活動である。
主催者側は(紺野部長と同じく)これでいいものができると思い込んでいるのだが
私は否定的であった。
大阪ガスのように危機感を全員が共有しての活動なら成果はあるのだが。
そしてなんとか開催にこぎつけたオフサイトミーティングは社長の参加でも活気づき、
◎ 2日間、じっくり話し合って気心が知れたせいか、場をいっぱいに使ってやりとりする
みんなの口調は打ち解けていた。
「どうやって仕事にゆとりをつくるか」
「なぜ品質はよくならないか」
「会社における信頼関係とは何か」
社長は新鮮な気持ちでテーマを眺めた。
いかに目標を達成するか
いかに生産性を上げるか
いかにムダをなくしてコストを削減するか
とりあえずは現状のあり方、やり方を前提に、それをよりよくしていく方向で議論されるのが
普通。これを今現在、立脚している足下、つまり前提そのものからみなおして、そこにある
問題を発見し、議論するような「場の設定」そのものがなかった。
第6章 ビジョンを掲げる
◎ 「それぞれの個は自律的に動いているが全体としては秩序がある」という状態は、
組織のひとつのあり方です。状況によっては、一見、みんなが勝手に動いているかに
見えてそうではない自律分散的な活動の方が効率がいい場合もあります。
今日のように企業の活動範囲がボーダーレスになって、しかも進路が見えない状況の
なかでは、集中コントロールによるマネジメントには能力的な限界があります。
群れ全体が自由に行動範囲を拡大し、どんな状況でも秩序を保って行動するには、
小さい単位が自律的に動けるようなマネジメントの方が柔軟に動けてスピードが
あって、効率もいいことが多いように思える。
風土改革ノート6
○ いろいろなオフサイトミーティング
1 部門横断型「耕し」のオフサイト
2 部署内「親和」のオフサイト
3 テーマ別「知恵出し」のオフサイト
「気楽に」「まじめに」「人の話に耳を傾け」「根幹を成す問題提起がある」
これに加えて、議論を活発化させるためには「毛色の変わったメンバーの参加」も大切な要素である。
⇒ 私自身はすべてのタイプを自然にやってきたという自負がある。
今回、それを理論的に立証してくれたという喜びがある。
今後もこのオフサイトをいろいろ仕掛けていきたい
第7章 正念場の機器
・まじめな雑談の効果
直接的に課題を解決したり処理したりする場ではないけれど、課題という制約がないだけに
広い範囲の問題を吸着し、ノルマではなく自然な問題意識と気軽なやりとりによって、
問題解決の周辺環境を整える作用をする「まじめな雑談」は、言うなれば「ハンドルの遊び」
の時間だ。
風土改革ノート7
◎ 創造とは、収束よりも発散の中からのほうが種がみつかりやすい
会議(収束)とミーティングの一番大きな差は、そこで生み出されるエネルギーの差。
正式の会議で終わった後「よし、やるぞ」と思わせるものは少ない。
これに対してノルマのない気楽なミーティング(発散)ではエネルギーが湧き起こりやすい
○ 知恵を出す(問題を見つけ、全体像を浮き彫りにする)機能
は、時間の限られている会議ではムリで、ミーティング(気楽にまじめな話をする場)に
譲ったほうがいい。
第8章 奇跡の再生
関係者の回顧
○ 話し合うことが出発点ですね。話合いの効果?うまく言えませんが、結局、黙ったり、
臭いものにふたをしたりするから腐敗していくわけでしょう。雑談だって何だって気楽に
話ができるというのは、常に相互に情報や気持ちが流れている状態だから問題が隠れない。
さらに、誰が何を考えて話して、何をやっているかが見えていれば、必要な者が必要なときに
アクセスして力を借りたり助けたりできる。何かインターネット組織って感じですけど、
そういう集団には自己回復、そういう作用があるような気がします。
○ 一種の人的インフラ整備
インフラが整備されると、場が作りやすくなる。それにつれて風土・体質が変わってくるんですね。
もう誰も「言ってもムダ」とは思わなくなるんです。そう思っていない人は今でも結構いますから、
誰もがとは言い切れませんけどね。でもいいんです。そういう人がゼロになるなんてありえないし、
やりたい人がやるというのが基本ですから。
でも、そういう人たちに周りもつられて変化する部分はあるし、全体としては、いろんなことや
常識が変わってきたような気がします。
◎ 情報というのはエネルギーによって伝わる
自発的に参加して、形式にとらわれない「質の議論」をするミーティングなんかは、
場の持つエネルギーが物事の進行に推進力を与えていることがわかります。逆に、
普通の会議を起点にプロジェクトの推進なんかをやろうとすると、結局は、持ち帰った分担課題を
こなすだけという消化仕事になりやすい。そういうことも実感として分かってきました。
◎ まじめな雑談
幸運を呼び込む「何ものか」というのは、企業として、「勘」を働かせることができることが
要素のひとつ。
そこで「何ものか」を持つには、そういう「勘」を養えるよう日ごろからアンテナを立てる努力を
しておかねばならない。
そのための方法はいろいろあるが、割合簡単に実行できて、成果も上がりやすいのが「まじめな雑談」
の習慣である。愚痴を言い合う「普通の雑談」ではなく、前向きのエネルギーが働きあう「まじめな
雑談」」では非常に多くの情報が引き出され、やりとりされる。断片的ではあっても新鮮で生き生きした
情報が飛び交い、そのお互いの刺激でまた新しい情報が生み出される。
こういう状態をいつも経験していると情報による刺激を受けてアンテナが育ってくる。
新しい情報の刺激がアンテナをつくるのである。
◎ 決断は一人で
「勘」は誰もが持っているわけではない。
アンテナが育ちやすい環境にいても、その中でアンテナを育て得る人はやはり少数なのだ。
したがって、多数決で決めるとやはり勘は働かないことが多い。
したがって、もし新しい芽を育てようとするなら多数決はやめて、それを見分ける「勘」の
働きそうな人を前面にたてて、その人の決断に頼る必要がある。
勘の働きやすい人を見つけるというのはひどく難しそうに思えるが、じつはそうではない。
「勘」の働きそうな人というのは、近くにいる人ならば見分けがつきやすいものである。
といいうことは、そういう情報が企業の中で日ごろから大切にされているかが肝心な点なのだ。
もうひとつは「合議に頼るのではなく、一人で決める」というマネジメントの存在だ。
このルールさえ生きていれば「勘」の働く人間に決断させる、という選択をしさえすればよい。
◎ 幸運の種
を引き寄せる「何ものか」が、結局、風土・体質であり、風土・体質を強化しうる
マネジメントのルールなのだ。
以 上