野口 悠紀雄 ダイヤモンド社 (2007/05/31 出版)
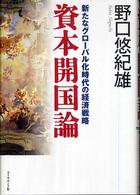
これも会社のE先輩の推薦図書である。
経済関係は自分では決して手に取らないので、大変ありがたい。
野口さんはいろいろなところで登場しているので知っていたが、著書をまじめに読んだことはなかったのでいい機会となった。
読後感は、言っていることはそれなりにわかるがなんかちょっと違うという直感である。
リーマンショックの後で読んでしまったからかも知れないが、その前でも製造業から脱却して金融業に移行すべきという主張は
きっと違和感を持って読んだに違いない。
実体のない経済というものは私はおかしいと思う。
イギリスやアイルランドのように資本開国をして海外資本による活性化、成長を期待しているが
リーマンショック後の資本の退却は何だったのか。
そこにはバブルがあった。
レバレッジ経済、GDPの何倍もの架空のお金が資本になる怖さ。
それを今、まざまざと見せ付けられている。
この点を野口さんは残念ながら見逃している。
NHKでその特集が始まったところである。
NHKスペシャル マネー資本主義 第1回「“暴走”はなぜ止められなかったのか」
http://www.nhk.or.jp/special/onair/090419.html
紀伊国屋WEBの紹介記事はこうなっている。
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/9784478001301.html
1993年に世界トップだった日本の1人当たりGDPは、いまや、かつての欧州最貧国アイルランドの4分の3にすぎない。
この没落の裏には何があるのか。
世界経済の構造が激変するなか、日本は製造業中心の産業構造を温存した。
ここにこそ、現在の日本経済が抱えるすべての問題の根源がある。
21世紀型グローバリゼーションに適応し、新たな経済活性化を実現するための戦略を説く。
-------------------------------------------------------------------------------
共感を覚えたのは、小泉構造改革は何の役にもたっていないという厳しい指摘。
怖くなったのは年金問題の本質
そのあたりを各章毎にポイントを抜き出しておこう。
第1章 企業栄えて家計滅ぶ―格差問題の根底にあるもの
・家計から企業へ200兆円の巨額移転
金融緩和による金利の変化は企業が負債を減らしただけで投資には回らず経済活性化につながらなかった
そして家計の利子はマイナス、これが格差問題を拡大した
企業栄えれば家計も栄える時代ではなくなった
→納得である
・要素価格均等化定理
貿易が行われれば、貿易財の価格だけでなく、賃金などの要素価格が均等化する
日本においては社会保障費の増加 法人税は利益にかかるが、これは関係なくかかるので企業はその回避のため
非正規雇用を増やしたり、生産拠点を海外に移転することになる
→ 法人税の率ではなく社会保障費の問題か なるほど
◎重要な結論は、「景気回復にもかかわらず賃金が上昇しないという現象は、一時的なものではなく、
世界経済の構造変化に伴うものである」ということだ。したがって、それによってもたらされた格差拡大も、 構造的な問題である。
この理解が正しければ、格差問題は、対症療法的な対策や所得政策では解決できない。
それに対処するには、産業構造の改革しか方法がないのである。
日本では、世界経済の構造変化によってもたらされた変化が「デフレ」であるとされ、それに対処するために
金融緩和が行われてきた。しかし、そうした意識は誤りである。
したがってその認識に基づく金融緩和政策も誤りである。
⇒ この主張にはアグリーである。
NHK番組風に言えば、「ガッテン、ガッテン」である。
第2章 世界の大変化に追いつけない日本―アイルランドやイギリスが日本を抜いた理由
・離陸する脱工業化社会
OECDの統計によると、イギリスの2005年における就業者数
製造業 377万人に対し 金融不動産業 610万人で1.6倍
これに対して日本では
製造業 1147万人に対し 金融不動産業 272万人 (うち金融・保険157万人)
このことが1人当たりのGDPにおいて日本がどんどん抜かれた要因となっている。
⇒ 野口さんは、世界の趨勢は脱工業化なのに、日本の政府は旧態の製造業の支援策を行使して
生きながらえさせてきたのが失敗だと説いているが、それに対しては違和感を感じる。
冒頭に書いたとおりである。
21世紀型グローバリゼーション↓
・オフショアリング
この言葉はなじみがなかった。
組織内で行っていた業務の一部を海外に委託するもの。
コールセンターからデータ入力、ソフトウェア開発や専門的業務までインドなどにアウトソースする例が急増している。
まったく新しいタイプのグローバリゼーションで受け手国が急成長し、出し手国の企業の利益率が上昇している
日本は言葉の問題で取り残されている。
・先進国間の直接投資
ウィンブルドン現象と比喩しているがなるほどと感心
日本は資本鎖国している状態
★「リプチンスキイの定理」
① 資本が増大すれば、資本集約産業の生産量が拡大し、労働集約産業の生産量が縮小する
② 労働が増大すれば、労働集約産業の生産量が拡大し、資本集約産業の生産量が縮小する
③ いずれの場合にも、両産業の資本・労働比率は不変にとどまる。賃金率・資本収益率も不変にとどまる。
こうなるのは不思議な気がするが、生産要素が産業間を移動し、産業の生産規模が変化するからである。(と説明している)
しかし、現実には貿易が関係する。
製品輸入の増加も、日本の海外投資によって促進されている部分がかなりある。
タイに工場を建設して、いままで国内で作っていたテレビ受像機をそこで生産し、それを日本に輸入する」
といったケースである。
この場合には直接投資が貿易を増やしているが、逆の場合(輸入関税が高くなるケース)もありうるのである。
● FTAの疑問
日本のFTA(自由貿易協定)の相手国は、日本の製造業が立地している諸国がほとんどである。
つまりFTAは海外に生産拠点を移しつつある製造業のためのものなのだ。
他方で、日本国内の労働者にとっては、すでに述べたように賃金が低下するから、損失を意味する。
海外進出した企業の労働者だけでなく、労働市場を通じて全労働者が損失を被るのである。
FTAや東アジア共同体構想に反対する人はほとんどいない。
しかし、労働者の利害を考慮に入れれば、必ずしももろ手を挙げて賛成できるものではない。
それにFTAによって相手国の関税収入は減少するわけだから、それが何の見返りもなしに
実現できると考えるのは、あまりにもナイーブだろう。
現実のFTA交渉でどのような見返りが約束されているかわからないが、多くの場合において
日本の税負担者の負担にはね返るようなものであろう。そうであれば、納税者の負担において、
進出企業のコスト削減がなされることになる。それを考えると、FTAに対する疑問はさらに強まる。
⇒うーん。こういうことなのかなあ…。
しかしFTAを組まないと、どんどんほかの国同士でFTAを結んで、結果日本の貿易ができなくなる
ようなことになるのではないのかなあ。だから納税者負担でもやるべき?ということもあるのでは。
よくわからずに書いているので、本件については勉強してみないといけない。
○ 資本開国こそ日本経済の出発点
日本の場合にとくに重要なのは、資本を外国から取り入れることによって、日本企業の体質が変わり、
経営やビジネスモデルに対して質的な影響が及ぶと期待されている。
⇒ここには直感的に違う気がする。冒頭に書いたとおり
第3章 量の拡大でなく、質の向上を―本当に必要なイノベーションは何か
(この章はほぼアグリーである)
・成長至上主義では問題は解決しない。
① 出生率の引き上げによって労働力不足や年金などの問題に対処することはできない。
人口減少社会における最大の課題は、社会構造をそれに適応したものに改造することだ。
② 「イノベーションによって生産性の向上をはかる」という認識は正しいが、イノベーションは狭義の
技術開発だけではない。いまの日本で最も重要な「イノベーション」は、産業構造の改革である。
最も必要なのは、低生産性部門(農業、流通)の生産性を引き上げる(あるいは、資源や労働力を
そこから他部門に移す)ことによって、経済全体の生産性を引き上げることだ。そのためには、
これらの部門に対する保護策から脱却する必要がある。
⇒ここは異論あり。農業は非常に大事である。この復活を考えるべきであろう。
③ 現在の産業構造のままで成長率を高めるのではなく、経済活動の質を高めることが必要である。
そこで重要なのは、コモディティ化からの脱却だ。つまり、必要とされるのは、量的拡大ではなく、質的向上である。
●年金破綻の原因は制度設計のミス
制度発足時の保険料が低すぎたため、その後の経済成長に合わせて給付を改善するとき、保険料の引き上げが
必要になった。保険料引き上げの際に、すでに徴収した保険料についてさかのぼって引き上げることが出来ないから、
その分は今後保険料を支払う世代の保険料に上乗せされる。これによって、給付と受給の世代間格差が生じる。
これは制度設計のミスに起因する。つまり、現在公的年金に見られる世代不均衡のかなりの部分は、過去の
誤りに起因するものだ。
・コモディティ化からの脱却
「コモディティ(commodity)」は、もともとは「商品」という意味だが、最近ではもっと限定的な意味で使われている。
それは、「生産に格別特殊な技術が必要とされないため、差別化特性がなく、価格が主たる判断基準になる製品」
という意味だ。
第4章 難題山積の財政改革―これまで何が行なわれたか
⇒ この内容はよく知らなかったのでサラリーマンとしてはあらためて憤慨することとなった。
・保険料未納の根幹
年金についてなすべきことは多いが、緊急に措置する必要があるのは、国民年金の保険料未納問題である。
この問題の根底には、基礎年金に関する国民年金と厚生年金の財政調整の仕組みがある。
一見すると技術的なことと思われるかも知れないが、これを解決しない限り、未納問題は解決しないのである。
基礎年金の給付に要する費用は、各年金制度が「基礎年金拠出金」として拠出している。
問題は、各制度が負担すべき額の算出方法だ。
それはサラリーマンに過大に不公平な負担を強いる形になっているのである。
常識的に考えれば、各制度の負担額は、必要額を加入者の比率(本来保険料を支払うべき人の比率)で
割り振るべきだろう。しかし、実際には、被用者年金については「保険料を支払うべき人」の数を取るが、
国民年金については「実際に支払った人」の数をとることになっている。(つまり未納者は除かれる)
だから、国民年金の未納者が増えれば、国民年金が負担すべき額は減る。そして、その分だけ被用者年金が
余計に負担しることになるのだ。だから、国民の納付率がいかに低下しても、自営業などからの保険料徴収を
強化する必要はまったくない。なぜならサラリーマンが必要な額を自動的に補填してくれるからである。
なぜこのように不公平な制度になっているのかというと、もし国民年金についても「本来支払うべき人」の
数をとれば、国民年金の未納者が増えるだけ国民年金の保険料を引き上げなければならない。そうなると、
保険料引き上げと未納率上昇の悪循環に陥る。そうした事態を避けるために、今のような制度になっているのだ。
「取りやすいところから取る」というのは、税についても言えることだが、保険料の場合はあまりにひどい。
安倍内閣は、社会保険庁の解体を重要施策としている。しかし、以上で述べた制度が続く限り、
いくら組織いじりをしても、問題の解決にはならない。保険料徴収機関がどこになるにせよ、
「徴収できなくとも、厚生年金加入者が自動的に埋め合わせる」という現在の仕組みがある限り、
徴収機関が国民年金保険料徴収に本腰を入れるとは思えないからである。
・清算できるか
現在年金を受給している人々には、将来の年金を一時払いで払う。
また、年金受給年齢に達していない人には、過去に徴収した保険料を払い戻す。
つまり、現在の受給者の将来の年金給付の割引現在価値と、これまで支払われた保険料の累積額を、
現在の積立金で支払う。そして年金制度を清算するわけである。
⇒ こうすることによって民間の年金制度に移行させることができる
このような「清算」ができるかどうか計算してみると不足額は、実に800兆円程度という信じられないほどの巨額のものとなる。
⇒ 一定の想定の下で計算すると書いているが、その注を読むと、他の著書を引用しているだけだ。
計算の詳細は「日本経済改造論」(野口 悠紀雄、東洋経済新報
社、2005年)
これは非常に不親切だ、買って読んでくれとでもいいたいのか、
このあたりが野口氏の不誠意を感じる、少なくとも計算条件の概要は紹介しておくべきだ、こんな重要なところなのに)、
第5章 法人税減税では日本経済は活性化しない―「まやかし経済学」はやめにしよう
⇒ ここは勉強になったが、やっぱりちょっと違うのではと感じた
・法人税は所得税と違う
法人税は転嫁されず、株主の配当、キャピタルゲインや企業役員報酬の帰着する可能性が高いとされている。
そうであれば、法人税減税は所得分配を変えるだけ。したがって、法人税減税は高額所得者の税引き後所得を増やすので
格差を拡大することになるだろう。
・法人税よりもむしろ高い保険料の方
社会保障負担の半分あ雇用者負担だとすると、それはすでに法人税ようりもかなり負担になっている。
(法人税は利益に対してだが、保険料は従業員数)
社会保険料は今後も継続的な上昇が予想される。将来の法人の公的負担の動向を支配するのは社会保障負担の
動向である。したがって、公的負担と国際競争力の関係を問題にするのであれば、年金などの社会保障負担を取り上げるべきだ。
高い保険料負担が経済活動の海外流出の原因になることは十分考えられる。
つまり、社会保障の増加は、賃金の格差に拍車をかけるわけだ。
社会保障制度は、本来は労働者の福祉向上のために導入されたものだ。
それが、賃金の低下や雇用機会の減少をもたらすという、皮肉な事態が生じていることになる。
⇒ 納得である。
派遣の問題の本質はここにあると思う。
・法人税は投資に中立的
法人税負担を軽減しても、投資が促進されることにはならない。
その基本的な理由は、利子支払いが法人税において損金扱いされるため、法人税は課税後の資本コストを変えないことだ。
⇒ 確かにそうだろう。しかしフリーキャッシュフローについては間違いなく増える。
それをどう使うかは経営判断。
金融緩和でもまったく投資が進まなかった過去の日本の経営者なら投資は期待薄かもしれない。
しかしだからといって投資がまったくないかというとやはり減税されたほうが可能性は高まると私は思う。
第6章 資本開国こそが日本を活性化する―いま本当に必要なこと
・日本は損な役回りを進んでやっている
本当は、資本の面から見ても、日本人にとって、円安ではなく円高が望ましい。仮に円高になって経常収支の黒字が
縮小すれば、反面で国内支出が増えているはずである。消費であれば、日本の消費者はそれだけ豊かになり、
投資であれば、資本装備率が上昇して賃金が上昇するはずだ。
額に汗して貿易黒字を獲得し、それを蓄積した資産を「安く使わせてくれ」と海外から求められているわけだから、
日本は損な役回りを要求されていることになる。しかし、日本は、それが損な役回りであることに気づいていない。
むしろ、そうすることを望んでおり、嬉々として低金利・円安政策を続けている。
こうしたことになってしまうのは、日本の産業構造が製造業に偏ったままになっているからだ。
しかし、これまで述べてきたように、そのような構造を長期にわたって続けることはできない。
日本の産業の中核にあった製造業の多くは、中国をはじめとする新しい工業国家群にゆずらざるを得ない。
だから、従来の産業構造の維持は不可能であることを認識しなければならない。
しかし、金融緩和・円安政策は、古い産業構造を温存させる。
こうした政策から、新時代をリードする革新的な企業は、決して生まれないだろう。
現在の経済政策の最大の問題点は、「構造改革」が言葉として叫ばれながら、中核にある企業や産業の構造改革に
手がつけられていないことだ。実際に民間企業が行っているのは、後ろ向きの整理・縮小や、新しいビジネスモデルの
創出を伴わない合併統合がほとんどである。
これから脱却するための戦略的手段は、資本開国だ。
⇒ 最後の資本開国だ という結論に対しては疑問である。
資本開国によってでなければ企業改革が行われないと思っていることには違和感がある
・信じられないほど非効率な外貨準備の状況
日本は長保守的な債権運用で利回りが非常に低い。
そして野口さんは韓国での取り組みを賞賛している。
韓国は韓国投資会社が先進国株に運用している。
…日本と比べれば、一歩は前に進んでいるといえる。
⇒ その韓国の運用は破綻した、またアイルランドもしかりである。
野口さんはどのようなコメントを出しているのであろうか。
本書では、思い切りこんなことも書いている。
第一に、「金融業は虚像」とお考えの方は、イギリスやアイルランドが日本よりも豊かになった事実をもう一度思い出していただきた。
ただ次の主張にはなるほどと思う
第二に、日本はイギリスやアイルランドとは比べ物にならない有利な条件に恵まれていることを認識して
いただきたい。それはGNPとほぼ同額の対外資産を、すでに保有しているという事実である。
こうした巨額の資産を持っているからこそGNPの成長率引上げと同じことを「すぐにでも実現できる」のである。
以 上