仕事・人生・経営論
弘兼 憲史 光文社新書
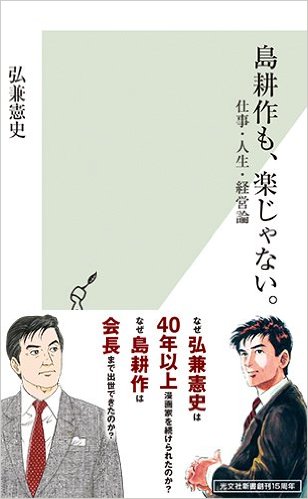
島耕作の仕事論
●情報源のバランスを取る
新聞や雑誌、本の場合、編集部、あるいは書き手が偏向していないか、
というのは常に注意している。
もし偏っていると感じたときは、その反対の側にたった本を読んで、
バランスを取るようにしている。
弘兼憲史の仕事術
〇 三上
余、平生作るところの文章、多くは三上に在り。
すなわち、馬上・枕上・厠上なり
欧陽脩
弘兼さんの場合はトイレよりも風呂場とのこと。
〇 人生を豊かにする1日の締め方
みんなが帰った仕事場で、ラジオを聞きながら仕事をする。
この時間、聞くことが多いのは、NHKの深夜番組「ラジオ深夜便」だ。
NHK出身のベテランアナウンサーたちによる落ち着いた語り口は、
深夜一人で仕事をするには丁度いい。
だいたい3時から4時くらいまで、日本の歌謡曲を聞いた頃、
そろそろ家に帰ろうという気になる。
これが私の営業終了である。
→ラジオ深夜便は家内もファンで聞いている。
作家五木寛之もファンでよく聞いているということを昨年のスミセイセミナーでお聞きした。
弘兼さんで3人目だ。
私の場合はここまで起きていることはなく、逆にたまに早く起きだしている時間帯だ。
したがって深夜便でなく早朝便となるが、まだ一度も聞いたことはない。
〇 私はマグロ
自分は、鮫やマグロのような回遊魚だと思うこともある。
停まったら最後、死んでしまうのだ。
〇 死にかた
病院に入って、3年も4年も苦しんで死にたくない。
原稿を書きながら、ぱたっと死ぬ − 漫画家として最高の終わりかただ。
島耕作のライバルたち
● 25歳までに才能はできている
(同郷の柳井正さんとの対談で)
(柳井)ほとんどの人が実際にそうなんですけど、与えられたものでしか自己実現はできないと思っているんです。
いま持っているものでしか自己実現はできない。
僕はいつも「人間のピークは25歳」と言っているんです。
→ そうなんだろうか…。この言葉にはちょっと賛同しかねるがあとに続く解説で少しは納得かな
われわれのようなビジネスマンでも、弘兼先生のような漫画家でも、あるいはスポーツ選手、
芸能人、学者、政治家でも、自分の才能にいつ気づけるかは、人によって違う。
ただし、いずれにしても、自分の持っている才能のもとは、だいたい25歳ぐらいまでにできている。
その才能にいつ気づけるか、という違いなんです。
● ブラック企業
今の基準で考えれば、私の若い頃はかなりの企業が「ブラック企業」だった。
さらに漫画業界というのは、徹夜が当たり前の世界である。
ブラック中のブラックだ。
そして、柳井さんが続けて言った言葉は、私の胸にストンと落ちた。
「それくらい一所懸命やらないと一人前にはなれないんじゃないですか。
不思議なことに、みんな大学を出たら一人前だと思っている。
どれだけ優秀な人でも仕事で一人前になろうとしたら、3年から5年はかかります。
普通の人なら一つのことを10年くらいはやり続けないと絶対に一人前になれません」
→ まったく同感。ブラックと感じる感覚はセクハラとも似ている。
本人に意欲、モチベーションがあればどれだけきつい仕事でもいきいき仕事ができて
充実しているものである。
一律の時間規制にはなんだかこれでいいのかとも思う。
一方で柳井さんのこの言葉は、25歳までで才能はできているという言葉と矛盾するのではないかと。
才能と仕事での一人前を同じように思ってしまうのでそう感じるのだ。
才能と一人前の意味はまったく違うから柳井さんは正しいことを言っているのだろうが
誤解するのではないだろうか。
25歳までで才能はできているという言葉はあまり好きではない。
死ぬまで成長したいという言葉の方がよい。
○ サラリーマン根性
大企業にもサラリーマン根性を持っていない人もいるんですよ。
そういう「いい人」は相手のことを考えて、お互いにとってベストな形を提案してくれる。
経営者感覚やビジネスセンスを持った人ですね。
柳井さんはファーストリテイリングの社員にこう言っているという。
「サラリーマンというのはもうない。本当はみんな自営業者なんだ。」と。
〇 結びの言葉
人間は死ぬまで未来がある。
ファーストリテイリングの柳井正さんはこう言った。
「僕は死ぬまで成長したい。それが一番いい人生だと思うんですよね」
私も同感である。
最後まで仕事をして、成長する。
これが私の、そして島耕作の「仕事・人生・経営論」である。