畑村洋太郎 講談社
弟子で「失敗100選」の中尾先生で同書で紹介しており読むことにしたものであるが、なかなかよかった。
失敗学創設の畑村先生の編集書である。
建築、土木や宮大工などの方々の経験からの気づきを載せて、それに畑村先生がコメントしている。
機械、材料の話しは多いが、現場の生の声は価値がある。
コメントは不要、むしろ邪魔の感さえした。
したがって、この書はあくまでは畑村先生が「収集・編集」した作品と言ってよい。
○ 第一章 材料分野 「破壊事故に学ぶ」
小林英男 東工大教授
「絶対に壊れない」という考え方を変えて、たとえば「今は問題なくても、30年経てば問題が生じる」
という認識があれば、それでOKなのです。逆に言えば、「30年経てば問題が生じる」と想定して
実際に30年後に問題が起これば、それは一番安全な状態だといえるのです。予測が可能だということは、
事故が起こる前にきちんとした対処ができるということを意味しているからです。
しかしいまのように、「絶対に事故は起きない」と広言しているから、結局は事故が起こったときに
対処できずに社会的に叩かれることにもなるのです。その意味でも、まず私たちが、「事故が起こるかも
知れない」ということを認めるところからものづくりをスタートさせるべきで、それを教えてくれるのが
破壊事故だと私は考えています。
畑村コメント
原子力専門の技術者は優秀な人が多いのですが、その分、他の分野に学ぶという姿勢が薄いのではないでしょうか。
他分野の事故を学べば、自分たちの分野でも同じ事故が起こる可能性があるということを簡単に知ることが
できるはずです。
○ 第二章 土木分野 「事故にはいろいろ背景がある」
松田 芳夫 財団法人リバーフロント整備センター理事長 (役人出身)
土木という分野は、技術的な問題もさることながら、どうやって資金を調達するかという財政的問題、
あるいは納税者である市民とのやり取り、土地を提供している地主さんとの関わり、政治家とのやりとりなど
たいへん人間臭い部分の比重が大きいのです。
…
…
起こったときに初めて、「やっぱり起こったか」となるわけで、事故防止のための日頃の努力は、
ほとんど評価されることがありません。
火事が起きないと、「私の町には消防署なんかいらないじゃないか」と言い出す人がいます。
火事がないというのは、消防署の人が日夜点検して、「ここの調理場は危ない」「消火栓を
つけておきなさい」「ここにモノを置いてはいけない」と努力している賜物あのですが、
それを「火事がないから消防署はいらない」というのは本末転倒もいいところです。
同じような理屈で、犯罪がないのに警察がいるのかという話しもあります。
何かのマイナスを防止するところに人員や予算を割いておくと、効果が上がれば上がるほど無駄だとして
その機関に対する風当たりが強くなるのが常です。
その人たちが頑張っているからマイナスを防ぐことが普通の人にはなかなか見えないし、わからないということだと思います。
事故防止には事故や災害の防止の努力を重く見て評価しないといけないのです。
(畑村コメント)
事故を防ぐには結局、いつも大事をとってばかばかしいと思えることでもきちんとやっていくことしかない。
・日比谷線の脱線の背景
日比谷線は道路の交差点で曲がる場所が多い。
それは都電の路線をそのまま線路としたため。
ルートを変えようとすると私有地の下を通り多額の保証金を払う必要があった。
1960年代は電車の連結も少なかったが、相互乗り入れで10両編成になると条件が変わってきた。
・全部を見渡せる責任者が求められている
芸術作品でなく土木の作品であっても、責任を持ってこれを行うプロジェクトマネージャ、リーダーを
作らねばならないというのが、長年土木の仕事に携わってきた私の感想。
・土木・建築工事の事故の場合でも、権威ある調査委員会を常設すべき。
そして再発防止の観点から事故原因をサイエンスとして分析をすることが必要。
警察が一番最初から出入りすると責任追及が怖くて自然に口が重くなる。
○ 第三章 建築分野 起こりうる事態をどこまで想定するか
嵩(かさみ) 英雄 工学院大学教授
・既存不適格にどう対処するか
既存不適格の建物は問題物件なので、阪神・淡路大震災クラスの地震にはとても耐えられません。
神戸以外の地域にもこういう構造物は多々ありますが、そのことをどう考えるかは大変難しい問題です。
たとえば、イギリスのように全部を立て直すということができれば一番いいのですが、コストの問題を
考えるとそうもいきません。これらをどうやって解決していくかというのが、建築の分野で現在も残っている
大きな問題だと思います。
・原子力仮想事故
最大想定事故に対しては設計で対処しています。
原子力ではこれ以外の想定外の事故を仮想事故と言っていますが、典型例がメルトダウンや炉心の溶融で、
これが起こったら手の打ちようがないから逃げ出すしかないということになっています。
その場合、余裕度のある計画とは逃げ出すことを可能にする立地条件を選ぶということになります。
原子力発電所は「事故が起こらない」という建前になっていますが、それでもなぜ都心に作らないかというと、
事故が起こらないようには設計できるけれどまったく想定していない事故、つまり仮想事故を想定しているからです。
仮想事故が起きた場合に逃げ出すには、ある程度人口密度が低くないといけないと考えられているので、
原則として原子力発電所は人口密集地には建てていないのです。
そして建築の失敗を防ぐためには、今後こういう発想も必要になると考えています。
○ 第四章 大量輸送分野 「鉄道の安全性は衝突事故の繰り返しによって高まった」
万代 典彦 JR東日本 新幹線運行本部長
なぜ起こる鉄道事故でJRの安全の取り組みは知っているので鉄道関係はあまり書くことはない。
・人間と機械の役割分担の境目をどこに置くかが常に問題となる。
想定されるあらゆるケースで柔軟な対応ができる仕組みにするためには、
人間を主体に置いて、機械が支援するという形が最もふさわしいと考えています。
ここは意見の分かれるところですが、たとえばATSやATCにしても、いかに運転士の注意力を持続させるかが
この種のシステムがトータルとして最大の力を発揮するための鍵ではないかと考えている。
◎ 人間が一番やりがいを感じて仕事をしているときは間違いも少ないはずです。
畑村コメント
システムがいまの形になるまでにどんな苦い経験と事故から学んだ教訓があったかということを、訓練とセットで
教えていくことが大事
「事故の歴史展示館」 福井県新白河の研修所 ← ここは9月に訪問できるので楽しみである。
○ 第五章 システム分野 ゼロからの新システムを構築する
宮島 弘志 JR東日本 運輸車両部企画担当課長
ATOS (Automous Decentralized Transport Operation Control System)の開発の話。
藤野駅でのATOS通信制御装置の故障からシステムダウン
この一番の原因は、ほとんど関係なくなった盲腸のような部分のLSIの製作不良。
重要度が低いので見逃されていた。
システム作りの難しさを痛感。
○ 第六章 エンジニアの失敗と成長
守友 貞雄 セイコーインスツルメンツ顧問
★★ これがすばらしかった。
思わずすべてPDFにとって自己実現道場に配布した。
マズローの5段階が出てきたので嬉しくなりました。
P232にマズロー5段階説で、その段階の欲求に現れる否定されるべき行動様式と
いうのがあります。
これって、原文にもあるんですかね?
⇒ ないとのことでした。守友さんのオリジナルでしょうとのこと
そこで唯一、否定されるべき行動様式がないのが「自己実現」の段階であるというのがあり、
これだ!と思いました。
自己実現ステージにいる人には、悪い行動は現れない!!
なんとすばらしい。
自己実現道場の命名もこの本質をついていたんだと思います。嬉しくなりました。
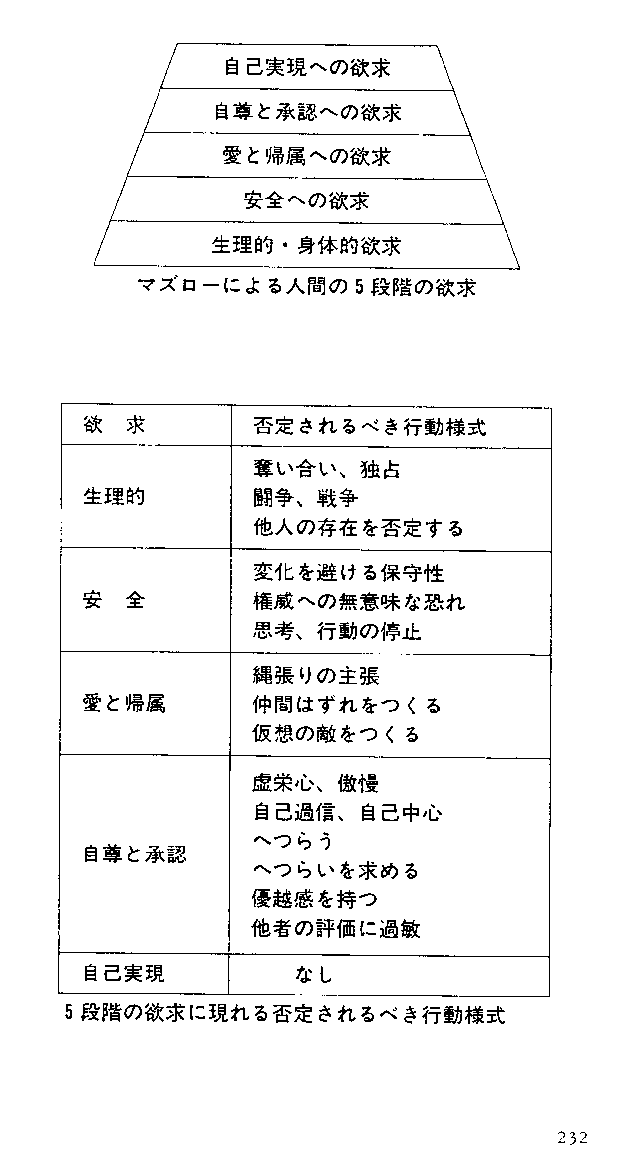
------------------------------------------------------------------
全文をpdfでとったので掲載するので、以下は簡単に目次と一部エッセンスのみ。
・失敗の克服経験が人をつくる
・失敗の瞬間から自己正当化が始まる
・人が介在している失敗は自然現象ではない
・失敗しない人が本当に優秀なのか
・タイミリミットから本当の仕事が始まる
・アクティブな劣等性が優秀なエンジニアになる?
・真の「決断の勇気」とはなにか
自分たちで優劣を判断し、責任をもって決断をする体験が、新しいものやシステムをつくる人にとって
一番大事。
世の中で起こっている事故を見ていると、この決断の勇気が持てないこと、結論を先送りすることで
問題が起こっているよう思えてなりません。
・人に聞くのは得である
・エンジニアに求められる資質
「知的能力」 知識、知能
「技能的能力」運動、腕
「態度能力」
「意志能力」 決意、決断、強い意志
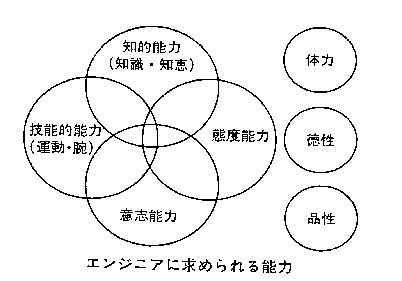
「態度能力」は心理学者の本明寛元早稲田大学教授が作った言葉。
人の心を理解する感性、気配りのタイミング アメリカの初等教育でのソーシャルスキルズという科目の翻訳で考えた
「意志能力」は、向上心や責任感とも密接な関係。この能力がなければリーダー失格。
なぜなら、保身ばかりで無責任な逃げの手しか打たず、たとえ失敗の予兆があってもそれを簡単に見逃してしまう。
どんなに知的、技能能力が高くても、意志が欠如している人はリーダーに不向き。
いつも「オレがオレが」で、「オレのこれでやれ」とアイディアを押し付けるとメンバーから嫌われる。
むやみに知識を押し付けた瞬間から、その人のまわりには人が寄り付かなくなる。
知識を求める人のまわりには、それを持っている人が自然に集まってくるという、そういう徳性を人間は持っています。
その意味では、自分のこだわりを捨てながらリーダーシップをとるというのが重要。
そうは言っても、誰でもこれがというアイディアはある。
それを捨てろと言っているのだはなく、そういうものはまわりの反応を見ながら最後の最後に出せばいいのです。
最初からゴリ押ししては反発を招くだけ。
・自己実現への欲求が人間を変える
マズローの5段階欲求の行動様式でネガティブなものを挙げて考察しているところには唸った。素晴らしい。
「保身」の気持ちは、生理的欲求と安全への欲求のネガティブな面があわさったものと考えられる。
失敗の原因となる「思考や行動の停止」、これも権威を無意味に怖れる安全への欲求からくるものと考えられる。
ネガティブなものをざっと見ていくと、愛と帰属の欲求には「縄張りの主張」などもある。
自尊と承認への欲求のネガティブな形としては、「傲慢」、「自己過信」、「自己中心的」でへつらいとか優越感を
持とうとすることですが、これらは言うまでもなくそのまますべて失敗の原因となります。
またネガティブな形は、失敗の原因となるだけではなく、創造行為を阻害する大きな要因にもなります。
ところが、欲求の中で唯一、ネガティブな形として現れないものがあります。
それが階層の一番上にある「自己実現への欲求」です。
これは充足を求める気持ち、生きている手ごたえをつくりたい、自分らしく生きたいなどと願うことで、
人間しか持たない欲求です。
そして、私の経験からいっても、この自己実現への欲求こそが保身や逃げなどのネガティブな行動を打ち消す手段に
なり得るのではないかと思うのです。
結局、つまらない失敗を起こさない、繰り返さない優秀なエンジニアというのは、自己実現の欲求を持った人の
ことだと思います。したがって、優秀なエンジニアになるためには、あるいは優秀なエンジニアを育成するためには、
こういう自己実現への欲求をいかに持ち、持たせていくかがポイントになるのです。
・褒められ叱られながら人は成長する
大切なのは、人間の心理的弱点(ネガティブな形で出ていること)を意識している人が近くにいて、
正しい道からはずれたときに叱ってやることなのです。
ネガティブな心理的な傾向が見えた瞬間に叱るというのは、極めて重要なことです。
それ以上に大切なのは、まず褒めることです。
何かにチャレンジしたから失敗があるわけで、そのときにチャレンジする気になったその決心を褒めるべきです。
褒められることで、その人は自分の行動に自信を持つようになり、さらにチャレンジする気になります。
積極的に行動したことを褒めながらも、失敗したときにはネガティブな心理の部分を叱られるという体験をすることが、
人間として極めて有利な心理的特性を持つきっかけになるのではないでしょうか。
・失敗体験が知識を生きたものに変える
・「教える」から「学ばせる」へ
・吉田松陰の啓育に学ぶ
○ 第七章 大工の失敗と成長
宮間 熊男 第61回式年遷宮総棟梁
いま振り返ってみると、私たちの仕事はそういう地域の文化に支えられている部分も大きかったのではないでしょうか。
楽をしようと思えばいくらでもできたのに、それをしないで一生懸命腕を磨きたいと頑張れたのも
人よりいい仕事がしたいという職人としてのプライドだけでなく、
自分が神様が住む御殿を作っているんだという真摯な気持ちがあったからできたのではないかと思っています。
○ おわりに
失敗をいたずらに怖れる態度は、逆に失敗に対する思考停止しか生まず、結果的に大きな失敗につながります。
大きな失敗は目に見える経済的な勝ちだけではなく、もっと大きな社会的信用まで失う可能性があります。
一方つねに失敗したらどうなるかという仮想演習を行うことによって、何かが起こったとしても、
その失敗を最小限で食い止めることができるようになります。
大切なのは「絶対に失敗を起こさない」ことよりも、
「致命的な失敗を起こさない」ことなのです。
2003年9月