佐々木 常夫 河出書房出版社
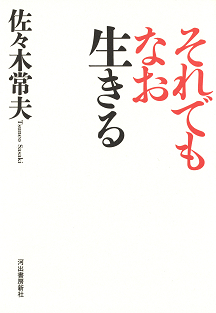
佐々木さんの著書は「ビッぐツリー」、「働く君に贈る25の言葉」で読んでいるので骨子については理解できている。
今回は仕事もリタイアして落ちついた雰囲気を感じさせる。
いつもこの本を読んでみたいなと思うものに当たる。
今回は、フランクフルの「夜と霧」(原題は「強制収容所における一心理学者の体験」)である。
◎運命を引き受ける それが生きるということ
どんな状況でも人の人生には意味があるとフランクフルは言います。
「人は何のために生きるのか」ということは、こちらから問うことができるものではありません。
「人生から問われていることに全力で応えていくこと」
つまり
「自分の人生に与えられている使命をまっとうすること」
だけができるとフランクフルは言います。
その人を必要とする「何か」があります。
その人を必要とする「誰か」がいます。
その「何か」や「誰か」のためにできることは何か。
それに全力で応えていきます。
そうすることで自分の人生に与えられた使命をまっとうします。
私たちの元にいつのまにか送り届けられている「意味と使命」を発見し実現していくのです。
→ 自分の使命に気づくこと。わかる気がします。
五十にして天命を知る。
佐々木さんはフランクフルを読んで人生観が変わったと書いてます。
それは、「運命は引き受けるもの」ということです。
→ よくわかります。
非常につらい経験を積むことによってその境地にたどり着くものなのかも知れません。
このフランクフルの著書で光を見た人がいます。
そのメルマガをこの本を読む少し前に見たので、フランクフルという言葉が頭に残りました。
ちょっと表現やとらえ方の断面は違うけれどもこの本を読んで人生の啓示を得たことは同じです。
このメルマガの言葉には衝撃を受けました。
そして佐々木さんの本からも同じフランクフルの名前を見つけることになりました。
致知のメルマガは引用OKなので引用します。
(全文引用ではなく一部を省略しております)
送信元: 【人間力メルマガ】 致知出版社 編集部
日付: 2015/05/29 08:07
件名: フランクルの公式 「絶望=苦悩−意味」
9歳で失明、18歳で聴力も失ったぼくが、東大教授となり、考えてきたこと
『ぼくの命は言葉とともにある』 福島智・著
3歳で右目の、9歳で左目の視力を失い、14歳で右耳の、18歳で左耳の聴力までを奪われ、
光と音の世界を完全に喪失した福島智氏。
絶望の淵から福島氏を救い、生きる力となった言葉とは、どんなものだったのでしょうか。
本日は、福島氏が、ヴィクトール・E・フランクルから学んだことの一部をご紹介いたします。
……………………………………………………………………………
フランクルの公式との出逢い 「絶望=苦悩−意味」
……………………………………………………………………………
二〇一一年に出した『盲ろう者として生きて』のもとになった
博士論文を二〇〇八年に東京大学に提出したのですが、
その論文を書く過程で、フランクルの『意味への意志』
という講演録をまとめた本を読みました。
この『意味への意志』も彼のアウシュヴィッツでの
体験をもとにした内容になっています。自らの体験から、
例えば彼が「この世には意味がある」と考えるに至った
理由が述べられています。
私はこの本の注釈の部分で、次のようなフレーズにたまたま出会いました。
「絶望=苦悩マイナス意味。
つまり、絶望とは意味なき苦悩である」
これを読んだ瞬間、点字を読む私の両手の人差し指の動きが
一瞬止まったと思います。
そして、「これはすごい公式だ」と衝撃を受けました。
なぜなら、この短い公式がフランクルの思想の中核を
端的に表していると思われたからです。
この公式でフランクルは、苦悩は絶望とは違うものであって、
苦悩には意味があることを示しています。
それはギリギリの苦悩を体験した彼だからこそ言えることであり、
だからこそ説得力があるのだと思いました。
そのとき私が書いていた博士論文は、私自身の苦悩の体験、
つまり目が見えなくなった後に耳まで聞こえなくなるという、
極限の苦悩の体験を振り返り、それを分析・考察するという
内容のものでした。
そこで彼の公式と出会ったので、これは自分の体験にも
シンクロナイズすることだと感じたのです。
つまり、盲ろうになってしまったとき、私は
「なぜ、こんなことが自分に起きたのか」と悩んでいたのですが、
それを振り返る過程と彼の公式がリンクしてきたのです。
時代背景や直面した状況はまるで違います。
また、生きるか死ぬかというギリギリの状況で体験した
彼の苦悩に比べれば、私が経験した苦悩は
ずっと生ぬるいものだと思います。
しかし、それでもどこかに似ている部分があると感じました。
私は十八歳で盲ろうになりました。
そのときに、
「どうして自分はこんな苦悩を経験しなければならないのか」
と自問しました。
その結果、
「理由はわからないけれど、この苦悩には何か意味があるんだ」
「これは自分の将来を光らせるために必要なものなんだ」
と考えることにしようと決めたのです。
自分がなぜ生きているのかわからないけれど、
自分を生かしている何ものかがいるとすれば、
その何ものかが私にこの苦悩を与えているのだろう。
ならば、私に与えられている苦悩には
何ものかの意図・意志が働いているはずだ、と思ったのです。
そういった自分の状況を振り返りながら論文を書いている過程で
フランクルの公式と出会い、改めて苦悩というものの意味が
整理されたように感じました。
◎働く意義
☆人は自分を成長させるために働く 成長することは生きる喜び
働くということは、人々にとって最も深く貴い行為です。
そしてその働くということには「よき心」がなければ結果が付いてこないのです。
自分がなすべき仕事に真摯に向き合い、謙虚で、他人を思いやり、感謝の気持ちを持ち、
強欲でないといった「よき心」、根底に「世のため人のため」といった「正しい考え方」を
持っていなければ人生や仕事はうまくいかないのです。
☆人は何かに貢献するために働く 尽くすことが生きる喜び
◎ 戦略とは「戦いを略す」
つまり極力戦いをしないことです。
→ おお!! その通りだ
圧倒的な力を持って相手の戦意を喪失させるのが一番カッコがいいが…。
☆ 「日々新たに」一日一日を大切に生きる
内省によって「経験」が「見識」に変わる
「経験はすべての教師である」と言った人がいますが、私はそうは思いません。
経験は最高の教師ではありません。正しく分析できた経験だけがよい教師なのです。
内省によって、自分はどういう道筋を通ったか確認できます。
内省によって「経験」が「見識」に変わるのです。
☆ いつでも「ありがとう」を
人は支えあって生きていく
ただ言葉だけでなく、心からの感謝の気持ちがなければ、相手には伝わりません。
どんな小さなことにも大きな感謝の気持ちをもつこと、それは心の持ちよう、心のありかたです。
→ 私には大きな出来事がありました。
ほんのささいなシーンだったのですがものすごく衝撃を受けたことがあります。
まさにこの項にピッタリな出来事が。
1987年初めての海外出張でアメリカを訪れていました。
ヒューマンパフォーマンスの会議で私は日本の原子力発電所のヒューマンエラーの分析結果を報告し
情報交換すること、新しいヒューマンファクターのシステムの勉強をするのが目的でした。
このヒューマンファクターの先方の課長さんでしたが、一緒に昼食だったか夕食だったか忘れましたが
そのときの給仕に対して「サンキュー」と言われたのですが、私から見て本当に心から感謝の念が出ている
と衝撃を受けたのです。
日本人からでなくアメリカ人の態度から思い知らされるとは思ってもみませんでした。
とてもすがすがしい光景でした。これは見習わなければと心に誓いました。
給仕はもちろん、掃除をしてくれる方々、どんな人にもお世話になっている。
感謝の念を心から伝えよう そういう姿勢を持つようになりました。
「ありがとう」という言葉を身体全体で使えるように大事に使っています。
なかなかいつも十分出来ているとは言えませんが…。
◎「情けは人のためならず」
このことわざは「人に情けをかけるのは、その人のためだけではなく、いずれは巡り巡って自分に返ってくるものであるから、
人には親切にしなくてはならない」という意味です。