川口マーン恵美 講談社+α新書
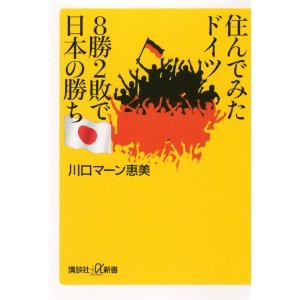
家内が2013年11月に親戚の奥さんと2人でドイツへ旅行してきた。
クリスマスマーケットが目的であったが、ドイツ人はとても素晴らしいとの感想を述べていた。
非常に紳士が多く、重い荷物で困っていたら、さりげなくサポートしてくれたと感謝の気持ちを何度も語った。
そして家内がこの本を借りてきた。
家内の旅行人としての好印象は、残念ながらこの本では感じることはできなかった。
旅行者ではなくずっと住んだからこそ感じることであったろう。
8勝2敗とは、かなり日本びいきというのは否めないが、価値観の相違というものも大きいと思う。
8勝2敗としているが、社会システム的なことがメインとなっているようだった。
項目として勝敗をはっきり表しておらず何が8勝で何が2敗かというのは定かではない。
感覚的に8対2という感じ。
勝っているのは、 「教育制度」、「交通機関の正確さ」、「格差のない社会」、「サービス力(便利な生活)」「電力制度?」などかな。
日本が負けているのは「外交」、「社会人となる就職システム」
ともにドイツが完全に大人の世界で日本は幼稚。これは明らかに勝負付けが済んでいる感じ。
ドイツに住んでいる川口さんが、何で尖閣に行くの!というイントロであった。
結論はハッキリ書いている。
・確かなことは、領土問題というのは実効支配をしたものが勝つということだ。
そして、実効支配にはそれを裏付ける軍事力が必要ということ。
これだけは、いろいろな歴史が証明している。
次はフクシマ、脱原発。
家内が読んだあと回してくれたのはここの記載があったからかも知れない。
ドイツ人の放射能アレルギーは日本人の比ではないということがよくわかった。
ドイツの再生エネルギー買い取り法の問題点をしっかり書いてくれている。
はっきり言って、原子力を全部やめて再生エネルギー主体などとても無理な話だということを
実感として語ってくれている。
ドイツの場合、大企業は免除(10GWhだとほぼ免除)されていることは初めて知った。
風上風力開発も大変コストがかかるようである。
第3章は休暇のお話
病気で有給を使う日本人。
長期休暇バカンスに使うドイツ人
ここは価値観の相違だろうから引き分けではないかと感じた。
ドイツ人の勤務時間の厳格さは、効率的に仕事をする風土を生む
だらだら日本人とは違う。
ただ、教師が勤務時間だけで給食も一緒にしないのは、彼女がかたっているように問題だと思う。
ドイツはレベルの低い仕事は移民にすべて任せている。
日本人は自分たちでやる。
ドイツでは移民の2世、3世が上記システムから落ちこぼれて底辺を形成している。
● 外国人労働者は、日本でもこれからどんどん増えていくことになるだろう。
移民や外国人労働者の導入は国の活力にもなるが、それは双方に長期的な利益があってのことだ。
単に賃金が安いからという近視眼的な理由で、安易に外国人を入れ続けると、いずれ労働市場は破綻する。
また、外国人労働者の不平等感が募り、社会不安をも招く可能性は高い。
ドイツは反面教師になるはずである。
日本にはEUというしがらみがない。もっと独自に、計画的に、冷静に、外国人政策を考えるべきだろう。
⇒後半でTPPには反対に意見を述べることにつながっている。
第4章 ホームレスが岩波新書を読む日本、チャンスは二度だけのドイツ
ドイツというかヨーロッパの格差社会の根本はこういうところかも。
ギナジウム(小5から高三)の卒業試験で大学入学が決まる(一浪はある)というドイツ
ただ試験内容は日本とはゼンゼン違う。
それがこういうことにつながる。
◎ ヨーロッパの外交や交渉を見ていると、双方が少し多めに主張しつつ、怒ったり笑ったりしながら、
だんだん妥協した素振りを見せて、なんとか合意に持っていくということを、皆が実にうまくやる。
しかも見事なのは、合意点に達すれば、その前に激しく攻撃し合っていても、まるで後腐れが
残らないことだ。これも、すべて、長年訓練してきたテクニックの一つなのだろう。
↓ そしてこういう提言に
この際、高校でも、討論し、論文を書き、自分の意見をフルにアピールする訓練をしたほうがいい。
悲しいかな、それは必ずしも日本人の美意識と一致はしないのだが、とは言え将来、私たちの控えめな、
和を基調とした文化が世界を制覇するようになるとも思えない。
そうであるならば、こちらのほうが国際社会で一般的となってしまっているルールに合わせていくしか
ないだろう。
◎ 親の過保護をやめよ説く
日本の教育の問題は、子供をうまく独立させてやれないことだと思う。
遅くとも高校の時点で、子供を大人にしてやるべきだ。
保護や指導ばかりでなく、責任の取り方を教え、大人として扱ってやれば、大学生はもう少し毅然とし、
日本の将来は明るくなるのではないかと思う。
今の日本人には、能力がないのではなく、ハングリー精神がないのだ!! とも一括。
第5章 不便を愛するドイツ、サービス大国の日本
この章は面白く読んだ。
それほど切迫感がないせいかも知れない。
ドイツの人は不便に不便をあまり感じていない。
そこへ日本人が済むとえらく不便、不満を感じる。
あたりまえが違うだけなのである。
子供の教育でもそうだったが、日本はすべてにおいて「過保護」なのかも知れないと
思った。
最後にEUにおけるドイツの苦悩から日本はTPPには加入すべきではないと説く。
この点は非常に勉強になった初めての視点であった。
農産物だけ考えていたのだが、そうではないということがよくわかった。
ユーロ導入は東ドイツ統合の時にフランスのミッテラン大統領から強すぎるマルクを殺す条件として
押し付けられたものと初めて知った。
● EUの手綱を握る主要人物は皆、財政破綻の南欧の面々だ。
彼らにとってヨーロッパを救うということは、すなわち自分たちを救うこと。
そのためには、ドイツにお金を出させようというところでは意見は一致する。
そして、彼らが一丸となれば、ドイツに反論のチャンスはほとんどない。
ドイツのEU内での形成は、恒常的に悪い。
TPPに参加すれば、日本はまさにドイツと同じ立場に追いやられそうに思えてならない。
ドイツも日本も、「永遠の加害者」で、たくさんお金を出しても、大して感謝されていないところも
とてもよく似ている。
しかし、それでも、「きっと大丈夫」と、日本人は思っている。
EU内で苦境にたたされているドイツ人が大丈夫と思っているように、なんとなく大丈夫と思ってしまっているのだ。
だが、私には、日本もドイツも少しも大丈夫に見えない。
(中略)
いまEUは、経済力やメンタリティーの違う国々が統合するとどうなるかという例を、如実に示してくれている。
そして、抜け出したくても、EUには脱退する決まりも、脱退させる決まりも、しかとは定められていない。
日本は、やめることのできない共同体に入ってはいけないのではないか。
今こそ日本は、ヨーロッパでのドイツの動きを注視しておいたほうがいい。
今後、アジアで日本がどう行動すれば良いか、そのヒントが必ず見えてくるはずだ。
以 上