竹内 均/[著] 講談社文庫
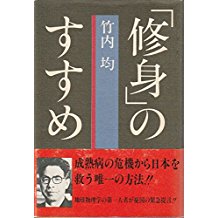
科学雑誌ニュートンの編集長だった東大の竹内先生が書いているので興味を持って
図書館で取り寄せて読んでみた。
理科系の人が書くこういう本は思考回路がよく似ているのだろうか
非常に読みやすく納得のいくものであった。
自然科学も人間としての人生の生き方も法則があるとの論調。
五聖人 モーセ;ユダヤ教、孔子;儒教、釈尊(ブッタ);仏教、キリスト;キリスト教、マホメット;イスラム教
これに共通する人間の黄金律としての教え
◎ 何ごとでも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ
(キリスト)
他人を害してはならぬ。……殺してはならぬ。
すべてのものは暴力におびえている。すべての「生き物」にとって生命がいとおしい。
己が身と引き比べて、殺してはならぬ。殺さしめてはならぬ。
(凡人にも理解できる言い方で、黄金律を実行すべきその理由が挙げられている(釈尊))
己の欲せざるところを人にほどこすことなかれ (孔子)
(この本のめざすところ)
倫理や道徳の基本はこのことに尽きる。
しかし、凡人の私たちにとって、人々からしてほしいことをそのまま人々にしてあげることは
大変に困難なことである。
その一方で私たちは、仏教で言う五戒あるいはモーセの十戒のうちいくつかを守って、
他人を殺したり、邪淫にふけったり、人のものを盗んだりはしない程度の自信は持ちうる。
しかし五戒のうちの妄語および飲酒は、これを守りきれないでいる人々がかなり多い。
つまり私たちは、黄金律を守りきれるほど善人ではないけれども、
殺生、邪淫および倫盗の戒律を守りきれないほどの悪人でもない。
つまり、私たちは中くらいの偉さの人間が、どういう基本方針に従って人生を生きたらよいか
考えるのが、この本の目的である。
☆☆ 福沢諭吉の人生訓
人生において、一番楽しく立派なことは、一生涯を貫く仕事があること。 ⇒これは響いた
人生において、一番さびしいことは、することがないこと。
人生において、一番みじめなことは、教養がないこと。
人生において、一番醜いことは、他人の生活をうらやむこと。
人生において、一番貴いことは、奉仕して恩にきせぬこと。
人生において、一番美しいことは、すべてのものに愛情を持つこと。
人生において、一番悲しいことは、うそをつくこと。
人生において、一番すばらしいことは、感謝の念を忘れぬこと。
⇒ いやーお見事というほかない。
竹内先生の主張もこの人生訓とほぼ同じだ。
「中庸」だけが違うかな
竹内さんの修身のすすめは
勤倹・貯蓄、正直・中庸、感謝・報恩、修身・斉家、外柔・内剛 である。
→勤勉・倹約を勤倹と言っておられるが、これは省略しないほうがいいと思う。
私には倹約が耳の痛い言葉であるが、年金生活者となった今、身に染みている。
仕事についてはニーチェのこの言葉は知らなかった。
このことを知って嬉しかった。ありがたい。
☆仕事と遊び
哲学者ニーチェ(1844-1900)は、人間の精神を3つの時代にわけている。
ラクダの時代
ライオンの時代
小児の時代
ラクダの時代は知識やデータの習得の時代であり、人々は勤勉を必要とする。
ライオンの時代は創造の時代であり、人々は孤独な勇気を必要とする。
小児の時代は勇気を超越した無邪気さと自由の時代であり、
仏教でいう菩薩のように、利己を超越して他人を利し、また救済する。
ラクダの時代を勤勉すなわち仕事の時代とすれば、
小児の時代は遊びの時代と言える。
つまりニーチェは、仕事を遊びに化することを、人間の精神構造の発達の最高段階としている。
⇒納得である。竹内さんは例として大橋巨泉を挙げているが若干違和感を感じた。
みんなが認める遊びではなく、本人は仕事を遊び感覚でできているようなことではないかと。
巨泉は遊びを仕事にしうただけであるのではないか…。
その違和感に対してちゃんとした解説を書いてくれている。
仕事か遊びかは心のもちようによって決まる。
したがって、仕事を遊びに化するという人生の理想に達する方法は、
その仕事を遊びと感じられるまで、仕事に打ち込んでみることである。
昔から名人上手と呼ばれてきた人たちは、みなこの道をたどって、
仕事が遊びと一致する人生の理想に達したのである。
ニーチェがラクダの時代と呼んだ勤勉の時代がそれである。
〇真の専門家は複雑な問題を単純化する → これもよかった
ある人がアインシュタインを評して、
「素人が複雑に考えている問題を単純化し、
素人が単純だと考えている問題をもう一度吟味しなおすのが
天才の仕事である」
⇒ これはヒューマンファクターの大御所で尊敬している黒田勲先生(故人)の大事にしていた言葉で
私がその出典を井上ひさしだと見つけてお教えしたら記念講演の際にお礼を言っていただいた
思い出のものと全く同じである。
・ むつかしいことをやさしく
・ やさしいことをふかく
・ ふかいことをおもしろく
・ いつも人間を愛しつつ
最後の言葉は黒田先生が付け加えたもの
3つめの面白くはニーチェの幼児の時代に当たりますね。
まさにニーチェとアインシュタインを併せた言葉で、本当にいいと思います。
第4章 正直・中庸のすすめ
⇒正直はわかるが、中庸というのがいまひとつピンとこなかった。
◎どうでもいいことについては中庸の道を選ぶ
→この言葉がわかりやすかったかな
この解説はデカルトを例にとり
「これはやってもいいことだろうか。それともいけないことなのだろうか」
といちいち考えるのは面倒である。
こういう場合には、もっとも常識的でもっとも穏健な意見に従うのが、
頭脳の浪費を避けるもっともよい方法である。
つまり、
自分の人生でやりたいことに全力を集中し、
それ以外のことでは、中庸の生き方をして手を抜こうという考えである。
こうなると、中庸はまことに積極的な徳目ということになる。
ただし、この場合に、自分自身のやり遂げたい人生の大目標を持っていることが前提条件である。」
●大都会の「不親切さ」を好んだデカルト
デカルトがこの世から隠れる場所としてアムステルダムのような大都会を選んだひとつの理由は、
ここではすべての便利なものがたやすく手に入るからである。
もう一つの理由は、田舎へ行けば悩まされるに違いない隣人の「親切」が大都会にはないことである。
地球物理学者の寺田寅彦も、彼の随筆の中で、これと同様のことを書いている。
●執着からの解放と中庸
私たちはとかく自分を中心として世の中を考え、
自分の意見が中庸で、また最善のものであると思いがちである。
しかし、それが世の中の穏健でまた常識的な意見と食い違っている場合には、
中庸で最良なのが彼らの意見であり、私たちのそれが極端な意見であることが多い。
◎人は人、われはわれ、されど仲良し
→ 武者小路実篤の言葉である。
それぞれの価値観を尊重するこの姿勢はまさに私の目指しているところである。
一神教でない日本人のよさであると筆者は訴えている。
百花繚乱という言葉がある。
ひとつの花だけに覆われた花園よりも、百の花がそれぞれの美しさに輝く花園をより美しいと見る見方である。
価値観の多様化するこれからの世界では、生半可な一神教や愛国心よりも
こういう見方がその威力をより発揮するであろう。
一神教の信仰や愛国心にこういうブレーキをかけるという点まで、
中庸の精神うぃお押し広げて考えたい、と私は思っている。
そして、この本の中でも、この点を繰り返し強調するつもりである。
こういう中庸の精神がなければ、神や愛国の名を借りた殺人が、地上から永久に消え去るときがないからである。
→ まさに最近はこの懸念がますます高まっていて危うい世界情勢でる。
第5章 感謝・報恩のすすめ
→この章は比較的わかりやすい
感謝はリーダー信条で自分が付け加えたものである。
◎思いわずらいが感謝を生む
苦労や思いわずらいを持つことはよいことである。
それによって初めて、人は傲慢にならず、他人への心からの同情をもつことができる。
また、自分が現在こいうして生きていられることに、素直に感謝できるようになる。
→まさに、その通りである。
●人気取りだけを考えた政治家
→このあたりは政治に関して書いていて、かなり筆者の痛烈な批判精神がでており若干違和感があるところであった。
ローマ帝国が滅びた理由
・ローマ市民たちは、無料のパンとサーカスの配給を受け、繁栄と福祉を楽しんだ。
しかし「ただほど高いものはない」このときすでに、ローマ人やローマ社会の腐敗や、ローマ帝国の没落が
確実に始まっていた。
→勤勉に働くことがなければ国は亡びるのである
現在の人気取りの日本政治は危うさが漂っている。「
☆奉仕ではなく報恩
感謝から一歩進んで、われわれは受けた恩に対して報いるところがなければならない。
これを奉仕ということばで表現しようとして、私はそれにやや思い上がったニュアンスがあるのに気づいた。
そのニュアンスをなくすために、私は以下で奉仕の代わりに仏教用語である報恩を使うことにする。
→報恩はサントリーの佐治さんの話で親がやっていたことを知ったので違和感はなかった。
その鳥居さんの報恩がこの本の中でも出てくるのである。
〇 イギリスの上流階級が実行した報恩
報恩はノブレス・オブリッジと一致する。
かつての健全だったイギリスの上流階級が何をしたか。
「彼らは全世界に植民地を作った」といった皮肉なことは言わないで欲しい。
今は彼らの健全だった面だけ注目するときだからである。
彼らは科学や技術の分野を開拓し、哲学、文学、芸術にいそしみ、
探検や考古学的発掘をし、美術館や博物館を作り、
また各種のボランティア活動をした。
いずれにせよこれらは、今日明日のパンのためとならず、
そういう意味ではまったく役にたたないものある。
私は常に「役にたたないものに栄光あれ」と言い続けてきた。
こういう意味で役に立たないことをするために人間は生まれてきたのであり、
またあくせくと働いていささかの貯を蓄えるのもそのためである。
自分自身や一家が食えないうちは報恩を口にすべきでないなどと言ったのは、
実は報恩にこういう特別な意味を含めたかったからである。
◎ 鳥井信治郎の報恩と中谷宇吉郎
匿名で学費の提供を続け、人工雪を作った中谷さん育てたお話が書かれている。
これは知らなかった。
「私は今は金も相当できて、みなさんにすこしくらいのお手伝いうもできるようになったが。
もとは非常に貧乏だった。しかしこの財産は、自分で働いてもうけたものとは思わない。
これは天からさずかったものと思っている。
それで君もあの学費は、天からさずかったと思っていたらいい。
返済の意思があったら、天へお返しなさい」
→いいですねー。これこそまさにCSRの精神ではないのでしょうか?
神でなく、天という言葉が私も好きです。
今の企業のCSRは匿名性がないですからね。
第6章 修身・斉家のすすめ
〇「修身」の意味
前章までにわれわれが実行してよい徳目として
勤倹・貯蓄、正直・中庸および感謝・報恩があることを述べた。
これらはいずれも過去の聖人や賢人が述べた徳目であり、
しかもその中から、できるだけ宗教的色彩の薄い、また凡人でも実行できるものを選んだ。
これらの徳目の実行を修身と呼ぶこととする。
〇外柔・内剛
外見は優しそうに見えるが、心はしっかりしている
現代風に言えば
外にはソフト、内にはハード
私は
「自分には厳しく、他人にはゆるやかに」と解釈している。
自分自身が身を修め、他人に模範を垂れるというようでなければならない。
他人には修身を強制し、自分は実行しないというのでは話にならない。
これはノブレス・オブリッジにも通じるものである。
●自分の身を修めることがすべての基本
「大学」には
明徳を天下に明らかにせんと欲するものは、まずその国を治む。
その国を治めんと欲するものは、まずその家を斉(ととの)う。
その家を斉えんと欲するものは、まずその身を修む」
とある。
〇パスツールと彼の妹および父の間に取り交わされた手紙
→家を斉えるとは家族内で価値観や喜びや悲しみをともにすること
その例を最近学者のパスツール家で紹介している。
●嫁と姑
→ この問題を取り上げている。斉家の立場からは嫁のほうが価値観を合せることにより努めるべきとの
主張があった。まあ私よりも二回りも年上の方ですからそうだろうなという感じで読んだ。
核家族化となり時代が変わってきていて昔よりも斉家は非常に難しくなってきている。
争いが妥協不可能な場合には、そもそも結婚をしないほうが良かったのである。
結婚のところで、結婚の必要条件は両性の合意であり、十分条件が価値観や喜びおよび悲しみについての
家どうしの合意である。
今ここで問題とする嫁と姑の争いは、こういう基本的な問題についてではなく、
よりささいな問題についてのものであるとする。
ここで、先に中庸のところで述べたことを思い出してほしい。
それぞれの人間には、一生の間にどうしてもやり遂げたいことや、
またどうしても譲れない問題がある。
しかし、それ以外のことでは、中庸の美徳に従って、
世間でごくふつうにやられているところに従うのがよいと述べた。
この生き方を、ここでも実行するのである。
第7章 外柔・内剛のすすめ
これからの時代は価値観の多様化する時代である。
そういう時代に、自分の価値観や原理や独創性だけを主張していたのでは、
世の中はうまくいかない。
こういう時代には、外柔・内剛を中庸と似たひとつの徳目とすべきである。
すなわち、自分の価値観や原理や独創性をかたく保つけれども、
これを他人には強制せず、また他人の価値観や原理や独創性を尊重することが望ましい。
「君子は和して同ぜず」というその「和して同ぜず」が、
すなわち外柔・内剛である。
武者小路実篤のいう「人は人、われはわれ、されどなかよし」もまた外柔・内剛である。
〇四季のめぐり
日本の季節、天気の変化のテンポは速く、人間のきまぐれさを連想させるほどである。
天気という呼び名はここからきている。
→ エッツ、そうなんだ。ゼンゼン知らなかった。
〇温和な自然
日本の自然が温和なのは、豊かな日光と水に恵まれているためである。
それともう一つ、日本の海岸線の長さは、世界の陸地を取り巻く海岸線のそれの7%をも
占めている。
日本の面積が地球の表面積の1400分の一にすぎないことを考えると、
これは異例とも言える海岸線の長さである。
この海岸線の長さが、日本の自然を海洋的で温和なものとしている。
→ エッツ、そうなんだ。これまた驚いた事実である
〇一過性の天災
→なかなか地震のことが出てこないと思っていたら出てきた。
一過性があきらめのよさにつながるとはなるほどであった。
日本はアジア大陸の成長のフロントにあり、さればこそここで地震や火山活動が活発である。
日本を特徴づける天災は、地震と台風である。
これらがいずれも一過性の天災であることが注目される。
〇一過性の天災が日本人のあきらめのよさや身軽さを作る
〇幕の内弁当の美学(栄久庵憲 ごま書房)
1 美しい造形
2 欲深い機能
3 創造を誘う装置
4 確かな原型
5 多様の統一
6 摂取不捨
7 楽しみの開発
8 臨機応変
9 むだのない文化
10 親切の極意
この10の条件をひとつの言葉で表現するのは難しいけれど、
これまでに繰り返し述べてきた外柔・内剛がそのひとつの言葉の候補者であるとだけは言える。
外柔・内剛は摂取不捨によってすべてのものを欲深く取り入れ、臨機応変とサービス精神によって、
多様を統一し新しい楽しみを作りだそうとする。これが外柔的特徴である。
しかし、そこには美意識を最優先し、むだのないものを切り捨て、だれもが味わえるようになるまで
問題を単純化し、そこに確かな原型を作り出そうとする一種の価値観が働いている。
これが内剛的特徴である。
日本人や日本文化のこういう特徴が夏の高温多湿、ミニュチュア的多様性、四季のめぐり、
温和および一過性の天災といった日本の自然に基因することを、ここでもう一度強調しておきたい。
まとめ
〇まず勤勉、正直、感謝を実行せよ
〇次に斉家、中庸、外柔・内剛を実行せよ
〇己の欲するところに従ってのりをこえず
外柔・内剛が行きつくところまで行けば、それは融通無碍(むげ)となり、また孔子の言った
「己の欲するところに従ってのりをこえず」ということにもなろう。
ある意味ではそれは、人間が幼児のような素直さに立ち戻ったことをも意味する。
しかし、これは聖人君子の達する境地であって、生半可な凡人がそれを口にすべきものではない。
われわれはまず地道に、勤勉、正直、感謝から始めるべきである。
〇修身を実行すれば必ずよい結果が得られる
私自身はまだ、勤勉、正直、感謝を息せききって実行している凡人である。
しかし、長い人生を通じて勤勉、正直、感謝を実行し、また自然科学者として生きてきた私にも、
それなりに理解できたことがただ一つある。
それは勤勉、正直、感謝を実行すれば必ずよい結果が得られ、この実行に欠ける場合には、
それなりに必ず悪い結果が得られたということである。
それは、まるで自然科学における自然法則のように狂いのない原因と結果であった。
釈尊の言った「因縁」はここを指すのであろう、としばしが考えたほどである。
〇栄えるものには栄えるだけの原因がある
一自然科学者にすぎない私が、この「修身のすすめ」を書いた理由もここにある。
人と生まれ、自分自身や一家や国の平和や幸福を望まないものはないはずである。
それを得る方法はただひとつしかない。
それは勤勉、正直、感謝から始まる修身の実行である。
私自身の経験、これまでの人生で私の見てきた個人、家、会社などの団体、社会さらには世界の動き、
これまでに私の読んだ古今東西の国々の歴史にかんがみて、私はこのことだけは確信をもっていうことができる。
栄えるものには栄えるだけの原因があえり、滅びるものには滅びるだけの原因がある。
その原因はただ一つ、修身を実行するか否かだけである。
〇修身の実行と自然科学における実験
何よりもまず小さい勤勉、正直、感謝を実行してみることである。
私にだまされたと思って、それを実行してみて欲しい。
必ずよい結果が得られるはずである。
「竹内の言っていることは正しいらしい」という実感が得られるはずである。
そういう実感が得られたら、もう一度、さらにもう一度、小さい修身を実行してみてほしい。
またよい結果が得られるはずである。
ここで言っていることは自然科学における実験であり、
こういう実験の積み重ねによって、結局は相対性理論や量子力学の原理的な正しさが確認された。
それとまったく同じことが、修身にもあてはまるのである。
この意味で修身は経験科学であり、
紙の存在や宗教とは一応無関係なものである。
一部の宗教家からは非難されるかも知れないけれども、
これが一人の地球科学者である私からみた修身である。
こういう意味の修身をみなさんにおすすめしたくて、
私はこの「修身のすすめ」を書いたというわけである。
→勤勉、正直、感謝の実行をこれでもかというほど力を込めて何回も書かれている。
あとがき
文庫本になった喜びを表現され、そして追記をいくつかされている。
私の好きな「自己実現」ということばも出てきた。
修身を実行したものは栄え、実行しなかったものは衰えると述べた。
これが立身出世を思わせて嫌だという人のために、これを現代風に言い換えてみよう。
近頃よく「自己実現が人生の理想である」といった言葉を目にし耳にするようになった。
私の理解するところでは、自己実現は、
「自分の好きなことをやりながら、その結果が他人によって高く評価される」
ことを意味する。
これが自己実現の定義だとすれば、それが人生の理想であることは、
個人主義的傾向の強い最近の若者には特によく理解されるはずである。
ところで繰り返し述べた修身(勤勉・正直・感謝)はこのような自己実現のための
必要にして十分な条件である。
勤勉が必須条件であり、正直および感謝が十分条件である。
仮に勤勉であっても、正直および感謝を怠る人はだれからも相手にされない。
したがって彼の仕事が高く評価されることはないからである。