楠瀬 良/著 中公新書ラクレ
【内容紹介】
「今日はできればレースに出たくないなあ」「絶好調!誰にも負ける気がしない」など、
馬の気持ちがわかったら−。競走馬の心理と行動に関する研究の成果を余すところなく紹介する。
武豊との対談も収録。
【著者紹介】
1951年生まれ。東京大学大学院、群馬大学大学院を経て、日本中央競馬会(JRA)入会。
日本装削蹄協会特別参与。農学博士・獣医師。著書に「サラブレッドは空も飛ぶ」など。
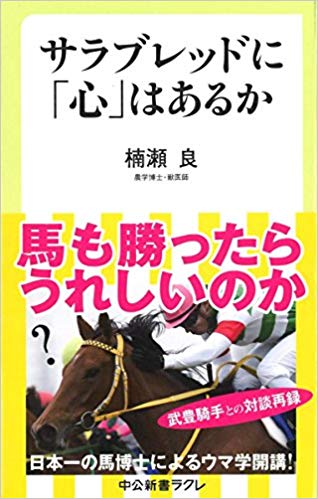
タイトルに対する明確な答えは書いていなかった。
でも、いろいろなことを知ることができた。
なかなか読みやすい本。
耳をピンと立てているのはいい気合、ダメなのは耳を折っている時、これは恐怖心
人間はできないが、セルロースを馬や牛は微生物の助けを借りて消化しているので草だけで筋肉ができる。
毛づやがいいのは厩舎がよく手をかけている証拠
群れの中での社会的順位(どれが偉そうにしているか)は
「勢い」と「しつこさ」 で順位いこだわりが強い馬が上になるようだ(笑)
こんなまとめを最後にしている。
動物で見られた現象をそのまま人間社会に当てはめるのは、軽率であり、現に慎むべきだとは考えます。
しかし、「勢い」=「モチベーションの高さ」と「しつこさ」=「志の持続」は人間の社会でも自らを
高めるためにはきっと不可欠なことだといえるでしょう。
馬の妊娠期間は11か月で人間より長い
(ゾウ20か月、キリン14か月)
ゴール後、騎手が首筋を愛撫してねぎらうのはいいこと。
苦しいレースを走りぬき、力を出し切った馬はゴールを過ぎればハミから解放され、
騎手から愛撫を受ける。これらのことは馬にとって何よりの報酬となり、次への競馬とつながっていきます。
牝馬の方が牡馬よりも難しいらしい。
人の指示に従わない場合、牡馬ならビシッと懲戒すると素直に従うようになるのに、
牝馬の場合は叱るとむしろどんどん悪くなってしまうケースが多いそうです。
こうした差は牝馬の方が恐怖心を持ちやすいことに原因があるのかもしれません。
初めてのジャパンカップのときに欧米の馬は非常に落ち着いていると競馬関係者は驚いたそうである。
この事実は初めて知った。
筆者は訓練により初めての刺激に動じないようにいろいろ工夫と手間をかけることにより
落ち着いた馬を育てることができると実証している。
アメリカの馬は疲れて止まるが、日本の馬は柵で止まると言われているが
牧場の広さは1haでは少ないが2haあれば十分。
事故防止のために正方形が望ましい。
馬房の敷物は稲ワラ、麦ワラが最適。
若ゴマへのブレーキングの教育は毎日行うことが効果的。
→やはり毎日練習するということは大事だということでしょう。
馬の比重は0.95と水より軽いため、プールに入っても沈むことはありません。
また多くの馬は脚が水底に届かなくなれば自然に泳ぎ出します。
水中では水の抵抗を受けるため、前進するには強い推進力が必要となります。
馬の場合、主に後脚が水を蹴ることでその推進力が生み出されます。
この動きは同時に後躯の筋力強化につながります。
ただし水中と陸上では四肢の動きが異なるため、陸上で走行するために必要な
筋力すべてが鍛えられるわけではありません。
そこで考案されたのがウォーター・トレッドミルと呼ばれる装置です。
いわば動く歩道(トレッドミル)を水に沈めたような装置で、馬は胸元まで水に
つかり、床の動きに逆行して進みます。水の浮力で体重が軽くなり脚部への負担
は軽減されますが、四肢を床につけ陸上とほぼ同じ動作をするため、鍛えられる
筋肉は陸上での運動とほぼ同様になると推測されます。