(長寿、イノベーション、経済成長)
吉川 洋 中公新書
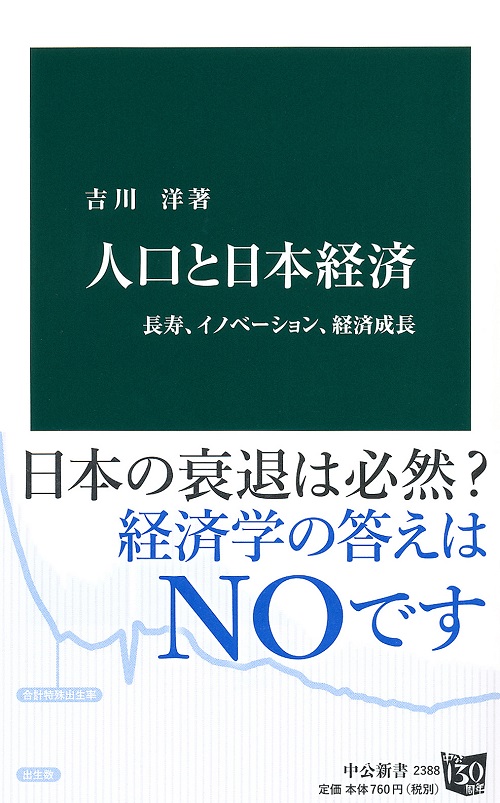
図書館の新刊から見つけて読んでみた。
なかなかよかったと思う。
第1章 経済学は人口をいかに考えてきたか
ケインズは知っていたが「ロバート・マルサス」は知らなかった。
マルサスは「人口論」を記している。
マルサスの人口の原理 は納得である。
原則1 人が生きていくためには食糧が必要不可欠
原則2 男女両性の性欲は今日同様いつまでも大きく変わることはない
食糧があるところで人口は増えるが
人口は抑制されない限り「等比数列的」に増えるのに対し、
食糧の方は「等差数列的」にう増えるに過ぎない。
倍々ゲームの人口に対して1,2,3の食糧 納得である。
ケインズは、若きマルサスが説いた過剰な人口が生み出す悲惨さを
「Pの悪魔」となずけ、一方で老マルサスが指摘した失業の問題を「Uの悪魔」と呼んだ。
P:Population
U;Un-employment
・スウェーデンの人口論
クヌート・ヴィクセル(1851〜1926)
「最適な人口」
それ以上に人口が増えると平均的な福祉の水準が、もはや上がるのではなく逆に下がってしまう。
つまり、最適な人口とは、一人当たりの平均的な福祉の水準を最大にするような人口である。
・生物学者によると、体重60kg程度の「雑食大型動物」の適正密度は、
1平方キロメートル当たり1.5頭だそうだ。
現在もアフリカ等で自然に近い狩猟生活をする人々の人口密度は
1平方キロメートル当たり3人程度だそうだが、
地球全体の平均人口密度は1平方キロメートル当たり44人になるのだから、
「適正密度」のなんと30倍、明らかに人口は過剰なのだ。
(長谷川[2015])
●AI,ITは人間の仕事を奪うか? P85
⇒ここは若干私は見解が異なるが志向方向は正しいと思う
先進国の経済成長は人口の成長というよりも、
主として「1人当たり」GDPの成長によってもたらされる。
労働生産性の上昇は、労働者の頑張り、やる気、体力ではなく、
広い意味での「技術進歩」つまり「イノベーション」、資本蓄積、産業構造の変化などに
よってもたらされる。
…… 略
機械化によってある職場で特定の仕事にかかわる雇用が失われるということと、
人間の労働に対する需要が根こそぎ失われるということは、まったく別のことだ。
多くの人は具体的なイメージを伴いやすいということもあり、
昔から人のやってきた仕事が機械に置き換えられ、雇用が失われることに恐怖心を持ちやすい。
しかし、歴史を振り返ってみると、話はむしろ逆なのである。
つまり、経済全体で労働に対する需要が旺盛で人手が足りなくなり、賃金が高くなる結果、
ある種の仕事について、「省力」のため機械が導入されてきたのである。
そもそも18世紀イギリスで、ワットなどによって蒸気機関の発明・改良がなされたのも、
賃金の上昇に対するリアクションだった。
AI,ITは人間の「頭脳」を代替する点で旧来の機械とは違う。
しかし、ブルドーザーがそれまでの人間の「筋力」に頼るしかなかった仕事を代替したのと
本質的にどこが異なるだろうか。
もう一つ忘れてならないことは、AI,ITによって作りだされるモノやサービスを消費するのは
人間ということだ。消費する人間がそうしたモノやサービスを購買する。
当たり前のことだがモノやサービスを買う人は、購買を可能にするだけの所得を得ていなければならない。
すでに述べたとおり、歴史を振り返ると、伝統的に人間がやってきた仕事の多くは機械によって
代替されてきた。しかし、その結果、人間は「お払い箱」になったのではなく、
むしろ労働生産性が上がり、賃金は上昇してきた。
つまり人間は機械のおかげで豊かになってきたのである。
⇒最後の部分は異論はない。
ただAI,ITはこれまでと違う。
落ちこぼれる人間が増えてしまい(人間ができる仕事が限られてしまう)、それが社会を暗くしないか
不安がある。
芸術、スポーツ、娯楽 このような分野でのサービス業が増えていくことになるのだろうか。
会計士の仕事がAIに奪われるというような記事も最近目にして、ほんとうだろうか?と思うが
もしそうなれば資格を有するようなインテリジェンスの高い仕事もなくなってしまうのだろうか。
第3章 長寿という果実
ジニ係数を寿命にも当てはめて算出しているところが面白かった。
そしてその推移を見ながら、以下の結語となっている。
戦前の日本も一部の人が言うほど「悪い」社会ではなかった。
そういう人がいる。
なるほど、一つの社会がすべての意味で悪かったというようなことは稀であろう。
探せばどこかよいところが見つかるに違いない。
しかし、人間社会の総決算ともいえる平均寿命、そして寿命のジニ係数の推移を見ると
戦前の日本は大問題ありの社会であったと言わざるを得ない。
(井崎の理解→ジニ係数が高い:富の財閥への集中 寿命のジニ係数も高い:寿命の不公平)
戦前とは対照的に、戦後は一転して寿命が急速に延び、日本は世界の最長寿国になった。
これは、戦後日本の最大の成果なのである。
第4賞 人間にとって経済とは何か
この章が筆者としては一番書きたい思いがつまっているように感じた。
また私自身、知らないことも多く勉強になった。
☆需要の飽和 ; ロジスティック曲線
このカーブは知っていた。
どんな需要もほぼこのカーブに従う。
だが、飽和しない需要がある!
奢侈である。
これが経済のドライバーなのだ! という説はあながちおかしくはない。
なるほどと膝を打った。
節約、節約では経済成長はない。
うーん。
だが、果たしてそれでいいのかという難しいテーマだ。
古代エジプトのピラミッド、中世の教会は、いくらつくっても、それがもたらす便益が減少することはない。
したがって、需要は飽和しない。
しかし、現代の先進国の経済では、既存のモノやサービスに対する需要は必ず飽和する。
こうして経済は慢性的に需要不足に悩まされることになる。
☆☆ プロダクト・イノベーション
そこで必要となるのが
新しいモノやサービスの誕生 なのである。
実際、今日、日本も含めて世界の自動車産業をけん引しているのは、
ハイブリッドカー、電気自動車、スマートカーなど新しいタイプの自動車だ。
そもそも日本の自動車産業が世界のリーダーとして自らを確立したのは、1970年代に
資源節約、燃費効率といったことがグローバルな課題となったからだ。
そうした課題に応えるイノベーションを通して日本の自動車産業は世界のフロントランナー
となったのである。
事情は今も変わらない。
新しいタイプの車を生み出すプロダクト・イノベーションがなく、
旧来のガソリン車だけだったとしたら、需要は「人口」によって規定されるに違いない。
そこではロバートソン・ケインズが強調した「需要の飽和」が必ず貫徹するであろう。
ここでいう需要は車の台数ではなく、1台あたりの価格を台数に乗じた需要総額を
問題としていることに注意しなければならない。
時代の要請にこたえる新しい自動車が新たな成長を生み出しているのである。
それは人口と1対1に対応するものではない。
この後、身近な例で紙おむつを挙げている 大人用が子供用を上回ったとのこと。
→ しかしこれは寿命増による超高齢化の進展で新しい需要ができただけで
何もプロダクト・イノベーションと言えるものではないのではないかと感じた
● ミルのゼロ成長論
19世紀 ジョン・スチュアート・ミル 「自由論」
ミルの理想 (「経済学原理」)
人間にとって最善の状態は、
誰も貧しくなく、さらに誰も豊かになろうと思わず、
豊かになろうとする他人の努力により誰も脅威を感じることのないうような状態である。
人口が増えると必然的に「人口密度」が高くなってしまう。
これに続けてミルの言うところは、情報化社会の中で絶えずケータイ、メールを通して
他人と接触し続けている現代人に反省を迫るものだ。
・人間にとって、いつも他の人間と接しているような社会は、理想の社会ではない。
孤独、つまり時としてたった一人になることは、
人間が自らの考えや精神を高めるために不可欠なものである。
● 世界一貧しい大統領 ウルグアイのホセ・ムヒカの2012年国連演説
貧乏な人とは、少ししかモノを持っていない人ではなく、
無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことです。
人間の歴史は、経済に背をむけるロマン主義的な思潮と、
それを批判する「合理主義」の相克の歴史ということすらできる。
● 人間の動物的寿命は42歳
「ゾウの時間、ネズミの時間」 本川達夫教授 によると
ネズミでもゾウでも人間でも動物はすべての心臓が15億回鼓動すると死ぬ。
ただし心臓の鼓動1拍に要する時間は、体重が大きい動物ほど長い。
体重3tのゾウは、体重30gのハツカネズミに比べると、
1拍に要する時間が18倍長い。
ハツカネズミの寿命 2〜3年
ゾウの寿命 70年
人間は15億回打つ年齢は42歳
これが生物学的に見たときに「自然な」人間の平均寿命だとすれば、
先進国の平均寿命はその2倍の長さに近づきつつある。
これまで抜き書きして抜け落ちている重大な部分は
文明が進化すると、出生率が落ち、いずれは滅びる という過去の歴史。
まとめとして、筆者は経済成長を否定しない。
豊かな生活は享受すべきとの立場。
そのために今後もプロダクト・イノベーションが必須だと説く。