C.サレンバーガー [著] 十亀 洋 [訳]
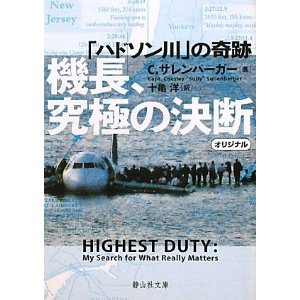
ハドソン川への緊急着水、全員生還のニュースは素晴らしいものだった。
その立役者であるサレンバーガー機長の書下ろしである。
ヒューマンファクター研究知人の札幌のSさんから読後メモが送られてきてこの本のことを知った。
この6月の電中研のヒューマンファクターセミナーで約2年ぶりにお会いするので
この本は読んでおこうと家内に借りてきてもらった。
とても素晴らしい内容だった。
いい本を紹介してもらえたととてもうれしい気分である。
当日の事故機の状況を時系列的に説明する中に、機長のこれまでの人生について織り込んで
それがとても自然に溶け込み説得力を持って読者に訴求している。
とにかく5歳の時にパイロットになることを決めていてそのとおりの人生を送っているところがすごい。
唯一、奨学金制度で士官学校を受験したときは危なかった。
海軍兵学校の推薦が出てしまい行きそうになったところ、推薦者の辞退が出て希望どおり空軍士官学校に行くことができた。
これもサレンバーガーさんの願いが通じて神様がそのようにしてくれたのではないだろうか?
家族とのことはビックリした。
今の奥さんとは再婚。子供ができず、養子で2人の娘をもらった。
生まれたばかりの赤ちゃんをすぐに引き取る養子なんてビックリした。
パイロットの仕事は家族との時間が非常に少ない悩みというのは言われてみればその通りなのだが
知らないことであった。
自分の父親は家族を優先、そして家は自分たちで手造りで作ったという思い出話にも驚かされた。
アメリカのパイロットの処遇は現在はあまり恵まれたものではないことがよくわかった。
年金が破たんしていることは何度もでてきた。
勤務地の空港までは空席待ちのエコノミーで搭乗してゆく。
食事もサンドウィッチだけ済ませることもあり、ファーストクラスのビフテキがうらやましく感じながら
操縦していることを知り、なかなか大変なんだなーと。
そのうえコスト低減のあおりで機長の威厳も低下している。
この点はとても心配しておられた。
安全よりも定時運行
「機長権限」が航空業界の安全を保ってきた
引退間際の機長のコラム
パイロットになった頃を回想し、パイロットを含めたすべての従業員が規則に従う
かどうかで判断される今の状況を比較していた。
「判断力を買われて雇われたはずなのに、今では規則を守るかどうかで評価される」
と彼は書いている。
多くの点で、航空会社の仕事が標準化されてきたことは良いことだ。
適切な運転手順が確立され、パイロットはそれに従わねばならない。
チェックリストを無視するようなカウボーイ型の機長はもういなくなった。
しかし規則遵守だけでは不十分だろうと思う。
アル・スレーダーのような適切な判断力が何より大切なのだ。
優秀なパイロットの考え方はこうだ。
機長がもっとも優先すべき最大の責務は、安全を確保するころだ。
私たちはよく言う。
「我々にはパーキングブレーキという武器がある」。
安全な飛行ができると機長が確信できない限り、飛行機は出発しない。
権限には大きな責任が伴う。
機長はクルー全員にチームとしての一体感を感じさせ、
その一員として行動させなければならない。
すべての経験、智識を駆使して瞬時に判断を下し、できないことを把握しつつ、持
てる力をすべて発揮する。
そんな緊張した状況がいつ訪れるかわからない。
それを自覚し、プロとしての重圧を背負うのが機長の使命なのだ。
山之内さんの本でも書かれていたが自動化のワナにも触れる。
通常運転ならいいが、いざ変更せねばならない事態に遭遇する場合、自動化以前は簡単にできるものを、
解除&再設定のため20回もボタンを押さねばならないというお話はその通りだと思った。
サレンバーガー機長は搭乗者を飛行機で出迎え挨拶をしていることを書いていたが
そんな機長さんみたことないなー。
コックピットにその顔をちらりと見ることはあっても、機長自らがお迎えして
挨拶しる姿などこれまで一度も経験がない。
とてもいい習慣だと思う。
学ぶ姿勢が素晴らしい。
とにかく常に勉強されている。
事故から学ぼうとする姿勢には見習うべきものがある。
惨事になった事故は、それから学ばなければ亡くなった方々に申し訳ないという思
いが強い。
自分ならどういう行動を取ったか、どうすべきだったかを学びそれを活かそうとす
る熱意ある姿勢は
本当に敬意を表したい。
この態度の半分でもいいからみんなが持っていたらすばらしいことになるだろう。
1989年7月のユナイティッド航空232便 油圧系統すべて使用不能からの生還の話が出ているが、
あの御巣鷹山の事故の教訓が生きているのではないかと思った。
調べてみると、「その通り!!」であった。
サレンバーガーさんと同じように、航空関係者はありそうもない場合でもちゃんと手順を検討して
訓練までしているのである。原子力関係者としてはこの姿勢を本当に学ばねばならないと痛感する。
このへインズ機長の苦悩のことにサレンバーガーさんは触れている。
185名が生還できたが111名が死亡した。
ハドソン川へ不時着た1549便の事故のあと、このへインズ機長から連絡があったそうだ。
スーシティーでの事故の後、彼は世界中であの事故の体験を語ることに多大な時間を割いてきた。
20年間で1500回以上の講演を行い、講演料は寄付に回すかまったく無料で講演してきた。
彼が語ることは、彼の体験から我々に学んでほしいことだ。
コミュニケーション、日頃の準備、実行力、協調性、そして彼が言うところの「運」の大切さを訴え、
あの事故で命を落とした乗客たちに対する、消えることのない悲しみについても語り続けている。
へインズ機長は、あの事故の犠牲者に捧げる講演を行ってきたのだが、この講演が彼にとっても
治療になったそうだ。安全問題の講演をしていると、事故で生き残った者の罪悪感を見つめ直すことが
できる。「私の任務は乗客を地点Aから地点Bまで無事に送り届けることだった」と彼は語った。
「あれからしばらくのあいだ、自分が職務を全うできなかったと沈んでいたよ」とのこと。
今では77歳になったへインズ機長は、スーシティー事故当時、サレンバーガー機長と同じ58歳だった。
……
あの事故発生後の歳月を経るうち、へインズ機長は長男をバイク事故で亡くした。
次は妻が稀な感染症に罹患して死亡した。
加えて娘が白血病で骨髄移植するしかなかった。
こんな苦境にいたへインズ機長は、232便で彼が果たした役割が忘れられていなかったことに
勇気づけられた。娘の手術は保険でまかないきれなかったが、スーシティー事故の生存者をはじめ
数百人の人々から50万ドル(6000万円)以上の寄付が集まったのだ。あの事故で愛しい家族を
亡くした人々からの寄付さえ寄せられた。
へインズ機長は長期間にわたって折にふれ人々の善意に触れてきた体験を語ってくれた。
そのおかげで、1989年のあの事故で彼ができたこと、できなかったことについて心の整理が
つけられたという。
……
「ほかにもっとできることがあったのにと、きっと思うに違いないよ。
だれでも後知恵が次々と浮かんでくるものだ。私たちもしばらくはそうだった」と彼は言った。
いろいろな方から手紙が寄せられているが、事故で副操縦士であった父を亡くした女性のことが
印象に残った。テリーサは「長年、私は父の人生の最後の数分間がどんなだったろうと想像してきました。
もう家族に会えないという恐怖と嘆きでいっぱいだったろうと思ってきたのです。父がパニックと
悲しみに包まれて生を終えたと思うと、たまらない気持でした」
1996年バリュージェット592便事故
国家運輸安全委員会の首席調査官は、テリーサに父親は最後の瞬間まで機体を着陸させることに集中していたに
違いないと言った。多少の慰めは覚えたものの、それから13年の間、その言葉を全面的には信じられなかった。
調査官は実際に生か死かの危機を経験したことはないからだ。最悪の状況でパイロットが何を考えているのか、
彼はどうやってわかるのだろう。
だからこそ、私が『60ミニッツ』に出たことが、テリーサにとって重要な意味を持つことになった。
ニューヨーク上空でエンジンを失った瞬間から、私とジェフと二人でどうやって1549便を安全に地上に
戻すかということ以外いっさい考えなかったと話した。それを聞いて、テリーサはいわば悟りを開くことが
できたのだ。
「あなたがどれだけ集中して目の前の仕事に取り組んでいるかを聞いて、私はやっと心の平静を取り戻しました。
あなたが実際に事故を生き抜いた方だからです。ようやくクレッグ調査官の言葉が本当だったことが
わかりました。父は深い悲しみのなかでこの世を去ったのではありません。最後まで自分の仕事に必死に
取り組んでいたのですね。あなたにはどれだけ感謝しても足りません。あなたの話を聞けて本当に
よかったと思っています」
妻のローリーはテリーサの手紙を読んで涙を流した。この手紙のことが頭から離れず、ある日とうとう
テリーサに電話をかけることにした。二人は1時間も話し続けた。パイロットの妻とパイロットの娘として、
想いを分かち合ったのだ。「二人とも心の重荷が軽くなったわ」ローリーはあとで私に言った。
アメリカの価値観についてショックな思いの記述で出ている。
「キティ・ジェノヴェーゼ事件」の衝撃
13歳のときにテレビで見た事件が脳裏に焼き付いていると。
キティはアパートの外で刺殺された。
見ず知らずの犯人に襲われ、性的暴行を受ける彼女の悲鳴を多くの隣人たちが耳にしていた。
しかし伝えられるところでは、彼らは何もしなかった。
38名の住人の不作為 「傍観者効果」
このような人の価値観がどうしても理解できなかった。
そして13歳の筆者は「キティのような人が助けを必要としていたら、かならず行動を起こそう」
と堅く誓ったという。
この悔しい思いが、ハドソン川の奇跡ではまったく逆の事実に触れて感動するのである。
すなわちニューヨーク中の船が速やかに救助に集まってくれたのである。周辺の方々の手助けが本当にうれしかったと。
アメリカの価値観は死んでいない!と。
機長の持ち物で手元に戻ってきた所持品の中に
地元の図書館から借りたシドニー・デッカーの「JUST CULTURE」(「ヒューマンエラーは裁けるか」)があった。
この本は私も読んだのであるが、残念ながら読後記はしたためていないことが判明。
このときはアメリカも日本も同じなんだなあと感じたことを覚えている。
最後の結びの言葉がいい。全文を引用する。
私はケイトとケリーに、私たち誰もが、何が起きても対応できる準備を整えておく義務があると教えてきた。
娘たちには自分を磨き続け、職業のうえでも私生活のうえでも絶えず学び続けてほしい。
多くの人々と同じく、娘たちも人生の終わりにはこんな単純なことを自問するだろう。
「世の中の役にたてただろうか?」。その問いにイエスと答えられる人間になって欲しい。
私の人生を逐一振り返ってみても、幸運に恵まれていたという思いは変わらない。
5歳のとき将来の夢は生涯飛び続けることと決めて、16歳になるとソロ(単独飛行)で、
クック氏の草地の滑走路の上空を夢中で旋回していた。
あのとき以来、飛行への情熱が私を支え続けてくれた。24歳で戦闘機パイロットになった私は、
数秒か数フィートが生死を分かつからには、すべてに対して注意を払わなければならないと学んできた。
57歳の私は、マンハッタン上空でエンジンを失ったエアバスA−320を操縦する白髪頭のパイロットであり、
生涯にわたって蓄積した知識と経験を使おうとしていた。
この間ずっと、空を飛ぶことへの情熱が冷めたことはない。私は今でも、初めての飛行機に興奮し、
コンベア440の窓に顔を押しつけていた11歳の少年のままだ。私は今でも、ハンナ通りの家の上空を飛び、
母と妹に翼を振ってみせている10代の生真面目な若者のままだ。私は今でも、道を示してくれる先人のパイロット
たちに畏敬の念を抱いていた一途な空軍士官候補生のままでいるのだ。
HPに掲載されているというのでSさんの読後記を引用させてもらおう。
ヒューマンファクター事始
ヒューマンファクター講座 番外28 ヒーローには運がある