�@�@��P��u���Y�ƂƂ̕ۑS�𗬉�v
�@�@�q��@�̐����ɂ��āi���{�q��j
�P�D�@���@���@�F�@�Q�O�O�Q�N�W���R�O���i���j�@�P�R�F�R�O�`�P�U�F�S�T
�Q�D�@�� ���@�F�@���{�q��i���j�H�c������
�R�D�@�e�[�} �F�@�u�q��@�̐����v�ɂ���
�P�R�F�R�O�`�P�T�F�O�O�@�@�q��@�̐����Ɋւ���Љ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�P�T�F�O�O�`�P�U�F�O�O�@�@�������w
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�P�U�F�O�O�`�P�U�F�S�T�@�@���^����
�i�T�v�j
���q�͊w��ً̈Ǝ�𗬂̑�P��łi�`�k�̐����H��̌��w�ɎQ���i�Q���ҁF�Q�O���j�����B
�q��@�̃����e�i���X�͌��q�͂��ڎw���Ă���ێ���������S�Ɏ��{���Ă��銴������B
�����̂�����Ƃ��Ă͊��S�Ɋč��^�B�������ڍs�������͂Ȃ��B
�������A�@�했�ɐ����_���Ԋu�͍��y��ʑ�b�̔F�}�^�[�ƂȂ��Ă��肨������Ƃ͕ύX�ł��Ȃ��B
�ڍד_�������͂S�`�T�N�ɂP��B
��ԊĎ��ۑS�Ɋ��S�Ɉڍs�i�X�T���j���Ă��邪�A����̓}�C�N���v���Z�b�T���ڂɂ��
���j�^�����O���\�ƂȂ������Ƃ��傫�ȗv���B
�����O�Ō̏�f�[�^�x�[�X�̉^�p���s���Ă��肤���܂�������i�ƊE���N���[�Y�j�B
�ۑS��p�͑��R�X�g�̂X���i�l����݁j�Ɣ��ɒႢ�B
���ɍ����I�ŐM�����̍����ۑS���o���Ă���Ɗ������B
���q�͂̍��̕ۑS�͍q��ƊE�ł͂R�O�N�O�̂��́B
�q��ƊE���Q�l�ɂ�����ォ�Ȃ�Ȃ��Ƃ��ł��邾�낤�B
�i�ڍוj
�O�D�W��������܂�
���q�͊w��ً̈Ǝ�𗬂̑�P��łi�`�k�̐����H��Ɍ��w�ɎQ���B
�Q�W�l�̐\�����݂ł��������A���d�͑O���̃f�[�^�������蔭�o�̂��ߎ��P���݂̂̎Q���ƂȂ葍���Q�O���̎Q���ƂȂ����B
�c�����������A���m���[����������D�o���ł̑҂����킹�͑����������̂��������B
�S�T���O�̏W�����������炵�����ߗ�[�̂Ȃ��Ƃ���łӂ��ӂ������Ȃ���҂��Ă����B
�P�ԏ��͉��t����B���d�̖��ŗ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă������A�{���͂��̒����c�̒c���Ƃ��Ė`�����A�����邽�߂ƌ�ł킩�����B
�����ĂR�����x�łi�`�k�����ꌚ���ցB��q�ň�ʌ��w�̕�����͂�Q�O�����x�����B
�V�K�̉�c���ցB
���i�͐����m�̗{���̂��߂̍u�`���s�������ł���Ƃ̂��ƁB
�����͎����Ŏ����̔��@�Ŕ����ĉ������Ƃ����܂��������܂�Ȃ��X�^�C���ɍD�����������B
�ŏ�����Ō�܂ŕi���Ǘ������P�l�i���w���̐����͂Q�ǂɕ����ꂽ�̂ł��̎����������P�l�j��
�őΉ����ꂽ�B���������Ƃ���͌��K���ׂ������m��Ȃ��B
�i���Ǘ������̘b�͂����ւ��[�����̂��������B
�̌n�����Đ������Ă��炦�A���^�������ł��藝�����[�܂����B
������͐�������ł͂c�b�|�P�O�̂l�����i�S�D�T�N�ɂP�x�̑傪����ȓ_���j�����w�����B
�P�D�i�`�k�̊T�v
�@�P�T�P�@�̃W�F�b�g�@��ۗL�B
�@�����S�W�@�A���ۂX�R�@�A�ݕ��P�O�@�@�i�V�S�V���R�X�@�A�V�S�V�|�S�O�O���R�Q�@�ۗL�j
�@�ۗL�@���ł͑債�����Ƃ͂Ȃ��i�X�O�O�@�̍q���Ђ�����j�����ې����嗬�Ȃ̂Ŕ���グ�ł͐��E�ł���ʁB
�@�H�c������͂P�O�O�O�l�B
�@��Ƃ���镔���͒��������̊W����ʉ�Љ����Ă���B
�Q�D�q��@�̕ϑJ
�q��@�̕ϑJ�ɂ��M���������シ��ƂƂ��ɐ������@���ω����Ă����B
�@��P���ォ���S����փW�F�b�g�@�͕ϑJ���Ă���A���̋Z�p�i���ƕۑS���@���W�B
��P����@�P�X�T�O�N��̂V�O�V�A�c�b�|�W
��Q����@�P�X�U�O�N��̂V�Q�V�A�V�R�V�A�c�b�|�X
��R����@�P�X�V�O�N��̂V�S�V�A�c�b�|�P�O�A�`�R�O�O
��S����@�P�X�W�O�N��̂V�U�V�A�V�S�V�|�S�O�O�A�`�R�R�O�A�`�R�S�O�A�l�c�|�W�P�A�V�V�V
����̋敪�̓e�N�m���W�[�̑���B�ޗ��̐i�������邪��ɓd�C�V�X�e���ŋ敪����Ă���B
���Ȃ킿�A
�^��ǁ@���@�g�����W�X�^�@���@�h�b�A�W�ω�H�@���@�}�C�N���v���Z�b�T�i�p�\�R���j�A�f�W�^����
����ɉ����ăR�b�N�s�b�g�̏斱�������ω��A�@�t���猾���ƁA
��S����́@�Q�l
��R����́@�R�l�@�q��@�֎m�P�l���K�v�ł������i�}�C�R������ցj
��Q����́@�S�l�@���ې��ɂ̓i�r�Q�[�^�i���E�j���K�v�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�b�N�s�b�g������]�����o���Ĉʒu���m�F���Ă����B
�i�h�b�ňʒu�m�F�\�ƂȂ����j
��P����́@�T�l�@�ʐM�m���K�v�������@�̂̓��[���X�ʐM�i�g�����W�X�^�œd�b���\�ƂȂ����j
�d�q�̔��W�ƃ����N���Ă���B
��T����͂Q�O�N�ȏソ���܂��o�Ă��Ȃ��B
�P�l���H�͂��蓾�Ȃ��B�|�ꂽ�悤�Ȏ���A�딻�f�̏ꍇ�����ł��Ȃ��B
���������ă[���l��肵���Ȃ��B���Ȃ킿�������c�B
��肩���߂ł͉^�]�m�Ȃ��̎��т͂��邪�A��s�@�ł͒N�����Ȃ����낤�B
�p�C���b�g�͏���̂P�l�ŁA���������^�]�̔�s�@�B����͎�������܂Ő��������邾�낤�B
�ȏ㐢�����������̂͐����Ɩ��ڂɊW���Ă��邩��ł���B
�R�D�����̊T�O
�g�s Hard Time ���鎞�ԂŌ���
�n�b On Condition�@�@�@�@�@�@����I�����Ń`�F�b�N
�b�l Condition Monitoring�@�@����܂Ŏg��
��P����̐^��ǂ̎��͂g�s�������B�^��ǂ̃t�B�������g�͂悭�ꂽ�B
�I�[�o�[�z�[���������T�O�B
���ꂪ�V�i�ɂ����n�Y���悭�̏Ⴗ��B
�����̏�A�q���[�}���G���[�ł�������悤�Ȃ��Ƃ��悭�N�������B
�I�[�o�[�z�[���ŏo�Ă�����s�@���悭�g���u�����N�������B
�ˁ@���ł��o�����Ăg�s�͂悭�Ȃ��B���ł�����ł����̂͂�߂�I
On Condition�@�@�g�p���Ԃŕs�m��B��������Ŋm�F�B�����ł͂Ȃ������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�^�C���̎R�A�u���[�L�V���[�̌��݂Ȃ�
�@�@�@�@�@�@
Condition Monitoring�@�d�C�n�̐i���ɂ��̏�`�Ԃ��ω��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�d�C���i�̓����_���t�F�C�����[�Œ���I�Ɍ�������Ӗ����Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�����ʼn���܂Ŏg�����Ƃ����l����
�@�@�@�@�@�@�@�@�����ĉ�ꂽ�獢��Ƃ���͂Q�d�A�R�d�ɂ���Ƃ����v�ɂ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�}�C�N���v���Z�b�T�ŏ������Ȃ��Ă����̂ł��Ƃ��ȒP�ɑ��d�����o�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ̂��炢�̕��i���b�l�ɂȂ��Ă��邩���ׂ��l�����i�C�e�B�b�h�q��ɂ����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�X�T�����炢���b�l�A�S�����n�l�A�P�����g�s
�@�@�@�@�@�@�@�@���͉���܂Ŏg���v�ƂȂ��Ă���B
������@�@�n�b�̌��������́H
�i�j�@���܂��܁B
�@�@�@�@�@��ł܂��������邪���N�`�������Ƃ��܂��܂ł���B
�@�@�@�@�@�̏ᗦ���瓱���Ĉ��S���������Ď��������肵�Ă���B
�@�@�@�@�@�M�������グ��Ύ�����������B
�@�@�@�@�@�̏ᗦ�̃f�[�^�͎��ЂŎ����Ă��邪�A���[���h���C�h�̂��̂Ǝ��Ђ̗��������Ȃ���
�@�@�@�@�@�����̂Ƃ��낪�ۂ����Ă������̂ƈ������̂�����B
�@�@�@�@�@�ۂ����Ĉ����̂͂ǂ����������B
�@�@�@�@�@�ۂ����ėǂ����̂͑��Ђ������Ă���B
�@�@�@�@�@���S�ɊW���镔���͉��ł����ЂɌ��J����B
�@�@�@�@�@�ǂ����Ŕ�s�@��������Ƒ����ꏭ�Ȃ���e�����邱�ƂɂȂ邩��ł���B
�@�@�@�@�@���[���h���C�h�̃f�[�^�͔�r�I�ȒP�Ɏ�ɓ���悤�ɂȂ��Ă���B
�@�@�@�@�@�i���J���H�Ǝ��₵���Ƃ���A�u�C���_�X�g���[���C�h�ɕ��I�ł���v�Ƃ̉B
�@�@�@�@�@�@���J�����ꍇ�A����Ȃɔ�s�@�Ō̏Ⴕ�Ă���̂��ƕs���S�Ɏv����̂��܂����j
�@�@�@�@�@�������ڂ��������邪��������鎞���ɏW�����邱�Ƃ��ł���Ό������ł���B
�@�@�@�@�@�P�Q�������P�S�������ɏo����P�T�O�@�������Ă���̂Ō��ʐ��ł���B
�@�@�@�@�@�������A���̊Ԋu�͑�b�F�ƂȂ��Ă���̂ŐM�����f�[�^�����čq��ǂƐՂ��邱�ƂɂȂ�B
�S�D�@�̂̐���
�@�Ԋu�̓W�����{�ŐV�s�V�S�V�|�S�O�O�̏ꍇ
�@�@��s�O�_���@�@�@���t���C�g�i�Q���ԁj
�A�@�`�����@�@�@�@�@�U�O�O��s���Ԗ��@�i�I�[�o�[�i�C�g�W���ԁj
��Ƃ��ăG���W���A���A�r�Ȃǂ̊O���_���B
�B�@�b�����@�@�@�@�@���ې��U�C�O�O�O��s���Ԗ��͂P�W�����̑������@�i�V���j
�������R�C�T�O�O��s���Ԗ��͂P�W�����@�V�@�@�@�i�V���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�p�l���Ȃǂ��O�����n���̋@�\������쓮�����ȂǍו��ɂ킽����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڍׂɓ_���E����
�C�@�l�����@�@�@�@�@���ې��@�U�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�P���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@�T�D�T�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�P���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂̍\���I�ȓ_������C��O��I�i�R�O�O�O���ځj�Ɏ��{
���Ƃ��Ƃ`�`�c�����Ƃ��Ă��������A�I�[�o�[�z�[���̊T�O�͊��ɂȂ��Ȃ��Ă���A
���̍��ڂc���Ȃ��Ȃ��Ă���B
����琮���̊Ԋu�͑�b�̔F�ƂȂ��Ă���B
�������͗������������̂ŗ^�����������蔲�����肷��i�@�̂����ł͖c��܂���j�̂�
���ې����͕��ׂ��悯���ɂ�����̂œ_���Ԋu���Z���B�^���T�C�N���ɂ��N���b�N��������̂�
����B���̔����m���A�����m������_�����Ԃ����߂��Ă���B
���{�͊C�O�����ێ�I�Ȋ��Ԑݒ�ɂȂ��Ă���B
�@�̂̐i���Ǝ��тɂ��_���Ԋu�͉��тĂ��Ă���B
�l�����̏͌��w��̏͂ŏڂ������|�[�g����B
�T�D�����̐�
�@��S�O�O�O�l�K��
�@�H�c���ƕ��@�P�O�O�O�l
�@���c�@�@�@�@�P�Q�O�O�l
�@���i�@�@�@�@�@�U�O�O�l
�@�G���W���@�@�@�T�O�O�l
�@�{�͍̂���ō��������ƂȂ��Ă��Ă���A�Ⴄ�����̌n�̎q��Ђ�ݗ����Ă���B
�@�܂��A�C�O�ɂ��o�����Ăl�������o����悤�Ɂi�����A�V���K�|�[���j���A�N�ԂQ�O�@���x��
�@�C�O�ɂ�点�Ă���B
�@����̓s�[�N�J�b�g����ł���B�l�����ɂ͔g������̂Ńs�[�N�ɍ��킹�Đl�Ԃ��������Ă�����
�@�������Ă��܂��B���Ȃ킿�V�O�`�W�O���̐l���Ƃ��Ă���B�I�[�o�[�����������C�O�ɃV�t�g���Ă�点�Ă���B
�@�����M������ۂ��ߓ��{����P�O�����x�̃X�^�b�t���P�����h���풓�����Ėڂ����点�Ă���B
�@���i�ɂ��Ă͑��̉�Ђɂ��o���B���ɓd�q���i�͋����Ƃ��낪��邱�ƂƂ��Ă���B
�@�i�`�k�C�`�m�`�C�i�`�r�ŕ��i�̐����S�����茈�߂��s���Ă���B
�@�܂��\���i���̂��̂������Ńv�[�����܂��傤�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B
�U�D�M�����Ǘ�
�@�@�E�����̎��{
�@�@�E�f�[�^�̋L�^
�@�@�E�f�[�^�̏���
�@�@���s����͂��e�탂�j�^�����O�v���O�����̉��P���u�i���������A���P��ē��j���s���B
�@�@���Ѓf�[�^���Q�l�Ƃ���B
�@�@�d�v�Ȃ��́i�s����j�͍��y��ʏȍq��ǂ֕��邱�ƂƂȂ��Ă���B
�@�@���́i�A�����J�̘A�M�q��ǁi�e�`�`�j�̂悤�Ɂj�����̏��u�ϋ��P�ʕ�v
�@�@�Ƃ������̂��o���B���ꂪ�o�����Ƃ�����ԓ��Ɏw�����ꂽ���Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�@�@���̊��Ԃ͂��낢�날��A�Q���ȓ��A���������璷���̂ł͂T�N�ȓ��̂��̂�����B
�@�@�ʏ�͌̏ᗦ���O�D�P���A�b�v����w�͂��q���Ђ�����s�����Ƃɂ���Ĉ��S��������
�@���Ă䂭�B���������������̂����݂�݂��Ȃ���q���ЂƂ��ĔF�m����Ȃ��B
�@�@�����A�ŋ߂͕ۑS���̂��̂��ϑ����Ă悢�Ƃ������ɕς���Ă��Ă͂��邪�c�B
�@�@
������@�Q�d�A�R�d�ɂ��Ă��邩����v�Ƃ������Ƃ����A�P�n���_�E�������ꍇ�A�ǂ̂悤��
�@�Ή��ƂȂ�̂��H
�i�j
�@���̌�����������ł������ƂƊW����B
�@
�@�P�OE-9/�ײĎ��ԂȂ�N���Ȃ��I�Ƃ������Ƃ��Ă���B
�@�P�OE-9/h �N���Ȃ�
�@�P�OE-6/h�@�@���܂�N���Ȃ�
�@�P�OE-3/h�@�@�N����
�@
�@�V�X�e�����ɂP�OE-9/h�ƂȂ�Ό̏�͋N���Ȃ��ƍl���Ă悢�Ƃ������ƁB
�@�ǂ����Ă����ꂪ�B���ł��Ȃ��ꍇ�ɂQ�d���A�R�d�������ĒB������B
�@���Ȃ킿�P�OE-3/h�̂��̂Ȃ�R�d������P�OE-9/h�ƂȂ�B
�@�@�P�OE-3/h�~�P�OE-3/h�~�P�OE-3/h���P�OE-9/h
�@�����ʼnƂȂ邪�A
�@�@�P�̏�ł͐�ɖ߂�Ȃ�
�@�@�Q�̏�ł��@�V
�@�Ƃ����̂������m���]���ŁA
�@�@����ȃV�X�e�����P�̏ꍇ�@�R���ȓ��ɒ����Ȃ���
�@�@�@�@�@�V�@�@�@�@�Q�̏ꍇ�@�P�T�Ԉȓ��ɒ����Ȃ����@
�@�ƂȂ��Ă���A�ړI�n�֒����Ă��璼���̂ŏ\�����Ȃ��̂ł���B
�@�G���W���̏ꍇ�A�G���W�����Q�̔�s�@�͂P���Ƃ��Ƃ����ɍŊ��̋�`�ɍ~��邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@�S���Ă����s�@�Ȃ�P�Ȃ�ړI�n�֍s���邪�A�G���W������������K�v������̂łǂ��ɍ~��邩�͂��̓s�x���߂邱�ƂƂȂ�B
������@���������œ����Ɍ̏Ⴗ�邱�Ƃ͂Ȃ��̂��H
�i�j�@���i�͋����̏�Ȃ̂œ��������͍l���Ȃ��Ă悢�B
�@�@�@�@�@�������A�����l��������\�t�g�E�F�A�͓����_�E���͔��z�Ƃ��Ă���B
�@�@�@�@�@���̂��߃W�����{�ł́A����V�X�e���i�\�t�g�j�𑽏d�����Ă��邪�A�S���Ⴄ��Ђɓ������̂����ĂQ���Q�d�������B�@�@
������@�R�~�܂�����́H
�i�j�@����������B
�@�@�@�@�@���̏ꍇ�́u�ϋ��P�ʍ��v���o����邱�ƂɂȂ�B�@�@�@
������@�q��@�̎����́H
�i�j�@��{�I�ɂȂ��B
�@�@�@�@�@�o�ώ��������鎞���������B
�@�@�@�@�@�����̘J�͂Ƃ����Ō������Ȃ��Ȃ鎞������B��̂R�O�N���炢�B
�@�@�@�@�@���̂��������͂����炯�Ŕ�ׂ�B
�@�@�@�@�@��`�̊����\�v�����������Ȃ�Â���s�@�����ʂƂ��đޖ���]�V�Ȃ�����邱�Ƃ�����B�@�i�q�[�X���[��`�@�y�C���g��m�C�Y�ւ̋K���j
������@�����e�i���X��p�́H
�i�j�i�`�k�P�T�P�@�̐�����p�́A���z�P�O�O�O���~�ő��o��̖�X���ł���B�i�l����܂ށj
�@�@�@�@�O�ɕ��������Ƃ����邪�i�q�̕���������ƍ��������悤���B
������@���̌����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��H
�i�j�������ڌ���������̂͂Ȃ��B
�@�@�@�@�q���Ђ̍s�������������Ƃ���Ă��邩�ǂ���������̂����̌����ł���B
�@�@�@�@���S���m�F�����ƌ�������̂ŁA���̌��������P�O�����x����Ă��ċL�^��
�@�@�@�@�T���v�����O�`�F�b�N����B
�@�@�@�@�������������Ƃ��A�n���R��������ĂȂ��Ƃ��w�E�����B
������@�@��̐M�����̂��Ƃ��茾���Ă��邪�l�דI�Ȃ��́A���Ȃ킿��Ɣ\�͂͂��邩
�@�@�@�@�܂��߂ɂ�邩�i������Љ�Ӑ}�̐M�����Ƃ������j�A�Г��̃��`���`�x�[�V����
�@�@�@�@�̑�́H
�i�j����͈�ԔY��ł���Ƃ���ł���B������������������ė~�����B
�@�@�����Ƀ��`�x�[�V�������グ�邩�}�l�W�����g���Y�݂܂����Ă���B
�@�{�̂͋����������Ǎ�����Ă���B
�@�@�@�@�Ђ�Ⴂ�������͈��������œ����Ă���B
�@�@�@�@�������̋C�����������ė��Ă���̂�������B
�@�@�@�@�����[���_�E�����ǂ�����Ėh���ł������n���Ȋ����͂���Ă��邪�A����ł͂Ȃ��B
�@�@�@�@���E���ŔY�݂܂����Ă���B
�@�@�@�@�����m�͍��Ǝ����{�Г����i�i�Г����i�̕����������j�@�R���R���
�@�@�@�@�V�����Z�p���ǂ�ǂ���邽�ߏ�ɕ����Ă����˂Ȃ�Ȃ��������d�����B
�V�D���w��
�@�c�O�Ȃ���W�����{�̓h�b�O�i�n���K�[�ƌĂ�ł����j�ɓ����Ă��炸�A
�{���͂c�b�|�P�O�̑�V��ڂ̂l�����̂P�Q���ڂ������Ă�������B
�Q�O�l���O���[�v�ɕ����Đ������Ă��ꂽ�z���������������B
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w�Ґ����p�{�[�h
 �@�@�@
�@�@�@
�X�N���b�v�{�b�N�X�B�����Ǝ��o���Ȃ��\���ƂȂ��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h�b�O�̍ʼn����B
 �@�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���K�[���̗l�q�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂̓h���́A�͂����Ėڎ��ɂ��N���b�N�`�F�b�N�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̌�K�v�ɉ����Ĕ�j�����{�B
 �@�@�@
�@�@�@
�G���W���͍ŏd�v���B�G���W���P��P�O���~�������ȁB�@�o���^�C�v�̃W�����{�ł͂P��P�T���~�B�������͂�����B
 �@�@
�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ُ�̌��������G���W���͏ڍ������s����B���ꂪ�����B
 �@�@
�@�@
DC-10�̃G���W���̓}�C�R�������Ă��Ȃ��^�C�v�B�@�@�@�@�ُ킪���������ꍇ�̓v���O���Ă��錊����CCD�J���������Č�������B
 �@
�@�@�����͂Q��ށB�i�`�k�̖��O�������������m�Ƃ����łȂ������m

�@
�@�����ꂩ��O�͊����H�B
 �@�@
�@�@
�@�Q�K�ɏオ��@�����������w�B�h���͎���Ă���B�܂��͊O�ς̏�����ڎ������B�K�v�ɉ����Ĕ�j�������{�B
 �@�@
�@�@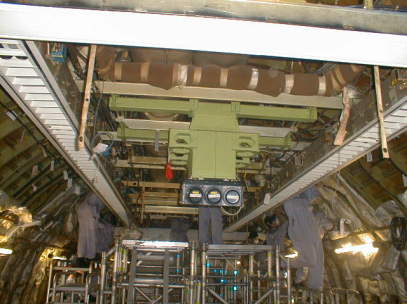
�@�@���������̌����B
 �@
�@
�C�X��g�C���ȂǑ����͑S���O���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�̂̊O�́|�T�T���ɂ��Ȃ�B�����I����ۉ��ނ����t���Ă���Ƃ���B
�@
 �@
�@�@�@�@�@���㕔�̋_�N�g

��ƕ\���Y���[���ƕ��ׂ��Ă��鎖�����B
�W�D���w���̐����A���^
�E�C�O�����H��ւ̏o���͂��������Ă���B
�@�{�[�C���O�������ׂ͖���Ƃ����̂��킩���ăE�`�����ƌ����o���Ă���B
������@�G���W�������j�^�[���Ȃ����s���Ă���ƕ��������ǂ��������̂��H
�i�j�@�G���W���̓d�q�@��Ƃ��ăR���s���[�^�i�}�C�N���v���Z�b�T�j�����Ă���̂�
�@�@�@�@�@��Ƀf�[�^������B
�@�@�@�@�@���������s�@�ɓ��ڂ��Ă���R���s���[�^�Ƀf�[�^�𑗂�A�����@�Œn��֔z�M����
�@�@�@�@�@����B
�@�@�@�@�@������펞�i�`�k�̃G���W�����ƕ����Ď����Ă���B
�@�@�@�@�@�����s�@���̓��A���^�C���Ő��������Ă���̂ł���B�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�f�d�ł͂��̃T�[�r�X���G���W���C���_��ł���Ă���B���Ȃ킿�A�G���W���P�䓖����
�@�@�@�@�@�P���ԓ�����̃����e�i���X��p��ۏ��܂��B���̑���f�[�^��S������B
�@�@�@�@�@�����āA�f�d�����j�^�[���ĕK�v�Ȏw�����o���B
�@�@�@�@�@�G���W���P�@�͖�P�O���~�B�����Ȃ����ł����Ζׂ���B�����瑁�߂̎��ł��Ƃɂ�肻���������Ƃ�B�����悤�Ƃ���l���B
�@�@�@�@�@�l�b�o�g�@:�@Machine Cost Per Hour�@�_��ƌ����B
�@�@�@�@�@�T�O�h���i�P�T�O�h�����������H�j�Ƃ������Ɉ������i����Ă���B
�@�@�@�@�@����ɂ̂��Ă���q���Ђ��������i�`�k�͌_�Ȃ��B���Ђł��B
�@�@�@�@�@�������Ȃ�f�d�̉A�d�ƌ��Ă���B�������֍s������_�����Ǝv���Ă���B
�@�@�@�@�@���̌_��ɂ��G�A���C���̐����\�͂��ቺ���Ă���ƁA����������ƒl�i���グ�Ă���Ǝv���Ă���B
�X�D���z
�@��ϖ��ɂ�����ł������B
�@�q��ƊE�͌��q�͓��l�A�����M�������K�v�ȕ���ł��邪�A���̕ۑS���@�͂R�O�N����s���Ă��銴������B
�@���q�͂��x��Ă���ƌ������ق����������낤�B
�@���낢��q���g�͂��炦���Ǝv���B
�@��͂����Ɏ��H�ɂȂ��ł������ł��낤�B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@