小笹氏の著書はモチベーションカンパニーを読んでいるので詳しくはそちらで。
「モチベーション自己革命」
小笹 芳央 講談社
小笹氏の著書はモチベーションカンパニーを読んでいるので詳しくはそちらで。![]()
この本は小笹さんの会社であるリンク&モチベーション社のガリレオ研修を受講したときに
無料では気がひけるので手土産持参した御礼にいただいたものであった。
ガリレオ研修の内容と同じであった。
出張報告作成がこの本のおかげで充実できた。
研修の内容は添付するが、研修で抜かれた部分で自分を認識するところがあった。
「職務指向特性」である。
ゼネラリスト、スペシャリスト、ハンター、フォーマーの区分で、自分はゼネラリストになった。
◎「ゼネラリスト指向」は、組織や職場での一体感を重視し、
組織成果の極大化を目指そうとする組織重視指向を示します。
広範囲な知識や経験を持とうとし、組織のためにそれを活用しながら、
個人の個性や技能を全体最適の視点からとらえようとする傾向があります。
うんうん、そのとおりどだわ。
モチベーションがアップするとき
・組織の連帯感や一体感を肌で感じるとき
・各人が組織全体の視点を共有しているとき
モチベーションがダウンしやすいとき
・全体視点ではなく自分の視点やペースにこだわる人間同士の対立に直面したとき
・組織やチームへの所属意識が希薄な立場に身を置いたとき
セ ミ ナ ー 受 講 報 告
【セミナー名】ガリレオ
【開催日】2005/6/15
【開催場所】株式会社リンクアンドモチベーション 大阪支社
大阪市北区梅田2-4-13 阪神産経桜橋ビル9F
http://www.lmi.ne.jp
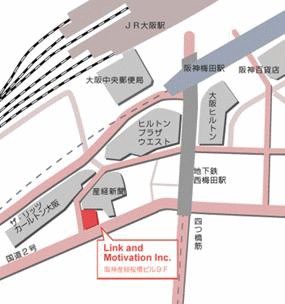

受講者は23名。我々Bチームだけが5名で残りの3チームは6人だった。
リンク社を使っている会社の人事担当者が多いといいう感じであった。
【研修内容】
あっという間の4時間であった。きっちり17時に終えるところがプロである。すごい。
楽しいグループ演習をしながら、いろいろなことに「気づく」という仕掛け。
若い人が楽しく自分のモチベーションをコントロールする術を身につけることができることを狙いとしているが、マネージャクラスにでも十分新鮮である。
0 リンク社の特徴
① unfreeze → ② change → ③ refreeze
心理学をベース。
3つのステップが必要。
組織を変革したいとき、多くの企業が②から入ってしまう。
自分自身の気づき(①)が必要。これがなければ何も変わらない。
この気づきを支援するプログラムを提供する。
北風ではなく太陽的アプローチを目指す。
エデュケーションとエンターテイメントをあわせたエデュテイメントを目指している。
Edutaiment
アクティブモチベーションコントロール
前向きにコントロールする技術
社員が身につけさせたい、スキルをつけさせる
という企業が増加中である。
背景としては、
最近の環境変化で人も変わらないといけない
上位下達のピラミッド組織ではなく
現場で考える組織 ネットワーク型に変化 例 U.S.Army
そして自立型人材が求められている
研修としては、これまでテクニカルスキルに中心があたっていたが、
変化が激しい時代では、それよりもポータブルスキルに当たる
セルフコントロール、タスクマネジメント、コミュニケーションの能力を高めることの方が
効果的である。
ベースとなるモチベーション特性(性格)は変えにくいがポータブルスキルは普遍的であり、変えうるものである。
1 自己特性の把握
火山島から逃げろ! の演習
難破船から漂流した島で共同生活していたが、ボートが見つかった。
脱出できる船の定員は5人
ボートの発見者であるあなたのほかには4人しか乗れない。指名権はあなたにある。
そこで火山の噴火が起こった。残るものは「死」しかない。誰を選ぶか、8人のうち4人を選ぶ究極の選択を迫られる。船で出ても生きて帰れる確率は60~80%だ。
そしてチームとして結論を出せという。一人一人残す人間のカードを火山の絵の中に助けて欲しいとの彼らのメッセージを読みながら放り込んでいく。同じカードを選んだ人は一緒に放り投げることができる。これを時計回りで順に回す。
これは自分と向き合う。自分のこだわりをみつけるための演習だそうだ。
多数決で決めるのは不可!チームで結論を出さねばならない。
とにかく絶対に妥協はするな!徹底的に議論して自分のこだわりを出す。
正解はない。
4チームのまとめは以下のとおり。我々はBチーム。
エッセイスト(男性70歳) D
気象学者(女性60歳) B,C,D
国会議員(男性50歳) A,B,D
タレント(女性30歳) A
妊婦(妊娠4ヶ月) C
外科医(男性20歳) A
オリンピック選手(女性19歳) A,B,C,D
子供(男7歳) B,C
本来の演習ではもっと時間をかけて徹底的にやるそうである。
私は船で出て生還するというミッションを考えて最適なクルーを選んだが(気持ち的には非常に心苦しかった、特に噴火した火山の中にカードを放り込むのは非常につらい作業であった)、和食さんは人道的見地から妊婦、子供を選んでいた。また、生還して帰った後の批判を考える人もいた。グループ別でも意見が分かれ生還を第一義に考えるのが基本が3チーム、Cチームは和食さんと同じ人道路線であった。全く同じ選択がないというのも非常に面白い。
そしてグループのメンバーか自分の特性についてのコメントを言い合う。
その後、欲求特性をチェックシートでみつける作業を行った。
① ドライブ欲求
y軸+ 勝/負 敵/味方 損/得
② アナライズ欲求 x軸+ 真/偽 因/果 優/劣
③ クリエイト欲求 x軸マイナス 美/醜 好/嫌
④ ボランティア欲求 y軸マイナス 善/悪 正/邪 愛/憎
私はタイプA ①③(第2象限) 達成支配欲求
和食さんはタイプD ②④(第4象限) 審美創造欲求
でした。
ただx、yの値が小さければ傾向は極端ではないというもの。
それぞれタイプによってモチベーションのアップダウンの要素が違う。
Aタイプのモチベーションが下がるのは
・ 権利や権限を剥奪されたとき
・ 周囲が低い業績のものを容認したり、高い業績に対して無関心
・ 提案を無視されたとき
Dタイプでは
・ 一貫性のない(矛盾した)指示や、期待にさらされた時
・ 非生産的な会議に出席するとき
だそうです。うーん私はDタイプの事項でも十分下がるけどなあ。
この自分の特性を知った上でセルフコントロールをしようというのが狙い。
2 コントロール可能な領域の理解
演習「箱根君へのアドバイス」
希望どおり営業に配属になった新入社員の箱根君が元気がありません。
先輩のあなた(6年目の優秀な営業マン)は課長からアドバイスをしてくれと頼まれて
話を聞きます。すると出るわ出るわ、不満、グチが。
この課題に対しては、箱根君へのアドバイスをシートに書き込む個人ワークから入ります。
変えられるもの vs 変えられないもの
変えられないものにいくら不満を持っても意味がない。
変えられるものにエネルギーを集中して買えよう。
自分 vs 他人
思考・行動 vs 感情、生理反応
未来 vs 過去
「選択理論心理学」がベース
トップアスリートは、変えられない「過去」に対しては気持ちは全く向かず
みんな未来志向です。
実は、このワークでは若手自身が同じような悩みを持っているケースがあり、次の視点の切り替えを行う訓練になっているのである。
3 視点の切り替えの観点の理解
演習「古代遺跡のナゾをとけ!」
バラバラになったプレートの文字を見つけるというチーム対抗戦。ブロックを組み立てて並べてみるがなかなか解明できない。

モチベーションと一体何の関係があるんだい??と疑問に思いながらも、ゲームへの挑戦意欲は高い。それぞれが意見を出し合い難問にトライするのだが…。
一回回答をしてみたが、失敗。
各チームとも同じような感じで声が聞こえてくる。
そして第2ヒントが。
アッ!!わかった。
見えた!!
みんな大喜びである。タッチの差でCチームに先をこされたが2番手でゴール。
達成感がありましたですなあ。
これは、第2ヒントで「視点」が変わったからであった。
それに近いことは意見としては出ていたのだが、まとまりきらなかった。
第2ヒントが提示された途端にほぼ一瞬に全員が理解したというもの。
この仕掛けは企業機密として明かさないでおく。
視点を変えることがいかに大事かということを身をもって体験するのである。
これも「気づき」である。
最終的には行動を変えるのが目的だが、
その前には「思考」を変える必要がある。
「思考」を変えるためのの具体的な6つの視点の説明。
スイッチ&フォーカス さほど目新しいものではない。
① タイムスイッチ法 : 時間軸を切り替える ロングスパンで見る
②
ズームスイッチ法 : 視界の高さ、幅を切り替える
③
ロールスイッチ法 : 役割を切り替える
④
ゴールフォーカス法: ゴールから現在を見直す
⑤
チャンスフォーカス法:隠されたチャンスに目をむける
⑥
リスクフォーカス法: やらないリスクからものごとを考える
講師の駒込さんは②を使っているとのこと。嫌なことがあれば世界地図を眺めるのだそうである。
4 きっかけの活用の理解
最後は時間もおしていたので簡単に。
時間がたてばモチベーションは着実に下がる。
したがって途中できっかけをつかんでモチベーションアップを図らなければならない。
◎ きっかけは待つのではなく「きっかけ」を創る。
自らが積極的にきっかけを創り出すのである。
研修では、各自にきっかけとなりそうな事項を挙げてもらう。
5 ガリレオ研修の費用
1日~2日 10~30人 (グループ構成が可能な人数)
対象者 若手から中堅
費用 80万円(1日10名につき)