〜「話が通じない」の正体
黒川 伊保子/著 新潮社
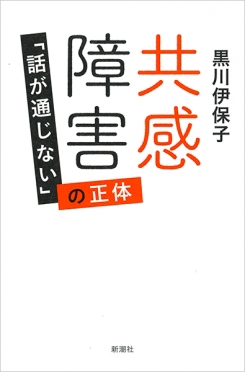
【内容紹介】
挨拶を返さない、同僚の片付けを手伝わないなど、家庭や職場で「当たり前のこと」ができない人々。
その原因は性格や知能ではなく、脳の認識の違いだった。脳科学から、困った人とのつきあい方を読み解く。
夫のトリセツで、
☆ 最近、私は2つの衝撃を受けた
それは自分が左ききだったことと、自閉症スペクトラムだったこと。
60年近く生きていて、初めてそれが判明したのである。
という事実を知って非常に驚いたのであるが、夫のトリセツではその経緯については全く書かれておらず
一体どういう風にしてその診断を得たのであろうか知りたくてしょうがなかったが
この本で詳しく書かれていて、とても納得、理解できた。
また突如フェイスブックを止めてしまった理由についても書いてあり、これまでどうしてか全くわからなかったのでよかった。
本件について、まず書き残しておこう。
1 自分が左ききだったこと
P70 左利きのお尻には“くぼ地”がある?
スポーツトレーナ^トレーナーの山本裕司先生に指摘されて驚いたとのこと。
仙骨の形が左利き典型だという
「仙骨はお尻の始まりの骨にふさわしくカーブを描くのだが、山本先生によると、そのカーブの形に2種類あるのだという。
多くの人が腰椎との接合部からふっくらなのに対し、いったんへこんでからカーブを描く人がいる。
前者はDラインなのに対し、後者はS字ラインなのである。
(実際はそこまで極端じゃないのだが、イメージとして)、そして左ききの人はそのS字カーブを持つ傾向が強い。
昔から、お尻の始まるところに扇状のくぼ地があり、よその人にはあまりないことには気づいていた。
(親も夫も息子も左利きの中に、息子の嫁が同居するようになってマジョリティではないことに気づかされたそうな)
「お母さんのお尻は、キューピィちゃんみたいに始まりのところが三角にへこんでてカワイイね」
「お友達にはあんまりいないかも」
東京医科歯科大学の角田忠信先生の研究室での脳の実験では左脳偏重型(すなわち右利き)と指摘されていたのですぐには左利きの指摘に納得
できなかったようである。
→ 59歳でわかったらしい。
全く自覚がなかったが、意識して左を使うとあれまあ、うまくいくのでそれ以降は左利きを意識して生活していてうまくいっているらしい。
そんなこともあるんですなあ。
2 自閉症スペクトラムだったこと
P134 私が自閉症?、
自閉症スペクトラムであることを知ったのは、自閉症カンファレンスの会場だった。
自閉症判定のためのさまざまな手法の紹介を受けていたのだが、どのテストも、自分が完全に自閉症タイプであることを示していたのだった。
障害のイメージが強い「自閉症」だがこの言葉は悪い!と黒川さんは言っている。
アメリカの「オーディズム」 (独自脳)という表現には後ろめたさが微塵もない。
→ そうだよなあ。オーディズムという言葉には人間としての尊厳と個性を感じる。
この勉強を始めたのは、親友で自閉症グループホームのプロデューサーの平岡美穂子さんとの知己が大きかったとのこと。
脳科学者として、ミラーニューロンの働きから自閉症の正体を黒川さんは解き明かしていく。
なかなかわかりやすい。
アメリカ発祥の2歳から5歳までの早期療育 (Early Start Denver Model ;ESDM)の重要性がわかる。
日本ではなかなかできていないが本当に大事なことだと思う。
3 フェイスブックを止めてしまった理由
P39 ツイッターだと炎上する?
インスタグラムは伝えたい第一属性が画像だけれど、ツイッターのそれは言葉だ。
ロッシの笑顔の画像には「いいね!」を送る以外にないが、「ロッシ、すげいなあ」ということばには、
「でもさあ、最近」とか「本当にわかって言ってるの?そのすごさ」とか、ひとこと入れてしまいたくなる何かがある。
写真は「対象の状況」だが、ことばは「投稿者のものの見方」だからなのだろう。
インスタグラムの「いいね!」は、ロッシの笑顔や、その瞬間を写し取った投稿者の手腕に対して贈るものだが、
ツイッターのコメントは、投稿者の意見に対して送るものだから。
フェイスブックに至っては、伝えたいのは「時分という人物」「ブランド」である。
私は、自分が何者かよくわかっていないので、フェイスブックは何年も前に挫折してしまった。
何をどうアップしても、現実の自分から乖離していく感じがつらくて。
結局、「今、心の琴線に触れた光景」を写真にとって、「心に浮かんだことば」を添えてインスタグラムに投稿することの積み重ねの方が、私らしい気がする。
友人たちのインスタグラムにもそう感じる。
日常風景から切り出すワンショットは、彼女たちのやさしさや聡明さやセンスの良さを端的に表している。
私はことばの感性や研究をしているのだが、こういうとき、「ことば」という存在の罪を思う。
ことばにすればするほど、本当の気持ちから乖離していくという事態がときに起こる。
ことばが主体の情報媒体はこのジレンマとともにある。
本だってそうなのだろう。私のこお数十行の文章だって、「それは違う」と言いたい読者はいるはずだ。
私は本を書きながら、その苦しさを常に思う。
ツイッターを愛する人は、私がインスタグラムにあげた軍配に、ざらっとした気持ちになっているに違いない。
男女脳の違いを諭せば、男女は違わないと信じる人が、早寝を推奨すれば、夜眠れない人が居心地が悪くなる。
私の本を無邪気にたのしんでいたのに、小石に躓いたような気分になったとしたら、本当に申し訳ない。
けれど、私はその苦しさを引き受けて、それでも、自分の世界観を表現する。
それが著作だと。私は観念している。
読者の方が、そのざらつきをスパイスにして、「黒川伊保子」を楽しんでくれていると信じて。
→ いやー、私にはよく響きました。ますますの伊保子ファンになりました。
非常に内容の濃い、すばらしい名著であると感激した。
発達障害の子供さんで悩む親御さんは是非手にするよい。
最後(おわりに)でこの本を書くきっかけが書かれていたが、
「エナジーバンパイア;人の気持ちをなえさせてしまう人のこと」について書いてほしいと新潮社のスタッフから注文があったことを受けて
ADHDの障害を持つ部下からの相談も受けていたこともあり、
「共感障害」というキーワードにたどりついたとのこと。
そして自閉症の勉強を始めたら、なんと自分自身が自閉症スペクトラムということが受けてみたテストで判明したとのこと。
そして合点がゆき、この書となった。
lキーワードは
◎ 「認識フレーム」 である。 この違いを意識することで生きていきやすくなるのである。
そして第3章では、ますます共感障害の大人が増えるという危機感を提唱している。
是非、一読を。
◎自閉症を脳科学する
目次は新潮社のHPで書かれていたのでちゃっかり拝借した。
https://www.shinchosha.co.jp/book/352551/
はじめに――「話が通じない」は、心ではなく脳の問題である
第一章 脳が違えば、見ているものが違う
「定型」がわからない
男たちの気持ちがわかる理由
「定型」を知る
大阪のいじり
京都のはんなり
江戸っ子のすかし
SNSという共通語
ツイッターだと炎上する?
地域差よりもSNS差
人が自分と同じ感覚だと思い込む危険
脳は、世界のすべてを見てはいない
女は男の遺伝子に惚れる
男力を見抜く認識フレーム
美男美女の災難
体臭も重要である
カクテルパーティ効果
「世界」は、脳が作っている
人生の「主賓客」
わかってもらえないのは、認識フレームが違うから
後ろ向きじゃないのに!
認識フレームが違えば、正義が違う
キャッチフレーズを付けよう
人生の黄金の扉
時代が違えば、人の気持ちも違う
尖った時代、べた甘な時代
大衆全体の認識フレームには周期がある
若者が傷つきやすい時代
人生は認識フレームで出来ている
左利きのお尻には“くぼ地”がある?
脳と利き手
逆手使いのアドバンテージ
ものが消える
探していた1ピース
母語が違えば、脳が違う
魔の刻とき
フルムーン・ベイビー
勝ち負けって、なんだろう
それでも、男女は違っている
マイノリティの居場所を作る
みんな何かのマイノリティ
第二章 共感障害とは何か
認識フレームの欠如が個性を作る
脳の理想の使い方
エリート脳、二世脳
天才脳、「時代の寵児」脳
典型フレーム優先か、独自フレーム優先か
自閉症という名称の弊害
自閉症を経済力に変えるアメリカ
障害としての自閉症
感じすぎる脳は、「世界」がわからない
ことば獲得のメカニズム
ことばの始まり
ミラーニューロンが「ことば」と「世界」を創る
「存在」をうまく認知できない自閉症児の脳
愛が足りない?
愛では解決できない
早期療育だけは特別
増え続けている発達障害
ESDMを脳科学で考える
「ぎりぎりセーフ」のほうが深刻
「判定」されない共感障害
自閉症スペクトラム
社交的な共感障害者もいる
私が自閉症?
葉を見て、森を見ず
思い返せば問題児
自閉症なのに、コミュニケーションの専門家
見れば、踊れる
自閉症児はミラーニューロン過活性だった!
記憶の「静止画」
素数の匂い?
ADHDは自閉症の対極
ADHDの素敵な個性
脳内ホルモンが、脳を動かす
ジェットコースターも怖くない
個性か、成績か
エリートを目指さなければいい
「世間をなめているように見える」を自覚する
第三の共感障害
共感障害の正体
第三章 共感障害と生きる
挨拶ができない子を見逃してはいけない
二つの指導法
共感障害者を導く方法
「ウルトラマンのカラータイマー」を使え
うなずくこと、メモすること
エナジー・バンパイア
カサンドラを疑え
自分が共感障害かもしれないと思ったら
「気がつかなくて、ごめん」は何より大事
周囲の所作が「風景の一部」に見えている
なぜ、おしり拭きを取ってくれないの?
大人になったら、友だちは選んでいい
やる気のない部下が、かわいい部下に化ける
割り算ができない?
数学のセンスも共感力
共感障害が増えている理由
共感力は授乳中に作られる
人類を進化させよう
おわりに――「共感障害」の発見