デイル・ドーテン 野津智子訳 きこ書房
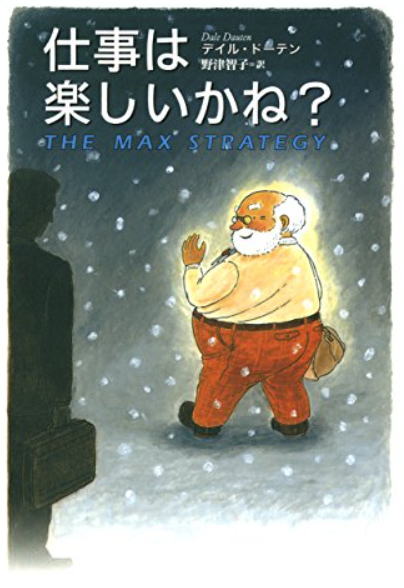
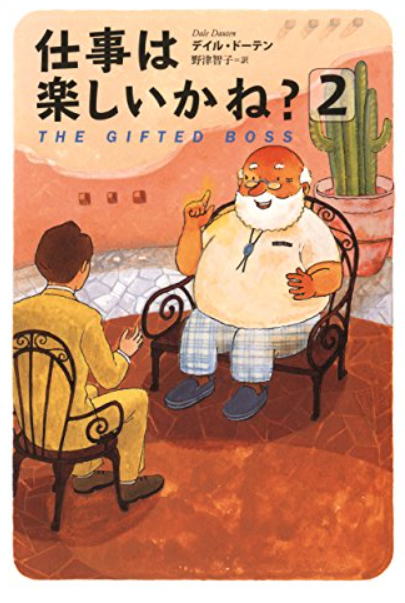
山中伸也さんが苦しい時に出会って元気づけられた本と知って、読んだと思っていた。
日経ビジネスに書評が出ていたので、ああ、読んだよなーとうれしくなって読むと、
どうも内容が違う。
おかしいなあ??と、奥様にお願いしたところ、
私が以前読んだのは最終講義だった。
その前にその1とその2があり、日経ビジネスの書評はその1であったことがわかった。
同じタイトルだったので紛らわしい。
その1は書評にもあるので、つまみ食い的に印象に残ったところを書き出した。
http://blog.koreboku.com/entry/20080210/1202657316
◎ 他人を凌ぎたいと思うなら、まず最初に越えるべき、だけど一番難しいステップは
「並みの人」をやめることだ。
完璧以上に素晴らしい
この言葉になかほどで遭遇。
先に読んだ本でこの言葉が心に残っていたのでうれしかった。
完全というものはない。
常にそれを超えることを目指すべき。
世界記録は塗り替えられるためにある。
ホーソーン効果 (実験を試みたら30%生産性が向上した)
ホーソン工場での実験からわかること
◎ 人は試すことが大好きだ。みんな自分から進んで実験に参加するんだから
◎ 人はチームの要になりたがり、そして「実験」グループはエリートのチームだ。
自分はチームの要だと信じ込むと、人々は互いに協力し合うようになり、そのために監督者の
仕事までどんどん自分たちでこなすようになる。
◎ 現代においてリサーチをする人たちは、「完璧な」リサーチのやり方を求め続けている。
そのために視野がどんどん狭くなり、ついには何も見えなくなってしまっている。
彼らはものごとの相乗作用について見過ごしてしまっているんだ。
ひとつの小さな変化の中にこそこそ隠れていても何も起こりやしない。
だけどその何もない状態を一気に変えたら、何かすごいものが手に入る。
(ホーソンの場合だと、生産性が30%上がった)
⇒ このことは非常に示唆に富む。
面白がって、注目していろいろ試してみたらいいんだ。
被実験者の気持ちが高まれば結果はすごいことが起こる。
そういうふうにすればいいんだ。
納得である。
☆チームのモットーは常にこれ、
「何か新しいことに挑戦しよう!」
☆ 本当の達成というのは、あるべき状態より良くあることなんだ。
ただ良いだけじゃなく、目を見張るようなものであること、
マジックだね。
☆ あらゆることをしろ、素晴らしいアイディアはどこからやってくるのかわからないのだから。
☆ いいかい、できることはどんどん変えてごらん。
みんなが、君が変えていることに気付くくらいになんでも変えるんだ。
好奇心を旺盛にすること。
実験好きな人だと評判になったら、みんなの方からアイディアを持ってきてくれるようになるうよ。
☆ 新しいアイディアというのは、新しい場所に置かれた古いアイディアなんだ
⇒言い訳の組み合わせの例示でこれを説明していた。なかなか面白かった。
☆ 試してみることに失敗はない
その2
主人公がマックスに電話をして教えを乞うところから始まる
マックスの誘いで1週間後にフェニックスへ飛んだ。
空港での助言ですっかり成功者となった彼は、望む以上に出世してしまったための
問題を抱えていた。
☆ 大切なのは単に経験を積むことだけではなく、ほかの人たちと一緒に経験するこ
と
本物の上司 それは会うのが楽しみで、君を高いレベルに引き上げてくれる人
→この話は最初に読んだ本のなかでもでてきた。私の好きなフレーズである。
その人と一緒にいるときの自分が一番好き
→そのような関係になれる人に本当になりたい
優れた上司は 規則ではなく高い基準を決める
ひとつの基準は千回の会議に匹敵する
→ 社員に共有されればこれほど強いものはない
TSSEIの信頼、安心、あったかというイメージでもよいと思う
ここにこそ、みんなの拠り所が、基盤がある。
ここにこそ、他社を引き離し、抜きんでる術がある。
そしてこここそが、みんなが力を合わせるところだ。
優れた上司は 答えを教えるのだはなく質問を投げかける。
部下に答えを見つけさせることのほうが、答えそのものよりも大切である。
→ これは自分のなかに入っていると思っている。
質問はこの2つでいい。
もっといい方法はないか?
これが君にできる最善のことか?
☆ ビジネスの哲学は「手助け」というたった一つの言葉の中に凝縮されている。
その2は人材発掘のようなテーマでいい上司といい部下がいい仕事をするというよ
うなテーマに
なっている感じ。
素敵な人は素敵でいいのだが、何か違和感を。
また役所主義的と規律を否定しているようなところも感じた。
アメリカには監査役がいない。
監査役視点でとらえたとき、私は、規律ある職場というものを求めている。
すべての社員がその規律を愛し、誇りを持ち、ストレスなくその規律を守る。
そのような、一人ひとりがそういう社員になれるような職場を求めている。
同じことをこの本の作者も考えているのだろうが、ちょっと違うかな?という感じ
を持った。
1と3は納得の内容だったのだが、この2はイマイチという感想を持った。
この言葉は気にいった。
☆ 目標は君の職場を「最高の人が働くにふさわしい最高の場所」にすること
仕事は楽しくなかっちゃだめだ。
職場から笑い声が聞こえてこなければ、君のやり方は間違っているということだろ
うね。