山田 昌弘 筑摩書房
これまでは教育のパイプラインに乗っておれば、自動的に就職ができ、それ相応の幸せを得ることができた。
すなわち教育のパイプラインに入れば、こういう人生になるという希望がみんな得られたのである。
ところが、時代の変化でこの機能が破綻してきている。それによって個々人は希望を持つことができなくなってしまった。
その現状を説明している。
衝撃と納得の内容ではあるが、最後に、「ではどうすればよいのか?」に対しはまともに考察ができていない。
それが不満であった。
では、恒例により残った箇所を記録しておく。
○ リスクとは何か
→ わかりやすくリスクについて説明している。
この本のことも思い出したので引用しておこう。
「リスク心理学入門」 岡本 浩一 サイエンス社
リスクは危険とは違う。リスクは原義が「勇気をもって試みる」という意味であるから必ずしも悪い意味ではない。
何かを得るためについてまわる危険性であり、必ず出会うわけではないというニュアンスがある。
危険が伴うことを知りながら、その危険に出会うかも知れない状況に身をさらして、何かを達成しようとするとき、
その危険をリスクと呼ぶ。(虎穴にいらずんば虎子を得ず)
ここでは、リスクを「何かを選択するときに、生起する可能性がある危険」という意味で使いたい。
たとえば、原子爆弾はデンジャーだが、原子力発電はリスクである。
人々の生活を豊かにする電気を供給するためにあえて冒す危険が原子力発電のリスクなのである。
もうひとつ、不確実性とリスク。リスクは、生起する危険の内容について想像でき、ある程度計算が可能という意味を含んでいる。
コロンブスが大西洋に初めて乗り出したケースは、客観的に見れば「不確実性」であり、2度目の航海以降は「リスク」。
○ リスク発生の社会心理的影響 − 自己実現の強調
近代社会の形成に伴い、選択のリスクが生じたことによって、人々の社会意識に影響。
前近代社会においては、リスクを冒して新しいことをすることは、喜ばれないどころか、
秩序を壊す行為として禁止される場合がほとんっであった。
しかし、近代社会が到来し、社会や個人を「よりよい状態」に変化させるために、「リスク」を冒すことは
賞賛されるものとなった。現世での自分の「心のよりよい状態」を目指して、選択して、努力することは、
社会から評価される「よいこと」となったのである。
このことは、個人の生活や意識にとって重大な変化をもたらした。
それは、社会における「自己実現」の強調である。
ここでは、自らの意志で選択し、自分で思い描いた状態を実現することを「自己実現」と定義しておこう。
運命に縛りつけられていた前近代社会に比べれば、現状に「不満」を感じる人々にとって、努力すれば抜け出せる
「希望」がもてる社会である。
しかし、自己実現の強調は、個人の生活や意識にとって、プラスの側面ばかりではない。
まず、選択肢が多様化しても、その選択肢が実現できない場合が発生する。
だから、リスクなのである。
自己実現できない状態に出会えば、自己不全に陥る。中には絶望感に陥り、自殺する人も出てきてしまう。
自己実現ができずに、状態が悪くなったとしても、誰のせいにもできない。
つまり、「自己責任」概念が発生する。自己責任は、個人の感情状態に相当の負荷をもたらす。
同時に、自己実現の強要という事態も現れる。リスクをとることが賞賛されるとなると、リスクをとらないでいること、
自分の理想を持たないこと、目指さないこと自体が非難されるものとなる。
近代人には、理想的な状態を自分の力でもたらしなさいというプレッシャーが、常にかかることになる。
このあとリスクの普遍化に議論が進む。(要約)
高度成長時代には、高望みや冒険をしなくともそこそこの生活を求めれば安定した生活が約束されていた。
教育のパイプラインに乗っていれば将来の予測が可能でそこに希望を持てた。
高度成長期の日本では、まだ生活自体が貧しかったゆえに、ほとんどの人は希望を持って、一所懸命働き、家族を持つことができた。
「豊かな生活」という目標があり、それを実現可能にする経済成長があったからこそ、希望と安心の両立が可能だったのだ。
しかし現代ではそのプロセスが崩れ、将来は不確定性の高いものになってしまった。
安全な居場所がなくなった。人はリスクを取ることが必然の世界になった。
そしてリスクの個人化(自己責任の強調)に向かった。
その結果「運にたよる人間」が増大するということに至った。
○ 運に頼る人間の増大
リスク化が進み、自己責任が強調されると、自由化論者が想定した結果(将来設計について戦略的に考える人が増え、
社会が活性化するという仮定)とは逆のことが起き始めている。
それは、「運だのみ」の人間の出現である。リスクは誰にでも起こり得るが、結果的に危険な状態で陥らなくてすむ可能性もある。
そうなると、リスクに備えて事前に努力しても無駄だということにつながる。
すると多くの人々から希望は消失し、やる気は失われるというわけである。そして、努力せずに、リスクに目をつむり
現実から逃避して生きるという、「自己責任」とは逆の人間類型を産み出す危険性がある。
運に頼る人間とは、競馬などギャンブル好きの人間のことではない。
自分の人生自体をギャンブル化してしまう人間のことである。
その典型的な例を「フリーター」や「パラサイト・シングル」に見ることができる。
アルバイトをしながら夢を追いかけるフリーターは、夢が実現しなかったときのことを考えない。
高収入の男性と結婚できることを信じて、リッチなパラサイト生活を送る未婚女性は、結婚できないケースを想定しない。
彼らが「運よく」就職できなかったり、結婚できなくなったとき、彼らに救いの手を差し伸べる人は出てくるのだろうか。
(後でそのような彼らのことを「社会の不良債権化」と呼んでいる)
悪い時には運任せになるというのは前述の岡本浩一氏(「リスク心理学入門」)が心理学的に説明している。
◎ プロスペクト理論:確率認知の理論
ポジティブな選択肢の場合にはリスク・アバース(回避)な認知 ★100% 800ドル 85%の確率で1000ドル
ネガティブな選択肢の場合には冒険的リスク・テイクな認知 100% 800ドル失う ★ 85%の確率で1000ドル失う
統計的に3:1で、期待値の低い方を選択する結果が得られている。私も人にためしてみたが同様な割合であった。
これも表現方法を工夫するだけで誘導されるので注意が必要。
○ 職業の持つ意味
近代社会では、仕事は「社会の中で役にたっている」「自分が社会の中で必要とされている」という
「アイデンティティ(=社会の中で自分が存在してよい理由=生き甲斐)」の感覚を与えるモノとしての役割が与えられた。
宗教が衰退した近代社会では、「自分が社会の中で必要とされない」と思うことほど、つらい状態はない。
仕事をすることを通して何か社会の役にたっている(これから役にたつ、役にたっていた)ことが、
一つの「生き甲斐」の感覚を与えるのである。
→ 全くそのとおりだと実感している。
経済の成長期には、仕事の2つの役割はうまく機能していた。ほとんどの男性は、収入の増大する定職に就いていた。
そのため、家族の生活を支え、かつ向上させることができ、また企業の中でキャリアをつけるシステム故に、
「自分が企業にとって不可欠の存在」だと実感することができた。
つまり、企業−正社員システムは、社員に、給料だけでなく、アイデンティティも供給していたのである。
→ 今でもそれを志向できないのか?してはいけないのか?
そんなことはないと思っている。
それゆえ、企業正社員システムの崩壊は、男性のアイデンティティの供給をストップさせることになる。
(多くの女性は、家事・育児という家事労働を担うことによって、夫や子供にとって不可欠な存在であるという実感を得ていた)
従って、現在日本社会で生じている失業やフリーターの増大は、単に経済的生活問題だけではなく、職を失った人や定職に就けない人々の
アイデンティティを脅かす要因となっている。
→ なるほど。正社員でない人たちのことを言っていたのか。
職業の不安定化は、人々のアイデンティティ問題を介して、社会秩序の不安定化の問題までつながっているのである。
→ 納得である。
○ 求められる能力の変化
「大量生産、大量消費」時代には「修身雇用、年功序列」でよかった。
現代社会は、グローバル化やIT化が進み、モノよりサービスが優勢になる時代である。
そして、何よりも、生活するには困らない程度の豊かな社会が実現している。
そこでは豊になった消費者が求める多様な商品を、より安く提供しなければならないという圧力が加わり続ける。
現代社会の消費者は
・他人との差異 (ボードリヤール)
・美的感覚(クールさ − 内閣府「未来生活懇談会報告書」)
を求める。
消費や評価をみせびらかすための消費の時代の到来(松原隆一郎氏 「消費資本主義のゆくえ」ちくま新書)
今後企業によって求められる能力(ライシュ)
「変人」と「精神分析家」
○二極化する雇用
クリエイティブな能力、専門知識をもった労働力を必要とし、またそれと同時にマニュア通りに働く単純労働者も必要とする。
「中核的な正社員」と「アルバイト」の二極化が進展
カリスマ美容師や有名なソムリエは高収入。その裏には、膨大な数の下働き美容師や資格はあるが仕事のないソムリエが控えている。
○ 旧来型の職
国内に残存する従来型の職種としては公務員がある。
公務員は、競争がない、効率があまり求められない、専門能力はほとんど不要、外国人を雇えないという条件があるので、
単純な事務からスタートし、管理職に上がるというルートが残る。
ただ全雇用の1割程度であり、減少傾向にある。
マスコミや教育界も日本語の障壁があるので国際競争から免れている。
○ 夢見る使い捨て労働者
フリーターの若者のことをこのように総括している。
若者が教育のパイプラインを出て就業す際に「プリズム屈折」で正社員とフリーターに分けられている。
昔はみんなそれなりに就業できていたのであるが。
→ フリーターは不良債権と呼んでいるが、これはうまい(と言えば語弊があるがあえて使う)表現だと思う。
単に職業的に不安定な人々の増大に引き起こされる影響は、経済の領域にとどまるものではない。
人々の「希望」という心理的問題と直結している。
職業は人々にアイデンティティ感覚を与える。職業を通じて、社会から認められるという感覚を得、生きる糧にしているのである。
そのような感覚から疎外された人々が大量に出現すると、社会にとって不安定要因になることは間違いない。
○ 自暴自棄型犯罪
1998年を起点として凶悪犯罪が増えている。
目に付くのは、青少年、なかでも20代や30代の無職男性が引き起こすものである。(池田小事件、幼女連れ去り事件など)
それも金品目当てや物取り、恨みなどによる「必要に迫られての犯罪」ではなく、
「犯罪を犯すための犯罪」、つまり、殺人や営利目的でない誘拐など、まったく自分の利益にならない犯罪が増えている印象がある。
→ これも希望が持てなくなった若者の姿なのであると別のところで述べている。
怖いと思うし、これではダメだと真剣に思う。
○ 自己実現の罠
いつまでの理想を追い続けているフリーターやパラサイト・シングル。
昔は教育パイプラインでの選別時に諦観が伴っていた。
今は、教育パイプラインに多額の投資をした親の援助もあって、
現実の自分をしっかり見据えることもなく理想、夢を追い続けている。
→ 株で言えば損切りが出来ていないということでしょうか…。
○ 教育システムのリスクと2極化
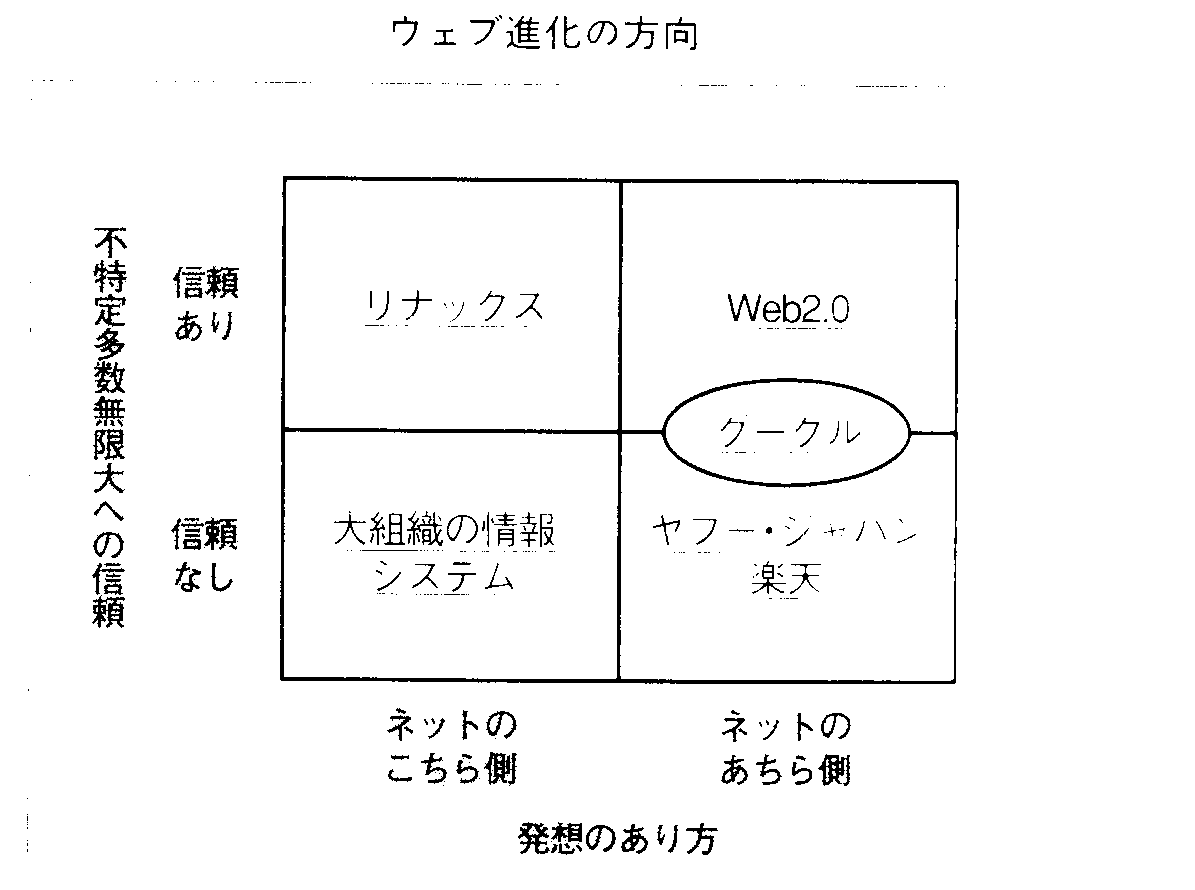
パイプラインに亀裂が生じ、パイプラインから漏れてしまう「リスク」が発生し、「運よく、もしくは、実力によって」
パイプラインを流れ続け、相応の安定した職に到達する人と、パイプラインの途中で漏れてしまい、「卒業という事実」を
生かせず、アルバイトなどにならざるを得ない人との間で格差が広がっているのである。
・博士号取得者 3割は高収入の研究職だが7割は収入低く不安定
パイプラインを流れる個人にとっては、「漏れるか」「流れ続けるか」が、人生を分けるポイントとなる。
うまく流れ続け、安定した職にたどり着いた人は、「勝ち組」。
しかし、漏れた人は「負け組」として職業生活を始めることになる。
フリーターとなって、流れ続けた人に比べ不安定な将来が見通せない職に就かざるを得なくなったり、
別の道に入るために余計な苦労をしなければならなかったりするのだ。
そしてパイプラインを流れている間、どちらになるかは事前にはわからないからこそ、「リスク」と言えるのである。
パイプラインを流れ続ける人と、漏れる人との質的格差とは、「努力が報いられるかどうか」という格差である。
つまりパイプラインから漏れた人は、パイプラインに入るために費やした努力が全く無駄になるという経験をするのだ。
高度成長期なら、「学校に入りさえすれば」職業に就くことが保証された。
それが崩れた根本的理由は、社会経済構造が転換したことである。
青少年の意識が変ったからではない。
○ 学校システムの肥大化
学校を職業需要以上に作りすぎたこと、もしくは、職業の需要が減退しているにもかかわらず学校の数が変らないことも
漏れが大きくなる要因である。
○ 期待切り下げの困難
よく、「就職のレベルを落とせば良い」「自分の能力に見合った職に就くべき」という議論がある。
そして現実に、公務員試験などでは高校卒業程度の試験区分に、大卒者がこぞって受験するということがある。
しかし、レベルを落とすことは、心理的になかなかできないことである。
上のレベルを目指すために行った受験勉強、努力などを「無駄」にする行動だからである。
→ ここはちょっと違和感があってしようがない。
山田さんは学校教育システムを職業に就くためのパイプラインとして捉えているが
本当にそうなんだろうか?受験勉強、点数だけとる勉強で果たしてよい社会人になれるのだろうか?
漏れる人間は悪くなく、社会構造が変ったせいだ。としているのも不満だ。
私は社会構造が変っても変っていけるような人間に教育してこなかったことが悪いと思う。
人づくりは会社で叫ばれているが、子供の時の教育が非常に重要だと。
井深大氏の懸念の方がピンとくる。
山田さんは教育関係しか従事したことがないのも、視野が狭い感を受けてしまう。
教育パイプライン肯定の姿勢にも感じる。
研究では大変な努力をされていることや、主張もしっかりしているので敬服するが
何かもうひとつ足りないものを感じてしまう。
山田昌弘
【略 歴 】 1957年 東京都生れ
1981年 東大文学部卒業。
1983年 同大学院社会学研究科修士課程修了
1986年 同博士課程単位取得退学。
東京学芸大学教育学部社会学研究室助手。
2004年 米国カリフォルニア大学バークレー校客員研究員を経て
東京学芸大学教授。
【主な役職】 内閣府国民生活審議会委員、東京都児童福祉審議会委員
○ 自己責任の強調 − 希望の剥奪
生活保護などのセーフティネットを利用すれば、生存しつづけることはできる。
ただ、このような最低限の経済保証は、人々に安心や希望をもたらすだろうか。
ニューエコノミーの「負け組」とは、単に生活ができなくて、住居がなくなったり飢えに苦しむ人ではない。
「生活に希望が持てなくなってしまっている人」である。
相対的に豊かな社会では、人間はパンのみで生きているわけではない。
希望でもって生きているのである。
ニューエコノミーが産み出す格差は、希望の格差なのである。
一部の人は、努力がオールドエコノミーの時代以上に報われるが、その反対側では、努力が報われないと
感じる人を産むのである。
→ 希望で生きる。生きる希望か。
その希望をニューエコノミーが奪っているという主張。データもしっかりしめしている。
それは山田さんのロジックがこうだからである。
最初はこの部分には強く打たれたが、こうやって書いているとオレは違う。
「使命感」だ。自分の使命、会社の使命
使命感を感じるとその達成まで死ぬわけにはゆかぬ。
死ぬ場合は後輩に託さないといけない。
自分の希望でいきる?
ああなりたい、こうなりたい。そういう希望か?
自分の生まれてきた使命はこういうことにあるんだ!
そういう強い使命感を感じることが人を生きることに駆り立てる。
自分の生きる使命を見つけたとき、それはどんな苦労があろうとも幸せなのではないだろうか?